|
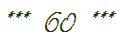
「お荷物は全てこちらに運ばせて頂いていますけれど、大事なものにもしものことがあってはいけませんので、開けるのは坊ちゃまがお見えになってからと思いましたの」
部屋に入りながらミランダが言うと、デュアンは、有難うと答えた。彼のために用意された部屋はアトリエともそう遠くないところにあって、次の間、居間、寝室、書斎を備えた豪華なスイートだ。もちろん、寝室には洗面室とバスルーム、それにひと部屋分がゆうにありそうなクロゼットも付随している。
ゲストルームは比較的モダンにアレンジされた部屋が多いが、ここは重厚なアンティークの調度で満たされたクラシックな雰囲気のインテリアだから、この子の年齢には多少そぐわないかもしれない。しかし、このたびはデュアンは正式に跡取り息子としてモルガーナ家に入ったとあって、貴族的洗練とも言うべきテイストに慣れてもらいたいというロベールの意向からこの部屋が選ばれたのだ。もちろんそれは事前にデュアンとも相談した上でのことだし、ここを見せられた時に彼自身もこれまでと全く違うオトナな感じが気に入って決めたことでもある。
「では、どの箱から開けましょうか」
居間に入って来ながら、山積みの箱を見てミランダが言った。
「じゃ、まず一番大きいそれからかな。中身はぬいぐるみだから、寝室に運んでくれる?」
「はい」
言って彼女は箱を開け、中を見て、あら、可愛い!
と声を上げた。
「でしょ?
あ、そっちの大きい包みふたつもそうなんだけど、みんなぼくのお気に入りたちだから大事に扱ってやってね」
「かしこまりました」
ミランダはにっこりして答え、デュアンも手伝って二人は両手いっぱいに箱から出したぬいぐるみを抱えて寝室に入って行った。
「そのコたちはソファで、こっちはベッドにしようかな?」
デュアンがちょっと迷ったように言う横で、ミランダは笑っている。
「じゃあ、ここに置きましょうか?」
「うん」
ソファに抱えていたぬいぐるみを置き、それから彼女は居間に大きな包みの方を取りに行ったようだ。それの梱包を解き、寝室に運んで来ながら言っている。
「これはすごいですわね。本物のシェパードみたい」
「そうなんだ。それ、おじいさまがプレゼントしてくれたんだよ」
「あら、そうでしたの」
「それはベッドね。最近のぼくの抱きマクラだから」
デュアンの言うのへ微笑して、ミランダは大きなぬいぐるみをベッドに寝かせた。
そんなふうにして二人は次々と箱を開け、中のものをそれぞれに相応しい場所に収めてゆく作業に取りかかったが、デュアン一人の荷物だし、この年頃の子の持ち物だから多いとは言ってもそれなりの量だ。あらかた落ち着くのにそんなに時間はかかりそうになかった。
次の箱を開けて中を見たミランダが、ちょっと驚いた表情で別の箱を開けていたデュアンに尋ねている。
「これは、画材ですわね。すごい量ですけど、デュアンさまも絵をお描きになるのですか?」
彼女は軽い気持ちで尋ねたのだろうが、デュアンの方はふいにここの当主が大画伯であるという事実を思い出し、即座には答えかねてえ〜っと、という顔をした。メイドとはいえ目が肥えているに違いない相手に、はい、そうです!
と答えるには、さすがのこの子もまだまだ自分に自信がない。
「...まあね。イラストだけど」
とりあえずそう答えたデュアンに、ミランダはその戸惑いには気づかず言った。
「じゃあ、とても大事なものですわね。どちらにお運びしましょうか?」
彼女が自分の絵を見たいとまでは言わなかったことにほっとして、デュアンが言っている。
「じゃ、アトリエ兼用で使おうと思ってるから書斎に。本もあの部屋でいいよ」
「はい」
それらを今度はそちらに運んで、一緒に机や本棚に収めながらデュアンが尋ねた。
「ねえ、ミランダはここに来て長いの?」
「そうですわね。お勤めし始めてもう5年にはなりますから、長いと言えば長いですし、短いと言えば短いとも言えるかもしれません。なにしろ、こちらには何十年とお勤めの方が少なくありませんので、私などまだまだ新参扱いですもの」
「そうなんだ。そう言えば、ジェームズやチャールズのような人もいるんだものね」
「はい。お二人ばかりではなく、マーサさんも結婚されて一度はお辞めになったんですけれど、旦那さまを亡くされてからまた戻られたそうですし、アーネストさんなどはもう、なにしろこちらの敷地内でお育ちになったわけですから、論外の長さで」
デュアンはそれを聞いて、お父さんが"ヌシ"なんて言うわけだと笑って頷きながら言った。
「そういう人は他にも多いわけ?」
「多いと言いますか、十年以上お勤めの方が半分以上だと思います。それでいて、お辞めになる方はめったにありませんから、ここに採用して頂けるのはなかなか大変なことなんですのよ。まさに"狭き門"ですわね」
ちょっと自慢そうにミランダは言った。それにデュアンが不思議そうに尋ねている。
「ぼくなんかは、お屋敷に勤めるなんてけっこう窮屈そうに思えるんだけど、希望する人ってそんなにいるものなの?
ミランダだって、他のこと何でも出来そうじゃない?」
「有難うございます。確かに他のお屋敷でしたら、今どきそうまで人は殺到しないかもしれませんわね。ただ、こちらは特別ですから」
「特別ってどうして?
お給料が凄くいいとか?」
いささかお坊ちゃまらしくない現実的な質問に、ミランダはくすくす笑って答えた。
「それもありますけれど、何より環境が違います」
「ああ」
彼女の言う意味が、今度はデュアンにもなんとなく理解出来たらしい。
「お屋敷そのものの立地ということだけではなく、普通に生活していては、これほど素晴らしい美術品に日々親しんだり、お見えになる上流の方や著名な方とお話ししたりする機会なんてまずありませんものね。他と違ってこちらにはロウエル卿のような、社交界にいても滅多にお目通りがかなわないような方も見えられますし、そういったことも含めていろいろなことがとても勉強になりますの。アーネストさんはいつも、モルガーナ家の一員であるということに、誇りを持って勤めて欲しいとおっしゃいますわ」
「なるほど」
「ですから、ここにお勤めを希望するのはそういうことを大切にする人間が多くて、また、それでなければ採用もされません。他にオブライエンさんやコーエンさんの名声を慕って、その下で修行したいですとか、それで厨房や庭回りも希望者が多いですわね」
ミランダの話を聞いているうちに、デュアンはモルガーナ家の内部事情が他のお屋敷とはかなり違っているらしいと分かってきたようだ。彼女の言うとおり、厨房はジェームズのシェフ養成学校のようなものだし、庭回りは庭回りで、庭園や植物について知り尽くしているチャールズの元で学ぼうというガーデナーやフロリストの卵が少なくない。御大たち自身は生涯一料理人、生涯一庭師、という頑固なポリシーに従ってその道を貫き通しているわけだが、大昔と違って今どきは料理人も造園家やフロリストも立派に世界的名声や成功を得られる華やかな職種なのである。だから、その最高峰に師事して現場で学びたいという熱心な若者が後を絶たなくても何の不思議もないだろう。しかし、その中でも選ばれるのは当然、それぞれの仕事そのものに情熱を持っているような者ばかりだ。
人事に関してディはアーネストに丸投げしているが、そもそもアーネストという人がまた自身、大学院まで卒業しながら末は教授という周囲の期待を蹴っ飛ばして現職に就いたような筋金入りの芸術至上主義者である。その彼の最上級の審美眼でもって採用を決めているのだからハンパな者などいようはずもないが、それとてもやはり、当主であるディの性質や嗜好と不可分ではないだろう。
「じゃ、マリーヌやシャロンは?
ここに来てどのくらいになるの?」
「マリーヌは三年ほどですわね。シャロンは昨年入りました。どちらもまだまだ物事を知りませんので、坊ちゃまのご用を承るという大任にはキャリアの点でいまひとつなのですけれど、熱心なよい子たちですし、デュアンさまには年齢が近い方が馴染んで頂けるのではないかということで」
聞いてデュアンも、確かに年が近い方が気軽に何でも話せそうだなと頷いている。
そんな話をしながら、あちらに洋服、こちらに本と、居間と各部屋を二人で行ったり来たりしてあらかた片付け終わった頃、ドアをノックする音が聞こえて来た。デュアンが誰?
と尋ねると、私でございます、とアーネストの声で答えがあった。
「あ、どうぞ。入って」
デュアンが答えるとアーネストがなにやら分厚いファイルを数冊抱えて入って来て、一礼してから言った。
「お荷物の方、落ち着きましたか?」
「ミランダが手伝ってくれたので、もうあらかたね」
「では、後で誰かに空き箱の方を運び出させるようにしましょう」
「ええ」
「それでデュアンさま。このファイルなのですが...」
言って彼は抱えていた重厚な革装丁のファイルを、居間のテーブルに置きながら続けた。
「今回のお披露目に、ご招待する方々のリストになっております。様々な事情がありますので、社交界でも特に主だった方々と、モルガーナ家と関係の深い著名人の皆さまに限られていますが、それでも招待状をお送りする方が200人ほどおられ、それに同伴される方も含めれば実際にはその倍近くがご出席下さることになると思います」
"主だった方々に限られ"てその数なのかい?、とデュアンは内心呆れていたが、その先を聞いてまたまたぶっ飛んだ。
「デュアンさまには今後、当家と大きく関りのある方々について少しずつでも覚えて頂かなければなりませんが、それは各国にまたがりますし、リストにすれば千人は下らない数になってしまいます。ですから、まずは最重要の方々のみということで、とりあえずこれに目を通しておいて頂きたいと」
"アーネストと呼び捨てにするように"と言われた時に薄々感じてはいたことだが、デュアンはこの辺りから本格的に"モルガーナ家の王子さま役というのは、これはなかなか大変なことらしい"と悟らざるを得なくなったのだった。それほど深くは考えず、"お父さんが困っているから"というわりと軽い気持ちで引き受けたことだったので、今になって自分はその実態についてまるで分かっていなかったんでは?と気づいたのである。"クランドル社交界名門中の名門"とか"大きな会社をいっぱい持っている"とか、アタマでは知っているつもりだったのだが、その事実を支えるのは、例えば"千人を超える世界の重要人物とのつきあい"であったり、現代のメディチ家とまで称されるほどの"芸術世界へのさまざまな貢献"であったりするのだということが、今アーネストに言われたことや、さっきミランダと話したことから想像がついてきたからだ。
これは確かに、逃げたメリル兄さんの気持ちは分からないでもないなと納得できたが、デュアンのような根っからの社交家には、それはけっこう面白そうと受け取れたようだ。同時に早くからこちらに移ることにして正解だったとも思えてくる。アーネストはあまり驚かせてはと、すまなそうにリストの件を切り出したのだが、デュアンはそれへ確信を持って、分かりました、と答えた。
「凄い数だけど、これも伯爵さま修行と思えばなんか燃えますね。頑張って覚えます」
その意気込みはアーネストにはちょっと意外だったらしく、驚いたような表情で言っている。
「いえ、あの、なにしろ数が数ですし、あまりご無理なさらなくても...。大体のところで」
「ええ。でも、面白そうだし。どんな人か知ってる方が、会った時の印象も残りやすいでしょう?」
「それはもちろんそうなのですが」
言ってアーネストは存外にデュアンが"跡取り"という立場の重要性を今既に認識し、熱心に務めようとしていることを知って嬉しくなったようだ。にっこりして続けた。
「デュアンさまの方からそう仰って下さると大変助かります。しかし、先の長いことですから、始めからあまりご無理なさいませんよう」
「大丈夫ですよ、出来るだけにしておきますから」
「お分かりにならないことがありましたら、いつでもお尋ね下さいませ」
「はい」
デュアンの答えに頷くと、アーネストはミランダに箱を次の間にひとまとめにしておくよう指示してから出て行った。それを見送って、彼女はテーブルの上に置かれたファイルの山を見ながら言っている。
「大変ですわね、デュアンさま」
いくらか同情的な表情のミランダに、デュアンは笑って答えた。
「大丈夫、このくらい。記憶力はいいんだよ。どっちかっていうと、こういうの得意な方だし」
それを聞いて彼女もデュアンが可愛いばかりではなく、なかなか頼もしい跡取り王子さまらしいと好感を新たにしたようだ。
「私にお手伝いできることがあったら、何でもおっしゃって下さいね」
「有難う」
殆どの箱を開け終わっていたし、後の細々したものは自分でやるからとデュアンが言うので、ミランダは散らばっていた箱をつぶしてひとまとめにしておいて部屋を出て行こうとした。しかし、それへふと何か思いついた様子でデュアンが尋ねた。
「あ、ねえ、ミランダ。おじいさまのお部屋ってどのへんなの?」
「はい、すぐ近くですけれど、シャンタン伯爵にご用でしたらご案内いたしますよ」
「そう?
今すぐでなくてもいいんだけど、じゃ、後で連れてってくれる?」
「もちろんですわ。お呼び下さればいつでも...」
言って彼女はデュアンが自分やアーネストたちの呼び方をまだ知らないかもしれないと気づいて、電話のところに連れてゆくと、内線のどのボタンを押せばいいのか説明した。
「寝室の電話にも同じ機能がありますので、どちらからでもこのボタンを押して下されば誰かが必ず応答致します」
「ああ、前に泊まった時に教えてもらったような気がするけど、これね?」
「そうです」
「分かりました。じゃあ、後で」
「はい」
それでミランダは用を終えると、一礼して部屋を出て行った。デュアンは今日から自分の私室となった広いスイートの居間にひとりになり、ふと緊張感が薄れたようで軽い溜め息をついている。それほど意識していたわけではないが、朝から自分は随分気を張っていたかもしれない。
荷物は殆ど片付いていて後は小さな箱が2、3個と、持ってきたスーツケースがあるだけだから整理するのは後でもいいし、さて、どうしよう、と思いながらデュアンは部屋を見回した。それからなんとなく寝室の方に歩いて行って、天蓋つきの大きなベッドやアンティークなソファを、沢山のカラフルなぬいぐるみが占拠しているのを見てふいに楽しくなったようだ。前に来た時には当然空っぽだったので"ヨソのうち"という感じだったのだが、お気に入りたちが引っ越してきてみると既に"自分の部屋"という気がしてくるから不思議なものである。中でも、ベッドの上とサイドに置かれている祖父からもらった大きなぬいぐるみたち、―
シェパードとライオンなのだが、これらは実物大リアルタッチで実に本モノっぽいから、この部屋のインテリアともばっちりマッチしていた。そう気づいてデュアンは、やっぱり、おじいさまって趣味がいいなあ、と改めて感心する気持ちになっている。
それから彼はまた居間に戻り、今度はテーブルの上を見てアーネストが置いて行った数冊のファイルに注意を引かれたようで、ソファにかけてパラパラと繰って見始めた。確かに200人という数は凄いが、見ていると皆がクランドルではトップクラスの人々だけに、デュアンがテレビや新聞、雑誌で見て知っている人たちも多いと分かって来た。そうなると無理に覚えようとするまでもなく、おお、この人は、とか、あ、あんな人が、と、夢中にもなろうとういうものだ。結局これはデュアン的には、こんな有名人みんなに会えるなんてラッキ〜、という種類のものらしい。中にはもちろんIGDの代表者として、既に会ったことのあるアレクだの、メディアを通じてよく知っているマーティアやアリシアだのの名前もあり、記載されている人物全てには簡単な経歴と写真も添えられていた。
見ているうちにデュアンは、ふと千人ものリストとなるとコンピュータで使えるデータがあればいいんだけどなと考え、一度聞いてみようと思った。無ければインプットしてもらえばいいだろう。その辺り、パソコン通で既に達人なデュアンのことだから、リスト繋がりで詳しいデータがネット検索できれば印象にも残りやすいし、千人と言ってもこれは案外に楽勝かもしれないぞと思えてくる。
こうして、デュアンのモルガーナ家入り第一日目がゆっくりと過ぎて行こうとしていた。今までとは違う生活が、いよいよ始まったのである。
original
text : 2010.3.3.〜3.12.
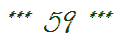

|
