|

跡取り息子のモルガーナ家入り初日ということでジェームズもまたまたハリキったらしく、その夜のディナーもちょうど季節のジビエやら、すっかりデュアンの好物と化しているフレッシュのフォアグラやらを調達してきて最高の料理を楽しませてくれた。もちろん、それに合わせてとっておきのワインが開けられたことは言うまでもない。デュアンがかなりのワイン好きの上に、既に相当飲めることをディもロベールも知っているから、特にロベールはどうせなら早いうちからいろいろ教えて、末はテイスティングできるくらいに覚えさせようと目論んでいるようだ。
ディナーの後はいつものようにサロンに移り、また楽しいひとときを過ごしてから皆はそれぞれの部屋に戻ったが、十時も過ぎる頃になるとデュアンがミランダに案内されて祖父に会いに来た。
「なんだ、デュアン。まだ眠らんのか?」
孫を迎えて嬉しそうに言ったロベールに、部屋へ入りながらデュアンが答えた。
「まだ十時ですよ。今どきの子供は、夜が遅いんです」
デュアンの冗談にロベールが笑って居間へ促す後ろで、ミランダは一礼すると扉を閉めて下がって行った。
「部屋の方は片付いたかな」
「ええ。ミランダが手伝ってくれたので、もうすっかり」
「そうか」
話しながら二人は居間のソファに向かいあって腰を降ろした。
「それでね、おじいさま」
「うん?」
「実はあの...」
この子には珍しく切り出しづらそうにしていたのだが、少しして意を決したように抱えていたB4サイズほどの封筒をテーブルに置いてから言った。
「お約束していた、自信作です」
「お?」
聞いて、ロベールは意外そうな顔をしているが、それへデュアンは真剣な顔で続けた。
「夏休み以来、ぼくはこの作品を描くために精魂傾けました。ですから、これは今のぼくの全てを賭けたものです。これ以上は、今のぼくには描けないと思います」
デュアンがいつもに似ず、殆ど決死の覚悟とも言いたいような悲壮なまでの表情をしているので、
ロベールはその様子を内心微笑ましく感じながらもココで笑ってはいかんなと思ったようだ。真面目な顔を作って言っている。
「分かった。では、心して拝見させて頂こう」
「はい。よろしくお願いします」
言って、デュアンは封筒から数枚のイラストボードを取り出すと、重ねて祖父に差し出した。ロベールはそれを受け取り、最初の一枚を見ていきなり目を瞠った。デュアンはこれまで作品を見せたがらなかったし、既にメリルがあの通りの才能を示しているのだから、三人しかいない孫のうちもう一人にまで同等のものを期待しては欲張りすぎというものだろう。そう思って彼も、デュアンについてはそれほどの期待はしていなかったのだ。しかし、それだけに見せられた絵のインパクトは大きかった。
一番上のイラストボードにはお伽噺のお城を背景に、パレードするサーカス隊が描かれている。先頭をゆくのは煌びやかな衣装を纏って大きな象に乗った少女だが、彼女を乗せた象の前足を上げた姿が圧巻なのだ。その描写はもう"イラスト"の域を遥かに超えて、絵画的ですらあった。そして、後ろには動物たちやピエロなどが連ねられてあり、一面にコンフェッティが舞い散り、弾むような動きを伴った大胆な構図は誰の目をも文句なく奪うようなものだ。
パソコン少年のデュアンはもちろんデジタル作画も大の得意だが、今回ばかりはメリルへの対抗上、全て肉筆で描いている。従って、その絵からは彼の本来のデッサン力の高さがイヤが上にも窺い知れた。デッサン力でゆけば、それはもうメリルと大差ないレベルにあるだろう。しかし、問題はそんな基本的なことばかりではなく、原色使いも鮮やかな画面が、既にデュアンらしい個性を発揮しているという点だ。メリルの絵はたゆとうような幽玄な色彩感覚がクラシックな魅力を醸し出す画風なのだが、こちらはデュアンの明るさとパワーがそのまま現れているかのようで、気持ちいいくらいに迷いがなく、色彩はストレートに迫ってくる美しさだった。
ロベールは見るなり絵に目を奪われて唖然とした様子だったが、しばらくしてやっと細部まで検分する余裕が戻ってきたらしい。デュアンが心配そうに見守る側で、納得したように大きく頷きながら見入っている。
次の絵は、今度はピエロが主人公だ。鮮やかなブルーに白でぼかしをかけたような背景に、カラフルな衣装のピエロのマイム・パフォーマンスがモーションごとに描かれて連写的に連なっていた。先ほどのに比べてどちらかと言えば静的な作品で、なにがなし道化の悲哀すら感じさせるようなムードすらある。技術的にはデジタルならばそれほど難しくなく描けるものかもしれないが、デュアンは肉筆でピエロのワン・モーションごとの動きを見事に重ねていた。
そして最後の三枚目。これもまた、見るなりロベールをにっこりさせないではいない。その画面には亜麻色の巻き毛の美しい少女がアップで描かれているのだが、まさに"夏の少女"とでも題したいような作品で、ひまわりのように華やかで生き生きした屈託ない笑顔が画面の上半分を占め、ノースリーブのドレスは白に赤い水玉、ふんわりしたスカートが画面の下半分を占めていた。人物の輪郭には微妙なコントラストが加えられて夏の陽射しが表現されており、この色使いがまた絶妙なのだ。絵の中の少女は十代半ばくらいだろうが、エヴァがもう少し年を取ったらこんなふうになるに違いない。
どの絵もシャープで現代的でありながら見る人をストレートに幸せにしてくれるようなもので、それはそのままデュアンの生来の性質と不可分ではないと思われた。芸術が自己を表現するものであるとするならば、既にデュアンのそれは立派にその域に達しているのだ。しかも、これほど華やかな画風なら、商業的にも将来の成功は約束されているようなものだろう。
ロベールは三枚の絵を更に代わる代わる検分して最後に深い溜め息をつき、いやはや、驚いた、と言って側に来ていたデュアンを見た。少女を描いたイラストを指しながら言っている。
「これなんか、来月のヴォーグの表紙になっても不思議はないよ」
「ヴォーグなら載りました」
デュアンがこともなげに答えるので、ロベールはまたまたびっくりした顔で言った。
「なに?」
「さすがに表紙ってわけにはいきませんけど、ママがよく描くのでクランドル版のヴォーグの編集長とは親しいんです。それで他の雑誌に載ったのを見てうちにも描きなさいよって言ってくれて。好評だったらしくてその後も何回か続けて載ってるんですけど、ママが今からあまりそれが仕事みたいになるのは良くないって言うし、ぼくも気にしないとは言ったけど、やっぱり親の七光りみたいのでずっと続けるなんていいことじゃないと思うので。自分が自信を持てるものを描いて、それに相応しいところに売り込みに行くっていう方が理想ですからね。でも、今もたまに描かせてはもらってますよ」
祖父が自分の"自信作"を認めてくれた様子なので、デュアンは嬉しそうだ。彼の言う通り、その年齢を考えてカトリーヌが大半を断っているだけで、様々な仕事の依頼が少なからず舞い込んでいるのも事実である。一方、
ロベールはデュアンの言うのを聞きながら、しかし、これは親の七光り程度のものではないぞと密かに考えていた。
「いやね、きみのイラストが雑誌に載ったりしているらしいとはディからも聞いていたが、正直これほどとは思っていなかったんだよ。なにしろ、きみも見たと思うがメリルがああだろう?
孫のうちに一人くらいはそういう才能のある子がいても許されるだろうが、二人もなんて欲張り過ぎというものだ。実際、この絵を見て一瞬、さすがの私もマゴ可愛さに目が曇っとるのかなと心配になったほどだよ」
聞いて、デュアンは笑っている。
「しかし、ヴォーグともあろう雑誌の編集長が気に入るほどなら、私がこう言っても差し支えあるまい。素晴らしい!」
「本当ですか?」
「もちろんさ。これはぜひともディに見せなさい。いかにあいつと言えども感心せざるをえないから。おじいさまが太鼓判を押してやるぞ」
「え、あの...。じゃ、...じゃあ、近いうちに」
"ディに見せる"という段にまでなるとさすがに今でもデュアンはビビってしまうらしく、逃げ腰の様子で答えた。その気持ちが分かるようで、ロベールは笑って言っている。
「うん。ま、決心がついたらでいいから、見せるといい。あいつだって、文句は言えるまいと思うがね」
「はい」
「他にはないのか?
"自信作"でなくても構わんぞ。もっと見たい」
「あ、じゃ、選んで明日持って来ます。けっこう数あるんで」
「分かった。そうだな、今日はもう遅いし、明日の楽しみということにしようか」
それからまたロベールは手元の絵に視線を戻し、確かにこれはいい絵だと思いながらしばらく飽かず眺めていた。デュアンは、やったね!、と思いながら、側でその祖父の様子を嬉しそうに眺めている。
original
text : 2010.3.26.〜3.27.
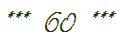

|
