|
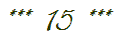
「で、まあそんなわけでな、先代からディが一代飛ばしてこの家を継ぐことになったんだよ」
三兄弟を迎えてのモルガーナ家でのディナーは、予定通り七時に庭に面した豪華なダイニングでスタートした。メイン・ダイニングはゆうに六十人の客を一度にもてなすことができる大きさがあるが、こちらはもっと少人数での集まりのために用意されている部屋で、ちょうど今日のような規模の正餐には最適のスペースだった。
瀟洒なクリスタルのシャンデリアの灯りの下、5人がついている大きな円卓の中央には、銀の燭台に美しい意匠のキャンドルがともり、その側には庭で丹精された花々がたっぷりと生けられている。花はテーブルの上ばかりではなく、部屋のあちらこちらに飾られて優しい香りで部屋を満たしていたが、たっぷりとドレープを描いた重厚なカーテンに縁取られたフランス窓の向こうにも何本もの蝋燭がともされて、暗い中でも幻想的で優美な庭の光景が見渡せるように主の気が配られていた。
それぞれの前には代々受け継がれてきたらしい銀の食器とカトラリーが並び、さきほどからアーネストの指示でオードブルにグルヌイユのフリット、続いてオマール海老のスープ、魚介類の煮込みと次々に目を楽しませる色彩豊かな料理が供されている。もちろん、そのひとつひとつにカーヴからとっておきのワインが選ばれて、磨き上げられたくもりひとつないグラスに最上の状態でなみなみと注がれていた。
ディは三人の母親たちに彼らの好みや好き嫌いがないか、ワインはどのくらい飲めるのかなどを詳細に聞いて、それからアーネストと相談して皆が楽しめるようメニューやワインを決めていったのである。料理人はそれに従って最上の素材を調達して今日のために備えたわけだが、三人とも裕福に育っている子供たちだから口も奢っているだろうと、メインの肉料理に子ウサギの肉と一緒に使うためのフォアグラなどは、本場からフレッシュを空輸させさえしたほどだった。
三人いる料理人のうち料理長であるジェイムズは、先代の頃からモルガーナ家にいることもあって、この家にとうとう跡継ぎとなるべき子供たちが現れたことにアーネスト同様大喜びしている。そのせいもあるのだろうが、今日の料理はどれもいつにもまして絶妙な仕上がりを見せていた。
素晴らしい料理を楽しみながら、ロベールはモルガーナ家とシャンタン家の歴史や、自分とベアトリスが結婚した時の経緯など、三人にこの家の子息として知っておいてもらいたいことをあれこれ話していたが、それも肉料理の前にひと休みのソルベが運ばれて来る頃には一段落ついたようだ。ロベールの話術は日頃から非常に巧みであるし、三人ともおおむね楽しんで聞いているようなので、ディはこの場は父に取り仕切らせておくことにしたようで、子供たちの様子をそれとなく気遣ってやりながらロベールの話に相槌を打つ程度にしか喋ってはいなかった。
「きみたちもお母さんから聞いているかもしれないが、そういう事情だから私とディの跡継ぎが未だに決まっていない状態でね。きみたちにもそれぞれ将来の希望があるだろうし、貴族の家を継ぐというのはこれでなかなか骨の折れる仕事で向き不向きもある。だからおいおいに調整して、なんとか折り合いのつく形で誰にどう後を継いでもらうか決めてゆきたいと思っているんだ。しかしまあ、その話は今はまだいい。ただ、きみたちにも少しそのことについては考えておいてもらいたいというだけでな」
その話を聞きながら、跡継ぎということについて子供たち三人の中で現実的に捉えていたのはおそらくファーンだけだっただろう。やはり生粋の上流階級で育っているだけに、この種類のことは折りにふれて聞くことのある話題だったからだ。一方、メリルは自分がこの家の長男であるという事実ですら未だにピンと来ていない状態だったし、跡継ぎと言われてもまるっきり他人事のようにしか聞こえていない。デュアンにしても、兄さんが二人いるんだからこれはぼくには関係ないよね、と、もっともらしく頷きながらもまさかのことに自分にその役が回ってくるなどとは想像してもいないようだった。
「で、どうだ、デュアン?
今日の料理は気に入ったかな」
シャンパンのソルベを美味しそうに口に運んでいるデュアンに、ロベールが笑って尋ねた。
「ええ、とっても。まるでレストランに来ているみたいなのでちょっと驚いています。レストランでだってこんなに美味しいの、めったに食べられない。なのにこれ、みんな自家製なんですよね?」
「もちろんさ。料理長のジェイムズはクランドルで三本の指に入る名料理人だからな。先代の頃からのモルガーナ家の財産と言ってもいい」
デュアンが頷いている横で、それを受けてファーンが口をはさんだ。
「ジェイムズ・オブライエン氏でしょう?
祖父から聞きました。本も何冊も出してらっしゃるし、ホテル・ソレイユのメインレストランも監督しておられるとか」
「そうだ」
「これはさすがにうちの料理長でもかないません」
「だろう?
なにしろ、彼がまだうんと若い頃にモルガーナの先代がその才能を認めてヨーロッパに修行に出したほどだったんだ。私もこっちに来るたびに彼の料理を楽しみにしているんだよ。ジェイムズも今日のことは喜んでくれていてね。きみたち三人のために張り切って作ってくれているんだから、たっぷり楽しんでほしいものだな」
「ね、おじいさま」
「なんだ、デュアン?」
「じゃ、オブライエンさんってずっとこの家に?」
「そうだよ。彼がヨーロッパから帰って来た時に、先代は店を持たせるつもりだったんだが、彼の方が何かと面倒な店を持つより、この家のために働きたいと言ってね。当時は今よりも更に来客の多い家だったし、出入りするのもなかなかに口の奢った連中ばかりだったから、ジェイムズとしてもその方が良かったんだろう。まあ、天才の常で料理に関しては相当気難しくて、味の区別もつかない客を相手にするのはプライドが許さなかったんだろうな」
「これまでもぼく、ここでごちそうになる時っていつもすごく美味しいなって思ってたの。だけどお父さん、そんなこと全然教えてくれないんだもの」
ディは横で笑っているだけだ。ファーンが言っている。
「そうすると、ソレイユの方は監督だけなんですか?
厨房へは?」
ファーンの問いにロベールが答えた。
「もちろん時々は顔を出しているようだし、メニューの大半は彼のアイデアだよ。しかし、あちら...、ボン・シャンスにもしっかりした料理長がいるわけだからね。ソレイユが経営難でモルガーナ家の傘下に入った時、レストラン部門があまりに弱体なので当時ここにいてジェームズの下でやっていてくれたサミュエルを料理長としてあちらに出したのさ」
「ああ、そうだったんですか。それだとスムースにゆきますよね」
「うん。きみはボン・シャンスへは?」
「はい、何度か連れて行ってもらったことがあります」
「そうか。なかなかいいレストランだろう?」
「ええ、だってなんと言ってもクランドルの最高峰なんですから」
あまりに当然のことをロベールが謙遜ぎみに尋ねるのでファーンは笑って答えている。それで話が一段落して、今度はロベールはメリルに話の矛先を向けた。
「で、どうだい、メリル、料理の方は」
「あ、はい。とても美味しいです」
「そうか。そういえばディから聞いたが、きみは画家を目指しているんだって?」
「え、ええ。はい」
母さんが言ったのかな、と思いながらメリルは答えた。
「なんだかもう、いろんな賞をもらってるそうじゃないか」
「あ、ええ。...まだ小さなものばかりですけど、ぼくのような年齢の者にはそれでも過分な評価だと思うので励みにしています」
「なるほどな。今度はぜひ一度、きみの絵を見たいものだ」
「はい...、そのうちに」
父への反感は別として、ロベールがメリルのことに本当に興味があって、仲良くなりたいと思ってくれているのがその態度から見て取れるのと、自分の思っていたよりずっと気さくで暖かな人柄のように思えるのとで、メリルも祖父には少し気を許しているようだ。お茶の時よりは、かなりましな受け答えになっている。しかし、ロベールにはメリルがそれだけ言うのも相当気を使っていそうなのが分かったので、それ以上あまりうるさくはしないことにしてその答えに頷き、次にファーンの方へ注意を移した。
「じゃ、ファーンはどうなんだ?
もう、将来何になるか決めてるのか?」
「いえ、まだそんなにはっきりとは。でも、ぼくには残念ながら芸術的な才能ってあまりないようだし...、見るのは好きなんですけどね。美術館や劇場にはよく母や従兄弟たちと行きます。だけど、自分が何になるかということになると、やっぱりビジネスの方が向いてるのかなって。大じいさまはそうおっしゃるんですけど、政治も面白そうだし」
「ほお、それはたのもしいな」
「まだまだ希望だけですよ。何をするにしても、まず大学まで漕ぎつけないと...」
ロベールはファーンの冗談に笑っている。
「ただ、最近IGDの活動にはとても興味があって、ああいうことが出来るんなら、経済の可能性って本当に無限に大きいなって思うんです。それで、ロウエル卿にはいつかぜひ一度お会いしてみたいものだと思っています。...もちろん、ぼくがもっと大人になってからですけどね」
アレクの名前が出て来たのでロベールとディは顔を見合わせて微笑を交わした。
「ほお、きみはアレクのファンなのか」
「そう言ってもいいと思います。そう言えば、お父さんはロウエル卿ととても親しいんですよね」
ファーンがディの方を見て言ったので、彼は頷いて見せた。それへロベールが言っている。
「まあなあ、子供の頃から厄介をかけるのはディの方で、こんなヤツをよく見捨てずに今まで友達でいてくれるものだと、アレクには私も感謝しているんだよ」
「え?
そうなんですか?」
「そこまで言わなくたっていいでしょう?
ぼくだってアレクには気を使ってるんですから」
「アレクの方にも言いたいことは山ほどあると思うぞ。まあ、それはいいとして、アレクと会ってみたいんなら、そのうち機会を見て紹介してあげよう。しかし、ロウエル家とクロフォード家も、もともと縁続きのはずだぞ」
「あ、それは大じいさまにも聞いたことがあります。でも、ぼくなんてまだとても...」
「いや、きみのような子ならアレクも喜ぶさ。な、ディ、そのうちアレクに話しておいてやりなさい」
「ええ」
「それは...、実現するんだったらすごく嬉しいですけど、逆にかえってなんか怖い気もしますね。ロウエル卿って、実際にはどんな感じの方なんですか?」
尋ねられて、今度はディが答えた。
「底抜けのお人よし。苦労知らずの脳天気お坊ちゃまで、未だにそれは大して変わってない」
「え?」
「おい、こら」
「だって本当のことですから。ま、会えば分かるよ」
意味ありげに笑って言うディにファーンは頷きながらも、それってロウエル卿のイメージと激しく違うかも、と首を傾げている。
「全くおまえというやつは何を言い出すか分からんな。アレクに言いつけるぞ」
「どうぞ。ぼくが彼をどう思っているかは、彼の方でよく知ってますから」
そのやりとりを横で可笑しそうに聞いていたデュアンが口をはさんだ。
「ロウエル卿ってすごく素敵な方ですよね。イメージ的にはお父さんの言うのと全然違ってるけど」
「それはね、ぼくが十代の頃、四六時中アレクと一緒にいたから言えることなんだよ。知らないかな、ファーン。アレクもきみが行ってる学校の卒業生だよ」
「ええ、それは教授に聞いてます」
「そう?
まあ、いろいろあって、ぼくは彼にだけは弱くてね。最近はアレクの方が忙しすぎて殆ど顔を合わせる機会もないままなんだけど、そういうことならそのうち一度一緒に食事でも」
「それならぜひ。楽しみにしてます」
そうこう言っているうちにメインの肉料理が運ばれて来た。さっと火を通した柔らかな子ウサギの肉に、フォアグラを厚く切って挟んだもので、ジェームズの自慢料理のひとつだ。
「わ、すごい。このフォアグラ、口の中で溶けちゃうみたい。美味し〜い!」
ひと口食べるなりデュアンが歓声を上げた。この子のくったくの無さは自然と座を明るくするもののようで、メリルでさえその様子に思わず微笑んでいる。ロベールも笑いながら言った。
「大絶賛だな。ジェイムズが喜ぶよ」
「だって本当に美味しいんだもの。ああ、幸せ」
「で?
デュアン、兄さんたちはそれぞれ将来の希望がしっかりあるようだが、きみはどうなんだ?
何かなりたいものはあるのかな?」
「え、ぼくですか?」
「うん」
「えーっと、あの」
「何だ?
言ってご覧」
「いちおう、なんていうか...」
「ん?」
「デュアンは、イラストレーター志望なんですよ」
「ほお」
「横から言わないでよ、お父さん」
「なんで?
いいじゃない」
「だって...」
「そういえば、きみのお母さんがイラストレーターだそうだな。テキスタイル・デザインの方でも有名だと聞いてるよ」
「ええ。まあいろいろあれこれ手を出すのが好きな人で、やってるうちに手広くなっちゃったらしくて」
「なるほどな。そうするとデュアンも将来は美術の方に進みたいわけだな」
「それはもう、勉強して進めたらいいなっていうだけで。才能あるのかないのかまだよく分からないし」
「だから一度見せなさいって言ってるだろ?前から言ってるんですけど、なんだかんだ言って見せてくれないんですよ」
「だって、お父さんに見せられるようなもの、ぼくまだ描けてないもの。ずいぶん慣れたけど、ぼくにとってはやっぱりお父さんは神さまみたいに凄い画家だし、見せてもし才能ないからヤメとけとか言われたら、ぼくもう再起不能だよ?」
「言わないよ、そんなこと」
「それでもダメなの!」
この様子には聞いている方も大笑いで、ロベールは、よしよし、じゃあ、自信作が描けたらまずおじいさまに見せなさい。それならいいだろ?と言った。
「自信作が描けたら、ですよ?」
「うんうん。楽しみに待っていよう」
「分かりました、頑張ります」
そんなこんなですっかり和気あいあいな雰囲気になり、肉料理が終わるとフロマージュ、それからデザートと、どちらも大きなワゴンで何種類も運ばれて来て、皆に好きなだけ取り分けられた。メリルもお茶の時よりは格段リラックスした様子でもあったし、まずはこのディナーは成功と言っても良いものになったようだなと、孫たちを眺めながらロベールは楽しく思っていた。
original
text : 2008.8.18-8.19.+8.24.- 8.25.


|
