|

メリルの通されたのは、アンティークを配して名画や彫刻で飾られた贅沢なスイートだった。デュアンたちの部屋もそうだが、ここも次の間の奥に居間と寝室が広がり、そこには快適に整えられたバスルームや洗面室も付いていた。
寝室に据えられたキングサイズのダブルベッドは、彫刻を施した4本の支柱に支えられる天蓋で覆われ、壁面には重厚な意匠のマントルピースが見える。その上に飾られているのは19世紀ロマン派の巨匠、ウィリアム・ターナーの真筆だ。居間のソファ・セットもアンティークの木部に上質の布でアップホルスターしたクラシカルなもので、足元には踵が埋まるほど毛足が長くて柔らかい絨毯、二つのフランス窓の両側にもふんだんに天鵞絨(びろうど)を使ったカーテンが流れ落ちていた。そして、窓の向こうに見えるのは見事に手入れされた、どこまでも広がっているかのような庭園である。そこには、のどかに芝を刈る庭師の姿さえ遠くに小さく見渡せるのだ。そんなディテールが集積するこの部屋は、実に貴族的な趣向という印象を、訪れたゲストに与えるだろう。
メリルは朝からの驚きの連続で、そろそろこういう贅を尽くした、威圧的ですらある光景にも目が馴染んで来てはいたが、部屋に落ち着いて周りを見回し、深い溜め息をついて、世の中には本当にこういう世界があるんだなあと、つくづく呆れる気持ちになっていた。当然、自分が実質的にその代々続いた家柄を継ぐべき、この家の長男であるなどということは彼の意識の中にはカケラすらもない。まさかのことに、この大邸宅や名画の数々、磨き上げられたリムジンや家族の数より遥かに多い使用人に傅かれた生活が、将来的に全て自分のものになるのだなどとは想像もしてみないのがメリルという少年だった。彼にとってそれらはみな、自分の日常とは何の関係もない別世界の他人事でしかないのだ。
そんなことよりも彼が今気になっているのは、祖父と父、そして弟たちとの初の対面の席で、どうしても不思議に思わざるをえなかったことの方だ。それで彼は、部屋に通されてからも何をするでもなくソファにかけて、そのことを考えるともなく考えていた。
どうしてあの弟たちは、あんなに楽しそうに和気あいあいと会話を楽しむなんてことができたんだろう。一番下のデュアンはこれまでもこの家に来たことがあるようだったが、ファーンは自分と同じように父とも初めて顔を合わせたみたいだったし、そもそもこの集まりの主旨からして彼らもこの家で息子として育てられたわけではないことが明らかだ。そんな境遇にこれまで置かれていて、自分たちの存在を今まで知らされていなかった祖父とはともかく、生まれてから長いこと、自分を放ったらかしにしていた無責任な父親と、顔を合わせた途端にこにこと打ち解けることができるなんてメリルには信じられない。
それは確かに、父が画家としてこれほど偉大であるということは、これまで迂闊にも自分が十分認識していなかっただけのことかもしれないし、母の言う通り、あれほどの芸術家ならこんなワガママ勝手で無責任な生き方すら許されて然るべきというのも納得できるような気にさせられる。しかしそれでも、自分はその父の生き方そのものをどうしても肯んじることができないし、後々どうなるにしても、まずはそのことから話し合うべきではないのかという気がして仕方がないのである。それをあの脳天気な弟たち ―
少なくともメリルにはそう見えた ― は、まるで気にしていないようで、そんな話題は露ほども出てこなかったのだ。メリルのような少年には、そのことそのものが一大クエスチョンマークなのである。
そんなことをとりとめもなく考えていたメリルの耳に、ふいにドアをノックする音が聞こえた。
「あ、はい?」
「デュアン坊ちゃまがお見えです。お通ししてもよろしゅうございますか」
執事の声が言うのへ、メリルは反射的に、ええ、どうぞ、と答え、ソファを立ってドアのところまで歩いて行った。
「あの...、お邪魔してもいいですか?」
メリルは廊下で執事に伴われて立っている可愛らしい少年が、父によく似た顔立ちをしていることにこの時初めて気がついた。確かに血筋でゆけば末の弟ということになるのだろうが、どうもその実感が未だにメリルにはない。
「あ...、はい」
何と答えていいか分からず、断る理由もないままに彼はデュアンを部屋に招き入れた。その後ろで執事は一礼すると扉を閉めて下がって行った。
しばし沈黙、という格好になったが、少ししてメリルは、このシチュエーションではとりあえず居間に落ち着いた方がいいのかなと気づき、やっとデュアンをそちらに通してソファにかけるようにすすめた。
「ごめんなさい。お邪魔してしまって」
「そんなことはないけど...」
「ぼく、ちょっとお話してみたくて。あの...」
「え?」
「あの、メリル兄さんって呼んでいいですか?」
ああ、そうか、この子は本当にぼくの弟なんだっけと改めて気づき、実感を伴わないままに、彼はそれでも一応、いいよと答えた。メリルにしてみると、初対面の"他人"の申し出を失礼にならずに断るには十分な理由が見出せなかったからだ。
しかし、デュアンの方はとりあえずは肯定的な答えにほっとしたようで、にっこりして彼を見ている。ところがその後の会話が続かない。どちらかと言えば社交家のデュアンをして続く言葉が出てこないほど、この兄のとっつきにくさはこれまで類を見ない種類のものなのだ。にこにこしている以外に座を保つ方法がないのである。
ファーンは弟と親しくなりたいと思っていることがデュアンにも難なく見てとれたので、いつもの調子で会話に飛び込んでゆくことができた。一方この長兄は、まるっきり自分と話したいとか、親しくなりたいとか、そんなことは考えてもみていないのがありありと分かるのだ。こういう相手の気持ちをどうほぐして会話に持ち込んで行ったらいいのか、それが分かるためには、まだデュアンはあまりにも幼い。
しばらく気まずい空気が流れた後で、しかし、口を開いたのは意外にもメリルの方だった。
「ねえ、...デュアン?」
メリルはこの子の名前は何だっけ、と少し考えてから思い出したらしく、確認するようにそう言った。
「あ、はい」
言ったものの、メリルは先を続けかねている様子だ。デュアンは黙って続きを待っている。その不自然な間を気遣ってか、しばらくしてやっとメリルが言った。
「きみは...、前にもここに来たことがあるんだよね?」
「え、はい。半年くらい前に初めてですけど」
「そう...」
言ってまた口をつぐみ、何をどう言おうか考え考えしている様子のメリルを見ながら、デュアンは兄を差し置いて自分だけ先に父に会ったことがあったのはマズかったのかなと少々不安な気分になっていた。それで気を悪くされているんだったら、快く受け入れてくれないのも無理はないかもしれない。
しかし、メリルの方はそんなことを気にしているわけでは全然なく、ただ、そうするとこの子は既に父との何らかの話合いを経て、今のように彼を受け入れることに決めたんだろうかと考えていたのである。そもそも、そんなことで自分が後回しにされたと思って怒るような狭量なところはメリルにはない。それどころか生来おっとりしていて、彼の母ですら自分の息子のことを"ちょっと普通と感覚がズレている"と感じているほど、この子は世俗的なことに、通り一遍の世俗的な反応を示すタイプの少年ではなかった。
「あの、兄さん」
メリルが黙り込んでしまったので、これは相当、機嫌を損じたのかと思い込んだデュアンは、確かに兄さんが気を悪くするのも当然かも、と一人合点してしまったようだ。それで、このままこちらが黙っていたのでは嫌われたまま終わってしまうんじゃ?
という気がしたらしく、なんとか会話に持って行こうと話しかけた。
「え?」
「あの、ぼくは母とふたりきりなので大家族ってすごく憧れてたんです。だからお父さんだけじゃなく、おじいさまと兄さんが二人もいっぺんに出来るなんてすごく嬉しくて。今日の集まりはとても楽しみにしていたんですよ」
「...そうなの」
メリルとしては、ふうん、そうなのかと思いながらちゃんと答えたつもりなのだが、デュアンからすると彼が振った話のコシをブチ折られたようなそっけなさに聞こえた。ましてや、そのこと自体にはメリルはデュアンの期待していたような興味は全く持っていないようで、従って話が続いてゆかない。それで、最初からはかばかしくゆきそうもなかった会話は、とうとう暗礁に乗り上げてしまった。
デュアンはディナーの前に少しでも兄さんたちと親しくなれたらと思っていたのだが、メリル兄さんに限っては、これは返って失敗だったかしらと不安になり始めている。自分が長兄を差し置く形になっているとはつゆ知らず、半年前に父に会うに至った経緯を説明しておいた方がいいのかなという気もするのだが、言い訳がましくなるのは逆効果かと思ったり、とうとう考えこんで言葉が出てこなくなってしまったようだ。一方、メリルの方はそんなデュアンの心配に気づくヨシもなく、まさか弟がそんなことで固まっているとは思わないものだから、自分の考えの方に気を取られてしまっていた。
自分はいきなり祖父だの弟だの言われてもそうそう親しみを持てるものではないと思うのに、楽しみにしていたということは、この子はそうじゃなかったのかな、とか、自分を長いことほったらかしにしておいた脳天気で不道徳で無責任な父親にどうして反感を抱かずにいられるんだろうか、とか、ぐるぐる、ぐるぐる、あれこれ考えて、何をどう言葉にしたらいいのかまとめるのに時間がかかっていたのだ。
しかし、しばらくしてメリルは、分からないなら聞いてみればいいんだなと結論したようで、やっと再び口を開いた。
「ね、ちょっと、聞いてもいいかな」
「あ、はい、どうぞ」
「きみは、お父さんと半年前に会って、それからいろいろ話し合ったの?」
「え?
話し合うって?」
「だから、本当のお父さんなのに、今までぼくたちを放っておいたこととか、きみとぼくのお母さんが違うこととか、そういうのって普通じゃないじゃないか。なんでそういうことになったのか、ちゃんとお父さんに問い質したのかなと思って」
やっと兄が話しかけてくれてほっとしたのも束の間、この発言は、デュアンには????????なものでしかありえなかった。そもそもの始めから、いや、ディが自分の父と知る遥か以前から、神とも崇拝して来た大芸術家のすることに疑問を持つとか、口を挟むとか、そんな僭越なことをデュアンは考えてみたことすらなかったからだ。ましてや、問い質すだなんて想像を絶するほどとんでもないことである。いったいこの兄は何をズレたことを言っているのかと、今度はそれが信じられなくてデュアンは言葉を失ってしまっている。そうとは知らず、メリルが続けて言っていた。
「だから、お父さんって酷い人だなとか、家族そろって一緒に暮らしたかったなとか、そういうこと、きみは思わなかったの?」
デュアンにとってさっきのに加え、これは全知全能とすら信仰している神サマに異教徒からいちゃもんをつけられたも同然のインパクトをもたらした。彼らの父に限って、そんなふつーのありきたりな生活なんて、デュアンは絶対していて欲しくすらなかったからである。それで、兄がずっと不機嫌そうなのは、どうやらそんなことに拘っているせいらしいと遅ればせながら気づき、その発言にも神聖冒瀆、言語道断と相当かっつんと来たデュアンは、長兄への遠慮もすっかり忘れて言い返していた。
「だって、彼はデュアン・モルガーナなんですよ!
全然似合いませんよ、そんなの」
「似合わないって、でも...」
「ごめんなさい。だけどぼく、もうずっと前からお父さんのファンだから。あんなに凄い絵を描くひとが、そんな普通の生活してるなんて、ぼくはちょっと想像もつかないし。ぼくは彼が本当のお父さんなんだってだけで、すごく嬉しいくらいですけど?」
なんで、兄さんはそう思わないんだと言わんばかりのこの強い反論に、今度はメリルの方が面食らっている。彼にしてみれば、父への自分の反感や疑問は誰でも納得してくれるようなまるっきり常識的なものでしかないと思うのだが、どうやらこの子にはそうではないようだと、はっきり分かったからだ。
ディの絵の本物を見た今となっては、メリルにも少しはこのデュアンの反論は理解できるような気もしたが、だからと言って手放しで父を認める気にもなれていないのは本当だ。彼らの父が偉大な芸術家であることは最初から分かっているし認めてもいる。しかし、問題はメリルからはあまりにワガママにしか見えない彼の生き方なのである。
しかしまあ、それについては母ですら自分と同じ意見ではないのだから、いろいろ見方もあるんだろうととりあえず納得し、メリルは次の疑問を弟に投げかけてみることにした。いくらなんでも、こちらの方は多少の共感は得られるだろうと思ったからだ。
「じゃあその...。お父さんとアリシア・バークレイ博士がとても親しいという話とかは?」
「ステキですよねっ」
その答えにメリルは内心ぶっ飛んで理解不能に陥ってしまい、今度はこっちがすっかり固まっている。デュアンは、彼の兄がどうやら身のほど知らずにも父に否定的な感情を抱いているらしいとやっと悟って、そのことそのものに本能的とも言える反感を覚えたようだ。それでことさら強く、力いっぱい"素敵ですよねっ"と言い切った後で、更にたたみかけるようにして続けた。
「ぼく、母の関係でいろいろなパーティとかにも連れて行ってもらえることがあるんですけど、それでアリシア博士って一度だけお見かけしたことがあるんです。ものすごくキレイな方ですよ。お父さんと一緒にいたら、それはもう本当に絵みたいに素敵だろうなって思うくらい」
メリルにとってはただでさえ常識を逸脱した関係である上、百歩譲って相手が男の子であるということも今時じゃ普通と割り切っても、それでもなお言いたいことは山ほどあるのだ。それをこの弟は手放しで素敵と言い切る、全くその神経が信じられない。これはもう、メリルにとってついてゆけない世界だったが、しかし、デュアンばかりではなく自分の母もそのことについては"アリシア・バークレイ博士からディを奪い取れる女なんて存在しないと思うわ"と言っていたし、もう一人の弟であるファーンも、どう見ても父に反感を抱いているようには見えなかった。そうするともしかして自分よりも彼らの反応の方が"常識的"で、自分は狭量にも取るに足りないつまらないことに拘っているのかという気にすらなってくるのだ。
ディの周りでは一般に、通常の常識は跡形もなく崩壊する。言うなれば、だからこそデュアン・モルガーナは画壇のみならず、広く芸術世界において既に神格化すらされ、熱狂的に崇拝されているのだと言ってもいい。アレクやマーティアを始めとして彼と親しい友人たちはみな、もちろんそんなことは先刻承知でディとつきあっているのだが、メリルはそもそも全く知ってさえいなかったから戸惑うのも無理はなかった。
弟がなんだか自分の言ったことに相当気を悪くしたようで、しかもものすごい剣幕で一も二もなく父の弁護に立ちそうな気配だったので、メリルもさすがにここでこの話題をこれ以上押すのは危険と悟ったらしい。いくらなんでもこんなところでいきなり兄弟げんかを始めたりしたら、父や祖父に何事かと思われるだろうし、そもそも自分が反感を持っているのは父であってこの弟ではないのだ。それで、デュアンの言い分はそれとして聞いておくことにして、あとは当たり障りのないことをひとつふたつ話してから、早々に会見を打ち切った方がいいだろうと判断した。今日はたった半日でもういろんなことがあり過ぎて、何をどう理解したらいいのか分からなくなっているのに、そんな状態で核心的な話題をこれ以上進めたら、とんでもない墓穴を掘りそうな気がしたからだ。メリルには何よりもまず、今日得た様々なデータをじっくりと分析して考える時間が必要だった。
original
text : 2008.7.29.+8.8.+ 8.16.
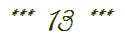
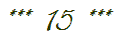
|
