|
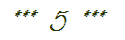
マーティアたちが到着するか、子供たちの居所について連絡が入るかするまで、出来ることは全て手配が済んでいる今、アレクにもディにも特に何もすることはなかった。それで情勢の変化を待ちながら、世間話でもしているより他なかったのだが、最近ではどちらも忙しくてのんびり旧交を温めているヒマもない二人にとって、それはなかなか貴重な時間と言えた。
ディは、こんなふうに自分が一番参っている時に長年の親友が側にいてくれることで、ずいぶん楽になる気がしていたし、それに彼はアレクやマーティアたちの現在の力をよく知っている。彼らが全力を尽くしてデュアンたちを救出しようとしてくれている限り、その成功率にはかなりの確率で確信が持てた。二人が連れ去られた原因そのものがIGDの活動にあるとはいえ、それはディとも決して無関係なものではないし、それどころかマーティアがこの「歴史の軌道修正」というとてつもないゲームを始めるための大元のアイデアを共有していたのはディ自身なのだ。彼と、まだ幼かったマーティアは、かつて歴史、政治、芸術、哲学や概念などについて、実に様々な意見を交わしたものである。
アトリエに腰を落ち着けたディとアレク、それにルイのために、アーネストがコーヒーのおかわりとサンドウィッチを用意してきてくれた。ディが前日から殆ど何も口にしていないのを気遣ってのことだろう。彼はディに「お召し上がりにならないといけませんよ」と珍しく指図がましいことを言ったが、それは殆ど普段と変わらない態度を貫いているこの執事が、内心ではデュアンのことのみならず、長年側で支えてきたこの家の主のことをも深く気に病んでいることを図らずも垣間見せる一言だった。
「うん。この後何がどうなるか分からないんだから、ぶっ倒れてるわけにもいかないしね」
「左様でございますとも」
「ベンソン夫妻は?」
「お部屋にお通しして、お休み頂いております。やはり奥さまの方が特におかげんがよろしくありませんようで、先ほどお薬をお持ちいたしました」
「そう...」
ディが表情を曇らせた横で、その気持ちを代弁するようにアレクが続けた。
「辛いところだな。これはもう、なんとしてもデュアンだけじゃなくそのエヴァという子も一緒に一刻も早く助け出してやらないと」
「同感だね」
言ってディは、さっきからちょっと気になっていたことを尋ねた。
「それはそうとマーティアたちは、ここへは何で?」
「空軍基地からヘリを使うと思うよ。それが一番早いから」
「ああ、じゃあアーネスト、たぶん西の車寄せに降りるだろうから、来たらここへ」
「かしこまりました」
中世から18世紀にかけて、モルガーナ家の本拠はクランドルで最も風光明媚と言われるイレーネ湖畔にあった。当時からの城は現在でもそのまま使われているが、この屋敷は18世紀頃に別邸として建てられたもので、その後、19世紀に入って当時の当主がこちらに本拠を移したという歴史がある。それはおそらく、産業革命を経て一気に盛んになり始めた近代的ビジネスに参入するにあたって、首都からも近いこちらの方に何かと利便性があったからだろう。貴族社会の華やかなりし往時には、ここで夜毎ゴージャスなパーティが催され、昔は馬車、時代が下ると豪華なリムジンが何台も何台も、次から次へと貴顕淑女を乗せて到着し、それらの車は屋敷の西へ流れて主を待つことになっていた。ディが今言った「西の車寄せ」とはそのような目的のために空けられているスペースで、ヘリの一機や二機、軽く着陸できるだけの広さがある。現在ではそんなに大掛かりな集まりが持たれることはめったにないが、それでもディが爵位を継いだ時や、デュアンとファーンをお披露目した時には、往時を偲ばせる豪華さで、沢山の高級車が居並んだものだ。そしてそれはモルガーナ家の権勢未だ衰えずといった光景でもあった。
そうこうするうちに時間が流れ、窓の外がそろそろ暮れなずむ様子になって来たころ、マーティアたちを乗せたヘリがディの言った通り西の車寄せに降りてきた。ローターの巻き起こす風に相変わらずの見事な黒髪を煽られながら降り立ったマーティアは、ディが幼かった頃の彼を描いた「天使」のシリーズの中の一枚を思い起こさせた。それは降臨した天使が足下に形相物凄く息絶えた魔物の屍を踏みつけ、血の滴る剣をその首に突き立てて宙を見据えているという壮絶な光景を描いたものだ。それはまさに現在の彼を予見したような構図だったかもしれないが、ただ、今のマーティアは子供の頃の可愛らしさの代わりに、既に透徹した気品とも言いたいようなものを身につけている。その意味では、ディの絵をすら超えるほど美しいと言ってもいい。
その後から降りてきたアリシアの方は、柔らかなハニー・ブロンドと珍しいすみれ色の瞳こそ相変わらずだが、どこか自分に自信を持ちきれていなかった少年の頃とは全く違っている。もともとマーティアに匹敵する天才児だったのだ。しかし12才になってマーティアの育ての親でもあるマリオ・バークレイ博士に引き取られるまで孤児として育ったせいか、子供の頃の彼は回りに対して非常に懐疑的で、周囲との接点を模索中といった感じだった。ごくごく内輪の親しい人間は別としてなかなか簡単には本心から他人に馴染まず、マーティアの後ろに隠れてばかりいるような、ちょっと控えめで可憐な可愛らしい少年だったものだ。しかし、ディが甘やかし放題にしたことと、最愛のマーティア・メイが始終側にいることとでその環境にすっかり安住している今は、マーティアが半分冗談で「手に負えない」と笑うほど、周囲に対して真っ直ぐに自分を主張し、何があっても不本意には曲がらない生来の強情な性質が遺憾なく発揮されている。そしてそれが今のアリシアの最大の魅力と言えるだろう。
マーティアは上質の黒のウールで作った重いロングコートと、さっきまで強い西日をさえぎるためにかけていたサングラスですっかり黒づくめだが、アリシアの方は控えめにフリルをあしらったシャツにサスペンダー付きの白いパンツ、上にはブルーフォックスのジャケットをひっかけている。白はアリシアのブロンドを最大限に引き立てるので、子供の頃からマリオがよく着せたがった色だ。
二人がエントランスの方へ歩いてゆくと、迎えに出たアーネストが足早にこちらにやってくるのと出くわした。
「マーティアさま、アリシアさま」
「やあ、アーネスト」
「久しぶりだね」
「遠いところを、お疲れになりましたでしょう」
「少しね。トシのせいか最近はこれだけ強行軍で動くとかなりこたえる」
マーティアの冗談にアーネストは笑って、何をおっしゃることやらと言った。一緒にエントランスの方へ歩きながら、マーティアが尋ねている。
「アレクが来てるだろ?」
「はい、午前中にこちらに」
「他に動きはない?」
「全く、ございません」
「調査課の連中、何やってんだろう。しょうがないな、もう丸1日経つのに」
いまいましそうに言ったのはアリシアだ。マーティアがそれを宥めるように答えた。
「知ってるだろ?
このあたりはこの屋敷みたいに広大な私有地の中に建ってる建物が多いからね。市内からこちらに向かって来るルートにはクルマ通りも人通りもごくごく少ないんだ。だからそこからデュアンたちを連れ去った連中の足跡を直接追うのは不可能だと思う。相手は分かっているんだから、後は情報戦にならざるをえないな」
「それはそうかもしれないけど、それならぼくがアークに残って情報分析してる方が早かったかも」
「だから言ったのに、来なくってもいいって。デュアンとは戦争中だろ?」
「それとこれとは別ですよ。生意気なガキだけど、やっぱりちょっと心配じゃない」
「素直に言えば?
けっこう気に入ってるくせに」
アリシアはそれには知らん顔をして答えなかった。
そうこうするうちに屋敷の玄関に着き、アーネストを先に立てて二人はディたちが待っているアトリエの方へ歩いた。
「やっとおいでになりましたね」
二人が入ってゆくとアレクが笑って迎えた。
「こういう際じゃなきゃこんな強行軍、二度とご免こうむりたいよ。マジで疲れた」
「悪いね、うちの息子のために」
ソファに沈みこんだマーティアに、ディが笑って言っている。アリシアはマーティアの座ったソファの背に両肘をついて、そのやりとりに微笑をうかべながら二人を見ていた。
「とんでもございません。こちらこそ平伏して平謝りに謝っても足りないような気分だよ。これにはおれも本当に参った」
「それにしても直接顔を見るのは久しぶりだ。最近は殆どアークにこもりっきりだっただろ」
「うん。まあいろいろと忙しいのと、おれがあまり動き回らない方が平和なのとで、なかなか船を離れる気になれなくてね。だけど、おれやアリシアに直接手が出せないもんだから、この始末だよ。これはこれからしっかり対策を考えないと」
言っているところへ側で携帯端末を使っていたルイが口をはさんだ。
「お話中ですが、子供たちの居所が判明しました」
「どこ?」
それへ飛びつくようにマーティアが尋ね、その場にいる全員がルイの次の答えに耳を澄ませた。
「ミレニア山中の別荘地です。建物も特定出来ました。ブルックス上院議員の持ち物ですが、組織との関係はまだ不明。単に無断使用されているだけかもしれません」
「どうだか分かったもんじゃないな。それについては調査続行、あとは...」
言ってマーティアは判断を仰ぐようにアレクを見た。実行部隊の手配はアレクに任せてあったからだ。後を受けてアレクが続きの指示をルイに伝えた。
「まず、子供たちがいる建物の近くにこちらも使える家がないか当たってくれ。この季節だから周囲の建物は殆ど無人だろう。持ち主との交渉は後でいい。それから別荘地からは離れた所にも適当な場所を確保して、待機してるクリフたちにヘリで向わせる。そこに目立たない車を数台先に回しておいて、そこからはそれで別荘地入りだ。全員私服。我々の動きを敵に悟られたくないからね」
「他は?」
「手配するクルマは車種を一定するな。クリフのことだから間違いはないと思うけど、メンバーは分乗してインターバルを置いて出発。同じルートは取らないように。間違っても、それが兵隊の集団だなんて悟られないようにと言っておいてくれよ」
アレクが言い終わるのを待ってマーティアがルイに尋ねた。
「デュアンたちがいる建物の見取り図は?
まだ入手していないようなら急いで手に入れるように調査課に指示を。手に入ったら、クリフたちのヘリに転送して対策を検討させて欲しい。合流したら一番に彼らの意見を聞きたいからね」
「分かりました。全て、そのように」
それぞれ指示を出し尽くしたことを確認するようにアレクとマーティアは顔を見合わせ、お互い納得して頷くとマーティアが立ち上がって言った。
「じゃあ、行きますか。とにかくミレニア方面に飛んで、まずはクリフたちと合流だな」
トシだの疲れただの言っていたわりに、今ここに着いたばかりのマーティアのフットワークはけっこう軽そうだ。それへアレクが尋ねた。
「ヘリは何で来たの?」
「シコルスキーだよ。場合によっては、アレクとルイを拾ってかなきゃならなくなると思ったからね」
「上出来」
「シコルスキーならまだ一人くらい乗れるだろ」
言ったのはディだ。それへ振り向いたマーティアにディは、ぼくも行くと言ったが、当然のことながら、マーティアは言下に却下した。
「冗談。正直言って、これは実質なぐりこみだよ。
連れてけるわけがないだろう?
子供たちは必ず無事に連れて帰るから、ディはここで待っていてよ」
「そういう状況だからこそだよ。きみたちの力を疑ってるわけじゃない。ただ、こんなところで手を拱いていて、万一のことでもあったら後悔してもしきれない。ぼくの好きなようにさせて欲しい」
またマーティアはアレクと顔を見合わせたが、彼が頷いて見せるので、とりあえずは折れて出ることにした。
「分かったよ。じゃあ、現場までなら同行してもいい。でも、そこでは必ずこっちの指示に従ってくれないか。でないと、デュアンだけじゃなく、ディの命の保証もできないよ」
「いいよ、そうしよう。ここにいるよりは数段マシだ」
子供たちの居場所が判明した以上、一分一秒でも惜しい気分なのは全員同じだったから、話がついたと見るや慌しく動き始めることになった。ディが行くと言い出したことで、アーネストはいつもの彼にも似ず悲壮なほど心配そうな顔をしたが、それは一瞬でひっこめられた。しかしアレクはそれを見て取っていたので、ディが着替えに寝室の方へ歩いて行った後で、アーネストに近づいて小声で言った。
「大丈夫、おれがついてる。デュアンもディも、必ず無事に帰らせるよ」
「アレクさま...」
それだけ気が動転しているのだろう。思わず彼のことを昔と同じにそう呼んだアーネストに微笑し、頷いて見せてからアレクはアトリエから出て行った。マーティアたちには何の準備も必要なかったから、既に部屋を出てヘリに向かっている。ルイはしばらくそこで出された指示を端末を通じて各方面に伝える作業に忙しかったが、それが終わると立ち上がってアーネストに一礼し、部屋を出て行った。暮れかける空がもの淋しく窓の向こうに広がるアトリエに一人で残されて、さすがにアーネストもそれ以上は平静を装っていることが出来なくなってしまったようだ。あまりの不安に頭を抱えて、彼はしばらく一人でそこに立ち尽くしていた。
original text :
2008.2.27.〜2.28.

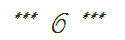
|
![]()