|

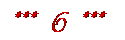
さて、加納家は実は五人家族だ。が、今のところ約一名の居候が加わって六人になっている。
「まや子さん、おはよー」
「まあ、未来ちゃん、やっとお目ざめねー」
庭のバラ園で庭師と一緒に花の手入れをしているまや子さんの所へやって来たのは未来である。みらい、と書いてみきと読むのだが、もうこの家に居ついてずいぶんになるのにそれ以外の素性は全く誰も知らない。
「よくお似合いよ、そのブラウス」
「まや子さんのお見たてがいいからだよ」
「ま、未来ちゃん、お上手」
「そお」
「嬉しいわ、着てくれるんですもの、未来ちゃんは」
「綾さん着てくれないもんね」
「そーなの。もうこのごろ輪をかけて、よ。男の子みたいになっちゃって」
未来の瞳は見事なくらいはっきりしたエメラルド・グリーンで、髪は色も抜かないのにずいぶん明るい茶色のふわふわした巻毛だから、長く伸ばしているのにはどこかペルシアねこめいた風情がある。男の子にしては華奢な肢体とよく回る口は、けれども少女のよう、と言うよりも、あくまで未来らしいのだ。始終軽口をたたいて地に足がついていないようなうわっ調子のくせに、存在感だけはしっかりとある。
「ぼくだって男の子ですよー」
「あらあ。未来ちゃんより綾ちゃんの方が勇ましいわよぉ」
「そーかな」
「そ。本当にどうにかならないものかしら」
「んー、難題だね」
「昔はね、もっとずっとかわいらしかったのよ。ドレスだってよく似合って、マキちゃんと並んだらお人形さんが並んでるみたいだったのに」
「ふうん」
「それが今じゃ...」
まや子さんは深く嘆息して続けた。
「いつもいつもシャツだのジーンズだの、スカートだって丈の短いのしかはかないし、お部屋にいなければ射撃場だし、大きなバイクは乗り回すし」
「そーだね」
「そーなの。修三さんたら綾ちゃんに悪いことばかり教えるんですもの。おまけにこの頃お仕事お仕事ってひとり占めにして連れて回って。あれはね、絶対綾ちゃんをひとり占めしたくって始めたことなのよ。ご自分がお仕事に出かけてらっしゃると、綾ちゃんと会えないものだから。くやしいわ」
「つまんないね、まや子さん」
「そう、つまんないの。マキちゃんだけだと何だか半分しかないみたいなんですもの。・・・でも、ま、未来ちゃんがいるし、今は」
彼女はにっこりして両手一杯にかかえた切ったばかりのバラの香りを嗅いだ。家族の、― 未来でさえも― 誰もが大好きな、未だに少女のように陽光を思わせる笑みだ。屈託がなくて、日本有数の資産家夫人だなどとは知らずに会ったらまず誰も思うまい。深窓のご令嬢でもここまで矯められることなく大輪の、しかも可憐な百合に育つ例などきっとそうはないはずだ。
「未来ちゃん、これ、お部屋に持って行くといいわ。とってもいい香り」
「ありがと、もらってくよ」
「哲(さとし)ちゃんまだ寝てるの」
「うん、寝てる」
「哲ちゃんもよねえ、小さい頃と変わっちゃったの」
「そうなの?」
「そう。小説家なんかになってから余計なのよね。綾ちゃんとだって昔はとっても仲が良かったのに、・・・二人でキャンプなんかにも行ったりして、マキちゃんと三人兄妹みたいだったのよ」
「ふうん」
「なのにこの頃、二人よるとさわるとけんかするんですもの。・・・綾ちゃんのお仕事が忙しくなった頃からね」
まや子さんはしかめっつらをして言っていたが、気を取り直して未来を見ると、朝ごはんは、と尋ねた。
「まだ」
「じゃあ十時のお茶につきあってくださいな。美味しいマフィンを用意してあげる」
「ん」
未来は嬉しそうににっこりした。
加納家の残り一人は綾より三つ年上の哲という。四年前、大学在学中に文芸誌の賞を取り、小説家として作品を発表するようになった。人気もなかなかのものだが、作品もさることながらその家庭的背景も取り沙汰される要因である。
彼は戸籍上では修三氏の遠縁にあたるのだが、子供のころ両親を飛行機事故で亡くし、まだマキも生まれる前に加納家に引き取られた。明るくて陽気な青年だが、健全で誠実に過ぎる性質が何かと綾と衝突するもとにもなる。常識で武装した一見正論は、日本に多くいる小説家たちの例にもれず一般社会で喜ばれるタイプだが、修三さんや綾のような特殊な視野を持った人間とは相容れるのが難しい、と言うより殆ど不可能だった。
「哲ちゃんこの頃お仕事ね、毎晩」
「そう、新しい小説のプロットが出来てきたんだって」
「まあ」
しかし未来はその哲が拾って来た迷い仔猫である。
いろいろな理由があるのだが、哲はあまり女の子に興味がない。かといって特別男の子の方に興味があるわけではないのだが、一応表向きはそういう態度を取っている。未来はなにしろこの容姿と軽さからもわかるように、生来まともな生活の送れる種類の男の子ではない。 事実住む所さえ確かにはなくて、なんとなく面倒を見てくれる誰かのところへころがりこんではふわふわ宙に浮いたような毎日を送っているのだ。
が、もともと一人や二人増えたところで困るうちでもないところへ持って来て、まや子さんときたらなんだろうと側へやって来れば世話してしまうという性質の持ち主である。しかも未来の容姿は彼女の趣味ともいえる「着せ替え人形」にうってつけだった。
綾がなんだかんだと逃げ回る昨今、マキは昼間学校、哲は庭いじりだのチェスだのは相手してくれてもそういう趣味にはまるっきり向かない。そういうわけで未来の受けはことにまや子さんによく、二人は日がな一日のらりくらりと世間話に明け暮れ、お菓子を作ったりお茶を飲んだりショッピングに出かけたりと、ずいぶん仲がいいのである。
prologue original text
: 1996.9.9〜10.15.
revise : 2009.11.11.
revise : 2010.11.29.
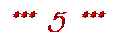
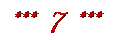
|
![]()