|

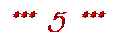
加納家のヘッドクオーターは都内でも最も美しい造形を誇る白亜の摩天楼だ。エントランスには緑が豊かに配されてプロムナードを彩り、重厚な扉の向こうに十階分はぶち抜いてある吹き抜けのアトリウムが広がる。床もレセプションブースも大理石で仕上げ、弧を描いた壁に八基並んだエレヴェーターは古風な時計型のフロアカウンターをその頭上に戴いていた。綾と修三氏はその最上階にある会長室にすでに着いている。この階には三つの続き部屋があって会長室の他は綾と裕介のオフィスだが、どの部屋もインテリアは三人それぞれの好みに合わせてあった。
修三さんのメイン・オフィスにはダークブラウンの絨毯が敷きつめられ、一面のピクチャーウインドウを背景にしてオークの大きな机、そして壁二面にも同じオークのパネルをはめて、そこには膨大な量の資料や本が収められている。その合間に40型の巨大なディスプレイ、ヴィデオの装置とコンピュータの端末が見えるが、それらに囲まれてイタリアの名門、B&Bの大きなソファのセットがゆったりと据えられていた。オフィスと言うよりも、もうすでに立派なサロンである。
しかしこの部屋は白大理石の空間にトップライトを通して陽光のあふれるレセプションを持ち、しかも奥にはソラリウムになった本当のサロンまで続いている。ここにはちょっとした一流ホテル並みのバーが備えられていて、大きな契約が成立した時など取引先を招いて祝杯を上げたり非公式の集まりを持ったりするのに使われる。
遥か足下に夜景を見下ろし天空には冴えた月が現れる夜などに、数百億という単位の契約をまとめて祝杯、というのは、何回やってもやはり気分のいいものだ。
「ゆーすけのやつ遅いね、修三さん」
「もう空港は出ているから、すぐ着くだろう」
修三氏はオークの机の向こうで革椅子に長身を沈めて綾に答えた。彼女はその机の端に浅くかけて、コーヒーを飲みながら言っている。
「裕介のやつ、顔見るひまがなかったから今日になっちゃったけど、言ってやりたいことがあったんだ」
「何?」
「あいつぼくが絶対にものにならないからやめとけってあれほど言っといたプロジェクトを、重役会に押し切られて去年グリーンライト出したじゃない。その結果がいかに惨澹たるものだったか。気が遠くなったもんな、実際」
「まあほどほどにしておいておやり。あんまり怒鳴ると自信なくすから」
「優しいなあ。そんなこと言ってるから甘く育っちゃったんじゃないの、あいつ」
修三さんは微笑を浮かべて綾を見ている。もうすぐ五十に手が届くというのに、全く彼と来たらますます洗練される一方で、年を取るということ自体知らないようだ。
若くして亡くなった彼の母親という人がまずもって絶世とつけても惜しくない美女だったから、彼女ゆずりの容姿は確かに子供の頃こそ気むづかしくて繊細に過ぎる印象があった。しかし生来傲慢不遜と言っていい、人の上に立つために生まれて来たような修三さんの性質は、その類まれな才知とあいまってそれを線の細いものにしなかったのだ。
一方綾は十代の頃の美少女がそのままちょっと大人っぽくなっただけ、みたいな神秘的で小悪魔めいた美貌、それは性別や年齢自体を全く無意味なものにしてしまうようなところがある。だからこの二人がこうして一緒にいる様子は、誰がどこで見かけてもちょっと割りこめない、次元の違う空気に隔てられているかのようだ。父と娘というような尋常な感じではないし、かといって恋人とか愛人とか、ありきたりな様子でもない。
スティーヴはよく彼らのことを神々の血を引いている種族と言う。人間の中に混在していても、その才知も思考も人間のものとは言い難く、それに根ざした外貌も画一的な羊たちとは全く異質、それは野生の獣と言ってもいいくらい自由で鮮やかだ。
それが人間には決して理解できない秘密を二人だけで護り、理解のできない言葉で語り合っているような、冗談を言い合っていても周りにたくさん人がいても、ちょっと目を見交わすだけで本質的なことは何もかも伝わってしまうような不思議な繋がりが二人にはある。それは彼らが共有している、血縁ではなくその精神性に根ざした種族的な記憶によるものと言っていいかもしれない。
綾はまだ裕介のことをぶつぶつ言っていたが、ふいに何か思い出したらしく話題を変えた。
「そうだ。ねえ、昨日アレックも来てたんでしょう」
「ああ」
この三日間、都心のホテル・グリフィンで、日米欧の主要な経済人を集めて修三氏が主宰する財団のコンベンションが行われていたのだ。
「会ったの?」
「会ったよ。そうそう、マキのバースデイ・パーティーに来てくれるってさ」
「ほんと」
「しばらくこっちにいるそうだからね」
「ふうん」
「新しく別邸を買ったと言ってた。スコットランドの方だそうだよ。そのうち中が整ったら招待するから是非来てほしいそうだ」
「楽しみだね、アレックって凝るから」
アレックス・ニコルソンは彼の古い友人で英国に爵位を持つ。修三さんより五つか六つ年は上だが親友と言ってもいいほどのつきあいで、子供の頃から彼の商用旅行について回っていた綾のこともよくかわいがってくれた。今では彼女にとっても親しいと言っていい友人である。
そんな話をしている所へインタ・コムのブザーが鳴った。綾が答える。
「何?」
― 松木さんが戻られました
「通していいよ」
しばらくしてノックの音が聞こえ、裕介が扉を開けて入って来た、のはいいのだが、間髪を入れずに怒鳴りつけたのは綾である。
「松木っ、おまえよくも恥ずかしげもなく帰って来れたもんだな。あれほどぼくが言っといたのに調子のはずれたことやっといてっ、貴様何年この世界でめし食ってるんだ、言ってみろっ」
「綾、待っ・・・」
「やかましい。そんなことでよくでかいツラして会長補佐だなんて言っていられるもんだ。いつまでたっても甘いんだよ、おまえは。二度とやりやがったらただおかないからしっかり覚えとけっ」
綾は勢いでまくしたてまくっておいてから、沈黙のあとほっとひと息ついて続けた。
「あー、すっきりした。言いたくって仕方なかったんだ」
裕介は壁にはりついてあとじさっていたが、その横で開いた扉の側にいた榊原遼多が言った。
「あの、お嬢さ・・・」
まだ秘書課に配属されたばかりの十七才の少年だが、書類の束を抱えている。
「綾でいいと言っているだろう。何回言ったらわかるんだ」
「はい、あの、でも・・・」
「本人がいいと言っている。何だ?」
「あの、先程お待ちになっていたデータが送られて来ましたので、至急お目にかけた方がいいと思いまして・・・」
「ああ、あれ。見せてみろ」
「はい」
そう言って彼は持っていたテレックスを綾に渡したが、彼女はそれにざっと目を通してから遼多を見た。
「これ、今朝来たのか」
「はい」
「やっぱりこの数字、気に入らない・・・」
ふいに綾は修三さんを振り返った。
「時間あるよね。ちょっと秘書課行ってくる。」
彼が頷くと、綾は遼多を連れて部屋を出て行った。とたんに静けさを取り戻した部屋の中で彼女の後ろ姿を見送りながら祐介が言っていた。
「会長」
「ん?」
「他家の教育方針に口を出すのはどうかと考えますが、しかし・・・」
「言いたいことは、よくわかるよ」
「ありがとうございます」
修三さんが同情したような顔で彼を見ると、裕介は態度を崩して泣きついた。
「・・・会長、どーしてっ、あれをあのまま放っとくんです?そりゃ、おれだってしまったとは思ってましたが、いきなりああまで怒鳴らなくたって」
「うん」
「会うたーんびに態度がでかくなって、もう」
「認める」
「しかもいつまでたってもぼく、って・・・。せめてあれだけでも・・・」
殆ど男ばっかりの世界でまだ若い女の子が仕事をしているんだから、とか、それはそれなりにあたしだって苦労しているのよ、とか、裏へ回って泣きごとのひとつも言うなら可愛げがあるかもしれない。しかし加納綾の場合、あれが思っきりの地なのである。かけ値なしの荒っぽい性格が申し分のない美貌と才能とに結びついているんだから始末が悪い。どこにも彼女が好き放題するのを止められる者など有りはしないのだ。
「しかし裕介、あれが綾だからね。仕方ないだろう」
「でも・・・」
「あれが今更女言葉を使ってまや子さんのような態度を取ったら、それこそ気味が悪くないか」
「まあ・・・、確かに」
裕介は少し考えてみて納得した。
「・・・でも、今日はシルクにレースのブラウスなんか着てたし、少しはそういう・・・」
「残念でした」
「え」
「あれはまや子さんとのきわどいかけひきなんだ」
「かけひき?」
「そう。二、三日前の晩ね、まや子さんが今度の重役会は支部のみなさんも見えるんでしょ、と綾に言った」
「はい・・・」
「で、びくっとした綾が、そーだけどお、とか言ってまや子さんの顔色を伺いつつ、そおだなあ、今度はシルクのブラウスなんか着てみよーかなーとか言ってその場は逃げた」
「ええ」
「まや子さんはわくわくして今朝になるまで待ったんだが、綾はブラウスだけシルクにして、・・・それも一番シンプルなやつ。で、あとは毎度おなじみの革のジャケットとパンツでお茶をにごしたというわけ。まや子さんもついこないだのレセプションで綾にサンローランを着せたとこだったから、それ以上強く出られなかったんだ」
加納家の事情をよく知っている祐介は、納得した様子でなるほど、と言った。
「それにあれがぼく、なんて言いだしたのはおまえに責任がある」
「え・・・」
その昔、彼女が十才の頃はまだ、"あたし"と言ってはいたのだ。
実の母親というのがけっこう荒っぽい喋りかたをしていたので、そのあたりは今と変わりがないが、ともかくも一人称はその頃までまだ女の子だった。が、その年、商用旅行につれて行ってもらうことになり、飛行機で待っていた裕介と顔を合わせたのはいいのだが、修三さんが彼に、「綾はね、いずれ私のあとを継いでくれるんだよ」と言ったところへ裕介が悪気はなかったのだが本気にせず、「へえ、綾ちゃん、えらいねえ」とからかってしまったのだ。
以来、である。
そのからかいにかっつんと来た綾は旅行の間中ぼく、と言い続けていた。始めは裕介に対する子供らしい対抗意識だったのだろうが、すぐもとに戻るだろうと思って誰もやめさせなかった。ところがご本人にしてみると性格が性格だけに合致してしまい、以来ずっとぼく、と言い続けている。今では周りの人間すら違和感を感じなくなり、従って言葉遣いは思いっきり男の子なのだ。ただ、綾の場合、日常喋っている言語の80パーセント以上が英語か他の外国語だ。だから彼女にしてみれば、既に日本語の第一人称など、どうでもいいものになっているのかもしれない。
ともあれ、裕介は綾よりゆうに十五は年上なのだが、なにしろ仕事ができるのは彼女の方で、そうなってくるとあの態度のでかさに反論の余地もない。彼だって一般的に言えば十二分に有能と言ってさしつかえないのだが、綾ときては比ではなく、しかも今やしっかり加納修三の跡取り娘なのだ。
とはいうもののこの二人、決して仲が悪いわけではなくて、綾は綾で小さな頃から知っているし、それなりにゆーすけ、ゆーすけ、と頼りにしている部分もある。し、裕介の方は本当のところ彼女のことがとても好きなのだ。だというのに子供の頃はまだあんなにかわいかったのに、と思う間もなく、あれよあれよと言う間にあの態度である。裕介自信もよく知っているように、この恋は実りそうもない。
昨今の綾は今日のように革のスーツにシルクのブラウスというヴェルサーチの組み合わせでさえごくごくたまにしか着なくて、アクセサリーだって一切なし。大体ここ数年、何の変哲もないコットンのシャツに洗いざらしたおしたジーンズなんてのが一番多く、もちろんオフィスにいてもその延長だ。スカートもはくにははくが足にまとわりつくのが大キライだから思いっきりたけの短い革素材のスカートなんかになってしまう。こういう格好をしていると、もろにすんなり伸びた美しい足の線なんかが目立ってしまうのだが、ご本人はまるっきり気にしていない。大体が、自分が人目から見て美しいのだというような認識がてんでないのである。
子供の頃から可愛いとかキレイというのは綾の前では禁句で、言っていいのはまや子夫人くらい。他から言われると賞賛どころか侮辱されているとさえ感じてしまうらしい。そんなわけだから、例えば裕介など屋敷に遊びに行って射撃場でこういう格好の彼女がライフルなんか持って立っていたりすると、どきっとしてしまう。修三さんと違ってどちらかと言えば積極的に女の子にかまうより仕事をしている方が好きだった裕介には、そういう方面の免疫が未だに十分ではない。もちろん彼だって気さくで優しい人柄がけっこう女性に受けていて、恋人だって過去に何人もいた。けれども綾という女の子は何をしていてもどこにいても鮮烈な印象があるくらいずば抜けて美しく、しかもご本人は無頓着だから裕介など特に目を奪われて唖然としてしまうのだ。
しかしその彼女もまや子さんにだけは頭が上がらず、どんなに逃げても三度に一度は例えばパーティーなどにひきずり出されて思いきり着飾らせられたりする。綾にとって、まや子さんの泣き落としほど恐いものはないと言ってもいい。
ちなみに綾は服を持っていないわけではなくて、子供の頃から今に至るまでドレッシングルームの壁二面がワードローヴとして設けられている。ことに最近では掛けてあるのはクチュールの逸品ばかりだ。が、これは全部まや子さんの趣味で、ショーのシーズンになると嬉々としてパリ、ミラノあたりへ出かけて行き、これは綾ちゃんの、こっちはマキちゃんの、という具合で際限のない浪費をやってくるのだ。ことに綾の場合ほとんど全てが無駄以外の何者でもない。そんな綾の三大趣味というと、仕事と射撃とマキの世話。哲あたりに変人扱いされるゆえんでもある。
「まあ確かに実際・・・」
裕介が妙にしんみりと言っていた。
「ああいう綾の方がおれにとってはまだしも、なんですけどね」
「そう?」
「ええ。ときどき、・・・まるっきりあきらめきったような・・・、厭世的ってのかな、そういう目でおれのこと見て、なんにも言わずに行っちまうことなんかがあって。・・・そういうときの綾はなんだか全く知らない別人のように思えてしまって。・・・不思議とね、会長。そういう時に貴方と綾は本当の親子じゃないかとさえ思ってしまうんです。・・・そうじゃないのはおれが一番よく知ってるはずなのに」
「裕介」
「はい?」
「私はおまえのことがとっても好きだよ」
「え・・・」
「綾も、だ」
「何です、突然」
「覚えておいて欲しいんだ。・・・例えそういう時でもね、私も綾も裕介のことが好きなんだってことだけは、さ」
彼はどこか淋しそうな微笑を浮かべてそう言ったが、次の瞬間にはもうもとの加納修三に戻っていた。裕介がその意図を問い返す間もなく彼は椅子から立つと、時間だな、行こうか、と言った。
prologue original text
: 1996.9.9〜10.15.
revise : 2009.6.13.
revise : 2010.11.29.

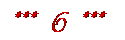
|
![]()