|

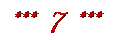
今日の重役会は年に数回行われる御前会議のうちのひとつで、世界中に散っている支局の役員が約四分の一は集まる。
先代にしてもそうだったが、修三氏の方針は有能なトップに各企業の運営はほぼ一任してしまい、それが問題なく動いている限り殆ど口を出すことはない。もちろんそれも任せている相手に信頼が置けなければ不可能なわけで、その人選の基準は当然のことながらとても厳しい。企業という集団も決してそれ自体が不変な存在ではないから、生き物のように新陳代謝を必要とするが、それを構成する最も小さな単位は言うまでもなく人間であり、その全体を決定するのもやはり個というディテールに他ならない。企業が健やかに存続してゆくためには、だからこそ人材という要素をお座なりにしておくことはできないのである。しかも、加納家の麾下に集まっているような大きなグループ企業体ともなると、その全体を特徴づける確固とした企業哲学があり、あらゆる面でそれは決定の基準として存在する。人選においてもそれは最も強く反映されていて、日本の企業には珍しい実力第一主義と言われ、それもあって各方面の役員も日本以外の国籍を持つ人が大変多いのである。
その文化的色彩を決定づける企業哲学は一言で言えば徹底した個人主義だが、すでに長い歴史を持つ日本有数の企業体であるにもかかわらず創造性と柔軟性に富み、日本の一企業というよりも世界的な評価を得ている理由はこの一点にあると言っても過言ではない。そしてそれは修三氏と綾の信条でもある。加納修三という男は生来、無能ということを蛇蠍の如く嫌うのだが、そのうえ二人とも企業の運営を単なる経済活動とは考えていないから、この点にかけては本当に徹底している。二人にとっての最大の知的興味はその哲学の有効性をシュミレートすることにあると言ってもいいからだ。
ともあれ日本という国は特に高度成長期を経たあと実力を育てることを社会的に怠って来たが、学歴社会などというものは世界経済圏の激烈な胎動とともにすでに崩れ去った竹細工の神話でしかない。加納家麾下の企業では昔からそんなものは一切通用しないし、だからこそ現在があると言ってもいいくらいなのだ。ここでは実力以外に有効なものはない。
綾は確かに日本有数の企業体のオーナーであり著名な経済人である加納修三の娘だ。しかし彼女が今ここでこうして六十名からの参会者を相手に方針の決定や決済に絶大な発言権を持っているのは、誰一人として綾をお嬢様だなどとは思っていないからに他ならない。
経済学、哲学、心理学など多岐の分野に渡って、博士号でさえ右から左に取れるほどの論文をいくつも書き、多くの研究所から誘われるほどの鉄壁の論理性を持ちながら、それでいてその論理に囚われない柔軟性が彼女にはある。そうした資質とこの十数年に渡る実績があるから周囲の誰もが綾を尊重するのだが、同時に綾も自分たちの部下に大きな信頼を置いている。逆に言えば、置けないような人間にどんな瑣末な末端でも任せておくことはできない。
修三氏にとっては彼が長い間かけて創り上げて来たこの帝国をそのまま変わることなく受け継いでくれる存在は綾しかいないし、それはとても重要なことだ。何故なら徹底した個人主義が概念の消去に対して有効であるかどうか、それは彼の代だけで実験結果の出ることではないから、現在のシステム自体が現状のまま、もしくはその方向性を保って発展しながら存続することが何よりも必要なことだからである。
文明という構築物はその構造の基底部に必ず哲学を必要とする。しかし民主主義も含めた殆ど全ての既存哲学は、ひとつを除いて次代の文明を支えるだけの強度を持たない。二人にとって彼らの統治下にある企業体は、そのミニアチュアであり実験場でもあるのだ。
*****
翌日綾はヨーロッパに飛び、いくつかの会議に出席して、事のついでに新しい工場の視察をすませ、東京に戻ったのはマキと約束していた土曜の午後ぎりぎりの所だった。大喜びしたマキは発表会でも演目のシンデレラ姫のヒロインを見事に踊り、綾に褒められるとごほうびにドライヴね、とちゃっかりおねだりして来た。
その夜は家族五人とおまけの未来も一緒にホテル・グリフィンにあるル・カトルで最高のディナーを楽しみ、とっておきのドン・ペリニオンを開けた。グリフィンは二十年近くまえ加納家のホテル部門で手がけた都内きっての超一流ホテルで、日本のみならず各国の王侯貴族、政治家や富豪、著名人の用に供するために建てられたものだから完全なメンバーシップ制だ。百室に満たない全室がスイートルームのみ、しかもこの天文学的な地価の都心にあって広大な庭園に囲まれている。
ル・カトルはその中でもこの二十年近く伝説的な存在のフレンチ・レストランで、シェフには十数年に渡ってフランス各地の三つ星で修行したと言われる田原
惣一郎を戴く。フランス料理まがいの西洋風料理しか出せない日本のホテル・レストランの中にあって、別格のオリジナリティを誇っているのも無理はない話だ。修三氏も綾もことにフランス料理にかけては全く目がなくて、ル・カトルは言ってみれば殆ど趣味で経営しているようなものである。逆に言えば、だからこそここを訪れるゲストからの評判もとても良いのだろう。
料理もワインも最高なのに加えて家族みんなでお出かけできるなどというのはめったにないことだったから、中でもマキやまや子さんのはしゃぎようと言ったらなかった。哲も綾にはからかい半分でにくまれ口をきいていたが、もとよりそれも彼女のことが好きだからに他ならないし、未来は未来ですっかりマキと双子の兄妹に見えるくらい仲がいい。だから、それが彼らにとって家族だけの最後の晩餐の夜になるなどとは、誰ひとり思ってみることさえ不可能だった。
prologue original text
: 1996.9.9〜10.15.
revise : 2009.11.11.
revise : 2010.11.29.
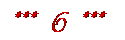
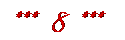
|
![]()