|

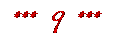
早朝のまだ涼しい空気が開いた窓から流れこんでくる。
綾はレースのカーテンが掛かったフランス窓の側で壁にもたれて靄がゆっくりと引いてゆくのを眺めていた。純白のドレッシング・ガウンに包まれた華奢な肢体は少女らしくしなやかで、絹のような光沢を秘めた肌も黒髪も、この黒曜石の瞳がなかったら人形に見えかねないほど完璧なコントラストで仕上がっている。
以前にも一度こんなふうに同じ思いで夜が明けてゆくのを綾は眺めていたことがある。絶対に続くはずのない至福と生涯消えることのない罪の意識。それを忘れていられたこと自体が錯覚だったのかと思えるくらい、彼女ははっきりと四年前の朝のことを思い出していた。終わる以外になかった恋、それがまだ自分の中で終わっていないとするなら、ウォルターに魅かれること自体が救いようのない間違いなのかもしれない。
綾は深いため息をついて過去の亡霊を振り払い、ベッドに戻った。すべて白で統一された夢のような空間に、ベッドのブラスだけが光沢を添えている。天井からはチュールのモスキート・ネットが天蓋から流れ落ちるようにしてクイン・サイズの大きなベッドを飾っていた。綾はベッドに腰かけるとまだよく眠っているウォルターを微笑して眺めている。
初めてステージを見た時も、RMCのヘッドクオーターで会った時も、それにここへ来て顔を合わせてからも、彼はあの冴えないめがねをかけっ放しで、ブロンドの巻き毛もいい加減に束ねていたから、綾は殆ど気にも止めていなかったことに今になって改めて驚いている。
― そりゃ確かに何人もガールフレンドがいたとしてもこれは不思議じゃない。これならハリウッドでもブロードウエイでも王子様で通用するよ、と綾はあきれていた。ドリーが言っていた"ルックスだけでも売れるのに"、という言葉がふいに頭をかすめて、綾は笑うと彼の耳の側に唇を近づけた。
「ウォルター、起きて」
「・・・・・」
「起きてよ」
それでも彼が起きないと、綾はため息をついて乱暴に大声を出した。
「起きろってば。ひとが優しく起こしてやってるうちに・・・」
彼女が言い終わらないうちにウォルターはぱっちり目を開いてにっこり笑った。
「あ、この、起きてたくせに」
「だってきみがあんまりかわいい声で起こしてくれるから」
「・・・・・」
「もう一回聞きたいと思ったんだけど」
「意地の悪いやつ、きらい」
「好きな子には意地が悪くなるんだ、ぼくって」
「ふうん」
「何?」
「別に。・・・ただ、言い馴れたセリフだなあと思って」
「まさか」
「信じられない」
「きみこそ自分から迫った経験がないとかなんとか言っといて」
「言ったっけ」
「言ったよ」
綾はしばらく首を傾げていたが、ふいに微笑してウォルターを見ると頬にキスした。
「じゃあ引き分けってことにしておいてあげよう」
「わからなくなって来た」
「何が?」
「綾が」
「どうして」
「ダンの話じゃおてんばのじゃじゃ馬娘で、並みの男なんか近くにも寄せないって聞いたのに」
「並じゃなければいいんだよ」
綾は笑って彼に寄り添うと今度は唇を重ねてから、おなかすかない?と尋ねた。
「そういえば・・・」
「夕食もパスしちゃったもんな。ここ、ろくに食べるものも置いてないし」
「何時?」
「まだ五時前」
「・・・お城に戻る?」
「んー、そうだなあ。・・・今戻れば昨日帰らなかったってばれないで済むけど」
綾が考えているとウォルターが言った。
「ね、綾」
「え」
「内緒にしとく方がいいの、やっぱり、これは」
綾は少し考えてから、別にどっちでも、と答えた。
「言う必要もないけど、ばれて困るってものでもなし。ダンのやつあれでけっこうカンがいいいから。・・・でもウォルターは困るかな」
「どうして。ぼくは・・・」
「デヴュー前だもん」
「そんなのどうだっていいよ。ぼくは歌を歌うのが仕事で、女の子に騒がれたいわけじゃないんだから」
「なるほど」
「何が」
「ダンの言ってた通りだと思って」
「・・・どう言われてたか見当くらいつくよ、音楽ばかで間がぬけてる」
綾は笑ってつけ加えた。
「でも一旦言いだすとテコでも動かない時があるって」
「まあね、性格だから」
「そういうとこが好き」
それからまた繰り返し唇を重ねている間に時間のことも食事のこともどうでも良くなってしまい、結局二人が城に戻ったのはすっかり陽が中天に登ってしまってからだった。朝からの録音の予定には思う存分遅れていてダンはおかんむりのご様子だったが、先に別のパートを録り始めていた。綾もウォルターもとりあえずそらっとぼけておいたものの、それでばれないわけがない。
夕方になって綾が一人でお茶を飲んでいると、録音が一段落したらしいダンが意地の悪い笑顔を浮かべてサロンに入って来て、ご一緒させて頂いてよろしいでしょうか、とバカ丁寧に言った。
「どうぞ、ご遠慮なく」
言って綾は手もとの小さなベルを鳴らしてフランソワを呼ぶと、ダンにもお茶を持って来るように命じ、あとは知らん顔をして雑誌を広げている。
「ひめー」
「んー?」
「そういえば昨日はお目にかかりませんでしたねえ」
「知ってるだろ、遠乗り言ってたもん」
「夕食もご一緒できなくて。昨日の鴨は絶品だったのになあ、残念」
「そりゃよかった。シェフに言っとくよ、喜ぶから」
「姫ってば」
綾はやっと見ていた雑誌から顔を上げてダンを見た。
「何?」
「抜群なんだよな、今日のウォルターの歌」
「へえ、ま、そうじゃなきゃバックアップのやりがいないけど」
「お言葉はそれだけ?」
「言いたいことがあるんなら言えば?」
「別にー」
「持って回んなよ。どうせバレてるってわかってるから、ぼくだって」
「開き直りましたね」
「別に。それで何かおっしゃりたいことは」
「いや。たださ、ちょっと意外だったもんだから」
「そう?」
「あいつが姫のこと気にしてるのは知ってたけど、まさか姫君の方で相手にするなんてね」
「まあ、そういうこともたまにはあります」
「どういう心境の変化なのかな、と思ったんだよ。ま、好奇心。気にしないでくれ」
フランソワがウエッジウッドのセットを運んで来てダンのカップにサーヴしてくれてから下がると綾が言った。
「ね、ダン」
「ん?」
「どうなの、ウォルター。真面目な話、いい作品になると思ってる?今の仕事」
「姫はどう思うんだ」
「ぼくは門外漢だからね。プロデューサーとしちゃ、あんたは一流だし、いちおう」
「一応だけ余計だよ。ま、正直言ってこれほどいいと思ってなかったってとこかな。良かったよ、ほんと。あいつをつまんないポップアイドルみたいにしなくてすんで。この所、業界中全域に渡ってちょっと低迷気味だったし、うまくすれば相当いい結果出るだろうね。プロモーション・ヴィデオがあたりまえになって来たせいで、みばばっかり良くて聞けたもんじゃねーっての多いし。ウォルターの歌はほんと、聞かせるからな」
綾は満足そうに頷いている。
「予定通り仕上がりそう?」
「予定より早いよ。はっきり言ってとっくにここで予定してた分なんて録り終えてるし、今はだめ押しでやってるみたいなもんだから。ただね、今一番スタッフも乗っちゃってるから、ウォルターが録りたいだけ録らしてやろうと思って。ストックなんていくらあったって悪いもんじゃないし、こう録るもの録るものずば抜けていいとさ、なんか恐いくらいだよ。ファースト用に十曲選ぶの悩みそう」
「ベタ褒めだね、それ」
「そうじゃなくて姫にまで頼むもんか。おれはね、あいつの歌に惚れてるんですよ」
綾は頷いていたがふいに深いため息をついて言った。
「・・・羨ましい話だ。アメリカの音楽業界っていうのは」
「なんで」
「演る方もスタッフも本気で音楽やってるから。層も厚いし幅も広い。イギリスはまた別の意味ですごいけどね」
「日本でロックバンドなんて呼べるしろもの、ルイス・キャロルくらいしかないって言ってたな」
「そういうこと。ま、キャロルのリーダーの市原 真摘(まつみ)だって歌はボブ・ウィルソンに教わったって言うんだから、結局根はアメリカなんだけどね」
「ボブ・ウィルソンって、あのニューヨークの?」
「そう。クラブシーンの帝王、不世出の名ピアニスト、ヴォーカルもすばらしいし。RMCも何回もレコード出させようとしてアプローチしてるけど、頑固なおじさんでね」
「なるほどなあ・・・」
「日本の芸能界は所詮ショウ・ビジネスと言えるほどのものですらない。もとがテキ屋、見世物小屋の類だからね。テレビの発達で派手に見えてるだけ。何だっていいのさ、金さえ稼げれば。それが世界の市場で通用しない理由。最近じゃ音だけはうまく作って洋楽ぽいけど、魂入ってないからさ、うすっぺらで雑で、それこそ聞けたもんじゃない」
「日本でレコード会社やる気ないの」
「ないわけじゃないけどね、勇気がないの。あまりに壊滅的だから」
「めずらしく弱腰ですね」
「問題は客の方だからだよ。歌謡曲とロックの区別もつかない。英語わかんないんだから当然だけどね。ろくな評論家いないし。けばけばしく飾りたててバカでかい音出してりゃロックだと思ってやがる。あれ相手に商売する勇気なんかぼくにはないよ。そんなものに投資するくらいならアメリカやヨーロッパにテコ入れする方がよっぽど面白い。それに洋楽のルートは確立されてるから向こうで出せば自然と国内に入ってくるしね」
「そういえばキャロルもRMCのアーティストだったな」
「そうだよ。もともと身内みたいなもんだからね。ぼくが口説いたの。あいつらミュージシャンになる気なかったからてこずったけど。友達がね、うまいこと言いくるめてくれて、おかげで契約してくれました」
綾はにっこりして続けた。
「こういう仕事は道楽みたいなもんだからほどほどにしとかなくちゃいけないんだけど、面白いんだよねー、こっちがいいと思ったものが受けたりすると」
「そりゃ、そうだろうな」
「ま、期待しまくってるから。・・・あ、そうだ、じゃあそろそろ予定通りってことでプロモーションの話とかも進めていいのかな」
「いいと思うよ。ドリーとも話してたんだけど、これは久しぶりに大きな仕事になりそうだし」
「この際プラザかウォルドルフアストリアででも大々的に人集めてあおっちゃおうかと思ってるんだけど」
「そりゃすごい」
「ウォルターにはまだ内緒ね。プレッシャーかけると悪いから」
「おー、姫とも思えない優しいお言葉」
「うるさいぞ」
「ま、ご期待に添えるよう、スタッフ一同がんばります」
「よろしい。・・・どうせ一度デヴューしたら当分ツアーだなんだって休むひまないと思うし。ストック録っておくのっていいかもしれないね。バハマの方も使うだろ」
「姫さえ良ければね」
「もちろん。約束したじゃない。どうぞ夏の間思う存分お仕事してください」
ダンは嬉しそうに頷いていた。
*****
それから綾はニ、三日のはずだった休暇の予定を電話とファクスでごまかして、二週間近く引き伸ばしていたが、それもなんとなくウォルターのデヴュー・アルバムとなる作品が出来上がってゆく過程と、ウォルターの側から離れ難いからに他ならなかった。ウォルターはウォルターで完全に舞い上がっていて、ダンにからかわれてもからかった方が拍子抜けするくらい機嫌が良い。もちろん録音は文句なしの仕上がりだ。
綾は十五日目の朝、東京での重役会にぎりぎり間に合う所でパリを発ったが、内心ここしばらくのサボタージュが修三さんにばれるとやばいかな、と心配しないでもなかった。
十七才のバースデイ・パーティで非公式とはいえ綾が跡を継ぐことを彼の口から公表されていたから、本当なら一日でもさぼっていられるような状況ではないのだ。けれどもそれを思ってみてさえ、バハマに寄れるだけの時間をどうやって作ろうか、と既に考え始めている自分に綾は複雑な気分だった。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.9.10.
revise : 2010.11.28.
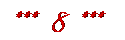
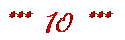
|
![]()