|

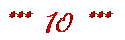
八月に入ってウォルターたちはバハマに移ったが、スタジオと加納家のヴィラがあまり離れていないから、そこに滞在することになっていた。パリ郊外の緑に囲まれたシャトーの後で、今度は四方に海を臨む光景が広がる丘の上のヴィラは見晴らしもよく、大きいと言ってもパリの家ほどではないのでもっとずっとくつろげそうだった。
鍛え上げられた錬鉄を細かな格子細工に仕上げた門は広く間隔を空けて配置されたコリント式コラム四本の門柱に支えられ、敷地の周囲には純白のバラスターが巡らされている。中世の城よりもずっとモダンで、夏の陽光を思う存分楽しめそうな開放的な空気に包まれていたが、ここにも腕のいい庭師がいるのか豊かな緑と鮮やかな花々が視界のどこにもあふれていた。
部屋の数は少なくて全部数えても八つ、けれどもどのスイートも手のこんだインテリアで飾られていて、それぞれのバスルームは大理石やオニキスで仕上げられている。そしてドリーが言っていたように、海を見晴らすテラスに設けられた半円形のプールがまたすばらしい。日の暮れともなるとそのテラスの端に立てられた高い四本のコラムの頂点にランタンで灯火をともし、その向こうに雄大な海を控えて暮れゆく空の燃えるような色彩の饗宴を楽しむことができる。もうひとつのプールは建物の反対側に位置しマスターベッドルームのテラスと続いているが、ユニークなのはその水が部屋にまで引き入れられていることだ。
ウォルターたちが着いてから二、三日してやっと綾はそのヴィラに顔を出した。ただでさえ忙しいところへ持って来て、マキも夏休みなものだから一緒にどこかへ行きたいとねだられて、ごまかすのが大変だったのだ。
けれどもその年の夏だけは綾は妹ではなくてウォルターと、彼のデヴュー・アルバムが出来てゆくのを側で眺めながら過ごしたかった。たぶん綾にはウォルターとのことがそう長く続かないことが心のどこかで分かっていたのかもしれない。ましてや彼がデヴューして成功すれば、そう不用意に会うわけにもゆかなくなってしまうだろう。ウォルターはともかく、綾の方が既にプレスに目をつけられていることは言うまでもない。
*****
プールサイドのサン・デッキで、日が暮れてゆくのを眺めながら綾が煙草をふかしていると、ウォルターが冷たいトロピカル・カクテルのグラスを持って来てくれた。
彼女は珍しく柔らかい光沢のある白いシルクのシンプルなサンドレスを着ていて、喋らなければ本当にヴィナスでもアルテミスでも言いすぎではないくらい美しい。背景のせいもあるのか神話を描いた絵のように神秘的だ。けれどもそういう綾を見るたびにウォルターは必要以上に近づくのが瀆神的な気さえして、気後れするのも事実だ。
あれだけ普段はおてんばとか野生児とか言うのがぴったりなくらい荒っぽくて元気で、外国語を使っているとはとても思えないスラングの多い達者な米語を話すこともあって彼もすっかり忘れているのだが、こういう時は折にふれて言葉がなくなる。単に育ちのいいお姫さまだからというだけでは済まない、絶対的な気品とでも言えばいいのか、それも綾のミステリーには違いなかった。
「あ、嬉しい。丁度飲みたいな、と思ってたんだ」
煙草を灰皿に消して綾が言ったので、ウォルターはなんとなくほっとして彼女にフルーツで飾った大きなグラスを渡すと、綾のいるデッキ・チェアの横に腰を降ろした。彼の方は何の変哲もない、いつものシャツにジーンズで、ついさっきまで仕事をしていたから眼がねもかけたままだ。綾は少し飲んでからグラスを側のテーブルに置き、ウォルターの頬にキスして、どうしたの、元気ないね、と言った。
「そんなことないよ」
「録音の方どうなの」
「絶好調。そろそろCD用の曲をどれにするかもめるくらい」
「そのわりには浮かなそうな顔してる」
ウォルターは笑って綾を見るとキスを交わしてから、長いこときみと会えなかったから、と囁いた。綾は微笑してほんとかな、と首を傾げた。
「ほんと。・・・忙しかったの」
「忙しいなんてもんじゃなかったね。パリでさぼってた分と、ここに来る時間を作る分と、夏の休暇を家族と過ごす約束をごまかすのと、・・・大変だったんだから」
「ぼくに会いたかった?」
「会いたくなくてそんな苦労すると思う」
もう一度くちづけを交わしてからウォルターが尋ねた。
「どのくらいここにいられるのかな」
「八月はこっちで過ごすつもり。・・・時々は出かけるけどね」
「最高」
「ここは気にいった?」
「すばらしいよ。スタジオもいいし。絶対いい作品にする。だから・・・」
「だから?」
「綾、もしね・・・」
「ん・・・」
「もし今度の仕事が成功してぼくがちゃんと認められたら・・・」
「うん」
しかし、ウェルターは先を続けられなかった。
「どうしたの?」
綾に促されても彼は黙っていたが、やがて小さなため息をついて、いい、その時のことにする、と言葉を濁した。
「なに、それ。気になるよ」
「今はいいよ。きっとまだ言わない方が」
ウォルターは微笑んだが、綾は不思議そうな顔をしているだけだ。まさか今自分がプロポーズされかかったと気づくには、綾もまだ子供でしかなかった。
ともあれ綾が夏の休暇をわざわざここで過ごすことにしたのがウォルターのせいだということは、ダンばかりではなく回りの連中にも既にバレている。だから隠す必要もなかったし、綾はウォルターがスタジオに行っている間に仕事を済ませ、時おりは出かけることもあったが、それ以外では殆どの夜を一緒に過ごしていた。
一か月も、しかもいつもならマキやまや子さんと過ごしているはずの夏休みを、仕事までさぼってどこで何をしているか修三さんにバレないわけはないとわかってはいる。けれどもそれもどうでもいいくらい綾はウォルターの側にいたかった。一度好きになると見境がなくなるのは以前のこともあるから自分でよく知っている綾だったが、それもあって長いこと誰も必要以上には近づけなかったのかもしれない。そしてウォルターの方もそれと同じくらい思いこみの激しい性質だったから、いい加減なところで終わるわけがなかった。
パリからこっちウォルターの書く曲と言ったらほぼすべてがラヴ・ソングだったが、それがまたどれも憎ったらしいくらい出来が良いことを、ダンなどはかえって心配していたほどだ。それらの曲は全部綾がいるから書けるんだろうということくらいダンには一目瞭然だったからである。しかもいくらお祭り好きの脳天気おじさんでも、四十にもなれば彼にだって綾とウォルターが性質以外では全くつりあいが取れていないことくらいわかる。もちろんウォルターはそのくらい自分でわかっているはずだったが、綾の方がわかっていないのも始末が悪い。二人の将来の破綻がウォルターの音楽に影響しないとも限らないのが彼には一番心配だった。
けれども当のご本人たちは、どちらも恋に狂っていてそんなことはどうでも良いらしく、ウォルターは折りにふれて綾に歌いかたを教えたり、彼女の音域に合わせて曲を書いたり、綾は綾でヨットやテニスに彼を誘い出すのに夢中だった。ベンやドリーや他のスタッフも加わって、セッションやクルーザー、それに夜ごと招いたり招かれたりのパーティーに明け暮れながらも仕事の方は順調だったから、ダンはそれが終わりに近づくまで何も口出し出来ないでいた。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.9.10.
revise : 2010.11.29.
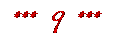

|
![]()