|

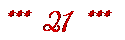
そして早くも五年が過ぎて今では綾も二十三才、あの頃のウォルターと変わらない年にまでなっていた。
ウォルターの方は留まることを知らないような成功を続けて米ロックシーンにおいて今では不可欠なビッグネームだ。現在まで発表した五枚のアルバムはどれも軽くミリオンセラーを記録し、スタジアム級のコンサートでも間に合わないくらいの人気がある。
綾がスティーヴと出かけた今夜のコンサートも演奏が始まるが早いか総立ちの大歓声で沸きかえっていた。その勢いのまま最後まで乗りまくり、アンコールの声援の中にはもちろん綾やスティーヴの声も混じっている。コンサートは大成功のうちに終幕を迎えようとしていたが、しかし、ウォルターは思う存分機嫌が悪かった。
「おいっ、ウォルター、もういい加減、客帰してやれよっ、五回目だぞ、アンコール」
「やだっ。今日はまだ、まだ、歌うんだっ」
長年コンサート・ツアーにつきあってくれているベーシストのグレン・ウィリスが止めようとするのにウォルターは耳も貸さない。
「狂ったんじゃないの。いくら昔の恋人が男連れて来たからって、そんなヤケになることないだろー」
「う、る、さいっ、ぼくは歌うと言ったら歌うんだっ。一人でも行くからね」
しょーがねーな、と思いながらもウォルターが言うのでは誰も止められない。グレンは他のメンバーに合図してウォルターの後を追った。予定された終演の時間なんか、とおの昔に過ぎ去っている。それでも帰りたがらない客に帰りたがらないウォルターでは誰にもどうしようもないのだ。結局のところ今やウォルターが主役なのである。
けれどもそうしながら今夜の彼は歌でも歌っていなければやりきれないような最低の気分だった。
― 綾と別れたのはもう五年も前だ。少なくとももう彼女はぼくの恋人じゃない。会うことはよくあっても、食事して、お話して、それじゃあ今夜はこのへんで、というおつきあいだ。畜生、だからってぼくが忘れられるとでも思ってるのか。生まれて初めて一生側にいてほしいと思った女の子に、プロポーズひとつ出来なかった情けない気持ちなんか絶対彼女にはわからない。あれからだってまだチャンスはあると思っていた。
次のツアーが成功したら、セカンド・アルバムが好評だったら、ワールド・ツアーが実現したら、今度やる映画音楽でその作品がアカデミー賞取ったら、サード・アルバムが百万枚を突破したら、その時はきっとって、それでぼくはこの五年間を生き抜いて来たんだぞっ。ところが目標はどれも簡単に実現したっていうのにハッピーエンドにはならない。綾は絶対、帰って来ない ―
コンサートが始まる前、綾はスティーヴと一緒にバックステージに花を届けた。そしてスティーヴ・ロジャースを紹介された時、ウォルターにはどうして自分と綾があれで終わらなければならなかったのか、やっと理解できたように思えたのだ。もちろん綾はスティーヴのことを友達としか紹介しなかった。新しい恋人だと言われたわけではないし、そういう風に見えたわけでもない。ただウォルターには、はっきりとスティーヴが綾と同じ世界にいる男だと直感的に分かったのである。
― ぼくが知らない綾を彼はきっと何もかも知っている、そういう気がした。
綾と別れたばかりの頃にダン・ロックウェルがそれを知らずに姫とうまくいってるか、とウォルターをからかったことがある。しばらくしん、とした沈黙が漂ったあと、ウォルターはふられた、と答えた。その時からウォルターが疑問に思っていたことがひとつあるのだ。ダンはどう慰めたらいいんだろうという顔をしていたが、ウォルターはため息まじりに、やっぱりぼくなんかじゃだめだったみたい、と言っている。
「まあそう落ちこむなって。な、ウォルター。女は姫だけじゃないんだから」
「でもさぁー」
「何だ」
「あーんなに綾が最高の女の子だなんてわかってなかったもんなあ、ぼくは。別れてから思い知らされるなんて余計悲惨だよね、ほんと」
ウォルターは綾の泣いた顔を思い出していた。あの場面でああまで素直に泣ける女の子なんてきっとめったにお目にかかれない。ましてや普段の綾は意地っぱりというか強情というか、人前で泣くなんて絶対しない種類の女の子なのに、と彼はもう一度深いため息をついた。
「ウォルター」
「え」
「姫はさ、特別なんだよ。おまえに限らずめったな男じゃつりあわないんだ。そう思ってあきらめろ」
「んー」
「な?」
ウォルターはしばらく黙っていたが、ふいに思い出したことがあってダンに尋ねた。
「ねえ、ダン」
「何?」
「彼女の家の銃のコレクションなんかと一緒に雑誌に載ってたんだけどさ、綾って射撃うまいの?」
「おー、そりゃもう上手いなんてもんじゃねえぞ」
「え・・・」
「おれも何回か一緒にクレー撃ちに行ったことがあるけど、もうこっちが惨めになるくらい百発百中、はずしたとこなんて見たことないもんな。まるで的の方から当たってくれてるみたいな感じ」
「へえー」
「それがどうかしたのか」
「ううん、別に。・・・でもそれってライフルとかショットガンだよね。拳銃なんかは・・・」
「もちろんそれもうまいよ。射撃は姫の親父さんの最大の趣味のひとつだからな。子供の頃から教わってたらしい」
― じゃあ綾はあの時、嘘ついたんだ。
女の子の趣味にしては勇ましすぎるから黙っていたのかとも思ったが、綾に限ってそういう種類の嘘はつきそうにない。だとすると ― 考えてみたがウォルターにはわからなかった。けれどもそれが理解出来ないということが致命的なのだと、その時彼は思ってもみていなかった。そしてそのままこの五年が経過して行ったのである。
ダンは相変わらずのひょうきんおじさんだが、ウォルターのファースト、セカンドを成功させたあとも既に新しいアーティストのディスクに関わっていくつもヒットさせていた。ウォルターにしても、もうすっかりチャートの常連、どこへ行っても人気者の大スターさまだが根は全く変わっていない。未だに音楽バカで、世事にうとくて、間が抜けているのだ。
ただ少し変わったことと言えば、住む所がヴィレッジの狭いアパートからアッパー・イーストのダンの住まいの近くになったことくらいである。ウォルターの場合、性格から言ってもはっきりしているが、別にお金持ちの集まる住宅街に住みたかったわけではなく、単に他のとこよりダンやドリーの近くがいい、という発想からのお引越しだった。それでも彼にとって気のいい年配のメイドと、煩わしい家政を預けてしまえる秘書兼用のバトラーの存在は、音楽だけに没頭していられるという点でとてもありがたい。
それからベンが今年ジュニア・ハイに進んだ。
ウォルターのファン第一号を自他ともに認める彼は、お祝いにギターをおねだりしてきた。ダンが買ってやると言ったのだが、ぼくはウォルターにもらうのっ、と言ってきかない。ウォルターもいろいろどれにしようか考えたのだが、結局彼がずっと使っていたもののうちの一本をプレゼントすることにした。
おふるになるみたいでイヤだったら新しいのにするよ、と彼はベンに言ったのだが、きれいにラッピングされた包みを開いて以来、殆ど片時も手もとから離そうとはしない。誰かが触れようものならもう大変である。
― 五年、というのはそんな長さだ。長いような短いような、ウォルターにもよくわからない。
彼は歌いながら視界のすみに最前列の綾とスティーヴを捉えていた。
この五年の間に綾はもうすっかり少女と言える顔をしなくなった。昔と変わらず威勢が良くて屈託がなくて、けれどももうあの頃の女の子では決してない。
― 今の彼女には硝煙の香りがする。
この曲の最後の一音を弾き終えたら、とウォルターは思う。
― 曲の中にぼくが恋した少女を閉じこめて、すべて終わりにしてしまおう。ぼくには音楽しか残らない。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.12.8.
revise : 2010.11.29.


|
![]()