|


「ねっね、スティーヴ」
「何だ」
「良かっただろ、ウォルターのコンサート」
「うん」
夜も遅くなってからやっとコンサートが終わり二人は街を歩いていた。
「やっぱりすごいよなあ。ぼくが見込んだだけはあると思わない?」
「そうだな・・・」
確かにコンサートは良かった。しかしスティーヴにはひっかかることがある。
― いったい綾はあいつとどういう関係があるんだ
コンサートの前、花を持って行くと言うので綾にくっついて行った時、ウォルターをデヴューさせたのが加納家麾下のRMCレコードだということ、そして綾が彼の才能を買って契約にまで持って行ったことくらいは彼女に説明されていた。ただ、紹介されて挨拶を交わしている間ウォルターは決して無礼な態度は取らなかったが、二、三どうしても険があるとしか思えないようなことを口にしたのだ。
綾はぼくのファーストのレコーディングの間中、側にいてくれたんだとか、とっても力になってくれたとか、その上綾の話では今夜のチケットもウォルターがわざわざ送ってくれたものだという。挙句の果てに綾に向かって、今夜はきみのために歌うから、ときた。スティーヴは気になって気になって落ちつかない。
「どうしたの」
綾が横から不思議そうに彼を見ている。
「いや、何でもないよ。それより、もう帰るのか」
「んー、どうしようかな」
「送るよ」
彼女は歩きながら考えていたが、やがて言った。
「踊りに行こう」
「あ・・・」
「そうしよーよ。明日はぼく休みだし」
言って綾は彼を見た。
「スティーヴ、忙しいの?」
「忙しかないけどね・・・」
「だったらつきあえよ」
「だめっ」
「どうして」
「だって・・・」
しばらく彼は答えられなかったが、否定するにはするだけの理由があった。
綾を連れて何度も踊りに行ったことはある。彼女はものすごく踊るのがうまい。スティーヴもキライな方ではない。ただ彼女はうますぎるのだ。なにしろリズム感がいいというのか黒人なみに音に乗ってしまうのである。しかも細くてしなやかな身体は抜群のスタイルときていて、踊り始めるとダンサーでも通るくらいセクシーだ。それで人目を引かないわけがないうえ東洋人となれば結果としては当然目立ちまくってしまうことになる。
ところが当のご本人はこと容貌ということになるとまるっきり自分というものを知らないから、例えば居合わせた他の客がどういう目で見ているかなんて考えもしない。スティーヴはこれがイヤで仕方がないのだ。他の男に ― 下手をすれば女性でも ― そんな色っぽいところを見せたりしないでほしい。ただいても箱に入れておきたいくらいなのに。
「言ってみろ。どーして、だめっ、なんだ」
「だって」
「だっては聞いた。先を続けろ」
「おまえって曲に乗り始めると止まらなくなるだろ」
「そお?」
「そーだよ。しかも神がかりというか・・・、とにかくものすごくヤバいんだよ、そーゆーのは」
「どうして?」
「あぶないのっ」
綾はワケが分かっていない。
「その気がなくてもそーゆー気分になってしまいそうな踊りかたするくせに。回りの男がどういう目で見るか・・・」
「へえ」
「なんだ?」
「それって心配してくれてるの」
「してるよっ」
「じゃあボディガードについて来てよ」
言って綾はさっさと歩き出した。スティーヴの言うことなんかまるっきり本気にしていない様子で歩きながら言っている。
「今日、金曜日だよね」
「そう」
「じゃ、テッドやジーンも来てるかも知れないし」
「綾」
「え」
「踊りに行くよりもっといい夜の過ごしかたを知ってるんだけどね」
「何?」
「ここからだとイースト・ヴィレッジまで出るよか近いし」
「なんなの」
「おれの部屋の方が近いんだ」
「で?」
「そっちの方がいいと思わないか、もう遅いし」
「だんだん言いたいことがわかって来たみたい」
「そう?」
「スティーヴ」
綾は立ち止まって彼を見ると、きっぱりと言った。
「ぼくは踊りに行く方がいい」
「・・・・・」
*****
キャブより地下鉄乗りたい、と綾が言うので、二人はイースト・ヴィレッジまでそれで行くことにした。スティーヴの側にいると安心するのか綾はいつでもまるっきり警戒ということをしなくなるようだ。よく彼は綾のことをおシャムと言ってからかうのだが、スティーヴに限らず親しい人たちの間にいると全く彼女は飼い主のひざの上で安住してしまった仔ネコみたいにくつろいでしまう。その中でも一番なつかれているのがスティーヴだ。
二人が地下鉄を降りて近くのよく出かける店に入ってゆくと、綾の言った通りテッド・ウィリアムズとジーン・ヴァーマンがフロアに近いテーブルにいた。綾たちが目に止まるとテッドの方が嬉しそうに二人のテーブルにやって来て、久しぶりだね、綾、と声をかけた。
「忙しくってね、遊ぶヒマもありません。近頃は」
「結構じゃない、儲かって。でもさ、せっかく遊ぶ時くらい保護者ぬきにしなよ。これじゃ口説こうにも口説けやしない」
「誰が保護者だって、テッド」
スティーヴが横から文句を言った。
テッド・ウィリアムズは彼よりいくつか年が下だが、ご同業でよく一緒に仕事をやっている、スティーヴにしてみれば気の置ける友人の一人だ。ジーンはそのガールフレンドで女優だが、今のところまだ端役でやっと映画出演など出来るようになったところである。年も綾とさほど違わない。もう何年も前から、あちらこちらスティーヴと一緒に遊びに出かけると行き合わせることが多いので、綾も親しくなってしまった。
「なんだよ、違うっていうの?いつもいつもくっついてて殆どうるさいパパじゃないか。スティーヴ、綾と年いくつ違う?」
「十三しか離れてないのっ」
「それだけ違えば充分だよ。いい加減あきらめれば?おれ綾のこと好きなのに邪魔なんだもんな、スティーヴは」
「おれの女だ、手を出すな」
綾は横でしらっとしていたが、そう言われて口を出した。
「誰が、誰のだって?」
「おーお、見事に否定されて。これでもまだあきらめない?」
「うるさい。言ってみたかっただけだ」
「ね、綾。どう見たって親父か兄貴だろ」
「まあね」
「おれとだったら八つしか離れてないし丁度いいくらいだと思わない?どう」
「前向きに検討しとくよ」
「綾っ、おまえまたそうやってっ。気を持たせるようなこと・・・」
スティーヴが叱るように割って入ると綾は言って悪いの、と無邪気に尋ねている。
「悪いっ。第一テッド、おまえだってジーンに失礼だぞ。こんなとこで別の女口説いて」
「ああ。・・・うん」
テッドはしばらく黙ったが、ジーンの方を見て手招きしながら答えた。
「だってさ、あいつはスティーヴに惚れてるもん」
「えー、そーなの。のしつけて進呈しちゃうよ、ぼく」
「綾っ」
「なに怒ってるの、スティーヴ。ずいぶんご機嫌悪そうね」
ジーンが歩いて来ると話に加わった。プラチナブロンドの真直ぐな髪とブルーの瞳が印象的な細身の美人である。優しそうな様子がスクリーンでも際立っていて、このところ仕事も増えているようだ。
「おまえがスティーヴに惚れてるって話をしてたんだ」
「あら、だめじゃない。内緒だって言ったのに」
「のしつけてくれるってさ、綾が」
「まあ、嬉しい」
「みんなどうしてそうおればっかり苛めるんだ。おれが何をしたとゆーんだよ。綾に毎度振り回されてる身にもなってみろ」
「好きで振り回されてるくせに」
テッドに図星を指されてスティーヴは黙った。
「ねー、スティーヴ、踊ろうよ。せっかく来たんだからさ」
「あーはいはい、よろしいですよ、お姫さま」
綾に言われて仕方なく彼は椅子を立った。
「なんだ、イヤなの」
「べつにぃー」
「そりゃそうよ、綾」
「どうして、ジーン」
「スティーヴはね、貴女を人前に立たせたくないんだもの」
「なんで」
「横取りされるのがこわいから」
「・・・ふうん」
彼女は疑り深そうにスティーヴを見た。
「なんだよ、その目」
「そういえばこの前、一週間ほど連絡の取れないことがあったよな」
「え・・・」
「ルイーズまで行方を知らなくて」
「・・・・・」
ルイーズというのはスティーヴの秘書か連絡係のような存在で、彼が仕事に出かけていてもどこにいるのか大抵よく知っている。
「その前が約ひと月の音信不通で」
「えっと。いつの話かな」
「バックレるのもいい加減にしろよ、スティーヴ。ネタは上がってるんだから。たいてい違う女とどっかに消えてるくせに」
「・・・それは」
「それは?」
「おまえが相手にしてくれないから」
「ふーーーん」
「やっぱりおれだって淋しいし」
「信じろと言う方が無理だと思わない、テッド?この素行なんだから」
「言えてるよなあ」
スティーヴは返す言葉がなくて困っている。それへ綾は珍しく優しい微笑を浮かべて言った。
「べつに怒ってるわけじゃないよ」
「そうか、ほんと?」
「だってさ、ぼくたちそーゆ、権利のあるような仲じゃないだろ」
「だからいい加減にあきらめろって言ってるのに、スティーヴ。あー、かわいそう」
「やかましい」
綾は笑ってフロアに歩いて行った。
「おい、待てよ、綾。せめて言いわけくらい・・・」
スティーヴが追いかける後ろでジーンとテッドがくすくす笑い交わしていた。
「綾ってば」
「何?」
「怒ってるだろう」
「何を」
そっけない言い方で受け流して綾は曲に乗り始めた。
軽くステップを踏んでいるだけでも、もう違ってしまう。周りの連中が文明という檻の中で飼い馴らされている羊だとすれば、綾は野生の獣と言っていいほど鮮やかだ。普通の人間の常識や意識、概念の範疇には生きていないからなのだろうが、その遥か上層に君臨する種族 ― 神々の血を引いていると言ってもいい。
― 加納修三もそういう人だからな。
スティーヴはそう思って観賞する方に回ることにした。綾が彼を無視して音に同化してゆくのをスティーヴは側で眺めている。危険なくらい完璧な美しさだった。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.12.8.
revise : 2010.11.29.
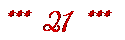
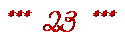
|
![]()