|
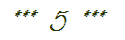
「そうか、やっぱりやりおったか!」
ファーンからデュアンが到着した時の、双子たちのあるまじき行状を聞いてウィリアムは大笑いだ。
「笑いごとじゃありませんよ、大じいさま。デュアンに何事かと思われちゃってるじゃないですか。あれはレディとしてやっぱり...」
「いやいやいや、まあ、おまえの言いたいことは分かるがな。それがあの子たちの面白いところなんじゃないか」
「大じいさまがそんなふうにおっしゃるから」
ファーンは呆れた顔で言っているが、ウィリアムはそれにまた笑って今度はデュアンの方に注意を移した。
「すまないな、デュアン。しかし、あの子たちには全く悪気などなくて、きみと友達になりたいだけなんだよ」
「ぼくはもちろん、嬉しいですけど。さっきはなんか、ちょっとスターになった気分だったし」
「そうか?
さあ、じゃ、そこに座りなさい。顔を見るのを楽しみにしていたんだ」
「はい」
「あ、大じいさま。これ、お父さんが大じいさまにって。デュアンが持ってきてくれたんですよ」
弟が示されたウィリアムの向かいの席に座る横で、ファーンが曽祖父に花束を差し出した。
「おお、これは見事なものだな」
言いながら受け取って、彼はデュアンに、ディによく礼を言っておいておくれと言った。
「ええ、伝えます」
「私も頂いたんですのよ。お部屋に生けさせましょうね」
「ああ、頼む。いや、花瓶に入れて今はとりあえずそこのマントルピースの上に置かせてくれないか。そうすれば、ここからよく眺められる」
アンナは頷き、側にいたメイドに二つの花束を預けた。メイドはアンナの指示に従って花を生けに出て行ったが、それと入れ代わるようにウィルが部屋に入って来た。彼も今日のランチに参加することになっているからだ。
「やあ、デュアン。いらっしゃい」
「こんにちわ」
「これで揃ったな。ウィルはそっちにかけるといい」
「はい」
皆が席につくとウィリアムはデュアンを見て言った。
「ファーンの弟でロベールの孫ともなれば、きみは私にとっても曾孫同然でな」
「本当ですか?」
「もちろんだよ。だから、兄さんがこっちにいるいないに拘わらず、もっと私のところへも遊びに来てくれると嬉しいんだが」
「はい。じゃ、お言葉に甘えて押しかけて来ちゃうことにします。おじいさまだけじゃなくて、ひいおじいちゃんまで出来るなんて、ぼくってホント幸せモノですよね」
デュアンが嬉しそうに言うので、そこにいる皆が笑顔になった。これは全くこの子の得意技と言っていいだろう。もちろん彼には作為的に気に入られようとか、ウケようという意識はまったくないのだが、逆にそれは自然に出てくる言葉とそれに伴う素直な感情表現であるだけに、誰もがすんなり受け入れて幸せな気分になってしまうのであるらしい。"ひいおじいちゃん"と聞いて、ウィリアムに至っては満面笑みになっている。
「"ひいおじいちゃん"と言ってくれるか?」
「構わないでしょうか?」
「聞くまでもない。私なら大歓迎だ」
言っているところへ執事のデイヴィスがメイドに手伝わせてアペリティフと、オイスターをメインにしたオードブルを運んで来てくれた。内輪のランチとは言え、モルガーナ伯爵家の跡取りを迎えてとあっては本格的なものになるのも当然で、しかも料理長はデュアンが"クランドルでは伝説のシェフ、ジェイムズ・オブライエンの作る料理を毎日のように食べている"ということを相当意識しているようだ。料理人としては、これは無理ない心情だろう。
「あ、美味しそう」
しかし、デュアンはあくまでくったくがない。それへウィリアムが言っている。
「きみを迎えてとあって、うちの料理長もはりきっていてな。後で忌憚ない感想を聞かせてやってくれるといい」
「分かりました。では、心していただきます」
「ね、デュアン」
カキにレモンをかけながらファーンが声をかけてきたので、デュアンはそっちを向いて、何?
兄さん、と尋ねた。
「ユージーたちのプレゼント、気にならない?」
「あ、ええ。ぼくもさっきから何なんだろうって思ってはいるんですけど」
「あら、じゃあ開けてごらんなさいよ。私もちょっと気になるわ」
アンナの提案を受けて、デュアンは、そうですね、じゃと言って、テーブルに置いていたプレゼントボックスへ手を伸ばしている。リボンを解いて包みを開けてみると、中から出てきたのは手作りらしい2体のウサギのマスコットだった。そんなに大きなものではなく、並べて机の上に飾っておけそうなサイズだ。白いウサギはドレスを、茶色のウサギはタキシードを着ていて、どちらもなかなか凝った造りになっている。それを見て、デュアンが意外そうな声を上げた。
「わあ、可愛い」
「へえ。二人で作ったって言ってたよね」
「でしたね」
「今回は本気で気合い入ってるなあ、二人とも。ちょっと、見せてくれる?」
「ええ、どうぞ」
兄にウサギを手渡しながら、しかし、デュアンは不思議そうな顔をしている。
「でも、なんで分かったんでしょう、ぼくがウサギを一番好きって。兄さん、教えました?」
ファーンは覚えがないと言うように首を横に振った。
「じゃ、偶然なのかな」
それへ、ウィリアムが横から口を挟んだ。
「いやいや、きみのことなら何でも既にリサーチ済みだろう。こういうことに関して、あの子たちの情報収集能力は一国の防諜組織にも匹敵するくらいのものなのさ。なかなかの地獄耳でな」
「大じいさま、それ、女の子の場合は自慢になりませんってば」
「そんなことはないさ。この情報が渦巻く時代にだ、生涯の伴侶を求めるともなれば、やはりそのくらい真剣でなくてはなるまい。女の子にとっては、一生の問題なんだからね」
「えっと、あの、ぼくも大じいさまって呼んでいいでしょうか?」
「おお。そうしてくれると嬉しいぞ」
「じゃ、大じいさま。そうすると、彼女たちって本気でアンナおばさまみたいに十六歳で結婚するつもりなんですか?」
「みたいだな」
「う〜ん」
「きみには想像もつかないくらい先のことかもしれんが、あの年頃の女の子はそういうことに夢中になるもののようだよ。ま、結婚云々はともかくとして、これから仲良くしてやっておくれ」
「ええ」
自分でも"一番好き"と言った通り、デュアンは"うさぎ魔"と言っていいくらいウサギ・モチーフのグッズに弱いのだ。その彼をして、どうやらもらったマスコットは大変気に適うものだったらしい。兄から戻された二体を大事そうにプレゼントボックスにしまって言っている。
「じゃ、ぼくも彼女たちに何かお礼を考えなきゃ」
ウィリアムはワイングラスを口に運びながら、それに笑って頷いた。それから少しの間、皆は食事に忙しい様子だったが、オードブルがあらかた終わる頃、ウィルが新しい話題を提供するように言った。
「それで、どう?
デュアン。旅行の準備はもうやってる?」
「もちろんですよ。何てったって1か月も旅行するなんて、この春休み最大のイベントですもん」
「だよね?」
ウィルが嬉しそうに言うのへ、ファーンがちょっといたずらっぽく口を出した。
「ウィルは、その話したくてしようがないんでしょう?」
「それはもう。半分は期待、半分は不安でいっぱいなんだよ、ぼくは。喋ってないと、それでアタマがはちきれそうで...」
「え、不安って?」
「だって、デュアン。きみやファーンはもうルーク博士やアリシア博士と一度会ってるからそんなでもないかもしれないけど、ぼくは正真正銘、初めてなんだから」
「ああ、そうでしたね。でも、大丈夫ですよ。ぼくがお話した感じでは、ルーク博士って気さくで、とても優しそうな方だったし」
「そう?
じゃ、アリシア博士は?」
「アリシア博士は、何ていうか物静かな雰囲気の方でしたよ。ああいう席だったからかもしれないけど、あまりお話しにならなくて。でも、ほんっとーに二人とも、お綺麗でした」
その表現に、みんなから笑いが湧いた。ウィリアムが言っている。
「今度ばかりは、きみたちが羨ましいよ。一度は私も彼らと会ってみたいとは思っているんだが、ああまで忙しそうだと、気軽にうちに招くということも憚られてな」
「でも、アレクさんから聞きましたけど、大じいさまは彼とはお会いになったことがあるんでしょう?」
「大昔の話だよ。彼がまだ、こんな...」
言ってウィリアムは手で子供の背丈を示した。
「しかしまあ、あの三男坊は、その頃からいずれ何かしでかしそうではあったな」
「そうなんですか?」
「うん。アルフレッド...、彼のお父さんのロウエル侯爵のことだがね。彼とは気が合って親しくつきあっていたから、何かの機会に自慢の三人息子を紹介されたことがあったんだ。よく覚えている。三人ともなかなか興味深い少年たちだったが、中でも末っ子は特に元気いっぱいで一家のアイドルみたいだったぞ」
「今では、世界のアイドルですよ」
デュアンの言うのに、またみんなは大笑いだ。
「確かにな。ま、彼らがいる限り、クランドル経済界は安泰だろう。せっかくそういう人たちと親しく話す機会を持てるんだから、いろいろ勉強させてもらってきなさい」
ウィリアムに、言われて子供たち三人はそれぞれに頷いている。
そうするうちにオードブルが終わると次はオマール海老を使ったジュレに春野菜をたっぷり添えた一皿、そして鴨のローストのメイン・ディッシュが供されて、もちろんウィリアムはそれぞれにデュアンのために自ら選び抜いたワインを用意させていた。以前、ロベールから孫が今既になかなかのワイン通だと聞いていたからだ。そして、最後のデザートは生チョコのタルトにガレットを添えてデザート仕立てにしたものだったが、これも今日の賓客がチョコレート好きとの情報をファーンから得ていた料理長が気合いを入れて選んだ一品らしく、それらのおかげでデュアンは総じてこのランチに大満足していた。
その後、今度は場所をゆっくりくつろげる広いサロンに移して、お茶の運びとなり、ここでやっと双子が呼ばれてデュアンに正式に紹介されることとなった。それを待ちに待っていた少女たちは、先ほどとはドレスを改めて現れたが、二人とも長く伸ばした柔らかなブロンドの巻き毛と鮮明なブルー・アイズを持ち、ドレスアップした姿は黙っていれば深窓のご令嬢で十分通る美少女ぶりだ。それは正に二輪の可憐なバラの蕾といった風情だった。ウィリアムがこの子たちに甘いのも、これを見れば当然かなとデュアンにも納得できたくらいだ。なにはともあれ、活発な女の子にはエヴァや、その他の学校の友達で慣れている彼のことで、最初びっくりさせられたわりにはすんなり好意を持つことができたようである。
華やかで賑やかな少女たちを加えてランチはそのまま午後のお茶に突入し、今度の旅行やそれぞれの学校の話、子供たちの日常生活の話題なども出て、結局、皆が気づいた時にはすっかり陽が暮れているという有様だった。カトリーヌの最初の心配はどこへやら、デュアンにとってどうやらここは母のところや今の家、そしてローデンの城に続く四番目の家ということになりそうだ。
original text :
2010.12.26.-2011.1.23.

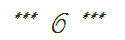
|
