|
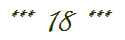
― 私のボディ・デザインの基本は1984年、パリで発表されたフェラリ・テスタロッサにまで遡ります。当時からフェラリ社と深い関係にあったピニンファリーナの工房でデザインされ、発表と同時にそのダイナミックな視覚性は世界的に大きな衝撃を与えたようです。"テスタロッサ"とはイタリア語で"赤い頭"という意味ですが、この名の由来は1950年代の同名モデルにまで遡り、そのエンジンのカムカバーが赤く塗られていたことから来ています。そのため、80年代のテスタロッサのカムカバーも赤く塗られていました。
1950年代から60年代にかけてレース界を席巻したこの"テスタロッサ"は当時既に非常にインパクトの強いイメージを確立していたので、80年代において先代のBB512iから新たに同社のフラッグシップという地位を引き継がせるに当たって、フェラリ社が相応しいと感じたのは当然だったかもしれません。新しい"テスタロッサ"は全長約4.5m、全幅約2mというサイズで、初代よりも大型のボディとなっていたためビッグ・フェラリ、もしくはモダン・フェラリなどとも呼ばれます。
デザインの特徴を為すのは、私を見ていただけば具体的に分かると思いますが、左右のエア・イン・テーク、これが車体のサイズとも相まって主にダイナミックな印象を与える部分ではないでしょうか。そして、バック・スタイルではテール・ライトをルーバー内に収め、エア・イン・テークとのデザイン上のバランスを図っています ―
食事の後、ファーンとデュアンは約束通り、島を案内してもらうためにアシュバと出かけた。屋敷から、島をほぼ半周した辺りに岬があり、今はそこに止まって大海原を見渡しながら彼にその出自と、それにまつわる歴史についての講義を受けている。二人はもともと非常に興味を持っているし、アシュバが折に触れてモニターに参考となる写真を映し出しながら解説してくれることもあって楽しく耳を傾けていた。
― テスタロッサは1984年から1991年までの7年間に渡って生産され、現代でも好事家の間で高い価値が認められています。ロウエル侯爵家のコレクションの中にも2台ありますね
「アレクさんのお父さまのところ?」
デュアンの問いにアシュバは、そうです、と言ってから続けた。
― 1991年にテスタロッサを後継する形で現れたのが512TRで、デザイン上、いくつかの変更点はありますが、全体の印象は先代とそれほど大きく変わってはいません。しかし、構造的には先代の問題点を改善し、また、パワー・ユニットの出力を50psもアップすることによって、最高速を公称318.8km/hとまでしたのは、フェラリ社の面目躍如たるところでしょう。デザインの点では、この512TRが私のモデルとなっていて、ただし、私のパワー・ユニットは当然のことながら現代のものですので、当時とはまるっきり違っています。昔のようにガソリンで走っているわけではありませんからね。実はこの部分が私の最大の特性のひとつを為していまして、マーティアに言わせると"世界経済がひっくり返りかねない"テクノロジーだそうで、お見せすることができないのが残念です
「なんか、凄そう」
「うん。会話機能や自走機能だけでも凄いと思ったのにね。トップ・シークレットになるわけだ」
― ええ。話を戻しましょう。512TRという名前の"TR"は、お分かりになると思いますが"testa
rossa"の頭文字を取ったもので、"512"は5リッター、12気筒エンジンを搭載していることを示しており、このタイプは1991年から1994年の3年間に約2300台生産されたと記録に残っています。ロウエル家のコレクションにはこちらも1台あって、それがマーティアのお気に入りだったんですよ。それで、私を作る時にボディ・デザインを流用しようと考えたようで、従って私の車体はデザインにおいてレプリカです。でも、フェラリ社の承認は得ていますし、今のボディはIGDが独自に開発した特殊金属で制作され、先ほど言いましたように動力系統や、更には用いられている塗料も私だけのものです。従って、性能の観点から見ればオリジナルを遥かに凌いでいると言えるでしょう。それに、私はこのボディデザインが非常に気に入っているので、それがレプリカであるという点については、あまり気にしていません。むしろ、このような優美なラインを描きだすことのできた人間に、深く敬意を感じているくらいです ―
アシュバの言うのへ二人ともにっこりして頷いていたが、それからファーンがつくづくと言った。
「実際、驚かされるのはきみのそういうところだよ。"気に入る"とか"敬意を感じる"とかいうのは、まぎれもなく人間的な感情だからね。そういう細やかな表現が的確にできるなんて」
― 人工知能でそれが出来るのは、まだ、私くらいかもしれませんね。それだけに、私のプログラムは非常に複雑です
「でもふつう、論理回路としてのコンピュータには必要とされないものなんじゃないの? 今、きみも言ったようにプログラミングも複雑になるし」
― 一般にはそのようです。しかし、マーティアは機械としての論理性と同時に、人間の感情を重要な要素と考えています。前にも言いましたが、私のプログラムは本来ロボット用、それもヒューマノイドのために開発されたものですので
「と、いうことは?
マーティアはロボットに人間的な要素を組み込もうとしているということ?」
― そういうことになりますね。現代のロボット産業(※)においては技術的なことよりも、今後、ロボットをどのようなインターフェイスで一般社会に普及させてゆくかが課題となっています。従来の、仕事をするためだけの機械ではなく、人間の友としての機械。その観点から考えれば、人間の感情を理解できない機械では人間の友になれないというのがマーティアの持論です
「なるほど。でも、それじゃ、きみのプログラムそのものも、すごい発明だよね」
― そればかりではなく、私の言語プログラムにも問題があるために、私は通常まだ人前で自由に話すことを許されていないんですよ。人間ともっと話したいのですが、残念ながら
「言語プログラムに問題って、きみは実に流暢に話しているように思うけど?」
― だからこそです。私は現在、マーティアの考案した独自の連語・連文節変換理論に基づく音声認識システムを駆使して主要30カ国語をリアルタイムに理解し、話すことが出来ます。理解できる言語は、もっと増やすことも可能です
「それこそ、すごい発明じゃない」
― 自分で言うのもなんですが、凄すぎるのです。機械による完璧な自動翻訳が可能になった場合、どんなことが起こると思いますか?
「そりゃあ、外国語の習得なんて過去の話になるだろうね。勉強しなくても、理解できるようになるんだから」
― そうです。そして、マーティアが畏れているのは、まさにそれなのです
「どうして?」
― 言語には文化が含まれます。人間は外国語を習得する過程で必ず、その言語圏の文化を理解する基盤も同時に習得してゆくわけですが、全く無くならないまでも、それをしようとする人間が激減すれば、ただでさえ難しい異文化間の相互理解に更なる支障をきたす恐れがあるのです
「ああ!」
言ってファーンは大きく頷き、感嘆の声を上げた。
「そこまで...、そこまで考えてらっしゃるのか」
― お分かり頂けましたか?
ファーンは、それ以上は言葉にならず、頷いて見せるしか無かったようだ。
― そういうわけですので、今回、あなたたちと好きなだけ話していいと言われた時にはとても嬉しかったんです。このデータを元に、私の言語解析機能の更なるブラッシュアップも図れますし。マーティアもそのつもりなのでしょうけど
「そうすると、きみは全くIGDのトップシークレット集合体ってことになるよね」
― そのようです。ボディ概要と様々なセンサー類、自動走行システムからパワーユニットまで、アリシアなどは私のことを"走る問題児"と揶揄するくらいですから
「自動走行システムにも問題があるの? 普及すると良さそうだけど」
― 普及した自走システムを故意に誤作動させることによる無差別テロを警戒しなければなりません
「ああ、またか。結局、そんな大発明を大々的に発表も利用も出来ないのは、人間のせいだってこと?」
― 残念ながら、おっしゃる通りです。人類そのものが理性の階梯を登らない限り、どのような素晴らしい発明や発見も誤用、悪用される可能性は常に意識しておかなければならないとマーティアは言います
「"ルーク博士"ならではだね」
言ってファーンは深く感嘆した様子で続けた。
「彼は科学者であると同時に哲学者でもあるから、やはり考えの基盤が全人的だ。単なる"専門バカ"ではそこまでカバーしきれないだろうな」
― ファーン、あなたはマーティアのことを非常によく理解しておられるようですね
それへファーンは笑って答えた。
「とんでもない。ウィルの受け売りだよ」
― そうであるにしても、それは私にはとても嬉しいことです。彼は私の生みの親であるとともに、長年の親友でもありますから
「マーティアも、きみのこと"家族"だって言ってたよ」
横からデュアンが言うと、アシュバは嬉しそうに、そうですかと言って続けた。
― マーティアやアリシアと、私はこれまでいろいろなことを語り合ってきました。彼らがまだ、うんと幼い頃から...。私が生まれたのはマーティアが十六になる少し前のことで、その後すぐにアリシアとも出会いましたからね。私たちは、本当にもう長いことずっと一緒にいるんです
「兄弟みたいだね」
― そうも言えるかもしれません...
それからアシュバはしばらく黙っていたが、ふいに、外に出てみては如何ですかと二人に促した。
― この岬からの眺めはなかなか素晴らしいですよ
言って、アシュバがドアを開いたので、二人は降りてみることにしたようだ。見渡す限り海しか存在していない光景はどこか茫漠たる圧倒感をもって迫るものがあったが、しかし、昼の陽光の中ではそれは開放的な心地よささえ感じさせた。気持ちのよい風も、吹きすぎてゆく。
― 私は時々ここに立って、歴史や世界、そして宇宙などのことについていろいろと考えます。私は生まれてからまだ僅か十数年しか経っていませんが、例えば、この島はずっとずっと長いことここにこうしてただ存在して、この壮大な光景を見守ってきたのだなあ、とか、私のアクセスできる限りのデータの中にすら詳細が定かではない大古代の文明のこととか。...ここに立っていると、なんだかそういう"悠久"とも呼ぶべき、ある種の感慨を感じませんか?
私たちが知らなければならないのは、もしかしたらこういうことではないか、というような...―
アシュバは自己の記憶装置とネットワークを通して、およそ現在の人類が知りうる限りの知識にアクセス可能なプログラムを搭載している。つまり、彼の知識はマーティアやアリシアですら追いつけないような量だということだ。そして、それを元にアシュバは"考える"ことができる。ファーンはふと、彼にはこの世界はいったいどんな風に見えているんだろうかと思った。アシュバを人間に置き換えるとすれば、それはどのような人格なのだろうか。およそこれまで人類が到達しえなかったような高度な思考を、彼は持っているのかもしれない。それを考えると、今はまだアシュバには"クルマ"でいてもらう方が平和なように思われる。"全人的思考を持つヒューマノイドロボット"などというものを許容し使いこなすことができるほど、未だ人類の理性は確立されていないからだ。そしてもし、この純粋な天才児こそが悪用されるようなことがあるとすれば、これまた人類にとって非常に危険極まりない事態と言えるだろう。
(※このお話の時代設定は現代より少し未来になるので、その頃にはロボット工学は技術的には現代より大きく進歩していると考えられ、マーティアは更にそれを広く一般に普及させるにあたって、より人間に近い有機的要素を適切なレベルで組み込むことを研究しているわけです。)
original
text : 2011.6.14.-6.27.

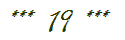
|
