|
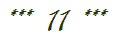
そんなこんなの日々が過ぎ、いよいよ子供たちにとって待望の春休みがやって来た。マーティアの招待を受けてウィル、ファーン、デュアンの三人は、まずはモルガーナ家のプライヴェートジェットでオーストラリアに飛ぶことになっている。オーストラリアはIGDと大変深い関わりを持つ国のひとつであるが、そこでは現在、大規模な都市、およびリゾート施設の開発が各地で進められているのだ。ヨーロッパから太平洋に向けて航行中のアークは一週間もすればごく近い位置にさしかかってくるが、子供たちはそれを待ちながら観光やIGDの施設見学を楽しみ、その後、ヘリを使って洋上で船と合流するのである。それからアークはマーティアたちの屋敷がある島のひとつに向かうというわけだ。
観光コースを選ぶにあたって当地は初めてのデュアンがまず絶対にこれはハズせないと主張したのは、言わずと知れたオーストラリア名物コアラの見物である。もちろん、抱っこして写真の一枚も撮らなきゃおさまらない。それで一行はまずブリスベンを目指し、ゴールドコースト観光を兼ねて近くの自然動物園でコアラやカンガルーなどと遊ぶ一日を過ごすことになった。その後、今度はファーンのリクエストでグレイトバリアリーフを訪れ、最後にウィルが希望するエアーズロックを見に行こうという段取りである。
この旅行にはこのところいつもデュアンの送り迎えをしてくれているロイが同行することになったが、彼はそもそもディが息子の安全を考えて付けたセキュリティ・ガードだから、これは当然のなりゆきと言えるだろう。しかし、ディはモルガーナ家の後継者という立場が常に誘拐などの危険性に晒されており、それくらいの用心を必要とするのだということでデュアンをあまり恐がらせたくないと思って、表向きロイは運転手ということにしている。その他には現地でガイドも兼ねた世話役として、IGDから一人付けるよう手配するとマーティアが言っていた。
出発の時点から最もノリにノってはしゃいでいたのはデュアンだったが、その勢いに釣り込まれてかファーンやウィルもテンションは高い。二人にとってもこんなに全てがスーパースペシャルな大旅行は殆ど初めてと言っていい経験だから無理もないだろう。ロイはガードとして付き添っているとはいえデュアンに付いて半年近くになるし、気さくで陽気な青年なので、この一行の旅はリラックスした楽しいものになることは間違いなかった。ブリスベンに着くと予定通りIGDのオーストラリア本部から、秘書課のマリエッタ・ラーソンが出迎えてくれた。ストレートのプラチナブロンドと緑の瞳を持つマリエッタはIGDのエリートらしくきびきびした立ち居振舞いの美女だが、マーティアが賓客をもてなすために差し向けるだけあって明るくて気配りの行き届いた女性でもある。彼女が観光に関わる様々な手配も全て済ませてくれていたから、滞在はスムースで心地よいものになりそうだった。
到着したのが午後だったため、その日はホテルのスイートでのんびり過ごし、翌日から五日間をゴールドコーストからグレイトバリアリーフ方面の観光に費やす。この辺りでは一般にマリン・スポーツも人気のあるアクティビティだが、それはこの後にアークやマーティアたちの島でたっぶり楽しめることになっているので、今回はもっぱら見物がメインだ。初日の自然動物園では予定通り可愛いコアラを抱っこさせてもらってデュアンは上機嫌。できることなら連れて帰りたいと言うほど気に入った様子だった。この動物園では動物は檻に入れられているのではなく、来園者とふれあえる環境に置かれているので、デュアンのみならずファーンやウィルも大いに楽しんだようだ。三人とも小さなペットは飼っていないが、馬には乗るので動物の扱いには比較的慣れている。
ゴールドコーストではビーチでの一日やショッピングも楽しみ、それからケアンズへ向かった。ヘリを使ってクイーンズランド州北東沿岸に広がるグレイトバリアリーフを眺めるのが主な目的だ。蒼い海とサンゴ礁の壮麗な光景は全長2000km以上にも渡って広がり、それを上空から俯瞰するのはまさに絶景で、みな口々に歓声を上げていた。周辺にはいくつもの島が散らばっているが、その中にはリゾート施設が充実しているものも沢山あって様々なマリンスポーツも楽しめる。特に海中の生物の多様さからダイビングは盛んだ。ただ、残念ながら今回、ここではゆっくり時間を取ることが出来ないので、ファーンはこの旅行中にぜひともダイビングをモノにして、いずれここも再訪したいと熱望していた。ちなみに、この大堡礁はこれまで温暖化を含め様々な危機に瀕して来たが、その保護と回復にもIGDは大きく力になっており、もちろん、ここばかりではなく世界各地における自然保護にも熱心な姿勢を示している。
また、ケアンズ観光ではこの他に見どころとしてグレイトバリアリーフと平行するように海岸線に伸びる約500キロに渡る熱帯雨林があるが、それに沿ってスカイレールと呼ばれるロープウエイが約7.5キロに渡って運行しているのだとマリエッタが教えてくれた。近くに来ているのだから聞けば乗ってみたくなるのは当然で、そちらにも回ってゴンドラでしばしゆるゆると森林のすぐ上を空中散歩して過ごす。アマゾンなどに比べると規模はさすがに小さいが、それでも総面積90万ヘクタールともなれば見ごたえは十分にある。ましてやここには多数の国立公園が点在し、世界でも珍しい植物、鳥類、爬虫類、昆虫なども多く生息しているのだ。太古の昔にはオーストラリア全土に渡ってこのような密林が広がっていたとも言われ、数千年を経た巨木や不思議な生き物たちの姿は原始の大陸の様子をも深く偲ばせた。一行はクランドルでの日常では見ることのできない鮮やかな色彩の植物や生き物を目の当たりにして、都市とは違うエキゾチックなムードをも存分に楽しむことが出来たようだ。
こうした観光の合間にIGDが建設している新都市やリゾート施設の見学も兼ねて、まだ一部のみだが稼働している遊園地を訪れたりもしたから、皆は五日間ですっかり遊び疲れてしまい、翌日一日はホテルで休養ということになった。それからエアーズロックを含む国立公園を見るため、大陸中央部に位置するアリス・スプリングスに移動だ。ここはオーストラリアの原住民であるアボリジニーズの聖地とも言われ、その壮大な光景と文化的背景から先のグレイトバリアリーフや熱帯雨林ともども世界遺産に登録されている。そういった事情からウィルはぜひ実際に見たいものだと思っていたのだろうが、他の二人もその圧倒的なまでの自然の偉業にはしばし言葉がないほど感動した様子で、既に詳しい知識を持っているウィルやマリエッタの解説を熱心に聞いていた。
こうして一行は約一週間に渡る観光コースをつつがなく見終え、今度はシドニーへ出ることになる。アークは順調に航海して予定通りの位置まで進んで来ていたので、翌日の朝にはマリエッタに深く謝辞を述べて四人は洋上のアークと合流するべくヘリで飛び立った。ここまででも十分に大旅行と言える行程だったが、彼らの旅はまだまだ始まったばかりだ。
ヘリで飛ぶこと約1時間、大海に流麗な威容を誇るアークの船体が眼下に見渡せるようになると、さすがに皆のはしゃいだお喋りも自然と止んでしまったのは無理もない。現代の科学の粋を結集し、贅の限りを尽くした最先端の外洋クルーザーとして一般に広く知られるアークだが、その実態はまさに"クルーザー"の語源の通り巡洋艦としても十分に機能する装備を搭載するバトルシップ、海上の要塞である。これはIGDでもトップシークレットの部類に入るので知る者は少ない。しかし、この船は巨大化したIGDというシステムのCPUであるマーティアとアリシアの安全を確保することを第一の目的としており、主にそのために"アーク"つまり"避難船"の名があるのだ。もちろんムダに全長300メートルを超える巨体を引きまわしているわけではなく、表向きの体裁に相応しく船上パーティなどの社交や要人との会談などにも大いに活用されている。
子供たちのリクエストでヘリはしばらくアークの周辺上空を飛んで、その白亜の優美な姿をたっぶり堪能させてくれてからデッキに舞い降りた。マーティアたちは現在、島の方に滞在しているということで、迎えに出たのは船長のイアン・マーシャルだ。彼はアレクの海軍時代に部下だった男で、アークの就航にあたってその管理者として絶対の信頼をおける者を必要としたアレクからの要請に応じて軍を辞し、現職に就いてくれた。もちろん、二人は海軍時代から親しい友人どうしでもあり、アレクが信頼を置くだけあってマーシャル船長は豪快で気持ちのいい性格の海の男だ。それで子供たちも初手から彼をすっかり気に入り、ましてやどこへ行っても一番に天性の社交性を発揮するデュアンがいることもあって、船長の方でも今回の客人たちをもてなすことに大いに乗り気になったらしかった。
船上にはスイートが数百あるので子供たちそれぞれが一室使うのに何の支障もなかったが、これまでの一週間で仲よし度を増した三人はできれば一緒の部屋の方がいいと望み、結局、マーティアたちの居室を除けばアークで最も快適なスイートに滞在することが決まった。占有面積は200平方メートルを軽く超えるという豪華さで、ベッドルームは四つあるからロイも皆の身近にいてやることができる。そこを拠点に数日間の滞在中、洋上でダイナミックなクレー射撃を楽しんだり、アークに搭載されている小型艇で巨船の回りを駆け回ったりトローリングを習ったりと、一行はいよいよ海らしい楽しみに興じて過ごした。マーシャル船長の話によると、この辺りでは時期を選べばホエール・ウォッチングやカジキなどの大モノ釣りも満喫できるのだという。
皆がそうやって遊んでいるうちにも船はのんびりと航海を続け、そうするうちにマーティアが居を構える島のひとつに入港した。ここはもともと無人島だったのだが、現在は彼らが住むためにだけ改良され、利用されている。アークが接岸できる規模の港や、そこから屋敷までの道路も見事に整備されていて、それだけ見ればごく限られた数の人間しか暮らしていないということが信じられないくらいだ。しかし、ここにはマーティアたちが折に触れて滞在する他は、屋敷の管理などのために必要とされる最少限しか人間は存在していない。
船長に見送られて港に降りると、車が2台、出迎えに来ていた。一台はアイボリーのベントレー、もう一台は赤のフェラリで、ベントレーにはまだ若い長身の青年がショーファーとしてついている。格式ばった場所というわけではないので制服ではなく平服で、顔立ちや髪の色から察するにおそらくどこか東洋系の血がまじっているのだろう。なかなかの美青年だ。一方、フェラリには誰も乗っていない様子だった。
「ようこそ。私はここの管理を任されているチャールズ・ダインと申します。ルーク博士は屋敷の方でお待ちですので、どうぞ」
言って彼が後席のドアを開き、四人に乗るように促す側でいきなり"チャールズ"とどこかから声がかかった。客たちは驚いてキョロキョロと回りを見まわしてしまったが、声をかけられた本人にとっては何ひとつ不思議なことは起こっていないようで平然と答えている。
「何だい?
アシュバ」
どこをどう見ても周囲には彼らの他に人はいないのだが、どうやら会話は成立しているらしく答えが返ってきた。
― ベントレーでも四人はちょっと窮屈でしょう。やはり、私が二人運びますよ
声のする方向を見て、客たちの当惑は更に深まったようだ。なにしろ、その声は誰も乗っていないフェラリの方から聞こえてきていたからである。
「そうだね」
しかし、チャールズはそれにもこともなげに返事し、今度は四人に向かって言った。
「お二人でしたら、あちらのフェラリにお乗り頂くこともできますよ。どうされますか?」
「あの...、二人、ですか?」
フェラリはどう見ても運転者を含めて二人しか乗れないツーシーターなので、ファーンが尋ねている。すると、彼の疑問に答えるようにアシュバと呼ばれた車はすい...、と彼らの前に寄ってきた。もちろん、だれも運転しているわけではない。それでウィルが何かに気づいたようで、思わず声を上げている。
「ああ!
もしかして、これって...。開発中というウワサだけは聞いたことがあったけど、まさかもう完成していたんですか?!」
ウィルの問いにチャールズがイタズラそうに笑って言った。
「ご存じでしたか」
「単に、ウワサだけですよ」
「ねえ、ウィル、ウワサって何なの?」
二人の話が見えないようでファーンは不思議そうな顔をしている。ウィルはそれへ、ちょっと自慢そうに答えた。
「コンピュータ制御の自動走行車両だよ。IGDを含めていろんな研究室で開発が進んでいるけど、まだどこも実用化には漕ぎつけていないはずなんだ。しかもこれは...」
「一般への普及は未だ想定されていませんが、アシュバはルーク博士が日ごろからお使いになっている車です。走行実績は過去十年以上に渡って蓄積されていますので、安全性は保証しますよ」
またこともなげにチャールズは言ったのだが、その意味はウィルには衝撃的だったようだ。
「十年以上?!」
「はい」
ウィルの知識としては現在でも開発途上にあるはずの技術が、十年以上も前に実用化していたということだけでも驚くべきことなのだが、他の三人には彼が驚愕している理由がよく分からないようだった。しかし、その様子から凄いテクノロジーであるらしいことくらいは見当がついたようだ。
「それは、ルーク博士ご自身が開発されたということなんでしょうね、やっぱり」
「正確に言えば、彼とその開発チームが十五年ほど前に完成しました。ただ、一般の実用に供するには技術的なもの以外の問題がいろいろと伴いますので」
チャールズの答えにウィルは頷いている。
「ここで立ち話も何ですから、詳しいことは後でルーク博士に尋ねられては?」
「...そうですね。めったにないチャンスなんだし」
ウィルは言って深い溜息をつき、従弟たちを振り返った。
「どうする?
ぼくとしては特にきみたちにルーク博士の天才ぶりを実感してもらいたい気がするんだけどね。もちろんぼくも、後でたっぷりと試させてもらうよ」
言われて二人は顔を見合わせた。いくら安全性が保証されているとはいえ、ドライバーのいない車になんかさすがにどちらも乗ったことはない。ベントレーの方が安全そうだとは思うのだが、一方で好奇心は残る。そうするうちに再びフェラリから声が聞こえてきた。
―
マーティアが待ちくたびれてしまいますよ。とにかく、行きましょう
今度こそ皆がその異常に気づいたようで、とうとうデュアンが"喋るんですか?!"と叫んだ。最初のでどういうことか分かっていたらしいウィルは、その驚きに満足げな顔で言っている。
「さっきも喋ったじゃない」
「だって、あれは...」
「ルーク博士は様々な方面の研究を並行して進めてらっしゃるけど、ロボット工学の分野でも権威だよ」
「ロボット?」
「そう。まあ、とりあえず行こうよ。ぼくは博士に山ほど聞きたいことがあるんだから」
アシュバがどうやら喋るどころか会話できるらしいと知って、ファーンとデュアンは爆発的に好奇心を刺激されたようだ。それでやっと話は決まり、四人はそれぞれ車に乗り込んだ。屋敷に着くころには、午後のお茶にちょうどよい時間になっているだろう。
original
text : 2011.4.2.-4.8.
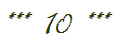

|
