|
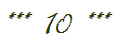
「やっぱり、ここでしたね。また、"自主休講"ですか?」
うららかな春の陽射しの中、気持ちのよい風に吹かれて木陰でうとうとしかけていたランドルフは、そう声をかけられて引き込まれかけていた夢から目を覚ました。構内を見渡すことの出来る丘の上は、昔からお気に入りの昼寝場所のひとつなのだ。見上げると、側にファーンが立っていて彼を見下ろしている。
「おー、おまえか。いい天気だな」
「そうですね」
「まあ、座れよ」
起き上がってランドルフが言うと、ファーンは頷いて側の芝生に腰を下ろした。
「おまえがおサボりとは、めずらしい」
「何言ってるんですか。もうとっくに授業は終わりましたよ」
「なんだ、もうそんな時間か」
「ええ」
「で、散歩でもしてたって?」
「あなたを探してたんです。講義にも出てないようだったので」
「なんでまた?
おれに会いたかったとか?」
ファーンはそれに笑って、しかし非情にも"いいえ"と即答した。ランドルフはがっかりしながら言っている。
「...期待はしてなかったけど。じゃ、なんで探してたんだ?」
「デュアンから伝言があるんです」
「デュアン?
ああ、あのカワイコちゃんか、おまえの弟」
「そうです」
「伝言って?
何?」
「この前、取材につきあってもらったでしょう?」
「ああ、あれな」
「そのおかげで今度の仕事がとてもうまくいったみたいで、すごく好評だったんですって」
「見た見た。みんな喜んでたぜ、協力した甲斐があったって。おれもちょっとびっくり。あれ全部、本当にあの子が描いたんだよな?」
「もちろんですよ」
「才能あるよなあ。おまえよりかさえ年下なんだろ?」
「ひとつ半くらいですけどね」
「それに、すっげえ可愛いしさあ。ダチが女の子と間違ったのも無理ないって」
「ええ」
「で、性格もいいんだよな。あの後おれ、お前からあのコに乗り換えようかなってマジ思ったもん」
「ダメです」
「お、妬いてくれてんの?」
「違います。可愛い弟を、あなたの毒牙になんかかけたくないだけ」
「ちっ、そっちかよ」
またまた冷たくあしらわれてランドルフはちょっとふてくされていたが、伝言があると言われていたのを思い出したらしく、それで、あの子が何だって?
と尋ねた。
「ご協力頂いたおかげでとてもいい作品になったので、あなたとお友達に何かお礼がしたいって」
「いいよいいよ、礼なんて」
「でも、デュアンはそういうこと、なおざりにしておけない子なので。それで、どうしたらいいかと」
「う〜ん、その律儀なとこも気に入ったな。じゃあ、今度デートにつきあってもらっちゃおうか」
「またもお。真面目に聞いてるんですから」
「いや、おれもマジで言ってんのよ。まあ、デートってのはアレだけどさ、この前会わせた劇団の連中が今度また公演やる予定なんで、見物に行ってやってくれると嬉しいなと」
「ああ、そういうことなら」
「おまえも一緒に来るだろ?」
「そうですね。デュアンひとりを行かせるというわけにもゆかないし」
「よし」
「でも、見に行くだけでは、お礼にならないでしょう?」
「いや、それだけでも喜ぶと思うけど...。なにしろ、まだ客集めるだけで大変らしいから。でも、そうだな、じゃ、何かうまいもん差し入れてやってくれるってのはどうだ?」
「いいかもしれませんね。デュアンにそう言ってみます」
「ん」
「あ、そうだ。見物人が多い方がいいなら、ウィルも誘っていいですよね?」
「なんであいつまで。せっかくおれが両手に花で芝居見物とシャレこもうってのに」
「何言ってるんですか。そういうのは、女性と一緒の時に言って下さい」
「いいじゃん。男でも女でもキレイどころに変わりはねえよ」
「まったくもう」
ランドルフがどこまでもからかい半分なのでファーンは呆れていたが、気を取り直して続けた。
「とにかく、この前はぼくたちだけで出かけたもんだから、後でその話を聞いてウィルがスネちゃってるんですよ」
「スネた?」
「ぼくも、うっかりしてて誘えば良かったんですけど、せっかくあなたと友人関係取り戻せたのにこういうことで実質ツンボさじきにしちゃった形になって...」
「あいつはいったいなんなんだ?
なんでそう、おれのやることにかまいたがるんだよ。もしかしてあいつ、おれにホレてたのか?」
「冗談言わないでください。ウィルに限って、絶対、そんなことはありません」
「力いっぱい否定したな」
「しましたよ。当然でしょう?
ウィルには、いいなずけだっているんだし」
それを聞いてランドルフは一瞬さすがに絶句していたが、それから、なんだとお?
と声を上げた。
「いいなずけだあ?
なんなんだよ、それは。いつの間にあいつにそんなもんが...」
「もちろんまだ正式に婚約したわけじゃありませんけど、親たちが"そうなればいいな"くらいに思ってる人がいるってことです。とても仲がいいし、ウィルも彼女のことが好きみたいだし」
「全く、これだから貴族ってな。何が悲しくて十六や七で婚約しなきゃなんだよ」
「あなたこそ、そんなにショックを受けるってことは、もしかしてウィルが好きだったんですか?」
「バカ言うな。おまえなあ、何回言ったら、理解するんだ?
おれが好きなのは、おまえ。いいかげん覚えろ」
「ヤメて下さい、それ」
「なんでだよ」
「いつもいつも、それで話が座礁するからですよ。ぼくは今、単にウィルを誘ってもいいかどうか聞いただけなのに」
「ああ、そうですか。全くもう、可愛げのねえガキだよ。分かった、分かった、なんでもいいから好きにしろ、よきにはからえ」
「そんな、投げヤリに言わなくても...」
「はいはい。ウィルが来るってんなら、おれは構わねえよ」
「じゃ、話してみます。それで、日程はもう決まってるんですか?」
「いや。今、準備中だとか言ってたから、どうせ今度の休み明けくらいになるんじゃないか?
行くんなら、詳しく聞いとくよ」
「お願いします。あ、それから他のお友達にもデュアンがお礼を言っていたって」
「ああ、伝えておく」
それから少し話が途切れ、ランドルフは何か考えている様子だったが、しばらくしてふいに、しかしま、なんだな、と言った。
「え?」
「おまえがあの我が校伝説の"氷の王子さま"のご子息だったことを考えりゃ、一筋縄でいかないのも当然だよなと思ってさ」
聞いてファーンは笑っている。
「教授連が言ってたけど、おまえの弟ってモルガーナ伯の子供の頃そっくりだってホント?」
「ええ。ぼくもお父さんに写真を見せてもらったんですけど、似てると言うより瓜二つと言った方が。違うのは瞳の色くらいですから」
「なるほどなあ。確かに見た目があれで、あの才能じゃ伝説にもなるわ。で、あの子はこの学校には来ないのか?」
「今のところは。あまり急激に環境が変わると、デュアンが大変だろうということで」
「ふうん。来ればいいのにな。可愛がってやるのに」
言われてファーンはつくづくと、その心配も、ありますからねえ、と答えた。
「心配って、なんだよ」
「いえ、あなただけじゃなくて。って言うか、あなたはともかく他にもいろいろと...」
「カワイコちゃんと見れば、ほっとけないって連中のことか?」
「まあ、そういうことです」
それにランドルフは笑って、悟ったように言っている。
「ま、人生いろいろだからさ。あいつらだって、たいてい悪気はないんだよ。しかし、あの子なら相当騒がれても不思議はないし、今んとこ来ない方が無難ってことか」
「ええ」
「そうかもな...。ところでおまえ、春休みどうすんだ?」
「春休み?
旅行ですよ」
「ああ、例の"ご招待"ってヤツか。ウィルが言ってた」
「ええ」
「休み中ずっと旅行たあ、いいご身分だね」
「何言ってるんですか。あなただって、しようと思えばいくらでもできるでしょ?
旅行くらい」
「おれは、遊んでるヒマねえよ。バイトだから」
「アルバイトなんて、そんなのしなくたって...」
「知ってるか?
労働は尊いんだぜ?」
「それは分かってますけど」
「ま、これも"社会勉強"ってヤツさ。おじ貴は、そんなことやってる間に成績上げろとか相変わらずウルサイこと言ってるけど、知ったこっちゃねえや」
「でも、この前の定期試験では二科目だけだったけど、ウィルを抜いたじゃないですか」
「何言ってんだい、それ信じてるんならおまえも甘いね。ありゃあ、ウィルのやつが手ぇ抜きやがっただけのことさ。悔しいけど今のおれじゃ、あいつにマジでやられたら抜けっこねえんだよ。ま、華を持たせてヤル気にさせよーって魂胆だろ。そんなことしなくても、そのうち追いついてやるけどな」
「例えそうだったとしても、三位以下とはダントツに離れてたでしょう?
こんなに短期間でこれほど成績戻すなんてってウィルも感心してたし、ぼくもちょっと見直してたのに」
「へえ、いつも厳しいおまえに見直されてたとはね。頑張った甲斐あったってもんだ。んじゃ、他の科目も戻してゆくか」
「他は相変わらず、壊滅的だったそうですもんね」
「ほっとけ。そんなにいっぺんに、あれもこれもやってられっか。それに、おれは集中力のヒトだからな。なにごともひとつづつ、全力投球がモットーなのさ。しかし、おまえが見直してくれるってんなら、もうちょい頑張ってもいいかなという気にはなるよ」
言われてファーンは頷きながらも、少し不思議な気分だった。これまでもランドルフには散々、好きだのなんだの言われているが、どうせからかっているだけだろうと大して気にも留めていなかったのに、ちょっと"見なおした"と言っただけで彼がずいぶん嬉しそうな顔をしているので、どうやら自分の発言は彼にそのくらいの影響を与えることができるようだと気づいたからだ。本気かなあ、と思いつつ、今はまだそれについて追及する必要までは感じられない。ただ、こうやって話すのは自分にとってもなんとなく楽しいことになっているらしいのにも、ファーンは改めて気がついている。あれ?
とは思ったがそれは口に出さないまま、夕食の時間が近づくまで二人は春の午後をとりとめなく話しながら過ごしていた。
original text :
2011.3.22.-3.27.
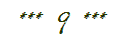
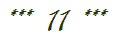
|
