|
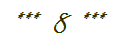
― あらあらあら、それは大変ね、とうとうなの?
「うん...」
― そうねえ。まあ、今まで内緒にしておけた方が不思議なのかもしれないし、私はシャンタン伯爵のお気持ちもよく分かる気はするわね。
集めるとなると、とにかく子供たちの母親に連絡を取り、コトの経緯を話す必要がある。そこで、ディはまず二番目の息子、ファーンの母親であるアナベル・ジェファースンに電話をかけてみた。
アナベルは家族や親しい者からはアンナと呼ばれていて、元はクランドルでもロウエル家やモルガーナ家と並ぶ大貴族、クロフォード公爵家の令嬢だ。まだ僅か16才の頃に実業家でもあった祖父の絶大な信頼を得ていた部下、クリス・ジェファースン氏に嫁いだが、その後、夫が飛行機事故で亡くなるという不幸に見舞われ、ディと出会う頃には既に未亡人になっていた。
ごくごく若い頃に二十歳も年上のジェファースン氏と結婚したとは言っても、これは政略結婚というようなものではなくて純粋な恋愛結婚だったらしい。アンナの話によると、彼女のかつての夫は当時三十代、第一線でバリバリ活躍していた将来有望な青年だったそうだ。それにまだほんの小娘だった私の方が熱を上げたのよ、という。まあ、なかなかのハンサムでもあったのだろう。加えて、真面目な青年でもあったらしく、15才の少女に告白されて始めは彼の方があわてていたようだが、生まれた時からよく知っていて仲の良かったアナベル、しかも美少女の呼び声も高かった彼女にそうまで思い込まれては彼の方も悪い気はしなかったらしい。幸い、祖父や父の理解も得られたので結婚することになったのだと以前アンナが言っていたのをディは覚えている。
しかし、夫との間で子供が欲しいわねとか言っている間に亡くなってしまったものだから、彼の死後、彼女はひとりぼっちになってしまったわけだ。もちろんその時は哀しみのどん底に突き落とされ、数年間、喪服を脱ぐこともできなかったという。それでも、生まれつき明るい性質が幸いしたらしく、そのうちなんとか立ち直ることが出来て、以来、気楽な未亡人として優雅に社交や旅行に明け暮れ、毎日を淋しいなりに楽しく送っていたのである。
そうこうするうちにディと出会い、当時三十代にさしかかったばかりの彼よりはいくつか年上で、しかも未亡人という自分の立場から、彼との再婚というようなことはまるっきり考えなかったようだが、しかし、夫に死なれて以来、ディほど彼女の気にかなった相手もいなかったのだろう。彼から、実は子供が一人いるなどという話を聞いて、子供がいたらきっと楽しいわねと思った彼女は、じゃ、私も生みたいわなどと言い出したのだ。
夫の死後も長いことジェファースン姓のままで通していた彼女だが、他の男との間に出来た子供にかつての夫の姓を名乗らせるにはしのびず、ファーンが生まれることになってからはクロフォード家に戻った。事実はそうなのだが、しかし、長年"ジェファースン未亡人"で通して来たこともあって、わざわざ実家に戻ったと公表する必要もなく、従って、彼女は現在でも公にはアナベル・ジェファースンということになっているのだ。
電話口でちょっとまいっているという様子で事情を話すディに、彼女は相変わらずの明るさでコロコロ笑って、いいわよ、じゃ、ファーンに話してみるわねと答えた。
ファーンは私生児とはいえ、なんといってもクロフォード家の血に繋がり、しかも、アンナは父や祖父にさえその父親が誰か明かしてはいないとはいえ、本来はモルガーナ家かシャンタン家の跡継ぎとして育てられても不思議はない出自を持つ子供だ。アンナは彼女自身も貴族の出であるし、それなりの年齢だけにそんな事情にも配慮したのだろう。それに祖父の奨めもあって、ファーンはふだん名門の寄宿学校で学んでいて、月に二、三度帰ってくる。ちょうど試験週間明けだったこともあって、彼女はちょっと話があるから帰って来なさいよとファーンに声をかけ、その週末、息子が帰ってくると実はこういうことなのよ、と経緯を説明した。彼の父親が誰かについては、数年前にきっかけがあってファーンにだけは既に話してあった。
「なるほど、とうとうそんな話になったんですね」
「そういうことみたいね」
「じゃあ、ぼくとしては初めてお父さんや兄弟たちと対面できるというわけなんだ」
「そうよ」
「それは、なかなか楽しみです。それで、いつなんですか?」
「そう言うと思った。いつかはまだ決まってないの。でも、あなたがいいならそう伝えるわ」
「そう。あ、でも、ぼくはいいとして、ぼくが今まで縁のなかったお父さんと会うという話、おじいさまたちはどう思われるかしら」
「それは大丈夫よ。ディからその話があってから、おじいさまたちにはもうお話したし、...あなたのお父さんが誰かは初めて明かしたわけだから驚いてらしたけど、そういう話になったのならまあそれはそれで良かったと言ってらしてよ」
「そうですか」
ファーンはダークブロンドに濃い蒼の瞳を持つ少年で、顔立ちや髪の色は極めて母親によく似ている。しかし、その瞳の色を見ればまごうことなくディの血を引いていると分かるほど、それはあの珍しい紺碧の貴石のような色なのだ。この年頃にしては既に背も高く、柔らかな髪は少し肩にかかるくらいに切り整えていて、なかなか凛とした美しい少年だった。
母がクロフォード家に戻ってから生まれたこともあって、彼女のみならず、祖父母や曽祖父、それに彼の叔父にあたるアンナの二人の兄たちからも可愛がられていて、大家族の中で幸せに育ってきている。元々、アンナは家族の中でたったひとりの女の子だったから、幼い頃から文字通りお姫さま扱いで、だからその彼女が父親の分からない子供を連れて出戻ってきたとしても、そんなことは家族の誰もまるで悪いようには気にしなかったのだ。それどころか、早くに最愛の夫を亡くし、今度は父親のいない子を産むことになった彼女を不憫にすら思って、みんながなんだかんだと厚遇してくれるほどだった。
加えて利発で闊達、それにまだ10才とは思えないほど落ち着いた性質のファーンは、今となっては特に彼の曽祖父のお気に入りで、それらのせいで「父親がいない」という事実も彼にとって日常マイナスを感じさせる要素には全くなっていない。クロフォード家の威光もあるのだろうが、それを抜きにしても成績もずば抜けて良く、既に信望の厚い性質を発揮してもいるファーンは、学校でも回りから一目も二目も置かれていて、いじめられるということとも無縁だったようだ。
そんな少年だったから、既に母から事情を聞いて知ってもいたし、実の父との初の対面とは言っても、必要以上に動揺した様子はなかった。事実、彼にとってそれは、「ちょっと面白そうなイベント」くらいのものだったのだ。それに、従兄弟たちがそれぞれ何人も兄弟姉妹を持っているのを見ていて、日ごろから羨ましいと思っていた彼は、父よりも兄や弟に会えるということの方が楽しみなくらいだった。
ともあれ、ファーンに関しては何も問題なく、話が進んでゆくようではあった。
original
text : 2008.7.9.
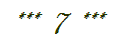
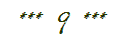
|
