|
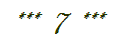
それから半年ほどする間にも、デュアンは折りに触れてモルガーナ家を訪れ、そのたびにどんどんディと仲良くなってゆくようだった。最初は自分を気に入ってもらえるかどうか、嫌われないかどうかと不安でいっぱいだったデュアンだが、会うたび話す時間が長くなり、そのうちに泊まって行ったら?
などという話も出るようになって、彼の父がすっかり自分の息子を気に入ったようなのは誰の目にも明らかに思えるようになってきた。そうするとデュアンの方でもほっとするのと嬉しいのとで、頻繁にディに電話をかけるようになり、それをまたディは迷惑がるどころか極めて嬉しそうに応対してくれるのだ。
そんなこんなで二人はいつの間にか冗談すら平気で言い合えるくらいになっていたが、それはアーネストをして、彼の主がこれほど楽しそうだったのは、マーティアが彼のモデルとしてこの屋敷に出入りしていた頃以来ではないかと思わせるほどだった。そして、その微笑ましい様子が、次第に見ているアーネストやマーサたちをも幸せにしてくれるものになっていったのは当然のことだっただろう。
そんなある日。クランドルに来る時はいつもモルガーナ家に滞在するディの父、ロベール・ド・シャンタン伯が、いつものようにディに愚痴り始めたのが全ての発端だったのだ。なにしろディは、そうは全く見えないものの、既に40も過ぎるというのにふらふらふらふら、いつになったら結婚するのか未だに分からないような有様で脳天気な毎日を送っている。しかし、未だ矍鑠(かくしゃく)としているとはいえそろそろ70を過ぎるシャンタン伯から見れば、モルガーナ家とシャンタン家、この名門両家の跡継ぎをこいつはいったいどうするつもりなのかと、顔を見るたびに問い質さずにはいられない心境になっても無理はなかった。
「だからだな、おまえはいったいそれをどう思ってると聞いているんだ。私だってもういいトシなんだから、跡取りのことはきっちり決めておきたいのに、おまえと来たらいつまでたっても遊び回るばっかりで、そろそろ少しは落ち着くということを考えないのか」
「そうですねえ...」
「何が、そうですねえ、だ、バカもの。だいたい、あんなにつきあう相手をとっかえひっかえしているのに、なんで今に至っても一度も"結婚"という言葉ひとつ出て来んのだ」
「それは、なかなかこれと思う女性に出会えないものですから」
「贅沢を言うな、贅沢を。第一、おまえがつきあっているのは、私から見てもモルガーナ家の奥方が十分つとまりそうなほどよく出来た女性ばかりだぞ。だから、いつおまえが結婚することにしたと言ってくるかと私は長年待ちに待って来たというのにこの始末だ。ちょっとは真面目に考えろ」
「考えてますよ」
「考えとらん」
「だって、お父さんはお母さんみたいな理想の女性に出会えたからいいですよ。でも、ぼくは...」
「聞いたふうな口をきくな、聞いたふうな。おまえに理想の女性像があるなんぞ、私は全くの初耳だ」
「ぼくにだってありますよ」
「本当にあるんなら言ってみろ」
言われてディは、つい考え込んで黙ってしまった。
「そらみろ」
「いえ、ですから...」
「結局、逃げ回ることしか考えとらんのだろう」
「そんなことありませんよ。ぼくだって、シベールが生きていたら」
「・・・・・」
「シベールさえ生きていてくれたら、お父さんが結婚したのよりずっと早く、ぼくだって結婚できていたかもしれないのに。ああ、そうだ。強いて言えば、ぼくの理想はやはり、シベールとか、お母さんみたいな女性だな」
「おまえな」
「はい?」
「私も長いこと、そのシベールの件があったから、おまえもなかなか彼女以上の女性に巡り合えなくて結婚する気にならんのだろうと好意的に考えてやっていたんだ。しかし、最近ではかなり分かって来たことがあってな」
「何ですか?」
「いくらなんでも十代の初恋が、そのトシになっても諦めきれないとは考えられん。結局、おまえはそれを免罪符にしているだけだ」
「そんなことありませんよ」
「ある!
全く、おまえというやつは。百歩ゆずって結婚するしないは置くとしても、あれっだけ沢山の女性とつきあっていながら、なんで隠し子の一人くらい作っておかんのだ。彼女たちの中に、子供の一人も生んでやろうという女性はいなかったのか」
「残念ながら」
「この、甲斐性なし!」
「お父さん、それはいくらなんでもひどい言い方なんじゃないですか?」
「単なる事実だろうが」
「だったらもし、ぼくに本当に隠し子がいたらどうするつもりです?
そんなのがのこのこ出てきたりしたら、お父さんだって困るんじゃないですか?」
「おお、いろ、いろ、いてみろ。困るどころか褒めてやるぞ」
ディはお手上げという顔をして、黙る他なかった。
ロベールは基本的に、いろいろ難ありとはいえ一人息子のディのことは目に入れても痛くないほど溺愛している。なにしろ、最愛の亡き妻に顔立ちがそっくりで、しかも彼女とすっかり同じ瞳の色までしているこの息子は、彼にとって今となってはただひとつの大切な妻の忘れ形見なのだ。芸術家としての資質も素晴らしいものを持っているし、性格も悪くない。だから、十分に自慢の息子と言ってもいい存在ではあるのだが、跡継ぎのことを真面目に考えているフシが見受けられないのだけは頭痛のタネだ。
一方、ディの方は、陽気でおおらかなラテン気質を持つこの父のことを尊敬してもいるし、愛してもいる。仲の良かった祖父も母も既に亡くなってしまっている今、ディにとって家族と言えるのも彼だけだ。しかし、跡継ぎはともかく、結婚となると自分の気が向かない限りはどうしようもないのが彼の性格でもある。それに、実際には存在する3人の子供たちも、そもそもディは跡取りにしようなどと考えて作ったわけではない。それについては漠然と考えないでもなかったが、そもそも子供たちはそれぞれその母親が欲しがったからいるのであって、だからディにとって彼らはお気に入りの恋人にプレゼントしたも同然の存在なのだ。だから、それを今更こちらの都合で跡取りにするの、引き取るのと言って取り上げるのはフェアではないような気もする。
それに、モルガーナ家のような大家の令息というものは、恵まれているようでいてこれでなかなか不自由な側面も多々ある。デュアンのようにせっかく可愛がってくれる母親の元で伸び伸びと育っているものを、家柄だの爵位だのと早くから重荷を背負わせるようなことになるのは、自分がその立場だっただけにディにしても出来れば避けたいことなのだ。
それでやっぱり、今はまだ、いないことにしておいた方が無難だろうなと考えてディは話を逸らそうと思ったのだが、さっきの彼の「もしいたら」という一言は、既にロベールにかなりアピールしてしまっていた。それに、親の目から見てもプレイボーイになっても無理はない美貌と才能の持ち主であるディに、子供の一人くらい生んでやろうという女性が現れない方が不思議だと常々思ってはいたのだろう。それでなんとなくピンと来たらしく、ロベールはその「隠し子」の話を追求せずにいられなくなったようだ。
「おまえ、今のはまさか本当じゃないだろうな」
「何がです?」
「だから、隠し子だよ、隠し子。本当にいるんじゃないのか」
「いませんよ」
「こら、白状しろ」
「いませんてば」
「だったらなんであんなことを言うんだ?」
「だから、単に話じゃないですか、もしいたらっていう」
「今まで、一度もそんなことを言ったことはなかったじゃないか」
「考えつかなかっただけですよ」
さすがに父親のことで、ディが随分困った様子になったのがロベールには手に取るように分かったらしい。しかし、それ以上はディを追求してもシラを切りそうだと思ったらしく、それで彼は一旦納得したと見せかけて、ちょうどお茶を運んで来たアーネストに何気に矛先を向けた。
「アーネスト」
「はい?」
「きみは知ってるだろう?」
「何をでございますか?」
「ディの子供のことだよ」
「は?
坊ちゃまの?」
予想もしていなかった質問をいきなり受けたせいだろう。それにアーネスト自身、デュアンの存在にすっかり慣れてしまっていたからなのだろうが、言ってから彼は珍しくあわてて、しまった、という顔をした。ディは頭を抱えている。しかし、それを聞いて喜んだのはロベールだ。
「おお、男の子なのか!」
「だんなさま、申し訳ございません!」
ディはアーネストに怒る道理ではないことくらい承知している。しかし、いつも冷静沈着なアーネストにとって、これは百年に1回、あるかないかの大失言だ。それだけに、本人が思いっきり恐れ入ってしまっているのも分かったから、ディは苦笑しながらもいいよという様子で頷いて見せ、早々に執事を下がらせた。
「こら。アーネストは知っていて、なんで私が知らないんだ?
え、おい」
「いや、ですから...」
「やっぱり、いたんだな。私もいるんじゃないかとは前々から思わないでもなかったんだ。しかし、おまえがそんなこと、おくびにも出さないもんだから」
「.....」
「で、いくつなんだ、その子は」
こうもはっきりとバレてしまっては仕方がない。こんなミスは一度としてやったことのないアーネストが口を滑らせるということ自体が天啓かもしれないなと観念して、ディはやっと本当のことを父に話す気になった。
「一番上が来年13で、次が11、三番目がそろそろ9才です」
それを聞いて、今度こそロベールは腹に据えかねたらしい。大爆発である。
「ばっかもーん!」
「お父さん、そんな怒らなくても」
「これが怒らずにいられるかっ!
じゃ、おまえはなにか?
私があれほど跡取りのことで頭を痛めていると知っていて、十年以上も子供のことを隠していたっていうことか?
しかも、なんだって? 13と11と9才って、それは3人も子供がいるってことなのか?」
「そういうことに、なりますね...」
「全く、なんてやつだ、この親不孝者。いるならいると、なんでさっさと言っておかん」
「いや、ぼくもいろいろと考えるところがあって」
「おまえに考えなんてものがあるわけがないだろう。いったい誰に似たんだ、そのちゃらんぽらんなところは。とにかくそれじゃ、三人とも母親のところにいるのか?」
「はい」
「3人も子供を作っておいて、どうしてその女性と結婚しないんだ?」
常識的に考えて、子供たちの母親は一人だろうと疑いもなく思っているらしいロベールにディはまたまた怒鳴られるのを覚悟で真相を白状しなければならなかった。
「それは、3人とも母親が違うので...」
言われてとうとうロベールは怒鳴る気力も吹き飛んだらしい。呆れかえって頭を抱え、しばらく黙ったままだ。
「お父さん?」
「.....」
「もしもし?」
「...どうせ、そういうヤツだ、おまえは。私はもう言葉も出ん」
「褒めてくれるって言ったじゃないですか」
「バカもの。それは子供がいたらという話で、おまえがそれを隠していたことについては心の底から怒ってるんだぞ、私は」
「はい...」
「いい、もうこれ以上は怒る気にもならん。ともかく、会わせてはくれるんだろうな、その子たちに」
ディは少し考えて、そうですね、と言った。
「母親たちがいいと言えば」
「とにかく集めろ。話はそれからだ」
そう言って、嬉しいやら腹が立つやら、複雑な心境でぶつぶつ言いながらロベールが自室に引き上げてしまうと、すぐさまアーネストがさっきの失言を謝りに来た。しかし、ディは既にそれについては殆ど気にしていない様子で、彼の執事にも天啓かもしれないから気にするなと言っておいた。
何事も、ものごとには起こるべき時というものがある。まだしばらくは隠しておけるかなと思っていたディだが、父の年齢や子供たちの年頃を考えると、そろそろ露見して然るべき時期だったのかもしれない。上の二人にはディ自身でさえ会ったことがなかったわけだが、こうして未だ公には知られざる彼の息子たち三人が、一堂に会することになったのである。
original
text : 2008.7.8.
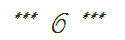
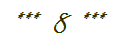
|
