|

祖父との通話を切ったあと、ファーンがまたもらったばかりの自転車の所に戻ろうとするとドアにノックの音が聞こえた。
「はい?」
「ファーン、ぼくだよ。今、ちょっといいかな?」
声は、一番年上の従兄であるウィルのものだった。彼は上の叔父リチャードの長男でもう15才になる。曽祖父にちなんで名付けられているから本当は"ウィリアム"なのだが、まぎらわしいのでふだん家族はみんなウィルとかウィリーと呼んでいた。彼もファーンと同じ寄宿学校にいて、今日も一緒に帰って来たばかりだ。
「ええ、どうぞ」
ファーンが答えると、ウィルはドアを開けて入って来ながらにっこりしている。いつも黒ぶちの重たい眼鏡をかけているのでぱっと見はトボけた印象があるが、眼鏡をはずすとなかなかどうして曽祖父ゆずりのハンサムな少年だ。しかし、成績優秀なのもどちらかと言えば何事につけてもつっこんで研究するのが好きという学者肌だからで、従って、自分の容姿をひけらかそうとは全然考えてもみないらしい。
「お邪魔じゃない?」
「いえ、全然。あ、座って?」
「うん」
年下の従弟が促すのに頷き、ウィルがソファにかけるとファーンもはす向かいのアームチェアに腰を降ろした。ナチュラルカラーの大きなソファを中心に据えて、ブラウンを基調にまとめてある天井の高い居間だ。この居間にはもちろん寝室やバスルーム、ウォークインクロゼットなどもついていて、そのひとまとまりのスイートがファーンの部屋なのである。どの一室も色調は落ち着いているが、選ばれている調度が若々しいので爽やかな印象があった。しかし、これまたまだ十歳そこそこの少年の部屋としてはオトナっぽすぎる趣向と言えるだろう。
メリルやデュアンにしてもそうなのだが、どうやらディの息子たちは三人とも、この年で既に両親ゆずりの並ならない美的感覚を発揮しているようだ。みな自分の部屋をどう飾るかについてそれぞれかなりコダワリがあるらしい。
「イヴから聞いたんだけど、シャンタン伯爵がいらっしゃったんだって?」
「ええ。ぼくは知っての通り、学校にいたから会えなくて残念だったんだけど」
イヴというのはウィルのひとつ下の妹、イーヴリンのことだ。優しくてたおやかな美少女で、ウィルとも、もちろんファーンとも仲がいい。
「女の子たちは、学校が始まるのぼくらより少し遅いだろ?
だから伯爵が見えたときにはまだうちにいたらしいんだけどさ、ユージーやロゼッタがもう大騒ぎだったって」
「え?
どうして?」
「だから、あのデュアン・モルガーナ伯が一緒に来られたことでだよ」
ウィルの言うのにああ、なるほどと思ってファーンは笑っている。ユージーことユージェニーとロゼッタは下の叔父であるダドリーの双子の娘たちだが、イヴとは比べものにも何もならないオテンバなのだ。年はファーンと同じくらいだから女の子とはいえまだまだやんちゃな盛りで、しかも、この二人は二人ともがとにかく美形に目がない。日頃から俳優だろうが歌手だろうが、美しい青年と見るときゃあきゃあ騒いでいる。その二人がナマでディを目撃する機会に恵まれたのだから、どんな騒ぎになったかは少なくともファーンには目に見えるようだった。
「そりゃ、大変だ」
「だろ?
学校に戻っても、その話で友だちと一週間ばかりずっと盛り上がりまくってたらしいから」
「へえ」
「もちろん、おじいさまたちにきつく言われていたから、きみのことでみえたなんてことはヒトコトも言ってないらしいけど、まあ、彼のお父さん、シャンタン伯が大じいさまの古い友人だということでね」
「それは助かった。今の時点であの二人の友だちに知れようものなら、お披露目の話がまとまる前に社交界中に広まってるでしょうからね」
「そういうこと。それでさ」
「ええ」
「シャンタン伯が見えたということは、きみが跡取りになる話、本格的に決まっちゃったってことなのかな」
「そうみたいだよ?
さっき、大じいさまもそうおっしゃっていたから」
「そうか...」
その答えを聞いてウィルがちょっと表情を曇らせたので、ファーンはあれ?
と思って、それがどうかしたの? と尋ねた。
「ん?
いやね。実は、ぼくはずっとぼくよりきみがこの家を継ぐ方がいいんじゃないかと思っていたから」
言われてファーンは驚いた顔をしている。従兄がそんなことを考えていたなんて、彼は今の今まで想像したこともなかったからだ。
以前、ウィリアムがロベールにも言っていたように、クロフォード家はよほどのことがない限り直系の長子相続が原則である。従って、ウィルの父が次の公爵、その次がウィルと、そんなことは家族の誰も改めて考えてみることすらしないほど決まりきったことなのだ。なにしろ、多少の例外はあるものの、それで数百年も来ている家なのだから仕方がない。しかも、ひとあたりがよく、人望もあって成績優秀というウィルが跡取りに相応しくないなどと考える者は、ファーンも含めて家族の中に一人たりともいるわけがなかった。
「しきたりとは言ったって、いまどきの世の中だろう? もともとあれは、誰が継ぐかってことでモメないために決まってることだって大じいさまもおっしゃっていたし、それなら跡取りってことになってるぼくが、自分から辞退すればそんなに問題ないじゃない。だからさ、きみがクロフォード家を継いでくれれば、ぼくは大学の先生にでもなって、のんびりやれるかもしれないな、とかね。都合のいいこと考えたりしてたんだけど、それにどう考えても、きみの方がその器って気もしたし。大学に進む時期になったら、そういう話を持ち出そうかと思っていたのに、でも、きみはシャンタン家に行ってしまうんだねぇ...」
言ってウィルは残念そうに深い溜め息をついた。ファーンが不思議そうな顔で言っている。
「どうしてそんなこと?
っていうか、なんでウィルよりぼくの方が跡取りの器だなんて思ったわけ?
ちょっと信じられないよ」
「う〜ん...。まあ、理由はいろいろあるけどさ」
ウィルはどう説明したものかと黙り込んでいたが、しばらくして言った。
「ぼくが一番ショックだったのは、たぶんランドルフのことじゃないかと思うよ」
なんでここにその名前がと、よほど意外だったらしい。それでファーンは、この子には珍しく鳩豆な表情で尋ねた。
「ランドルフ?
それってランドルフ・シンプソンのこと?」
「そう」
「なんで彼が関係あるわけ?
ごめんなさい、ちょっと脈絡がつかめなくて」
「だからさ、きみは彼と仲がいいじゃないか」
「仲がいいって、それ誤解だよ、ウィル。ぼくはいつでもからまれてるだけで」
「からむにしても、今のあいつがかまうってことがだよ。ぼくとはここ数年、口もきいてくれないんだよ?」
ランドルフ・シンプソンは三、四年前までウィルの親友だった少年で、もちろん今も同じ学校にいる。その頃まではウィルとも成績を張り合うほどの優等生で、非常に仲が良かったようだ。しかし、事情があって彼の両親が離婚することになり、そのあたりから素行がおかしくなった。夜中に学校を抜け出して怪しげな界隈を遊び歩いたり、無免許でバイクを乗り回したり、あまりお品の宜しくない連中とつきあったりと、おかげで今では回りから立派に"問題児"のレッテルを貼られている。当初、ウィルはそんな親友のことをとても心配して、そういう行動はやめるようにずいぶん説得しようと試みたらしいが、当時のランドルフは聞く耳を持たなかった。それどころか、なんとかしようとすればするほど彼の素行は輪をかけて悪くなって行くような気すらして、ウィルは仕方なく静観する側に回らざるをえなくなったのだ。
しかし、そのランドルフ、ファーンにとっては五つ近く年上の先輩ということになるわけだが、彼がちょっとした経緯から今ではファーンにずいぶんなついているのである。少なくとも、ウィルにそう見えるくらいには親しくしていると言っていいだろう。
「きみとつきあうようになってから、彼、けっこうマトモになって来てるだろ?
ぼくには出来なかったことだよ。学校に入った時からだから、あの頃でももう軽く五年越しの親友だったのに何も話してくれようとしなかったし。正直言って、彼が一番荒れてた時ってぼくにはどうしていいか分からないって感じだった。今だって、それは同じだけどね」
あれは"マトモ"と言うんだろうかとファーンは内心首を傾げていたが、確かに以前はもっとワルかったかもとは彼も思う。しかし、それはウィルが考えているらしいように、ファーンの説得力が効を奏したというわけでは全然なく、全てが成り行きだったのだ。
一年半くらいは前のことだっただろうか。その頃はまだランドルフは十分に正真正銘の"問題児"だったので、下級生たちの殆どは恐がって近づかなかったものだ。もちろん、ファーンにしても、そんな危ない、しかも五つも年上の先輩に積極的にかまおうなどとはまるっきり考えてすらいなかった。しかし、向こうの方がかまって来たのだから仕方がない。
おそらくはウィルの従弟ということもあったのだろうが、申し分ないトリプルA級優等生のファーンがナマイキにも見えたのだろう。あいつ、ガキのくせにちょっと態度デカくないかというわけで、少し痛い目を見せてやれということになったようだ。こういう学校では、よくあることである。
今でこそファーンもランドルフと、彼が日頃つるんでいる友人たちがそう悪くない連中だということは知っているが、当時はそんなことは知らないから、いきなり上背のある少年たちに回りを囲まれた時はけっこう恐い思いをさせられた。しかし、普通の優等生なら、それで泣いて許してもらって終わりかもしれないのだが、その辺りもファーンは"普通"ではない。うんと幼い頃からウィリアムのすすめもあって叔父のダドリーに拳法や空手を習っているからだ。
これで元々はケンカっ早い方だし、それにそんな経験も初めてだったので売られたケンカに手加減なしで相手になってしまい、気が付いたら案の定、ファーンはランドルフに参ったと言わせていた。その頃、既に有段者のレベルにあったファーンと、年上とはいえ実戦的な武道とは未だ縁のない少年たちでは、やはりファーンの方が強かったということだろう。以来、どういうわけかランドルフにすっかり気に入られたらしく、ファーンにとっては迷惑な話だが、行き合わせるたびにからまれてしまうのである。しかし、その経緯を知らないウィルには、従弟にランドルフの気持ちを和らげる何らかの方策があったように見えるのだろう。
ファーンは、自分を襲って来たなどという、ウィルが知ればかつての親友の凋落いかばかりと嘆くに違いない"悪事"をわざわざ耳に入れることもないだろうと思ってこれまで黙っていたのだが、彼がそんなふうに気にしているとなると、これは話しておく方がいいのかなという気もしてきた。当時ならともかく、今ではウィルの言ったようにランドルフの素行がいくらかマシになって来てもいるからだ。
「ねえ、ウィル」
「ん?」
「やっぱりウィルは誤解してると思うよ。ぼくがランドルフと口をきくようになったキッカケを知らないから」
「キッカケって?」
「実は、一年半くらい前かな。ちょっとやり合っちゃったんだ、彼と」
「やり合ったって...」
「つまり、ケンカ。向こうが売って来たから、仕方なかったんだけど」
ウィルはそれにかなり驚いて、え〜っ、と声を上げた。
「なにしろ相手が三人がかりだったから、ぼくも回避するようなゆとりなかったし、力いっばいやっちゃって」
「三人?
そりゃ、ひどい。昔の彼だったら考えられないようなことだ。ましてや、5つも年下の下級生に」
「と、思うと思ったからさ。それで言わなかったんだよ」
それを聞いてウィルはファーンの言わんとするところが理解できたようだ。
「なるほどね。しかし、いくら三人がかりとはいえ、きみが力いっぱいやっちゃったってことは...」
「そう。危うく、彼の腕を折ってしまうとこだったんで、ぼくも後でかなり反省した。でもなにしろ、トレーニングとか試合じゃなくて実戦的に使ったのは初めてだったし、けっこう必死だったから余裕もなくて」
「まあ、それはねえ...。一方的にからんで来たんだろ?」
「うん」
「どう考えてもそれは彼の方が悪いよ。それじゃ、折られたって文句言えないと思う」
「その前に向こうが負けを認めてくれたんで、ぼくも正気に戻れたからなんとかコトなきをえたというか」
ウィルにはそれで経緯が呑み込めたらしく、大きく頷いて、そういうことか、と言った。
「それ以来、どういうわけか、ぼくの顔見るたびちょっかい出してくるんだよ、彼は。いつも、からかい半分なんだけどさ。だから、仲がいいとか、そういう問題じゃなく...」
「それは、気に入ったんだと思うよ、きみのこと」
「それこそ、え〜、だよ。毎度、からまれてからかわれるぼくの身にもなってよ」
心底、困った様子でファーンが言うので、ウィルはくすくす笑っている。
「いや、ぼくの知ってるランディならたぶんそうだと思って。なんかさ、三人がかりって聞いた時は、あいつ変わっちゃったなって一瞬思ったんだけど、結局、潔く負けを認めたわけだろ?」
「まあ、それはね」
「そのへんは変わってないんだって気もしてさ。それにたぶん、もともと本気できみをキズつけるつもりはなかったんじゃないかな。からかおうとしただけで」
「どうだろう。かもしれないけど」
「そうかあ、なるほど、そうすれば良かったのか」
ウィルはその話を聞く前に比べれば随分楽しそうな様子になって、一人で何か納得したように頷きながら言った。
「"ペンは剣よりも強し"って言うけどさ、やっぱり"力の論理"ってあるよねえ。ダドリー叔父さんがよく言ってる通りだな。ぼくは、どっちかっていうと暴力では何も解決しないって思ってる方だけど、リクツだけでもやっぱりダメってことなんだね」
「相手によりけりだと思うけど、あの場合はそうだったかも」
「なにはともあれ、きみにケガがなくて良かったよ。ランドルフも痛い目見て、少しは目がさめて来たってことかな」
「目がさめて、アレ?」
「少なくとも、グレ始めた頃よりはかなりマシになってるとぼくは思うけど。そう言えば、最近、成績も元に戻ってきつつあるみたいだし。一時は壊滅的なとこまで落ちてたからなあ」
「そうなの?」
「うん。教授連も、ありゃ、しばらくほっとくしかないって殆ど見捨ててたもんだけど」
それを聞いてファーンは吹き出してしまった。
彼らの先生たちは、クランドルでも名門中の名門たる学校で教鞭を取るだけあって、なかなか一筋縄ではゆかない傑物ばかりだ。特に、上級生を教える教授たちはそれぞれの分野で大学でも講義を行うような識者ばかりであるし、それだけにみな人物でもある。だから十代半ばの少年が、ちょっと"問題児"に成り下がったくらいではそうそうビビったりするわけもなく、校則を破ればそれなりきびしく叱るし規定の罰も与えるが、まあ若いんだからというオトナの余裕をもって対応している。彼ら自身も、その大半が昔はそういう元気の良い少年であったことも幸いしているだろう。
教授連にとって生徒たちは、自分の若い頃を思い出させる存在でもあるようだ。
「でもまあ、きみは迷惑かもしれないけどさ。根は決して悪いヤツじゃないから、あいつがかまってくるなら相手してやってよ。ぼくが力になれれば良かったんだけど、同級生で親友だったっていうのが逆にマイナスに作用してるのかもしれないし。避けられちゃってるからね、ぼくは」
ウィルがちょっと淋しそうに言うので、ファーンは彼がまだ今でもランドルフのことを友人として好きなことに変わりはないんだなと思い、その気持ちを汲んで、ええ、と答えて頷いた。
「悪いヒトじゃないんだろうなってことは、ぼくも。けっこういいとこあるんだなって部分も見てないわけじゃないんで」
「そっか」
ファーンの答えににっこりして頷くと、ウィルは続けた。
「話は舞い戻るけどさ、跡取りのこと」
「あ、ええ」
「ぼくがきみの方が相応しいんじゃないかと思っていたのは、それだけが理由ってわけじゃないんだよ。うちを継ぐとなるとやはり、どうしても経済方面に進まざるをえないだろ?
ぼくは経済学そのものは面白いと思うけど、あくまでそれは薀蓄の部分に興味があるってことであって、実際に経営者として実経済に携わるとなるとその重さは全然別モノだよ。それは、父さんやおじいさまを見ているとつくづく思う。はっきり言ってぼくは恐いね、あんなふうに重い責任を負う立場に立つのは。それが沢山の人の生活に影響を及ぼすと考えるとなおさら」
「ああ、それはぼくももちろん思いますよ」
「そう?
だけど、大じいさまもよく言われるように、きみはアタマがいいだけじゃなくて、アクティヴに人をひっぱってゆけるパワーを持ってるとぼくも思うんだ。だから、そういう立場に立っても立派にやってゆけるだろうという気がするね。まあ、どちらにしてもシャンタン家の当主ということになれば、将来的にそうなるんだろうけど、実際、きみはこのごろますますリーダーに相応しい器になりつつあると見ていて思うよ」
言われてファーンはちょっと嬉しそうな顔をした。
「へえ。ウィルにそんな風に思われてるなんて驚きだな。ぼくはうんと子供の頃からずっと、ウィルみたいにならなくちゃって思って努力して来たのに」
「えー、なんで?」
「だって、ほら。ぼくは小さい頃、けっこうケンカっ早かったでしょう?
アンドルーにからまれると売りコトバに買いコトバですぐ取っ組み合いに突入しちゃったりして」
アンドルーというのはウィルの二人いる弟のうち下の方の子のことで、ファーンとは年も殆ど同じだ。それだけにアンドルーにとってファーンはライバル意識を燃やす対象になりやすかったらしく、ごく幼い頃は何かとからんでくるのが常だった。ウィルはその頃のことをよく覚えているようで、笑いながら言っている。
「そうだったね。母さんたちも、あの二人はよるとさわるとかまびすしいってよくボヤいてたし」
「でも、そういう時に決まって割って入ってくれるのがウィルでさ。それもダドリー叔父さんみたいに一も二もなくおまえたちヤメろってビシバシっと力で引き離すっていうんじゃなく...、彼にかかるとぼくたち殆どネコのコだったからね。でも、ウィルは、まあまあまあってまずぼくたちの間に入ってきて両側に分けて、それから懇々と説教を...」
言われてウィルは声を上げて笑った。
「そうそう、そうだった。だって、きみたちはいつも、あまりにもつまらないことでケンカ始めちゃうんだもの。おやつの取り合いだの、おもちゃの取り合いだの、うちの母さんがきみを褒めただの、贔屓しただの、もちろん母さんはそんなつもりないんだけどさ。で、挙句の果ては、ケンカしてるくせに何が原因だったかきみたち自身で覚えてないってことがよくあったじゃないか」
ファーンも言われて笑いながら答えた。
「うん、そう。それでそのたび、ぼくもアンドルーも自分たちがものすごいバカのように思えてさ。ウィルってやっぱりオトナだな、ああならなくちゃいけないんだなって思ってお互い気をつけようと約束するんだけど、でも結局また同じことやってるんだよね」
当時、まだ学校にも入る前のファーンたちにとっては、5つ年上のウィルがオトナに見えたのも無理はなかっただろう。もともとウィルは温厚で思慮深い性質をその父から受け継いでいるし、しかも当時、既にクロフォード家の嫡子という自覚が彼にはあったようで、いずれ人の上に立つ者として父や祖父、曽祖父を見習わなければとも思っていたらしい。
そんな従兄を見て育ったファーンにとって、転換期は今いる寄宿学校に入学した時にやって来た。クロフォード家では子供たちを幼稚園に行かせる習慣が代々なく、就学年齢になるまでは家庭教師をつけておくのが常だったので、ファーンはこの時初めて広い世間、実社会の片鱗に接する機会を得たと言っていい。
「学校に入って最初に思ったことは、ウィルって家でも学校でも変わらないんだなあってことだったよ。って言うか、学校では家にいる時より更に優等生だったし」
「そうだっけ?」
「うん。同級生や下級生ばかりじゃなく、上級生や教授たちまでウィルのことは信頼してるって感じだったもの。考えてみればアンドルーだってウィルにはいつも素直だし、なのに何故かぼくとはケンカになっちゃう。それって改めて気づくとけっこうショックなコトだったんで、何故だろう、と一生懸命考えながらウィルを観察してたんだ。すると、そのうちに分かってきたことがあって」
「観察されてたとは知らなかったな」
「実は、密かに見てたんだよ。そうすると、あなたはもともとそうなんだろうけど、なんていうか、いつもすごく落ち着いてて、何があっても慌てるとか、パニクるとかしないんだよね。言われたことにも、よく考えてから反応してるっていうか」
「ああ。確かにぼくはそういうところがあるかも。ただ、ぼくとしては考えないと反応できないってだけなんだけと。どっちかっていうと、おっとりしてるとか、のんびり屋とか言われるしね。そういえば昔、ランディには"おまえ反応遅い"とか言われてよく呆れられてたな」
「そうなの?
でも、ぼくはそれに気がついた時、これがコツだなって思ったんだ。だってぼくの場合、例えばアンドルーに何か言われるといつも間髪を入れずに反応しちゃってたから。それじゃ、売りコトバに買いコトバになるのは当然だよね。それが分かってからは、何か言われても腹を立てて反応する前にぐっとこらえてワンテンポおいて、それから反応するように心がけるようにしたんだ。そうするとアンドルーの方が調子狂うらしいってことに気がついたんで、これはいけるぞと思ってさ。ぼくたちのケンカが減ったのはそれからかな」
「なるほど。いつの間にかツノつきあわなくなってたから、学校に入って二人ともちょっとオトナになったんだなって思ってたんだけど、そういう裏があったとはね」
「うん。で、そうやってるうちに、アンドルーが"おまえ、なんでつっかかって来ないんだよ、面白くないじゃないか"って」
それを聞いてウィルは大笑いしている。
「その時初めてぼくは、彼がぼくにからむのはもしかしてジャレたいだけだったんだろうか?
と思うようになったんだ」
「あいつはさあ」
まだ笑いながらウィルが言った。
「いや、もう言ってもいいと思うから言うけど、あいつがきみにからんでたのは、アンナおばさまが原因だったんだよ」
「え、どうして?」
「だからさ、あいつは叔母さまのことが凄く好きなんだ。今でもだけどね。つまり、うちもダドリー叔父さんとこも、どちらも母さんが父さんの手伝いで家を空けてることが多いじゃないか。それで、ぼくたちに一番近いところにいるお母さん代わりって、アンナおばさまだったんだよ」
「ああ...」
「ぼくたち8人、自分の母さんより彼女の方が近い存在と言ってもいいかもしれないけど、特に、アンドルーはきみと同じ時期に生まれてるだろ?
だから、いつも一番側にいるきみが羨ましかったんだと思う」
今明かされる意外な真実に、ファーンはちょっとコトバを失っている。
「決して、きみのことがキライだったわけじゃなく、でも、アンナおばさまは優しいからねえ。お菓子焼いてくれたり、絵本読んでくれたり。あの頃はまだショーンは生まれてなかったけど、それでも彼女には8人子供がいたようなものなのに、みんなに分け隔てなく優しかったよ。もちろんおばさまは実の息子だからってきみだけ贔屓するような人じゃない。でも、実際に三歳になるまで一緒の部屋で暮らしてたのはきみだけだったし、その後も彼女の部屋に一番近いところにいるよね?
実の子供なんだから、アタリマエなんだけどさ。でも、それがあの頃アンドルーには気に入らなかったわけ。なんで、あいつだけって感じで」
「う〜ん。つまり、それって恨まれてたってこと?」
「まあね。いや、あいつもさ、アタマではぼくたちの母さんは別にいるって分かってたとは思うんだけど、子供ってやっぱり一番近くで優しくしてくれるヒトになつくじゃないか。だから、自分がアンナおばさまの子じゃないってだけで損してるって気分だったんじゃない?
今は、あいつもそこまでコドモじゃないけどね」
「そんなこと、想像してみたこともなかったよ」
「でも最近は、きみたちうまくやってるじゃない。クラブも同じだし」
「うん。ケンカにならなくなってから、なんとなく」
「あいつは、基本的にはきみのことが好きだと思うよ。ただまあ、そんなわけで心中フクザツだったんじゃない?
小さい頃は特に」
ファーンはそれへ深く頷きながら、まだまだダメだなあ、ぼくは、と言った。
「どうして?」
「だって、そういうことに全然気がついてなかったんだもの。まだまだ人間に対する考察が甘いなと思って。それ知ってたら、もっとずっと早く対処の方法があったよ、きっと」
「そりゃあ、きみのトシだもの、仕方がないよ。ぼくだってそういうの、始めから分かってたわけじゃないし。ま、それって経験とか、トシの功とかいうヤツの積み重ねなんじゃない?」
言われてファーンは頷いている。
「ま、それはそれとしてさ」
「ええ」
「きみがシャンタン伯爵の跡継ぎになるってことについてはもうはっきり決まっちゃったみたいだし、ぼくがこの家を継ぐのはもう運命と思って諦めるしかないかなとは思うよ。きみのお父さん、モルガーナ伯爵は、画家としてあれだけの仕事をしながらもモルガーナ家をしっかりと支えていらっしゃるわけだし、それを考えればぼくも、好きな研究を続けながら、ヘタな文章を書きながらでも、なんとかやってゆけるかもしれないなという気はする。弟たちも、いてくれるしね。これはもう腹をくくって、大じいさまたちを失望させないように頑張るしかないだろうな」
「ぼくは今までだってウィル以外がこの家の跡継ぎになるなんて、想像したこともなかったもの。大じいさまだって、おじいさまたちだって、そんなの全然疑いもしてないと思うよ」
「うん、まあそれはね。でも、ぼくの思惑はともかく、まずはきみの進路が決まったことにおめでとうを言わなきゃいけなかったね」
「有難う」
「これでぼくときみはこの先もずっと同じ世界でやってくことになるんだろうし、お手柔らかに頼むよ」
言って差し出されたウィルの手をファーンは嬉しそうにしっかりと握り返し、こちらこそと言った。それへウィルもにっこりしている。
「あ、そうだ。そういえば、ルーク博士の新しい論文がネットにアップされてるよ。もう読んだかい?」
「いえ、まだ」
「そう?
じゃ、読むといい。今回のテーマはミドルイーストで、特に宗教的、文化的見地からみたあの地域の特性を、政治や世界経済とからめて分析してあって凄く面白かったから」
「へえ。ルーク博士らしいね」
「うん。ほんと凄いよねえ、彼は。ぼくと大して違わない年には、もう今のIGDの基本的な構想を持ってたっていうんだから。正真正銘の天才だよね。どうしてあんなに、多極的な側面からものごとを的確に分析できるのか。アタマのデキって言っちゃえばそれまでなんだけど、ぼくから見ればあれは殆ど超能力だよ」
ファーンがアレクに心酔している一方で、ウィルのご贔屓はマーティアとアリシアなのだ。彼らのように将来はビジネスの世界を目指す少年たちにとって、IGDは現在やはり最もインパクトの強い企業体だということだろう。ましてや、その中枢にいる3人はIGDの成立以前からクランドル全体の注目を集めていたから、その存在感には相当なものがある。
「そうそう。この前のディナーの時、お父さんがぼくのことロウエル卿に紹介してくれるって約束してくれたんだよ」
ウィルがマーティアの話を持ち出したので、ファーンはふと父との約束を思い出したようだ。
「えっ、本当?」
「うん。彼が忘れてなければだけど、そのうち実現するかもしれない」
「それは凄い。ああ、そうか。モルガーナ伯爵とロウエル卿は、うんと子供の頃から親友どうしってよく知られた話だったよね」
「そう。それで、ぼくが"ロウエル卿を尊敬している"みたいな話をしたら、そのうち一緒に食事でもって。なんか全然夢みたいな話で、今でもまさかって感じがずっとしてるんだけど」
「それはそうだろうなあ。なんてったって、ロウエル卿だもの。ルーク博士たちにしてもそうだけど、よほどのコネクションがなきゃ会えるような人たちじゃないよ」
「期待半分、恐いの半分かな。でも、もし本当に実現したら、ルーク博士のことも聞いておこうか?
何か、知りたいことはある?」
「それは、もう山ほど。ぜひお願いしたいな。何よりもまず一番聞きたいのは、どんな勉強のしかたをしたらあんな風になれるのか、だよ。そりゃそもそもマネるのが無理な話だろうけど、その秘訣の一端なりとも垣間見れれば凄く参考になると思うから」
「あ、それはぼくも知りたい。うん、それに、機会があったら、ウィルのことも伝えておくよ」
「わあ。それってなんか、わくわくしちゃうね。これは、きみのお父さんがモルガーナ伯爵だったことに感謝しなきゃならなくなるかも。いつかはぼくもルーク博士やアリシア博士に会ってお話が聞きたいと思ってるし、そんなキッカケがあるならもう頑張って、本気で彼らに相手にしてもらえるくらいにならなくちゃ。それ考えるとなんだが、勇気と元気とやる気が沸いてきたぞ」
マーティアたちの話になるとウィルはこうだ。よほど彼らのことを尊敬しているのだろう。もちろんそれはファーンも同じだったから、その気持ちはよく分かる。積極的な経済主導による世界変革という、これまでの哲学が決して考えつきもしなかったような未曾有のゲームに真正面から挑戦しているIGDとその中心にいるアレクたちは、彼らのように理想の高い少年にとって既に英雄と言っていい存在だからだ。いつかはそのプロジェクトの一端なりとも担うだけの力を持ちたいものだとは、ファーンも常々思っている。
二人はそれからもその話で時間を忘れて盛り上がり、将来の協力関係を堅く誓い合っていた。
original
text : 2009.5.13.+5.14.+5.24.+5.27.
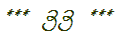

|
