|
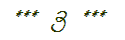
数々の名画が生み出されて来たディのアトリエは、彼の熱狂的ファンにとって既に伝説の聖域として語り継がれてさえいる場所だ。一度でいいから見てみたいというのはデュアンのみならず、全てのファンの殆どかなえられることのない望みと言ってもいいだろう。そんなところに、例え自分が彼の実の息子だからとはいえ、こんなにすんなり入れてもらえることになろうとは、デュアンもそれが実現するその時になるまで、とても信じられないようなことだった。ディが案内してくれて、アトリエの重い扉が目の前で開かれた時、本当に入ってもいいんだろうかと戸惑いと眩暈さえ覚えたほどだ。それほどこの子は長いこと、デュアン・モルガーナという彼と同じ名を持つ大画家に心酔し憧れていたのでもあった。
「どうしたの?
入ってもいいんだよ?」
「あ、はい...」
ディに促されてやっとデュアンは足を踏み入れることが出来た。昔はサン・ルームだったものを改装したのだと伝えられている通り、高い天井とロフトのようなスケールを持つそのアトリエの窓は庭に面して一面に広がり、庭と言うより神秘的な深い森とさえ見える庭園が一望に見渡せた。
大きなフランス窓の近くの一段高くなったフロアにはゆったりとしたソファのセットが置かれ、少し離れた一画にはおびただしい数の絵筆や絵の具が乗せられたテーブルと、それに画材が収められているらしい棚が見える。イーゼルに立てられた制作中らしい大きなキャンバスは、今は向こうを向いていてこちらからはどんな名画が生まれようとしているのかを見ることは出来なかったが、しかし壁面にはひと目でそれと分かるディの作品がいくつも飾られているのが見えた。
デュアンが何度も飽かずに足を運んだ数々の個展や、大切にしている画集ですっかり見覚えているものもあったが、新作らしくまだ外の誰の目にも触れていないようなものもいくつかある。どちらにしても運命的に歴史的名画として芸術史に残ることが確実なそれらの作品の迫力に圧倒されたらしく、デュアンは部屋を一歩入ったところで立ち止まってしまい、しばらく動けないほどだった。ディはその様子を楽しそうに見ている。
「あ...、あの....」
「何?」
「近くに行って、絵を見てもいいですか?」
「いいよ、どうぞ」
芸術家にとって、自分の精魂傾けた作品に純粋に感嘆してくれる鑑賞者ほど嬉しいものはない。先ほどから話をしていても、デュアンがどれほど画家としてのディを尊敬し、崇拝しているかはよく分かることだったので、既に目の前に広がる光景に夢中になっているらしいデュアンの様子をディは微笑ましく思いながら眺めていた。
このアトリエだけでも既に美術館の一室のように名画が居並んでいるのだ。幼いとはいえ、育ってきた環境もいいのだろう。既に絵を見る目が養われている上に、誰より好きな画家の作品ともなれば、デュアンにとっては宝の山だ。絵に近づいてゆくと、ディに遠慮することすらもうすっかり忘れてしまったように一枚一枚熱心に見入っている。それでディはゆっくり鑑賞させてやることにして自分はソファにかけ、煙草に火をつけた。
デュアンが子供の頃のディによく似ているせいなのだろうが、こうしてこの子が彼のアトリエにいる様子は、まるでタイムスリップして過去に戻り、まさに子供の頃の自分を眺めているような不思議な錯覚をディに起こさせた。自分もあの年頃にはああやって、沢山の巨匠の作品を飽かずに眺めて溜め息をついていたものだ。そう思って、ふと彼は、もしかするとこの子は自分でも絵を描いているのかもしれないなという気がした。デュアンの熱心さは、単に絵を見るのが好きという以上の次元にあるように思えたからだ。
それから1時間近くも経っただろうか。デュアンはすっかり夢中になって絵から絵へ、前の絵を離れるのすら名残惜しそうにしながら次々と見入っていたのだが、ふいに長い時間が経っていることに自分で気づいたらしい。はっとした様子で振り向くと、ディがソファにかけて自分を眺めている。彼の微笑にデュアンも恥ずかしそうに笑い返し、そちらへ歩いてきた。
「ごめんなさい、ぼく、夢中になっちゃって」
「いいよ、全然。そんな風に熱心に見てもらえると、ぼくも嬉しいよ」
「本当?」
「うん」
デュアンは深く満足の溜め息をもらし、それにしても凄いですね、と言いながらディのはすむかいのアームチェアに腰掛けた。
「そう?」
「お父さんの絵って色彩がヴィヴィッドっていうか本当に凄くって、いつも思うんですけど、どうやったらあんな色が出せるんだろうなって。本物はまた一段と迫力だし」
「きみも、絵を描くの?」
「え...。ええ、まあ。ぼくのなんて、文字通り子供の遊びですけど」
恐縮した様子で言うデュアンにディは笑っている。
「じゃ、この後は保管室の方に行こうか?
もっと見たい?」
「もちろんです」
「良かったら、その間に夕食の支度をさせておくよ。そのつもりで準備はさせているんだけど、遅くなっても平気かな?」
「ぼくは全然。でも、いいんですか?
あんまり長い時間、お父さんのお邪魔をするのも...」
「そんなの気にしなくっていいよ。カトリーヌには電話しておこう。帰りはうちのクルマで送ってあげるよ」
「はい」
「彼女は家にいるかな」
「ええ。いつものことですけど、連日の締め切りで悲鳴を上げてます」
デュアンがにっこりして言うのへディも笑って頷き、アーネストを呼ぶとディナーの用意とカトリーヌへの連絡を頼んだ。それから二人は保管室に移って、夕食の支度が出来るまで沢山の名画や美術品を鑑賞して過ごしたが、ディはもともと子供の頃から「絵のこととなると際限がなくなるから困る」と父のシャンタン伯に愚痴られるほど見ることも語ることも好きだし、デュアンの方もその点で全く彼に劣らないようだ。
ディはデュアンと話しながら、そう言えば、マーティアが初めてこの屋敷に来た時も、こうやってディナーの用意が出来るのを待ちながら、この保管室で絵を見ながら過ごしたものだったなと、ふと思い出していた。あれから長い時間が経ってしまったが、それはディにとってとても楽しかった思い出だ。マーティアも今のデュアン同様、そのころ既に美術にも芸術にも相当造詣が深かったし、ディにとっては珍しいくらい良い話相手でもあった。
そうしている間に最初のぎこちなさもどこへやら、ディナーの席に移る頃にはデュアンもすっかりリラックスしてよく笑うようにもなったし、ディはディでなかなかこの初めて会った「実の息子」が気に入ったようだ。薄情と言われても仕方がないほどすっかり放ったらかしにしていたのに、カトリーヌは随分みごとにこの子を育ててくれていたんだなと思う。頭の回転も速そうだし、美術や芸術全般についての知識もよく教えられている。こんなことなら、もっと早くこちらから会いたいと言えば良かったなあという気もした。
そんなこんなですっかり遅くなるまで話しこみ、これ以上遅くなるとカトリーヌが心配するだろうという頃になってやっとリモでデュアンを送り出すことになったが、その前に、ディは自分の部屋に直通でかかる番号を教え、いつでもまた遊びにおいでと言っておいた。もちろんデュアンは大喜びで、お邪魔じゃないんなら、もちろんすぐまた押しかけてきます、と約束して帰って行った。ほんの半日の間に、二人は親子というより、既にすっかり親しい友人どうしのように仲良くなっていた。
original
text : 2008.5.29.-6.4.
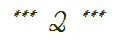

|
