|

とうとうやって来た父との対決、いや初の対面の日、もともと口下手だからあまりお喋りが得意ではないメリルのことで、母にはああ言ったもののいったいどうやって父に自分の不満をぶちまけたものかと、その朝になっても思案しまくっていたのだ。もちろん、前の晩はあれこれ考えて眠れたものではなかった。それでもなんとか迎えの車が来るまでには支度を整え、母と暮らしている大きな前庭を持つ白い瀟洒な家を出て、約束していたほんのワン・ブロックほど先の通りまで歩いて行った。
ゆったりしたブラウスに何の変哲もない濃い色のジーンズ、それへ丈の長いジャケットを羽織っていて、普段と変わらないアーティストなスタイルだ。メリルとしては別にそう見えるように意識してやっているわけではなく、こういう楽な格好が一番好きなだけのようなのだが、これでいつもスケッチブックだの画材だのを持ち歩いている様子は、誰がどう見ても既に"オシャレな絵描きさん"以外の何者でもなかった。メリルの場合、本当に絵が好きで四六時中打ち込んでいるから、よけいすんなりそう見えるのかもしれない。
母は今日くらい新しく作ってあげたスーツを着なさいよと言ったのだが、ブラウスもジーンズもおろしたてのものだし、内輪の集まりならこれで失礼じゃないでしょう?
とメリルの方が押し切ったのだ。何より、反感を抱いている父に媚びているように見られるのは絶対にイヤだったらしい。それに、メリルには生来"自分が自分である"ということを決して曲げようとしない頑固なところがある。マイラはそれがよく分かっているので、敢えてそれ以上は言おうとしなかったが、彼女にとっては日頃から、キレイな子なのに必要以上にオシャレに興味がないようなのが、母としてちょっと残念なところだ。もちろんメリルはメリルなりの好みに従って、この年頃の少年らしいオシャレをしているには違いない。けれども、ある程度の年齢になってからは彼女があれこれ楽しく選んだりオーダーしたりしたものに見向きもしなくなってしまっていて、男の子ってこういうところつまらないわねえ、とよくマイラにグチをこぼさせている。
そんなこんなでちょっとした紆余曲折が今日に至るまでにあったわけだが、それに加えて迎えの車を家から少し離れた所に停めてくれるように頼んだのは、伯爵家のエンブレムが付いたようなクルマが家の前に止まっていたりしたら、ご近所に何事かと思われるだろうという母の配慮だった。それはメリルも同じ意見だったから何も問題は無かったのだが、しかし、彼がいきなり度肝を抜かれたのは迎えに来ていた当のクルマそのものだったのである。
いったいこれが自家用車なのか?
とぶっとぶような純白のダブル・ストレッチ・リモなのだ。大型車のシャシを繋いで豪華な応接室のように内装を施した、世のウワサにのみ聞くあの巨大なリムジンというやつである。ロック・スターじゃあるまいし、と言いたいようなこんなクルマが、今どき、世の中に本当に存在するとはメリルは考えてみたことすら無かった。しかもそのフロントノーズには明らかにそれと分かるモルガーナ伯爵家のエンブレムが煌き、もちろん車体は曇りひとつないほど磨きあげられている。おまけにその横には制服姿のショーファー付きだ。
まだ若いショーファーはメリルの姿に目を留めて、それが迎えに来た本人であることを確認すると、そちらに歩いて来た彼ににっこり笑って、お待ちしておりました、と丁重に頭を下げた。よく躾けられて穏やかな、家の格を感じさせる気持ちの良い応対だった。それにどんな受け答えをすればいいのか、それは未だメリルの日常のマニュアルにはない。仕方がないので、こんにちわ、とだけ言って、ショーファーが開けてくれるドアからリモに乗り込んだが、そもそも、この時点でメリルはその日、あの脳天気な父に大敗するような予感はしていたのだ。それはあまりにもケタが違いすぎた。しかし、その時ですらまだ、彼はモルガーナ家がクランドル屈指と言われる大貴族であるということの意味を半分も分かっていなかったことを、屋敷に着いてから更に思い知らされることになる。
ともあれ、ディがこの、モルガーナ家でも二番目に大きなリモをメリルの迎えに出したのには理由があった。弟がいると聞いてとうとうメリルがブチ切れたらしいと知った彼は、まず機先を制して、こちらが彼を軽んじていたわけではなく、自分の息子として重く感じているというところを見せてはどうかという計略を思いついたのだ。このあたり、いくら「文句があるならぶちまけに来い」と言ったとはいえ、なかなかタダでぶちまけさせてやろうとはしないのがディのいぢわるな所である。
母親はクランドルでも注目を集めている人気出版社のオーナーであり、しかも彼女自身も文人であるとはいえ、ファーンと違って比較的普通の環境で育って来ているメリルが、いきなり見たこともないようなリモを目の前に置かれたらどういう反応を示すか。マイラからその性質をいろいろ聞き出してあったディは、無口でマジメな少年なら相当驚きもするだろうし、機先を制されて言いたいことも言えなくなるだろうなと予測をつけたのだ。別に文句を言われたくないのではないが、このぼくに意見しようというのなら、それなりのハードルは越えてもらわなければね、というわけである。もちろん、それで自分が決してメリルを軽んじていたわけではないと伝われば、それに越したことはない。しかし実際、息子がブチ切れたと聞いて面白がり、その心理を読んでバカでかいリモを迎えにやるようなところが、ディは既にメリルで遊んでいると言っていいかもしれなかった。それは、彼には珍しいことですらなかったが。
さて、まさかその当の父親に遊ばれているとは思ってもみないのはメリルの方だ。こちらは、そろそろ難しい年頃とはいえまだ僅か十二、三の少年でしかない。自分のことなどいるとも思っていなかったはずの父が、いったい何を思ってこんな丁重な迎えを差し向けたのか、その辺からしてメリルにはまるっきりワケが分からなくなっていた。もしかすると何も考えていなくて、ただ、貴族的習慣でこんなクルマを寄越したのかという気もする。しかし、反面、母から自分が彼に反感を持っていることも聞いているだろうし、これはちょっとしたご機嫌取りのつもりだとしても不思議はないとも思える。それなら、これくらいでご機嫌を取られてなんてやらないぞという気もするし、でも、もしかして本当に気を使ってくれているのだとしたら、顔を合わせるなり文句を並べ立てるのは悪いかな、という気もしないではない。
ついさっきまで、かなり「言ってやるぞ」という気分だったのに、父の意図を測りかねてメリルは相当腰が砕けた状態になっていたが、まさしくそれがディの狙いだったと気づくには彼もまだ幼かった。要するにメリルは、既にきっちりディの術中にハマってしまっていたのだ。
メリルが乗り込むとリモは粛々と走り出し、市内からほぼ1時間半ほどかけて郊外にあるモルガーナ家の敷地に入った。この周辺は、昔からクランドルの上流階級が、それぞれ広大な敷地を持つ屋敷を連ねているような閑静な場所である。だから、市内で生まれて育って来たとはいえ、メリルはこちら方面にはまだ来てみたこともなかった。
緑豊かな道の左右を、ゆっくりと走り過ぎるリモの窓越しに眺めながら、しかし、これまでの道々にあったどの屋敷も木々の向こうにせいぜいその片鱗が垣間見える程度なのだ。その光景を見ていれば、それらがどれほど広い敷地の中に建っているかは一目瞭然というものだった。そうするうちにふと彼は、確かにさっき両側の支柱に彫刻を戴く、古風な真鋳の門を通ったはずなのに、未だ建物が見えて来ないことに気がついた。あれ?
と思っていると、しばらくして道の向こうに左右両翼を持つ、メリルの認識では城と言ってさえ過言ではない大邸宅が、次第にその全貌を現わして来たから大変だ。それは、これほど広大な邸宅であるにも関わらず、門の向こう側からはその片鱗さえ伺えなかったのである!
これが大貴族ということなのかと、かなりショックを受けているメリルを乗せて、リモはゆっくりとその前庭を通り過ぎ、広いアプローチを持つ家のエントランスに静かに横付けされた。そこには既に黒服の執事と何人かのメイドが並び、この家の長男の到着を丁重に出迎える用意をして待っている。車が止まり、ショーファーがドアを開けてくれたので反射的にメリルは車から降りたが、それへ生真面目な様子で執事が近づいて来て、恭しく、ようこそおいで下さいました、と声をかけた。ここでもまた、メリルには全くありふれた挨拶を返す以外に方法はなかった。
確かにこれでは、彼の母が「格違い、身分違い」という気持ちになっても不思議はないかもしれないと半ばメリルは納得しかけていたが、しかし、マイラがそう感じていたことの本当の原因を彼は未だ目にしてすらいなかった。まさにその日は、メリルにとってこの先も、大ショックの連続が用意されているようなサプライズな一日だったのである。
これはもう文句を言うどころの騒ぎではないかもという気持ちになりながら、彼は迎えてくれた執事に伴われて、内心くらくらしながら長い回廊をディのアトリエの方に歩いていた。しかし、その廊下にもいちいち驚きのタネが潜んでいるのだ。
なにしろ、モルガーナ家は代々、美術品の蒐集でもクランドルで十指に入るとされるほどの家柄である。だから昔から芸術の世界とは縁が深い上、現当主は自身が天才と評価される世界的な画家と来ている。従って、その回廊には美術館のごとく、惜しげもなく名画が並んでいるのも不思議はなかったが、何よりも絵を描くことが好きで、将来は画家と決めているメリルにその価値が分からないわけがない。それで、これが個人のコレクションとはとても信じられないような夥しい数の絵や美術品が目に留まるたびに、彼はそれらにどんどん圧倒されてゆく気分にならざるを得なかった。
しばらくして、先にまだ、どこまでも廊下が続いているようではあったが、しかし、前を歩いていた執事が途中の扉の前まで来て止まり、メリルにこちらで皆さまお待ちでいらっしゃいます、と言った。そして彼が扉をノックすると、主らしい声が、入っていいよと答え、それを聞いた執事は扉を開いた。
「メリル坊ちゃまが、お見えになりました」
広い部屋の向こうには彼を待っていたらしい4人の姿が見え、アーネストがそう告げると彼らの視線が自分に向けられたのにメリルは気づいた。しかし、執事に促されて中に一歩入ったとたん、彼は父や祖父、それに弟たちらしい4人の姿よりも、そのアトリエに飾られている絵の数々に目が釘付けになってしまっていた。
回廊とは違い、ここにはディの作品だけが飾られている。それらは高さ2メートルもあるようなものが多く、それで扉から一歩入った所では、クラシックなスタイルでありながら、その大きさや色彩ともあいまって、一見してド迫力な印象を与えるディの絵が何枚も一望に出来ることになるのだ。
それが目に入った時、メリルは母が「格」だの「身分」だの言っていたのは、決して彼の父が貴族であることや、あの豪華なリムジンだのこの大邸宅だののせいではなかったのだと、はっきりと悟っていた。ディが、あれだけスキャンダル・メイカーとしてゴシップ誌の常連を演じていることでさえ、この際、メリルにもまるっきり問題外だと思えた。そんなことよりも、彼の父が"デュアン・モルガーナである"ということの意義が、その作品の実物を見たとき、メリルにもようやく理解できたのである。
なにしろ、メリルはもともと反感を抱いているから、わざわざ個展になど出向いてみたことすらない。それで、彼の絵は母の持っている画集で見てよく知っていると思っていた程度なのだが、印刷でさえ、それらの絵が芸術的に優れているということくらいは彼にも分かった。しかし、真筆となるとこれほど違うものかとつくづく思い知らされる。なによりもまず、その色彩があまりにも鮮やかなのだ。絵を描く者なら必ず、ディの作品を間近に見るとどうやってこんな色が出せるのかと思うようだが、その点、デュアンもそうだったし、メリルも例外ではなかった。それだけに、現代のどんなに精緻な印刷技術をもってしても、ディの絵を画集に再現することなどは不可能なのである。しかも、この大きさが、その大胆な構図の迫力をいや増す働きをしている。
腹は立つし、悔しいけれども、母の言っていたことはその絵を見たときメリルには十分に理解できた。こんな絵を描く人に、自分あたりが言えることなどありっこないと、まさにその瞬間にメリルは戦わずして敗北を悟らされていたと言っていい。しかし、驚きはこれで終わりですらなかった。
「やあ、よく来たね、メリル」
扉の側で固まってしまっているメリルのところへディが歩いて来ると、にっこりして実に優しげに声をかけたのだ。
確かに目の前にいるのは、雑誌などの写真でよく見知っているデュアン・モルガーナに間違いない。クランドルどころか世界中探しても並ぶ者などいないと誰もが認めるその繊細な美貌は、メリルが数えきれない雑誌や新聞、テレビなどのメディアを通じて、もう沢山と思うほど目にして来たものだ。既に四十代のはずなのに年齢などまるで問題にならないようで、ここ二十年ばかり彼の容姿は殆ど変わってすらいないと言ってもいい。それについては日頃から、それだけでもバケモノだなとメリルは意地悪く思っていたものだが、その実物と来ては、写真などでは本来の姿の十分の一も写し取れていなかったのではないかと思われるほどなのだ。
驚きの連続でマトモに受け答えする能力が停止してしまったかのようなメリルに、ディは、どうしたの? と尋ねた。
「え? いえ、別に何も...」
これほどの美貌と、あれほどの絵を描く天分、しかも知らぬものとてないプレイボーイの自分の父が、こんなふうに優しいもの言いをする人だとはメリルは想像してみたこともなかった。なにしろこれまで、彼の素行を見ていて、きっと自分の才能や身分に奢っている、どうしようもなく傲慢なヤツだと勝手に決めつけていたのだから、そのギャップは途轍もなく大きい。
ディは、そのメリルの様子にちょっとクスリが効きすぎたかなと内心笑っていたが、しかし、彼の長男が一番ショックを受けたのが自分の絵だとまでは、さすがに彼も考えていなかった。
「じゃ、こっちにおいで。みんなに紹介しよう」
そう言ってディは、メリルを促すようにその肩を軽く抱き、ロベールたちがいるソファの方へ歩かせた。既にすっかりディのペースにハマってしまっているメリルは、逆らうどころの騒ぎではない。
ディはメリルを皆の方に連れてゆくと、彼の祖父と弟たちを順に紹介した。パニクっていることもあってメリルの様子は不機嫌にすら見えていたが、実のところは何をどう理解して、どう反応したらいいのか分からなくなっていて、ここでも皆に、こんにちわとほんの短な挨拶を返すのがやっとだった。
ロベールはその様子を見ていて、なるほどこの子は他の二人と違うなと考えている。ディが言っていた通り、父親に反感を持っているのはその様子からも見てとれた。しかも、ディの子供には違いないのだろうが、デュアンやファーンのように父に似たところはまるで見受けられない。長めに整えたサラサラのブラウンの髪も、瞳や顔立ちも、母親似なんだなということはロベールにも容易に分かった。確かに綺麗な子ではあるが、ディとはまるで赴きが違うのだ。
しかし、さすがにそこはロベールもディの父親で、それほど外見上は似ていないこの一番上の孫が、ずっと子供の頃の息子に最も性質が近そうだということは、事前にあれこれ話を聞いている間になんとなく予測していた。
今でこそディはあんなふうだが、メリルと同じ年頃の頃には、確かにこんなふうに繊細で生真面目、簡単には他人に馴染まないような近寄り難い雰囲気があったものだ。もっともディが気さくに機嫌よく応対するのは今でもごくごく親しい者に対してだけで、そのテリトリーから一歩出れば、今でも彼は相変わらず「氷の王子さま」という十代の頃からの称号で形容されることが多い。つまり、彼をよく知らない者からは、"気難しくて無口な芸術家"と信じられているのである。
今ではそれが、いちいち自分の考えを親しくもない、もっとはっきり言えば彼にとってどうでもいい相手にくどくど説明するのがめんどくさいからだということをロベールもよく知っているが、確かにその「氷の王子さま」の称号に関しては、三人の息子たちのうちならメリルが一番ぴったりくるだろうと思わせられていた。
ディに促されてデュアンとファーンの横にかけたメリルにロベールが言っている。
「会えて、とても嬉しいよ、メリル」
「はい...」
「これでやっと三人揃ったわけだな。顔を合わせたばかりでリラックスしろと言う方が無理だろうが、まあ、今日、明日と三人ともゆっくりして行ってくれるということになっているわけだし、おいおいにいろいろ話も聞けるだろう。楽しみにしているよ」
今日の集まりのメインは今夜のディナーということになっているので、ロベールの言う通り、三人の子供たちは一晩泊まってゆくことになっている。しかしまずは軽いアフタヌーン・ティということで、アーネストとマーサが改めてお茶とお菓子をたっぷり運んで来てくれた。
メリルの登場で中断されていたとはいえ、他の4人の間では既に会話がはずみはじめていたところだったから、豪華なお菓子を何種類も乗せたワゴンの登場に誰からともなく歓声が上がっている。しかし、メリルだけがまるで楽しまない様子なのにふと気づいて、デュアンはメリル兄さんて、ファーン兄さんと違ってなんだかとっつきにくそうな人だなと密かに思っていた。しかし、もちろんこの子のことで、そんな印象は少しも表に出さない。
一方、ロベールは容姿も性質も三人三様に違う孫たちを楽しそうに眺めながら、なかなか面白いことになりそうじゃないかと思っている。何はともあれ、今日は彼の人生最良の日のひとつに数えて間違いはないようだった。
original
text : 2008.7.13.-7.21.+ 8.16.
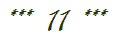
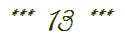
|
