|
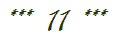
そしていよいよ午後になり、迎えにやったクルマで一番のりして来たのはデュアンだった。今日のために新しく作ってもらった服は、カトリーヌの好みもあってやはりブロンドのよく映える白で、中に着ているシルクのブラウスは大きなボウの付いたものだ。最初にこの屋敷を訪れた時に着ていたものとスタイルは似ているが、今日のブラウスには白地に淡いブルーのストライプが織り込んであってぐっとオシャレな感じが加わっている。
もう何回もこの家に来て、アーネストたちともすっかり親しくなっているデュアンだが、今日はおじいさまや兄たちに会えるということで、わくわくしながらもちょっと堅くなっているようだ。
「こんにちわ、お父さん」
「やあ、よく来たね」
アーネストに案内されてデュアンがアトリエに入って来るとディは立ち上がって出迎えた。後ろでその様子を見ているロベールは、初めて会う自分の孫が、アーネストの言っていた通り最愛の息子の幼い頃に生写しなのを見て驚くやら嬉しいやら、すっかり顔がほころんでいる。
「紹介するよ。きみのおじいさま。ロベール・ド・シャンタン伯爵だよ」
言われてデュアンはそちらを見ると、にっこりして、こんにちわ、はじめまして、と言った。その可愛らしさとはきはきした態度に、ロベールは一も二もなく陥落だ。
「やあ、デュアン。会えてとても嬉しいよ」
ソファから立ってゆくと彼の三番めの孫の肩に手を置き、満面笑みでそう言った。
「まあ、こっちに来て座りなさい。兄さんたちが着くまで、ちょっと話をしようじゃないか」
「はい」
三人がそれぞれソファに身を落ち着けるころ、タイミングよくアーネストがお茶とケーキを運んで来てくれた。ポットからカップに丁寧に注がれるお茶の良い香りが満ちてくる中でロベールが言っている。
「驚いたな。本当にディの子供の頃にそっくりだ。まるで30年前に戻ったようだよ」
「そうなんですってね。ぼくも、写真を見せてもらって驚いていたんです」
「そうかそうか。しかし、きみの瞳の色はグリーンなんだな。お母さんゆずりかい?」
「ええ」
「学校は、えーっと、そろそろ3年生か」
「そうです」
「なるほどなあ。知ってさえいたら、もっと早く会えたのに。しかし、これからはおじいさまとも仲良くしてくれるな?」
「もちろんです。ぼく、本当にすごく嬉しいんですよ。母の両親はもう亡くなっているので、ぼくには今まで祖父母という人がいなくて...。おじいさまと兄さんが二人も一気に出来るなんて夢みたいなことなんです」
「よし。じゃ、今度な、おじいさまの城に遊びに来なさい。とてもキレイなところだぞ」
「本当ですか?」
「おお、もちろんだとも。あちこち案内してあげるから楽しみにしてなさい」
「はい、じゃ、ぜひ今度の夏休みにでも。絶対ですよ」
「よしよし、約束だ」
二人が話している様子を横で見ていて、ディはあっという間に初対面の祖父と打ち解けたデュアンにちょっと感心する気持ちになっていた。彼との時もそうだったが、この子は全く素直にすいっと人の気持ちに寄ってくるところがある。作為的に気に入られようとしているわけでは全然ないが、デュアンの、相手と仲良くなりたいという真っ直ぐな気持ちがすんなり伝わって来るために、それが可愛くてこちらもついにこやかに応対してしまうようになるのだ。そうするうちにほんの少しの時間があれば、何年も前から仲良しだったように、打ち解けた雰囲気の中でお喋りしていることになる。
デュアンにとってこれは全く自然なことのようだ。特に意識する必要もなく、生来のものとして難なく出来てしまうことなのだろう。
そうこうするうちに、アーネストがファーンの到着を告げに来た。ファーンはクロフォード家のベントレーでご到着だ。クルマは今、正面の正門を入って来たところなので、あと5分もすればエントランスに着くだろうということだった。
「じゃ、着いたらここへね」
「かしこまりました」
ディの言うのへそう答えてアーネストが出て行ってからしばらくして、彼はファーンを伴って戻ってきた。
「ファーン坊ちゃまがお見えになりました」
言われて入って来た少年を見て、ロベールはなるほど、と思っている。彼がよく知っているクロフォード家の先代公爵の若い頃に、どことなく面差しが重なるところがあるような気がするのだ。一方ディの方は、初めて会う二番目の息子が、かつての恋人によく似ているのを見て微笑ましい気分になっている。ファーンはデュアンよりひとつしか上ではないはずだったが、もうずいぶん背も高く、ブラウン系のスーツとタイでおとなっぽく決めているせいか13歳くらいには見えた。
「ようこそ、ファーン」
「こんにちわ、お父さん。はじめまして」
礼儀正しくはあるが、適度なニュアンスでトゲのあるファーンの挨拶にディは笑っている。もちろん、ファーンには悪気はない。このシュチエーションでは、十分にウィットの効いた言い方だったと言えるだろう。それへ、なかなか頭の良さそうな子だと思いながらディは答えた。
「はじめまして。アンナは元気?」
「はい、相変わらずです。お父さんに宜しくと言ってました」
「そう。じゃあ、ぼくからもよろしくと伝えておいて」
「ええ、もちろん」
「じゃ、とにかくきみのもう一人のおじいさまと弟に引き合わせようか」
そう言ってファーンを促し、ディは彼を二人が待っているソファの方へ連れて行った。
「ロベール・ド・シャンタン伯爵。それと、デュアンだよ」
「よく来たね、ファーン」
ロベールがにっこりして言い、その横でデュアンもはじめまして、とだけ挨拶した。もう"兄さん"と言っていいのかどうかちょっと戸惑っている様子だ。
ファーンの方は二人に微笑を返して、はじめまして、会えてとても嬉しいですよ、と答えた。デュアンとひとつしか違わないわりには大家の令息らしく、落ち着いていて鷹揚な印象があるが、それは彼に限って嫌味になるようなものではなかった。むしろ、ロベールなどは、その様子にほぉ、と感心したほどだ。
「どうぞ、座って」
「はい」
ディが言い、ファーンはデュアンの横にかけた。
「ディから聞いた。きみのお母さんは、クロフォード家の先代公爵のお孫さんなんだそうだね」
ロベールの問いにファーンはにっこりして答えた。
「そうです。ぼくは、大じいさまの家で育ったんですよ。大じいさまだけじゃなく、祖父母や叔父一家も一緒に暮らしているんですけどね」
「なるほど、それは大家族だ」
「ええ」
「翁は、そうするときみのひいおじいさまということになるんだな」
「はい」
「もう90を過ぎてらっしゃるだろう?」
「今年95才になられました。でも、そうは思えないほどお元気です」
「そう、それは素晴らしい。私も若い頃は世話になったものだが、引退なさってからはお会いする機会もないままに来ていたんだよ。こんな縁もあったことだし、今度、一度ご挨拶に伺おうとは思っているんだが」
「大じいさまから伺っています。おじいさまのことはよく覚えておられますから、顔を見せて下さったら、きっと喜ばれるでしょう」
「そうか、覚えて下さっているか。それは嬉しいね」
「おじいさまのお若い時の印象は随分鮮明なようで、...特に、ベアトリスおばあさまと結婚なさった時のことが。クランドル社交界一と言われた美少女をまんまとさらっていきおったと笑って話しておられました」
言われてロベールも声を上げて笑った。
「そうそう、あの時は翁も結婚式に出席して下さって、散々苛められたものだ。クランドル一の美姫をかっさらってゆくとはけしからん、と言ってね。他にも社交界中の青年に恨まれたし、とてもビーチェを私の国に連れ去ってしまうことなんて出来る状態ですらなかったよ。そんなことをしたら、国を挙げて奪還戦争を起こされそうな勢いだったものだ」
それへファーンも笑いながら答えた。
「大じいさまが写真を見せて下さったので、ぼくもおばあさまのことは知っています。本当に美しい方だったんですね」
「それはもう、月の女神もかくやという美しさだったよ」
ロベールがいけしゃあしゃあと亡き妻を褒めて憚らないものだから、ディは横で聞いていて、全く、相変わらずだなと内心で笑っていた。ロベールがビーチェと出会った時、彼は三十、彼女は十六になるならず、つまり彼の方が殆ど倍の年だったのだが、妻にするならこの娘とひとり決めして1年がかりで口説き、恋人になってからも一人娘だから結婚はできませんと言い張る彼女を言いくるめて、後に義父となる先代のモルガーナ伯爵に結婚の許しを申し出た。
義父も始めは、良いお話ではあるが、娘には婿を取って家を継いでもらわなければならないので、と断る姿勢を見せていたのだが、そんなことくらいで諦めるロベールではない。仕事そっちのけで夜討ち朝駆け、殆ど日参状態で説得にかかったのだ。そうこうするうちに、ふと彼には、モルガーナ家は二人の間に生まれた子供のうちの一人に継いでもらえば良いではないかというグッドアイデアがひらめき、その通りのことを義父に言ってやっとお許しを取り付けたのである。もちろんその頃、自分より遥かに若いビーチェがそれほど早逝するとはロベールも思ってもみていなかったから、後に自分の方の後継ぎのことで苦労することになろうとは、予測することが出来なかったのも無理はない。
ともあれ、当時、彼の義父はまだ四十代半ばで、孫が家を継げる年になるまで十分に時間のある身であったし、話がそこまで進む頃にはビーチェの方がすっかりロベールに夢中になっていたこともあって、優しかったディの祖父は娘の気持ちも汲んでという気になったようだ。それに何より、これほど思いつめてくれる男に嫁がせる方が、娘は幸せになれるかもしれないとも思ったのだろう。その予想通り、結婚してからは彼女が三十代の若さで亡くなるまで、社交界一の熱愛夫婦として名を馳せたほどの仲の良さだった。
そして、その義父の厚情に深く感謝していたロベールは、彼を淋しがらせないためと、二人の子供にモルガーナ家を継がせるという約束を果たすためもあって、ビーチェを自分の国には連れて帰らず、生まれた子供もクランドルで育てて、自分の方がモルガーナ家に帰ってくるという生活を妻が亡くなるまで続けていた。彼の方は自国に自分の城を構える身とはいえ、結婚した当時、既に両親は亡くなっていたから身軽だったのも幸いしたのだろう。
そんなわけで、彼の亡き妻の話ですっかり座が盛り上がったわけだが、ロベールは今度はその話題をデュアンの方にふってみることにしたらしい。
「そうだ、デュアン。きみは、おばあさまの写真はもう見せてもらったかな」
「はい、お父さんに」
「そうか。美しい人だっただろう?」
「ええ、とっても。お父さんに顔立ちがよく似てらっしゃったんですね」
「そうなんだよ。こんなヤツだが、それで私は息子についつい甘くてな。そう言えば、そのディに似ているんだから当然のことなんだろうが、きみにもビーチェの面影があるなあ」
「そうですか?」
「うん、あるよ。今、気がついた。なるほど、改めて実感が沸いてきたが、きみもファーンも本当にディの息子なんだな。デュアンは顔立ちがそっくりだし、ファーンはその瞳の色がビーチェとディにそのままじゃないか。いや、これは全く嬉しいことだ。一気にこんな素晴らしい孫が二人も出来るなんて、私は幸せ者だよ。おまけに、まだもう一人いるとくるんだから。これは、悔しいがディに感謝しなくちゃならんな」
やっと言ったな、とディは内心思っていたが、表に出しては何食わない顔で微笑んでいるだけだ。
そんなわけですっかり和気あいあいなムードが四人の間に漂い始めた頃、今度はアーネストが最後の一人の到着を告げに来た。メリルがディに快い感情を持っていないことを、彼は既にロベールにも話してある。それで二人はアーネストが言うのを聞いていよいよだなと顔を見合わせ、微かに頷き合っていた。
original
text : 2008.7.10.-7.13.+ 8.16.
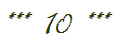

|
