|

春休みいっぱい、デュアンやディ、それにエヴァたちが滞在していたのでいつもよりずっと賑やかだった邸内も、学校が始まる時期が近くなって彼らをアークで送り出してしまってからは、ふいと元の静けさが戻って来ている。アークが入港出来るほど大きな入り江を持つこの島に、デュアンが言っていた通り、家と言ってはマーティアたちの今いるこの邸宅ひとつしか建っていない。緑の生い茂る南の島に、それはお伽噺の中の白亜の宮殿のように堂々と、けれどもひっそりと存在していた。
マーティアは客人たちといつになく楽しく話したり遊んだりしている間に山積みになってしまった仕事を片づけるために、彼の書斎
― とは言ってもそれは大統領執務室のようにゆったりして立派なものだが ―で、書類に埋もれてせっせと働いている。大きな机の上はプリントアウトされた書類の海で三台の端末が溺死しかかっているほど散らかって惨憺たる有様だったが、背景の大きな窓の外はのんびりした南の島の午後だ。屋敷の裏手に出るとすぐビーチということもあって、のどかな波の寄せては返す音も微かに聞こえてくる。
ふいに机の上の電話が鳴ったのでマーティアは受話器を取り上げようとしたのだが、それがあったはずの場所は既に書類が占領してしまい、掘り出して来るのに少しかかった。
「はい?」
― マーティアくんかね?
相手の声を聞いて、ようやく探しあてた受話器ではあるが、そのまま書類の海で溺れさせておけばよかったと彼は既に後悔している。
「そうですよ、ミロワールさん。何かご用ですか?」
― ご用ですか、ではないぞ、マーティアくん。きみはモルガーナ伯のご子息とその友達が誘拐されたという話をなぜ私のところに言って来なかったのかね。犯人は私と交換に二人を返すと言っていたのだろう?
「どこで聞いたんです、そんな話」
― 内緒だよ。
「聖職者が隠し事なんかしていいんですか?」
― ニュースソースを明かさないというのは、きみたちだって鉄則だろう。
「ヘンなとこだけ世俗的なことなんて覚えないで下さい。そんなこと言ってるから聖職者としてしくじるんですよ」
― 失礼なことを言うな。私がしくじったのではない。教会が私をしくじったのだ。
言われてマーティアは頭を抱えた。
「ミロワールさん、お願いですから、ヨソへ行って言わないで下さいよ、そんなこと。ただでさえ危ない世の中なんですから、これ以上面倒ごとを増やされるのはご免です」
― 分かっておる!
そんなことはどうでもいい。ともかく、そんな重要なことを、なぜ私に知らせなかったのかね、マーティアくん。
「だってそんなこと教えたら、また出て行くのなんのと言い出すでしょう?」
― 当たり前じゃないか。いたいけな子供たちが私の代わりに捕まっていると聞いて、見てみないふりなどできん。
「だからですよ。私だってその件で右往左往してる最中だったんですから、あなたのお守りまでテなんか回らなかったんです!」
― お守りとはなんだ、お守りとは。
「じゃあ、説得と言い直しましょうか?」
― 全く、最近の若い者は! 第一、年寄りのお守りは若者の義務と昔からきまっておる!
「自分だってお守りって言ってるじゃないですか」
― 揚げ足を取るな。可愛くないぞ。
「言っておきますが、私はもう30を過ぎてるんです。可愛いの可愛くないのというトシじゃありません」
― 何を言っておるか。私の半分の年にもならん子供のくせに。年長者の言うことは有難く拝聴するものだ。
マーティアは、これ以上何を言っても水掛け論になって楽しまれるだけだなと悟ったので黙る他無かった。それで相手はマーティアを言い負かしたと思って満足したのだろう。
― まあ、過ぎたことは仕方がないが、とにかく今度またこんなことがあったら、必ず私に知らせるように。
ぴしりと言い置いてから、彼は思い出したように続けた。
― それから、さっきも言ったが年寄りのお守りは若者の義務だ。しかし、きみが忙しいのは私にも分かっているから、今度アリシアくんでも遊びに来させなさい。彼に、また主の御心について楽しく語り合おうではないかと伝えておいてくれたまえ。ではな。
通話が切れたので受話器を置くと、マーティアは机の上につっぷしてへたってしまった。とにかく、あのじいさんと話すとどっと疲れるのだ。しばらくそうしていると、ノックをしてから答えは待たずに入って来たアリシアが、彼の様子に気づいて尋ねた。
「あれ?
どうしたの、マーティ。なんか疲れてない?」
「ミロワールさんからお叱りのお電話」
「え?」
「どこで聞いたんだか知らないけど、デュアンたちが誘拐されてたことを、なんで黙ってたんだっておかんむりでさ」
「ああ、あのおじいちゃんが知ったらそりゃ怒るだろうね」
マーティアは起き上がって机に頬づえをつきながらボヤいている。
「最近の年寄りは、なんであんなに元気なのかね」
「でもぼく、あのおじいちゃん好きだよ。仲良しだもん」
「だったら好物の甘いものでも持って、そのうちご機嫌伺いに行って来てよ。今度の件でまた機嫌が悪いみたいだからさ。あ、そうそう。伝言があったんだ。"主の御心について楽しく語り合おう"だって。ああ、うんざり」
「そんなこと言っちゃ、おじいちゃん可哀想だよ。マーティのこと気に入ってるのに。どうせ行くんなら一緒に行こうよ、ね?」
「やっぱり気に入られてたんですか?」
「そりゃそうだよ。マーティアくん、マーティアくんって懐かれてるじゃない。それに、あのおじいちゃんはさ、イエスさまが大好きなだけなんだよ。熱狂的ファンというか、誰だって好きなスターについてはお喋りしたいもんでしょう?」
「ジーザス・クライスト・スーパースターとは言うけどね...」
「ぼくは分かるなあ。ぼくだったら、マーティのことなら何でもいっぱいお喋りして自慢しまくりたいもの」
「やめて...」
「なんでよ。まあそれはともかく、ぼくたち、お父さんはいるけど、おじいちゃんはいないじゃない?」
「一応な」
「だから、これも縁なんだし、本当のおじいちゃんだと思ってワガママ聞いてあげなくちゃ。向こうは既にマゴのつもりなんだから」
「いつ、おれたちはマゴになったんだ?」
「そういうものなんだよ、そういうもの」
マーティアは、アンリ・ミロワール氏のことをキライなわけではないのだが、どちらかと言えば苦手なのである。彼のようなド天才、それも思想、哲学はお家芸で、ごくごく幼い頃から哲学史そのものの歪みとその原因を指摘できるほどの思考力を持っている者には、あまりにも分かりきっていすぎることでくどくどくだくだ論争をふっかけられることほど疲れることはないのだ。マーティアの超高性能なアタマの中では直感的に瞬時で演算されてしまうようなことを、アナログ展開しろと言われてもめんどくさいだけなのである。だから、彼は昔からマリオやディ、それにアレクやアリシアのようなよくよく彼を理解しうる知性に恵まれているとはっきりしている人間以外とは、そういうことについて話してみようと思ったこともない。通常の人間の知性では、究極的な思想や哲学というものは複雑すぎて、一生かかっても理解できないのが史実であり、歴史的通例なのだから仕方がないだろう。それはサルに世界の広さを知れと言うのと同じほど、無謀なことでしかない。
ともあれ、マーティアにとってミロワール氏の始末が悪いのは、なまじ一生懸命学習するものだから、普通の人間としてはかなり高度なところまで思考を進めることが出来てはいるのだが、それがヘタな哲学書などにもよくあるように中途半端で、究極的な視点から見ると、同時に考え合わせなければならない要素があちこちで欠落してしまっているために、論争を始めるとマーティアはそれについていちいち指摘し、解説してやらなければならなくなるところなのである。おまけに、なにしろこのじいさんはあまりにも勉強熱心で、マーティアから自分がそれまで考えてみたこともなかったような観点からの哲学的「新発見」を得ることで、新しい視野を開発するのが楽しくて仕方ないらしいのだ。「きみと話していると、論理とは人類にとってのあらゆる疑問に対する解答を、本来これほど明確にすることが出来るものなのだなと驚かされるよ」と彼は以前言っていたことがあるが、その「新発見」だの「明確にされること」だのは、マーティアにとってはタダの「当り前」なので、このギャップを埋めるのがめんどくさくて、ついつい近づかないようにと思ってしまうのだ。
IGDの保護下に入って欲しいと侯爵やアレクに言われた時、ミロワール氏は逃げ隠れするつもりはないと言ってゴテたわけだが、そもそもその時、マーティアがそれへクギを刺すようなご尤もなことをきっちり指摘してしまったのがいけなかった。これで彼はなかなか大人(たいじん)なので、相手がハタチそこそこの若者とはいえ、指摘されたことが本当に正しければ受け入れるだけの器量というものも持っている。それにマーティアがマリオ・バークレイ博士の秘蔵っ子であるとも既に知っていたので、その辺りから注目度がぐんとアップしてしまったのだろう。それに加えて、マーティアが気に入られたとすればアレかな?
と思い当るフシも確かにある。
それは以前、アリシアと一緒にご機嫌伺いに出向いて行った時のことだっただろうか。何かの拍子に彼が「私は主のあたたかなおこころざしについて、より多くの人たちに伝えたいだけなのに、どうしてこんなふうにそれを邪魔されなければならないのだろうね」とつぐつく、しみじみ言ったのである。その様子がいつものうるさい頑固じいさんに似ず、あまりにも哀しそうで、彼の無念な内心を物語っていたので、マーティアはついつい同情する気分になってしまったのだ。それで、「だからこそですよ、ミロワールさん。だからこそ、歴史の軌道は修正されなければならないんです」と、こちらもしんみりと答えてしまった。そのへんで、ヘタに共感してしまったものだから、マーティアなら自分の言わんとすることを理解してくれると思ってよほど嬉しかったのだろう。以来、アリシアの言う通りすっかり懐かれてしまったようだ。
キライってわけじゃなんだよなあ、と考え直して、マーティアはアリシアに、じゃあまあ、マゴは一緒におじいちゃんのご機嫌とりに伺いますか、と、仕方なさそうに言った。アリシアはにっこりして頷いている。
***************
オーストラリアのとある片田舎、郊外に牧場や農園が広がるのんびりした街の片隅に、その小さな家はあった。庭には青々と木々が生い茂り、家人の手入れが良いのか美しい花々がそこかしこに彩りを添えている。近づいて行くと、ペンキの剥げかけている木柵を張り巡らした前庭の向こうで、庭仕事をしている家の主を目に止めて、アリシアは丈の低い門のこちらから声をかけた。
「アンリおじいちゃん!マーティ連れて来たよ」
言われて振り返った老人は、二人を見て意外ながらも嬉しそうな顔をした。
「おお、アリシアくんか。よく来た、よく来た。マーティアくんなど可愛くないからどうでもいいが、きみは可愛いから入りなさい、入りなさい」
顔を見るなり思いっきり嫌味を言われてマーティアはあーあと思ったが、マゴとしてはおじいちゃんにただ負けていることもないかと思って、アリシアと一緒に門を入りながら言い返していた。
「お入用じゃないなら帰りましょうか? 私も忙しい身なもんで」
「今更帰らんでもいい! 入りなさい」
また嬉しそうにそう答え、彼は二人のところに歩いて来た。ついこの朝までマーティアたちがいた南の島とは反対に、ここではこれから秋を迎えようとするところだったが、陽射しはまだ十分に強く、北半球の初夏を思わせる陽気がまだ残っている。のどかな昼下がりの庭に、太陽が明るく降り注いでいた。
original text : 2008.4.11. (+2008.3.8.)
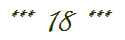
|
![]()