|
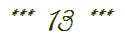
ディがバスを使ってから着替え、ベッドでほっとひと息ついた頃、寝室のドアをノックする音が聞こえた。とにかく今からちょっと眠ろうと思っていたので、遮光用のカーテンを引いた部屋の中はテーブルランプひとつですっかり夜のように暗くなっている。
「誰?」
「ぼく」
「いいよ、入っておいで」
デュアンは扉を少し開けて顔を出し、にっこりしてディを見ると部屋に入って来た。パジャマの上にガウンを羽織っている。シャワーを浴びて来たらしく、上着を脱いでディの横にもぐりこんでくると、ほのかにシャンプーの良い香りが漂った。
「う〜ん、やっと帰って来たなって感じ」
大きく伸びをしてデュアンが言うと、ディは笑っている。
「なにはともあれ、きみもエヴァも無事で良かったよ。ああ、そうだ。アレクが言ってた通り、事故に合ってるんだから医者に見てもらわないといけないな、二人とも。明日にでも病院の予約を取ろう。検査が必要になるだろうからね」
「うん」
「大したことはないって言ってたけど、痛くない?」
「大丈夫だよ。ちょっとぶつけただけだったんだから、もう治ってきてるみたい」
「そう、ならいいけどね」
「ねえ、ディ」
「ん?」
「ぼくのこと、たくさん心配した?」
「当たり前じゃないか」
言われてデュアンは嬉しそうに笑い、それからディに寄り添って唇を重ねた。何度かキスを繰り返してやっと満足すると、彼の腕におさまって幸せそうに言っている。
「嬉しかったな、ディの声が聞こえて来た時。きっと助けに来てくれるとは思ってたけど、本当にほっとしたんだ」
「怖かっただろ」
「それはね、もちろん。でも、一番気になってたのはエヴァのことで、さっき彼女も言ってたけど、そもそもぼくが目的だったことは最初から分かってたんだ。邪魔になるからってエヴァのこと、殺すつもりまであったのかどうかは分からないけど、乱暴なことしようとしたし。思い切り殴られたりしたら、女の子だもの、小さなケガくらいですまなかったら大変じゃない」
「そうだね」
「だから、なんていうか、自分が怖いのは怖いんだけど、エヴァが一緒だったから逆にしっかりしなくちゃと思って頑張ってたってとこはあるかな。女の子にみっともないとこ、見せられないしさ」
それを聞いてディは笑っている。この子も男のコだなあと思ったからだ。自分もこの年頃には、初恋の少女を守るためなら、どんなことでもしようという気分でいたものだ。ただし、デュアンの場合、エヴァはあくまで大事な友達という域を出ていないことははっきりしている。
「あ、そうだ。ね、ディ」
「何?」
「ロイはどうなったの?
ぼく、エヴァのことだけで手一杯で、ロイのことまではどうしてあげようもなかったから、ずっと気になってたの。意識がなかったのに、何もしてあげられなくて、もしかして死んじゃったりはしてないよね?」
言われてディも思い出した。なにしろ子供たちのことだけで頭がいっぱいで、そんなところまで気を回しているゆとりがさすがに彼にもなかったのだ。それに、運転手のロイが既に病院に収容されて手当てを受けていることは知らせに来た刑事から聞いてもいた。
「それは...、大丈夫だと思うけど。病院に運ばれたということまでは聞いたんだけど、その時点では意識がなかったそうだよ。でも、何かあったら連絡が来るだろうし、アーネストが何も言ってなかったところを見ると、容態に変化がないってことなんじゃないかな」
「そう...」
デュアンは少し表情を曇らせて心配そうな顔をしている。ディはそれにちょっと感心する気持ちになった。誘拐されて自分が一番危険な状態にいたというのに、ここ一年ほどずっと送り迎えしてもらっていてすっかり仲良くなっていたとはいえ、運転手の容態にまで気を回すとは、なかなかハンパではない神経を持っていると思ったからだ。そればかりではなく、エヴァのことにもずっと気を配っていたらしいのは彼女の発言からも明らかだし、以前から思ってはいたのだが、この子はもしかするとぼくよりずっと立派な伯爵さまになるかも知れないぞという気がするのである。
「じゃ、後でアーネストに言って、問い合わせてみてもらおう」
「うん」
「とにかく今はゆっくりお休み。もう何も怖いことはないし、二度とこんなめには合わせないからね」
言われてデュアンはにっこりするとディの肩に頭をあずけた。
「でもなんか、ぼく、今度のことでいろいろ考えちゃったな」
ディはデュアンの滑らかな髪を撫でてやりながら、どんなことを?と尋ねた。
「なんであんなことになっちゃうんだろうって。映画とかで銃撃戦なんか見てるとカッコいいとか思ったりしてたし、戦争ごっことかさ、そんなのは遊びでよくやるじゃない?
でも、今度のは現実で、やっぱり本当に人が死んじゃったりとかしてるでしょ?」
「そうだね。マーティアも言ってたけど、こちらは敵でも殺さずに解決したくても、向こうが殺しにかかってくるんだから、ある程度は仕方ないと思う。あれでも、アレクたちはかなりセーブして極力致命傷は負わせないように戦ってたと思うよ。爆発物も最低限しか使ってない。まあそれは、今回の場合、彼らの力の方が圧倒的に敵より勝ってたから出来たことだと思うけど」
デュアンたちが捕らえられていた3階から下に降りてくるためには、惨憺たる有様の階段や廊下を通って来なければならなかったが、子供たちにそんな惨状を見せたくないというアレクやマーティアの配慮から、デュアンもエヴァも目をつむっているように言われ、それぞれディとアレクが抱いて下まで降ろしたのだ。だから、デュアンは実際にその光景を見ているわけではないが、あれだけの銃撃戦が展開された現場にいた限りは、それについて真面目に考えるきっかけになっても不思議はないだろう。
「捕まってる間もね、やなヤツもいたけど、みんながみんなそうってわけでもなかったんだよ。ぼくのこと、手当てしてくれたりとか、エヴァのことも一人は殴ろうとしたけど、ぼくが間に入ったらやめろって止めてくれた人もいたし。でも、それでもみんな敵なんだよね、ああなっちゃうと。もう、どうしようもないっていうか、だから、どうしてあんなことになっちゃうんだろうなって。みんな、たぶん一人一人別々に会ってたらもっと違ってたかもしれないのに」
ディはそれへ微笑しながら答えた。
「それはね、デュアン。人間にとって解決しなければならない最大のテーマのひとつなんだよ。アレクたちはそのためにもああいう仕事をしているし、逆に言えばだからこそ単なる企業なら巻き込まれないで済むような事態も起こってくることがある、今度みたいにね。でもそれはこれまでもずっと歴史的に続けられてきた努力だし、続けてゆかなければならない努力でもあるんだ」
デュアンはまだディの言う意味を半分も理解できていないことは自分でもよく分かっていたが、なんとなく彼の言わんとするところは分かるような気もして頷いた。
将来、モルガーナ家の当主として立つということは、デュアンにもいずれそれが現実的な問題として降りかかってくるということでもある。ディはそれも含めて改めて話し合わなければならないなと思っていたが、当初は彼にとって長男にあたるメリルの拒否で、持ち上がり式にデュアンが家を継ぐことになったとはいえ、責任ある地位や立場につけば当然起こってくるはずの様々な問題に対して、この子なら毅然として立ち向かってゆけるだろうと今では半ば確信してもいる。最終的にデュアンがどういう判断を下すかはともかくとして、ディとしてはデュアンに後を継いでもらいたいと、以前よりずっと強く思うようになってはいた。
「そうそう、アレクがさ」
「アレクさん?」
「さっき、きみもちょっと聞いたと思うけど、今度のことは彼らの仕事に元凶があるからって、きみが帰って来たら何でもおねだりを聞くと言ってたよ」
「ほんと?
なんかそれって凄いかも」
「ヨットか別荘でも、おねだりしてみるかい?
なんなら、きみ専用のジェット機とか」
それへデュアンは首を傾げてしばらく考える様子だったが、すぐには結論を出しかねたようで、それについてはゆっくり考えることにして、と言ってから続けた。
「ぼくは今のところアレクさんよりディにおねだりがあるんだけど?」
「はいはい、何でもどうぞ。デュアンは頑張ったんだしね」
「あのね」
「うん」
意味ありげにディを見ると、デュアンはにっこりして言った。
「頑張ったご褒美なら、ぼくが一番欲しいのはディなんだけどな?」
さもあるだろうとは思っていたのだが、実際にそう言われてみるとディはちょっと不思議な気分になった。それはもう18年ほども前、当時ちょうど今のデュアンと同じくらいの年頃で天使のように可愛らしかったマーティアが、所も同じこのベッドの上で言ったこととよく似ていたからである。マーティアはその頃、あまりにも苦労知らずで甘やかされ放題のお坊ちゃまだったが、その根性を入れ替えてやろうとディが苛めまくったために、一時コカイン中毒にまでなってボロボロだったのだ。しかし、アレクのおかげもあったとはいえ、その後なんとか立ち直って見せ、それが嬉しくて何でもご褒美をあげたい気分だと言ったディに彼は「じゃあ、ご褒美にディをちょうだい」と言ったのである。
マーティアもあの頃は本当に可愛かったよなあと思うたび、アレクに譲らなければ良かったという気もするディなのだが、当時はともかく今のマーティアは、彼にとってどちらかというと仲の良い弟のような存在になってもいる。それに何よりアレクに譲ろうと思ったのは、性質的にマーティアには自分より彼の方がずっと相応しいだろうと思えたからだ。それが正しかったことを証明するように、アリシアのことがあってなお二人の関係はこの18年近く変わっていない。
実際、デュアンはその存在そのものがディの中でマーティアの空けた空白にすっぽりハマってしまうことになったため、実の親子でこんな関係にまで進んでしまっているのだ。ディはデュアンが彼に対する恋煩いであまりにも元気がないので、しばらく恋人扱いしてやっていれば納得していずれ可愛い女の子でもまっとうに好きになるだろうと考えていたから、元々はさすがにここまで行ってしまうつもりはなかった。しかし、デュアンのは単なる一過性の恋煩いどころの騒ぎではなかったようで、それほど一直線に思い込まれてはディにしてもいい加減にあしらっておくことが出来なくなったのである。それに加えてマーティアをアレクに譲って以来、アリシアはディとつきあってはいるもののあの調子で、マーティア、マーティアと完全にディだけのものになろうとはしないし、向こうから来てしまうのでかまっているうち必然的にとっかえひっかえになる女の子たちとの関係は、彼にとって全く普通の恋愛でしかない。だから、幼かったマーティアやアリシアにちょっかい出していた時のような面白みというものもまるでないのだ。
類まれな天才児たちの成長に関わるというゲームはディにとって大変楽しかったことではあるのだが、彼らがすっかり大人になった今となってはもうそんな楽しみも二度とは訪れないよなあと思っていたところへデュアンである。確かにIQ300も超えようかというバケモノのような天才児たちに比べれば、どんなに利発とはいえデュアンは普通の子供の域を出ない。しかし、こうして側に置いていると、始め思っていたよりもずっと様々な面を見せてくれて、これでけっこう楽しませてくれるのだ。それに引き取ってから10年親子として暮らすより、ほんの1年恋人をやっている方が、ずっと早くお互いを身近に感じられるようになったのも事実である。
そう考えると、息子としてであれ、恋人としてであれ、ぼくは今ではデュアンをずいぶん大切に思うようになってるんだなと今度のことで改めて気づくような気がしながら、ディは答えた。
「じゃあ、予約ということで承っておきましょう。ともかく、今はお願いだから眠らせて」
ディが本当に疲れた様子で言うので、デュアンは笑って彼にキスし、いいですよ、おやすみなさい、と言った。窓の外では、そろそろ太陽が中天にさしかかろうとしていたが、ディがサイドテーブルのランプを消すと、部屋の中はすっかり夜のように暗くなって闇に沈んだ。
original text :
2008.3.31.+4.3.


|
![]()