|


深い森を控えた洋館に今夜は一室残らず燦然と灯りがともっている。
夕刻を迎える頃からロールスやリモがひっきりなしに加納家の本宅へ乗りつけて来ていた。今夜はマキのバースデイ・パーティがあるからだ。毎年七月のマキのと十二月のクリスマス・パーティも兼ねた綾のバースデイには ― 綾はクリスマス・イヴの生まれである ― 親しい友人の他に各国の大使や在日の企業人などが集まりそれは壮麗なパーティが催される。ヴェルサイユ宮をも彷彿とさせるボール・ルームは見事な庭園に面し、夏の集まりには全てのフランス窓が開け放たれて園遊会の様相さえ呈するほどだ。
五つの大きなクリスタルのシャンデリアが煌き、管弦楽の流麗な演奏に人々の喧騒が重なる。中央に飾られた毎年パスティリー・シェフが腕をふるうバースデイ・ケーキはゆうに二メートルというスケールで、料理の方もこの本宅付きのシェフの他にル・カトルの田原惣一郎が加わって何日も前から準備が進められるという。全ての材料が吟味され、フランス各地から空輸されるものも少なくない。そして、とっておきのヴィンテージ・ワイン。毎年招かれる客が何よりも楽しみにしていると言われるものだ。
先代は無類のワイン通だったから、その頃からのストックの中には垂涎の的ともされる年代のものが数多く眠っている。もちろん修三氏も先代に劣らないワイン好きで知られるから客たちが期待するのも無理はない話だ。そして毎年その期待がはずれたことはない。ちなみにそれらのワインは全てがフランス産である。
前庭の車寄せに何十台も並ぶストレッチ・リモ、ベントレー、そしてロールス・ロイス。それからもわかるように出席者の全ては盛装で、日本中で最も洗練されたパーティとも言われるこの集まりに殊にご夫人がたの熱の入れようは尋常ではない。クリスチャン・ラクロワ、ジャンニ・ヴェルサーチ、シャネル、ヴァレンチノ・ガラヴァーニ、ヴァレンシアガと、ハイ・ファッションの巨匠たちの手になるドレスに競って高価な宝石をお召しになるほどだ。
しかしそれらの貴婦人たちが束になってもかなわないのが加納家の二輪の名花である。こういう場合、綾もマキに付き合って着飾らないわけにはゆかないから、まや子夫人がはりきるのなんの。
マキはラクロワの手になる純白のデコルテで白雪姫かシンデレラ姫のように可愛らしい。髪はテンドリルに結い上げて白百合を飾り、胸もとには十数カラットはあろうかと思われるダイアのネックレス、足もとは真珠を散らした白いシルクのパンプスですっきりとまとめている。綾は深いヴァイオレットのシースで抜群のスタイルを際立たせ、大粒のアメジストとダイアを散りばめたチョーカーにおそろいのイアリングだ。ちなみにドレスはディオールにオーダーし、宝石は最上の石を選んでカルティエで作らせた。もちろんどちらも今夜のパーティーのためだけにだ。
「羨ましい限りだよ、修。きみは」
テラスでグラスを片手にアレックス・ニコルソンが言っている。遠まきに今夜の主役たちを眺めながら修三氏に言ったのだ。伯爵の位を持つだけあってさすがに優雅な長身の紳士だが、実業家としても辣腕で鳴るやり手だから青灰色の瞳は意外に鋭い。
「そう?」
「全くね。あれほど美しい姫君を二人も娘として持てるなど。その上きみの奥方ときたら・・・。いったい彼女は本当に年を取っているのかね」
修三さんは笑っている。
「まるでご令嬢が三人いらっしゃるようだ」
「彼女の年齢については私もそろそろ自信がなくなっててね。数えるのをやめてから随分になるし」
「数える意味がないんだろう」
「まあ、そんなところかな」
そんな話をしているところへ綾が二人を見つけて歩いて来た。
「ハイ、アレック」
「おや、このような年寄りのところへわざわざお声をかけに来て下さるとは。光栄の至りですな、姫君」
アレックは大仰に言って一揖して見せた。
「どういたしまして。避難して来たんだからしばらく相手してよ。疲れちゃって」
「あいかわらず社交嫌いが直らんようだね」
「まあね」
「きみを目当ての紳士諸君も多かろうに。残念なことだ」
綾はしかめっつらをして見せた。
「それより修。例の事件でグリフィンに悪い影響はなかったかな」
「例の、というと」
「もちろんあの狙撃事件のことだよ。ほら、二か月ほど前の」
修三氏は全くのポーカーフェイスで、ああ、あれか、と答えた。綾もしれっとした顔で無邪気に口をはさんだ。
「あの時アレックも近くにいたんだって?」
「そう。こう殆ど目の前をね・・・」
言って彼は弾丸がかすめたような仕草をした。
「一瞬のことだったがね」
「不愉快な思いをさせてしまいましたね」
修三氏が言うとアレックは首を横に振った。
「いやいや、きみのせいではないさ。ただ、あれでグリフィンの鉄壁の名声に傷がつくようなことでもあれば、きみの方こそ被害者だろう」
綾が言っている。
「確かに中で起こったならね。でも屋外となると・・・。あれは防ぎようがない」
「なるほど」
「それに警視庁の所見によると使用された弾丸やその他の状況から見て遠距離からの狙撃だろうって。千ヤードかそのくらいと考えてるらしいけど、それだと狙撃位置は半径一キロ周辺になるわけじゃない。いくらグリフィンが万全の対テロ構造でも、そこまでの対応はしきれてないからね」
「城砦の死角というわけだね」
「そういうこと」
「そのことを皆さんもわかって下さったようでね。営業に差し支えがあるということはないようだ」
「それは良かった。しかし未だに犯人の背景もつかめんとは。意外に日本警察も情ないものだね」
「全く」
アレックの言うのへもっともらしく二人が頷いていると、マキがまや子夫人と、もう一人背の高い青年を伴って三人の所へやって来た。
「アレックおじさまっ。こんばんは」
ひとなっつこい笑みを浮かべてマキが言うと、アレックはいっそう相好を崩して嬉しそうに彼女を迎えた。
「こんばんは。今夜からきみも十八才か。すばらしいレディになったものだ」
「ありがとう、おじさま」
「外側だけだよ。なにしろ未だにぼくのベッドにもぐりこんで来て寝ちゃうんだから」
「ん、もおー、綾の意地悪」
マキがふくれっつらをするのをアレックは楽しそうに眺めていたが、ふいにまや子さんの横で微笑を浮かべている青年に目を留めて尋ねた。
「そちらは?」
修三さんはさっきから気づいていたらしく彼をアレックに紹介した。
「峰岸裕也くん。綾の友人だ」
「ほお」
「久しぶりだね、裕也くん」
「ご無沙汰していました」
「今日はわざわざマキのためにありがとう。帰国早々で忙しいだろうに」
「とんでもない」
「ああ、それからこちらはアレックス・ニコルソン卿。美術蒐集家としても有名だから知っているかもしれないね」
「スコットランドの?」
「そうだ」
「存じ上げています。確かすばらしい印象派のコレクションをお持ちでしたね」
「ほお。聞き知ってもらっているとは光栄だね。日本の若者もクオリティが高くなったようだ」
握手を交わしながら感心した様子でアレックは言った。
「彼は特別さ。画商のおば上をお持ちでね。その上、作家でもある」
「なるほど」
「お父さまにね、お話があるんですって」
「何?」
「・・・お話のお邪魔にならなければいいんですが」
「かまわないよ。それとも込み入ったことかな」
「いえ。おばに譲って頂いた絵の件で」
「ああ、あれ」
「お顔を拝見する機会があったら、お礼を申し上げなくてはと思いながら長い間日本から離れていて・・・」
「いや、こちらこそ良い投資をさせてもらった結果になったからね」
「ありがとうございました」
「ね、ね、綾。裕也に大きなぬいぐるみもらったの。こーんなのよ。マキが乗れるの」
「これだよ。わかるだろ、アレック」
綾があきれたように言うのへ、アレックは笑って頷いている。
「だって本当に可愛いのよ。見せたげるから来て来て」
「あー、はいはい」
「裕也もっ」
「はいはい、ご一緒しますよ、お姫さま」
彼は笑って言うと修三氏とアレックに会釈したが、その手を強引にマキが引っぱった。三人が行ってしまうとまや子夫人が微笑してアレックに言った。
「マキちゃんたらもう大はしゃぎなの。あの子裕也ちゃんのことお気に入りだったから」
「綾の友人だって?本当にそれだけ?」
「残念ながらそうなのよね。裕也ちゃんだったら息子に欲しいのに。とってもハンサムでしょ。きっと何着せても似合うと思うのよ」
まや子夫人が少女のようにはしゃいで言うのを二人は笑い交わしながら眺めている。夜中まで続くはずのパーティはいよいよ佳境を迎え、人々の喧騒もいっそう華やかにさざめきたってゆくようだった。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2009.1.18.
revise : 2010.11.29.
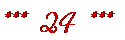
|
![]()