|

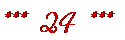
「お帰りなさいませ、お嬢さま」
「ただいま」
綾が家に入ってゆくと、まだ若いこの家の執事メイスンが出迎えた。
「何か変わったことは」
「東京のだんなさまからお電話がありました」
「そう。何て言ってた」
「明後日の朝こちらに見えるそうですので、お嬢さまも明日は東京へお帰りにならずにニューヨークにそのままいらっしゃるように、と」
「どうして」
「奥さまのお加減がよろしくないそうで、明後日ロックウェルさまのお宅で催されるパーティーにご一緒下さるようにとおっしゃっていました」
うぇー、と、綾は心の中で舌を出した。ダンならともかく、アーサー・ロックウェルは大の苦手である。
「まやさん悪いってどうかしたのか」
「かぜ気味でらっしゃるとか」
「そう・・・」
綾はまゆをしかめた。この季節になると時々まや子さんは体調を崩す。微熱が出たり、かぜをひきこんだり、のどを痛めたりと、大したことはないのだが心配のたねではある。大丈夫かな、と思いながら綾はメイスンにわかったよ、と言って自分の部屋へ歩いて行こうとした。
「お嬢さま」
「まだ何かあるのか」
「だんなさまがくれぐれもお逃げ下さるな、と・・・」
「え?」
「私が叱られてしまいますので、どうか・・・」
「あー、はいはい。わかりました。逃げません。ちゃんと出席します」
メイスンはにっこりして、ありがとうございます、と言った。
「遅くなって悪かった。おまえももう休んでくれていいよ」
「恐れ入ります」
綾は階段を登って部屋の方へ歩いて行った。
*****
部屋に入ると綾は後ろ手に閉じた扉にもたれかかって、いつになく真面目な顔でため息をついた。
― ぼくは未だにスティーヴが恐い。
どうしてだかわからないのだが、そして彼女自身も忘れている時の方が多いのだが、必要以上に触れられたり近づかれたりすると身動きが取れなくなるような気がして仕方なくなる。
綾はスティーヴと初めて会った頃のことを考えて、その時のことのせいかなとも思ったりしていたのたが、それは彼女にしてももう決着がついていることなはずだった。なのに今日も、だ。
綾がスティーヴをひっぱたいたのは単に怒ったためばかりではなかった。もう今更キスの一つや二つで喚かなくてはならないくらい子供ではないし、テッドだったら冗談で済ませてもしまえる。ところがスティーヴだけはだめなのだ。恐いという反動でつい高飛車に出てしまう。何故なのかは今の彼女には全く見当もつかない。
もう一度深いため息をつくと綾はリヴィングを抜けて寝室の方へ歩いた。充分にスペースを取った空間には象嵌細工を施したヘッドボードを持つクインサイズの大きなベッドが据えられ、フランス窓には高い天井から天蓋に飾ったカーテンが流れ落ちている。このニューヨークの屋敷にある彼女のスイートは東京のものよりもずっとシックで落ち着いた仕上がりになっていて、この寝室の奥には更にドレッシング・ルームが続いていた。
彼女は着ていた洋服をすっかり脱いでベッドに放り出すと、ローヴをはおってバスルームに歩いた。熱いシャワーを浴びていると不思議に気持ちが落ち着いて来るような気がする。スティーヴと門の前で別れてからずっと言葉に出来ない不安な気持ちが拭えないでいたからだ。シャワーだけにしようと思っていたのだが何となくそのままゆったりと身体中の力を抜いてしまいたくなり、綾はバスを使うことにした。
熱めにした湯に全身を預けてしまうと、とても幸福な気分になってくる。彼女はバスタブのふちに頬づえをついて意味もないのに微笑していた。
ウォルターと別れてから綾には何人も特別なつきあいかたをして来た相手がいる。ウォルターのように未だに友人である場合もあるし、大げんかしてひどい別れかたをした相手もいるが、そういう場合は例外なく綾が悪いのだ。できるだけ避けてはいるのだが、結婚という言葉が出てきてしまうともういけない。そんなことを言いそうにないはずの男ばかりとしかつきあっていないのに、結局相手の方が綾に夢中になってしまうのだから始末が悪いのも事実だが、そのわりに、と彼女は思っている。
― どうして誰ともつきあわないでいられないんだろう。その方が厄介もないのにな、そーしよーかな、これから。
そうだ、決心しよう、と思って西野安隆のことを思い出した。日本に帰ったら会う約束があったのだ。
*****
綾が新しいローヴを着て寝室に戻り、髪を乾かし終えた頃、ナイト・テーブルの電話が遠慮がちにベルを鳴らした。彼女はベッドに勢いよく身体を預け、大きく伸びをしてから受話器を取った。
「はい」
― 綾かい
「なんだ。やっぱり修三さんだ」
― そろそろ帰ってるんじゃないかと思ってね
「かけようかな、と思ってたとこ。まやさんどうなの」
― 少し熱があるくらいだ。ただ飛行機で長旅するとね、心配だから
「うん、そうだね」
「どこに行ってたか聞かせてくれるかな、不良娘」
彼は書斎の大きな机の前でゆったりした革椅子に深くかけて足を組み、微笑を浮かべて話していた。東京はそろそろ昼下がりだ。受話器から綾の声がしている。
― コンサートだよ、ウォルターの
「・・・・・」
― どうかした?
「別に」
― やだな、何か勘ぐってるでしょう。三日ほどこっちでやるからさ、行って来ただけだよ。
「誰と」
― え?
「誰かと行ったんだろう」
― スティーヴ。
それを聞いて彼がまた黙ったので綾も言わない方が良かっただろうか、と考えた。
スティーヴの性格と腕を彼はけっこう買っている。自身何度か会ったことがあるし、頭が良くて礼儀正しい、そういうスティーヴを個人的にはとても好きだ。しかしである。綾が彼にかまいすぎるのは、はっきり言って気に食わない。
「ねー、修三さん。どうしたの」
「どうもしませんよ」
「うそだ。どうもしなくてどうして黙るの」
「私にだって言葉につまる時というのはあるよ」
「どうしてつまったの」
「聞きたいのか」
「うん」
綾はベッドに足を上げ、大きな羽根まくらに沈みこむと煙草をくわえて火をつけている。
「きみが彼と何をしていたんだろう、と考えたからだ」
「コンサートに行ってきた」
「だけ、と誓って言えるのか」
「言える」
「ほお」
「言えるよ。ほんとだもん」
「そのうち彼に尋ねてみることにしよう」
「・・・・・」
「そらみろ、困るくせに」
「ねえ、修三さん」
「何ですか」
「過、保護、って言うんだよ、そういうの」
「とんでもない」
「どうして」
「娘の素行は親の責任だからね」
「へえー、親って言ったの」
「言いましたよ、悪いですか」
「いいえ、ちっとも」
「だったら何をしていたか、正直に言いなさい」
「いやです」
「どうして」
「嫉妬するから」
「私が?」
「そう」
「いまさら」
「え」
「もう、とおの昔からしてるに決まってるだろう。この放蕩娘っ!」
「まやさんによろしく」
「綾」
「おやすみなさーい。愛してるよ、修三さん」
笑って言うと綾は一方的に電話を切った。
東京では彼が通話の切れたことを知らせる音にしかめっつらをしている。仕方なく受話器を置いてから修三氏は椅子にもたれて窓の外に目をやった。そう言えば、と考えながら彼は天井を見上げた。
― あんな娘に育てたのは私だったっけな
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2009.1.18.
revise : 2010.11.29.
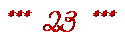

|
![]()