|

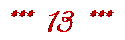
六月の半ばから始まったレコーディングもやっと終わりに近づき、あとはニューヨークに帰って総仕上げという段階にまで差しかかろうとしていた。
その頃には誰もがウォルターの成功を確信するくらい作品の完成度は高く、綾もダンに言っていた通り大きなパーティを開いて徹底的に彼のデヴューを飾るつもりで準備している。けれどもその中にあって一番幸せな顔をしていてもいいはずのウォルターが内心落ち着かないのも事実だった。
八月が終われば綾は仕事に戻るはず、とまだ彼は思っている。綾が見かけの傍若無人なもの言いとは逆に、本当は気がつくべきことにはちゃんと気がついて、しかも思慮深く思いやりがあることは一緒に過ごせば過ごすほどわかることだった。だからウォルターが余計離れ難くなるのも無理はなかったが、この夏が終わっても彼女が側にいてくれるかどうかはウォルターにも全く自信のないことなのである。
その夜もウォルターは真夜中に目を覚まして自分の腕で眠っている綾の無邪気な寝顔を眺めていたが、ふいに深いため息をついた。そうしていると綾は何の変哲もない ― ただちょっときれいすぎるだけの ― 十七才の女の子にしか見えない。それで、ぼくより七つも年が下なんだっけ、と改めてウォルターは思っている。
会った時からはっきりと強い自負に裏打ちされた態度と尊大にすら聞こえかねない口のききかたや言いたい放題の酷評、そのせいで彼には綾がそんな年でしかないということが本当には理解できていなかったようだ。
確かに経営に関する限りは有能で大人の考えがあるのだろうが、プライヴェートではやはり十七才の少女でしかないだろう。考えてみればウォルターのことだって気まぐれではないとも言い切れない。そうでないにしても唐突にプロポーズなんかするにしては二人の住むもともとの世界は隔たりすぎていた。
彼は綾を起こさないようにベッドを抜け出すと、ローヴをはおってバスルームに歩いて行った。
十代の頃からショウ・ビジネスの周辺にいたこともあって、ウォルターにかまいたがる女性はいつも一人や二人ではなかった。その中には今では有名な女優やヴォーカリストもいたし、しばらく一緒に暮らしていた相手もいる。そんなことを繰り返して来ていたから、音楽に較べれば女の子なんて自分にとってそれほど意味があるとも正直に言えば思っていなかった。それなのに綾が現れてからは全てが彼女を中心に回っている。そんなことは初めてだったから、彼は綾を失うのがこわくて仕方なくなっていた。
かと言ってどうすれば彼女を引き止めておけるんだろう、と熱いシャワーを浴びながらウォルターは考えている。
綾が単なるお嬢さまなら自分が認められるだけの仕事をすればいい。けれどもウォルターには綾が普通の女の子たちのように四季花の絶えない美しい家や調度、ドレスや宝石で満足するほど単純ではないことがもうよくわかっていた。そんなものなら今まで彼女にはいくらでも手に入ったし、その中で満足しているはずた。そうではないからこそウォルターには綾が特別なのだけれども、逆に言えばだからこそ厄介なのも事実だった。
綾は宝石よりも哲学に美と永遠を見出し、お手軽な恋愛よりも経済や歴史を魅力的な冒険と感じるような女の子だ。そんなものを彼女に与えられる男がいるとしたら、それは加納修三以外にありえなかった。
ウォルターはしばらくして寝室に戻るとベッドに腰かけて綾を見ていたが、ふいにナイト・テーブルにある煙草のパッケージとライターに気がついた。身体に良くないからやめなさい、といくら言っても綾はのべつまくなし煙草をくわえている。本当にもお、とため息をついて彼はそれを隠してしまうつもりでドロワーを開けたのだが、その中にあったものを見て手を止めた。
拳銃を見たことがないわけではなかったが、それが綾の部屋にあることがどうにもそぐわなくて理解に苦しむことだったからだ。そこにあったのはコルト・ガヴァメント.380オート、綾がいつも側に置いているものだ。日本って銃とか持っちゃいけない国だったよね、と思いながら彼はそれを取り上げてみた。モデル・ガンでもないらしい。
ウォルターはそれを持ってベッドから立つと、いたずらのつもりで綾に向かって照準を合わせた。
彼女が側で誰かの動く気配に気がついて眠りから覚め始めた時、ぼんやり開いた視界に飛びこんで来たのはコルトの銃口だった。綾は一瞬で目を覚まし、思わず半身を引き起こしたが、銃を持っているのがウォルターだとわかると、心の底からほっとして身体中の力が抜けて行った。
「あ、びっくりしたの、ごめん。ただちょっと本物らしいから・・・」
「ばかやろうっ」
綾は顔を上げて彼を見るとものすごい声で怒鳴った。
「え・・・」
「さっさとこっちよこせよっ、装填してあるんだぞっ」
「綾・・・」
「テーブルに置けったらっ」
彼はその見幕に圧倒されて拳銃をそっともとあった所へ返した。それを見てやっと綾は落ち着き、深いため息をついて言っている。
「どうせ銃なんか持ったこともないくせに、ヘタに素人が触って暴発でもしたらどうするつもりだったんだ。ばか」
「あんなこと言ってる」
ウォルターはベッドにかけながら笑っていた。
「何だって?」
「素人ってさ。きみだって的にあたるの。そんな細い腕してて」
「・・・・・」
「とか言って、案外百発百中だったりしてねー」
ウォルターは全く自分の言っていることを信じてなどいない様子で冗談口をたたいた。けれども彼女が茫然とした表情をしているのに気づくと不思議そうな顔をしている。
「綾・・・?」
「当たるわけ・・・」
「え」
「当たるわけないだろ、そんなの。ただの護身用なんだから」
「だよね、やっぱり」
ウォルターは単純に納得している。その横で綾は手を伸ばして煙草のパッケージを取ろうとしたが、今度はウォルターが止めた。
「だめだよ」
「どうして」
「肌が荒れるだろ」
どこかで聞いたセリフだな、どいつもこいつも同じこと言いやがって、放っといてくれ、と綾は思ったが、口には出さない。それをどう受け取ったのかウォルターはにっこりして綾を抱き寄せると、優しく唇を重ねた。
*****
綾が銃のことで顔色を変えたのは無理のないことと言えた。彼女には修三さんがまるで心配もせずに憎ったらしいポーカーフェイスを保っていられた理由がイヤというほどよく分かったからだ。彼はきみに相応しくない、という言葉の裏にあったのが、きみのことをウォルターが理解してくれるとでも思っているのか、という彼女の浅薄に対する嘲弄だということもはっきり認識せざるをえなかった。
綾はウォルターとのことを見透かされていた事よりも彼が無理にでも帰って来いとは言ってくれなかったことの方が格段応えていたのだが、深読みすれば考えてみろと言って突き放したのも綾の、ある意味では裏切りに対する彼らしい報復だということにも気がついた。
彼がどれほどプライドの高い男か綾はよく知っている。彼女は確かにその彼にとって唯一優越権を持っている人間には違いなかったが、裏を返せば綾にとってもそれは同じと言っていい。そしてそれを行使するには充分な注意が必要なことも綾は思い知らされていた。
確かにウォルターは綾や修三さんと同じように概念や現実というあらゆる幻影の向こうにある真実を見抜く目を持っている。それはまぎれもなく芸術家のものだ。けれども彼が光に属するとすれば綾は闇に、彼が闇に属するとすれば綾は光に、決して相容れない所にお互いがいることも事実だった。ウォルターには絶対に理解できない部分が綾の中にはあるからだ。コルトはそのどうやっても説明のつけようがない綾の内在を象徴していた。
例えば彼女は平気で人間に向かって引き金が引ける。自分と敵対する者や脅かす者に対して綾は容赦ということをしない。もちろんそれはそうしなければ生き残ってゆけない概念上の領域で生きているからに他ならないのだが、それも元来彼女の性質から出ていることだ。ある種の人間にとっては社会通念に自我を適合させることは死を意味する場合がある。そういう人間にとっては物理的な死よりも自我そのものが活動を停止することの方が余程恐ろしいことなのだ。
社会通念の存在しない所で生きようとすれば、その保護も当然受けることは出来ないだろう。しかも彼女の視点は宇宙的なレベルにある。地球を包含する宇宙的な視点から世界を見るということは、この世界に善も悪も、ましてやそれに連なるあらゆる概念が存在しないことを認識することでもある。
どれほど美しく聞こえるヒューマニズム的な論理でも結局のところそれは人間によって作られたものでしかない。ある人々にとっては正しく、ある人々にとっては間違っているか、バカげた冗談でしかないようなものなのだ。
世界のあらゆる場所で社会という組織集団が形成されている。もちろんそれ自体も巨大な幻影にすぎないが、それらは古代からある個人の、もしくは特定の集団の利益のために機能してきた。つまり人間という家畜を国家という柵に囲いこみ、飼育するためにこそ社会という組織集団が必要だったのである。
言い換えればあらゆる法も概念も囲いこまれた枠の中でのみ有効なのであって、一歩外に出ればそこを支配するのはまた別の理屈でしかない。絶対性のない論理が割拠する世界だからこそ、それを維持するためには力という後ろだてが必要になる。そしてそれはどれほど理想的な論理であっても免れ得ない法則なのだ。無法地帯に秩序を打ち立てるにしても力があってこそ、何故なら秩序そのものが幻影でしかないからだ。この世界に絶対的な正義など存在しない。
そして人間の世界の無法のすべてが人間自体の引き起こすものである以上、敵もまた人間以外ではあり得ない。もしそれを否定したければ厖代(ぼうだい)な歴史という記録を一切抹消するか、そうでなければアドルフ・ヒトラーから弁護しなければならない。
綾は根本的に作られた概念の檻の中で生きることを否定し、それを創ることの方を選んで生きている。だから彼女にはあらゆる既成概念は適用されない。またそうでなければ彼女自身が生きているとは言えないのでもある。けれどもウォルターはその同じことを認識しながら、戦い、壊し、再構築するよりも癒そうとする。彼の音楽も綾が経済を掌握しようとするのも同じ目的から出ているが、その方法はあまりにも違いすぎていた。
ウォルターに綾は理解出来ないだろう。それはオルフェウスにアテーナイと、それともシヴァの神と同化しろと言うようなものだ。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.10.7.
revise : 2010.11.29.
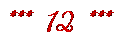
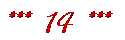
|
![]()