|
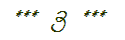
「それでね、お父さん。ぼく思ったんだけど」
生活時間がまるっきり違うこともあって、二人は普通の親子のように一緒に食事を取れる機会が少ない。引き取った責任もあるので、ディは息子をあまり淋しがらせないよう食事くらいできるだけ一緒にしてやろうと努力はしているのだが、そこは何と言ってもアーティストさまのこと。気分が乗れば真夜中過ぎても絵を描くのに没頭していることがしばしばで、しかも、芸術家のインスピレーションというものはハタ迷惑なほど時と場所を選ばず訪れてくるものなのだ。ディが自分の生活時間を規定されるようなこと ―
例えば結婚もそのひとつだったのだが ―
を何より嫌うのは、まさにそのせいだと言っていい。彼の時間は基本的に全て、絵を描くためにあるからである。そこへ持ってきて、ディにはモルガーナ家当主としてこなさなければならないスケジュールが常に山積みになっていて、これが家でゆっくり食事できる機会を更に少なくしている。もちろん、その他に女の子と遊ぶ時間もトッピングされているわけだ。
しかし、デュアンはもともと画家としてのディに心酔していることもあって、彼の画業を妨げるような行動は自ら一切取るつもりがない。ましてや幼いとは言え、自身もアーティストのハシクレであるのだから、気の乗っている時にそれをそがれるのがどんなにイヤなものかということもよく知っている。そんな状況だったから、こうしてディから食事のお誘いが来るのは、デュアンにとって現在一番の楽しみになっているのだった。
一方ディはディで、自分の邪魔をするまいと面倒なダダひとつこねずにいるデュアンの健気さが可愛いらしく、要するにこの親子、一緒に住むようになってからますます仲良し度を増してきているということだ。それにディが忙しいなら忙しいで、デュアンには世話をやいてやらなければならないカトリーヌという母がいる。だから、こちらに移る時に約束していたように、学校帰りには彼女とお茶や、ディがいないと分かっている時は食事も一緒にしてくるし、そこで泊まって翌日もまたそこから学校とか、週末ずっと母と過ごすということだってよくある。そんなわけで、デュアンにしても父が忙しいからと言って、そんなに淋しい日常を送っているわけではなかった。
デュアンの言うのへ、ディはワインを飲みながら尋ねている。
「ん?
なんですか?」
「だからぁ、チャールズもジェームズも、それにアーネストも、みんなカッコいいなあって。"その道のプロ"って、ああいう人たちのことを言うんだよね」
言われてディはデュアンを見ると、自分を指さして見せた。
「え?」
「ぼくは?」
どうやらディは、自分のこともカッコいいと言ってもらいたいらしい。デュアンはそれに気づくと笑って、それはもちろん、お父さんが一番カッコいいよ、とサービスしてやった。このテの冗談は気を許している時のディにとっては日常だから、今ではデュアンもすっかり慣れっこになっている。
「有難う」
春めいてきたこともあって、二人がランチを取っているのは陽射しあふれるサン・ルームのテーブルだ。今日は、新鮮野菜と魚介類をたっぷり使ったサラダのボールを卓の中心において、その周りには薄くスライスして小さく切ったパンに好きなものを乗せて食べられるよう、生ハムやスモークサーモン、サーディン、アンチョビ、フォアグラペースト、海老をタルタルソースであえたものやナチュラル・チーズの盛り合わせ、それにオリーブ、ケッパー、ザワークラウトなどが盛られた皿がいくつも並んでいる。もちろんフルーツのコンポートやドレッシングも何種類か用意してあって、それに仕上げとして爽やかな風味の白ワインが添えられていた。
これはデュアンがこのところ特に気に入っているラファイエット風のオシャレなランチ・メニューなのだが、これが時には中国風に飲茶になったり、ちょっと本格的なコース料理になったり、はたまたピクニック風になったり南国リゾート風になったり、なにしろ昨今、ジェームズがデュアンを喜ばせることに嬉々として料理人生命を賭けているので、ランチばかりではなく折に触れて様々なメニューで楽しませてくれるのである。それへまた、気配り少年のデュアンがいちいちその細かな工夫に気づいて、あれが良かった、これが美味しかったと褒めるものだからジェームズの喜ぶまいことか。そこで張り切る彼は、ますます新たな創意工夫を凝らしてデュアンの味覚に挑戦してくる。それを考えるとこの子は生来、ディ同様に"芸術のパトロン"ともなりうる資質を兼ね備えていると言えるかもしれなかった。
「ところで、アーネストが言ってたけど、うちにはきみのファンクラブなんてあるんだって?」
「え?」
「だからさ、きみがぼくを差し置いて、今やこの家の"アイドル的存在"になってるらしいって聞いたんだけど?」
「え〜っと...」
どう答えたものかと悩むデュアンの前で、ディは、ナマイキな、と言って息子に非難の目を向けた。
「だってファンクラブだったら、お父さんのだってあるじゃない」
「どこに」
「それはもう、世界中。あれ?
知らない?
ネットで検索すれば山ほど挙がってくるよ?」
「そうなんですか?」
「そうなんです」
「でも、うちのメイドさんたちは、ぼくよりきみの方がいいみたいじゃない」
「え〜、だって、それはやっぱり...」
「やっぱり?」
「騒ぎにくいじゃないですか、相手が相手なんだから本人の目の前じゃ」
「そうかな」
「それはそうですよ。ぼくあたりならともかく...。だいたいね、デュアン・モルガーナともあろう人が、息子の私設ファンクラブ程度のことを気にするなんて、信じられないよ」
「信じられないって、本人が言ってるんだから」
「それはそうだけど」
「まあ、父親としてはきみがみんなから愛されてるのは喜ぶべきことだとは思うけど...」
「でしょ?」
「ちなみに伺いたいんですが、何がどうなってファンクラブなんて成立しちゃったわけ?」
「え、それはなりゆきというか...。最初はミランダがぼくの絵を見て気に入ってくれて、励ましてくれるつもりだったんだと思うけどファンになっちゃったって。それで、新作描けるたびに見せてたら、マリーヌもシャロンも、それから他のみんなも一緒に見てくれるようになって、ときどき雑誌に載ったりするとすごく喜んでくれて、で、誰かがファンクラブみたいですねって言い出して...」
「それじゃ、会長はミランダ?」
「マーサだよ」
言われてディは、そういうことかと納得がいった。アーネストは"若いメイドたちの間では"と言っていたが、どうやらそれにはその総元締めである家政婦長のマーサも参加していたのであるらしい。本来なら彼女が皆をたしなめる立場であるはずなのだが、なにしろマーサもデュアンのことを孫のように可愛がっているから、このなりゆきは決して不思議ではない。アーネストもそれは知っているのだろうが、いや、知っているからこそ、どうしたものかと考えてディに相談したのだろう。
「なるほどね」
「それは、みんなにそんなふうに思ってもらえるなんてぼくだって嬉しいしさ。いいよね?
そんなファンクラブくらいあっても」
言われてディは首を傾げている。
「そうだねえ...」
「みんなにいろいろ感想とか言ってもらえると、次の作品の参考にもなるもん」
デュアンのアイドル性もあるのだろうが、それよりもどうやらこれは息子の才能の方に主体があるらしいと分かってディは考えている。しかし、しばらくして、ま、そういうことなら、と結論したので、デュアンはほっとしたようだ。
「たださ、お嬢さん方の控え室に押しかけて行くのはどうかと思いますけど」
「押しかけてゆくって、それは...」
「どうせなら、本格的にファンクラブにしちゃったら?
新作描けたら、お茶会でも開いて。その方がずっとゆっくり感想が聞けるだろ?」
「えっ、いいの?!」
「マーサが参加してるなら、問題ないと思うよ。みんなの都合だってあるんだし。ただ、一応きみはうちのお坊ちゃまなんだから、立場ということはよく自覚して」
「あ、はい。そうでした、嬉しくて忘れてました」
「忘れないでね」
「気をつけます」
これでとりあえず、デュアンがメイドたちの控え室まで出向いてゆく必要はなくなるのでアーネストも安心するだろう。後は、厨房と厩舎か、と考えて、しかしまたこの子はぼくと違って社交的というか、行動半径が広いなと呆れつつも感心している。ともあれ、何もかもを急激に変えろと言われてもデュアンだって窮屈だろうし、他は徐々に様子を見ながら対処していくしかない。
「ああ、それとね。話は変わるけどさ」
「はい?」
「レイ、知ってるだろ?
ロクスター侯の奥さんの」
「ええ」
「彼女が、きみもこっちにきてもう何ヶ月も経つんだし、そろそろ落ちついた頃だろうから遊びに来させろってうるさいんだよ」
「あ、お披露目の時に、絶対、遊びに来るのよって約束させられてたんだ」
「そう?」
「うん。ぼくは全然いいですよ?
面白そうな叔母さんだったし」
「デュアン」
「え?」
「きみは、なんて大それた発言を」
「え、何が?」
「レイのことを"叔母さん"だなんて。本人がいたら、首絞められてるよ」
「あ、失礼しました」
「彼女はね、きみのおばあさまの親友でもあった人で、うちとも本当に長いつきあいのある人なんだから、むやみとご機嫌をそこねないように。厄介だから」
言われて、ふとデュアンは首をかしげた。
「おばあさまの親友って。それっておばあさまが生きてらした頃のってことだよね」
「当たり前でしょう」
「...あの、お父さん」
「何?」
「あの方、いったい本当はおいくつなんですか?」
「そういうことも聞いてはいけません。こんなの紳士の常識だよ」
「だって!
もしおばあさまと同年代なんだったら、叔母さんですらないじゃないですか!」
「だから、知らなくていいことは知らなくていいんだよ。きみに彼女のトシを教えたなんてバレたら、ぼくの方が絞め殺されるから。できないよ、そんな怖いこと」
言われてデュアンは黙った。
「とにかくまあ、そんなわけだから。近々あちらを訪問すると答えてもいいかな?」
「それは構わないけど...」
「ぼくも一緒に行くから」
「ああ、それなら安心。だってぼく、なんか言っちゃいけないこと言っちゃいそうで」
言われてディは笑って頷いた。
「彼女も既にきみのことは気に入りまくってるから、めったなことでは怒らないだろうけど、とにかく女性をキズつける発言だけは控えてね。もてなくなっちゃうよ?」
「はい...」
そうすると、お父さんがもてるのは逆に女性を喜ばせる発言がウマいからなのかなと考えて、デュアンは彼と母が跡取り騒動のことでモメていた時のことを思い出した。確かに、その通りのような気がするし、それを考えると祖父が父のことを"取り得と言っては、絵を描くことと女性の扱いがうまいことだけ"と揶揄するのも無理はないかもしれないと思える。もっとも、デュアンには彼の父の取り得がそればかりではないことくらい、もう十分に分かっていることではあった。
食事が終わると春らしい装いのデザートがサーヴされ、二人はそれからもしばらくお茶を飲みながら陽射しの豊かな午後を一緒に楽しんでいた。それはデュアンにとって、今の日常の中で最も貴重な時間と言える。
original text :
2010.11.23.-12.10.
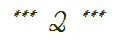

|
