|
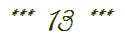
「どうぞ。どこでも好きなところに座って」
マーティアはサロンに皆を招き入れながら言っている。ここはメインサロンだから特に大きなスペースが取られ、天井はドーム状で空間の広さが強調される造りになっていた。アイボリーを基調にしてまとめられたインテリアに白大理石の床が涼しげな印象だ。一階の床は廊下も各部屋も殆どがここと同様に大理石で仕上げられていて、天井にドームを多用しているのもこの屋敷の特徴のひとつと言える。
大きな半円の出窓といくつものフランス窓はそれぞれドレープをたっぷり取ったカーテンで飾られ、今はどれも大きく開かれて午後の陽光とともに気持ちのよい風が流れ込んできていた。瀟洒な調度が配置された室内の中央には沢山のクッションを並べた大きなソファとアームチェア、それに気分をリラックスさせる心地よい香の香りも十分に行き渡っている。しかし、入って来た客たちがまず目を奪われたのは、何と言っても出窓の両側の壁に飾られた二枚の天使降臨図だろう。一目でそれと分かるディの作品である。
「わあ...。うちのコレクションの中にも見当たらなかったから気になってたんですけど、これ、ここにあったんですね」
デュアンは言って、思わず絵に近づいて行くと見入っている。
「ああ、ディがここに合いそうだと言って、もうずいぶん前にプレゼントしてくれたんだよ」
マーティアはこともなげに言ったのだが、デュアンにはそれが相当ショックだったらしい。
「"プレゼント"ですか?!」
「うん」
デュアンが何に驚いているのか、もちろんマーティアは分かっているから意味ありげに頷いている。この絵は十年以上も前のもので二枚が対になっているのだが、モデルがマーティアとアリシアであることは一目瞭然だ。しかも発表されたのが"二人の天使"シリーズから何年も経った後だったから、描かれている二人がそのぶん成長しているのは当然のことで、それがまたド迫力の美しさなのだ。その意味でもインパクトの強い作品だっただけに異常な反響を呼び、二枚が対ということもあってディの作品の中でも最も大きな金額がオファーされているもののひとつとして現在でも専門家や好事家の間で折に触れて話題に上る。もちろんディが手放す気になりさえするなら、いつでも言い値で買おうという蒐集家は掃いて捨てるほどいるだろう。
二枚それぞれの上部には降臨する天使が羽を広げ、その下には歴史の混沌を表現する様々な場面が走馬灯のように描かれている。それなのに色彩は決して暗いものではなく、むしろ天使を包む光がキャンバス全体にも及んで、見る者には画布そのものが光り輝いているかのような印象さえ与える。どちらも高さが2メートルもあるような大作で、その独特の色彩ともあいまって実にディらしいと感じさせる作品だ。
デュアンはこの絵の経緯と価値をよく知っているからディが"プレゼントした"ということに驚いたのも確かだが、同時に父がモデルにしたのがマーティアとアリシアであり、どれほど巨額のオファーがあろうとも売ることなどありえない作品を彼らが相手なら手放してしまうという事実に、ディの二人への寵愛いかばかりと実感させられもしたようだ。聞いてはいたがそれほどとはと思うと、なにがなしちょっとむっとした気分になっている自分にあれ?
と思いつつ、デュアンはマーティアに促されてソファにかけた。
皆が座るとマーティアはアームチェアのひとつにかけ、抱いていたリデルはそのまま膝に座らせた。兄妹と言うにはトシが離れ過ぎているが、それもそのはずでもちろん血の繋がりはない。リデルはマーティアの養父であるマリオ・バークレイ博士の実の娘だから、現在ではその養子となっているマーティアとアリシアは彼女の兄ということになるだけだ。その辺りの事情を知っているらしく、ウィルが尋ねている。
「リデルって、バークレイ博士のお嬢さんでしたよね」
「うん、そう。おれやアリシアには懐いてるんだけど、同い年くらいのコには馴染まなくてさ。まあ、いろいろあって、ちょうどうちに遊びに来てたんだよ」
リデルはマーティアの膝の上に満足しているらしく、二人のやりとりにも我関せずの様子だ。
「あ、で、そのアリシアは今、仕事でクランドルに行ってるんだ。きみたちがいる間には戻ると思うけど、帰ってきたら改めて紹介するよ」
マーティアの説明に皆、何の疑いも抱かずに納得しているが、事実はアリシアは"来るのは構わないけど、だからって何が悲しくてぼくがディのコドモをわざわざもてなしてやらなきゃならないわけ?"と言って帰って来ないだけである。今頃ディはその責任を取らされてアリシアに散々振り回されていることだろうが、彼が子供たちと一緒にここに来なかったのは、そういう事情があったからだ。だからと言ってアリシアは絶対に子供たちに会いたくないというわけではないらしく、彼らがいる間には顔くらい出してやると言っていた。要するに、誰のであれ子供の相手がめんどくさいというのが本音らしい。
「まあ、でも本当に遠いところよく来てくれたね。こういうところだけど、いろいろ楽しめるようにはしてあるから、ゆっくり遊んでって」
マーティアの言うのへ皆、嬉しそうに頷いている。一方で特にウィルは長いこと尊敬と憧れを寄せて来た"ルーク博士"が、思っていたよりもさえ遥かに気さくな人柄であることに改めて驚きを感じたようだ。マーティアの現在の肩書きを並べれば延々延々とキリがないが、その中でも"円卓会主席"、"賢人会主宰"、この二つだけでその意義をよく知っているウィルあたりにはもう近寄るのも畏れ多いという存在だからである。
"円卓会"というのは以前アレクが言っていた"無敵艦隊"の正式名称で、IGDオーナーであるアレク直属のブレイン集団のことだ。現在はマーティアとアリシアを含む十三人がメンバーとして名を連ねており、全員が高IQの持ち主であるが、IGDでは旧来の様々なIQ測定法による数値だけで採用を決めているわけではない。IQ値とはあくまで"指数"であって、他の多くの指数同様それが対象とする要素に対する充足度を示す値に過ぎない。翻って、IGDが必要とする人材には他にも様々な要素が満たされていなければならないので独自の測定法が考案されており、これに基づいて測定すると従来の高IQ保持者の大半はその値が激減してしまうことになる。知能と理性のバランスが取れていないからだ。
ともあれ、その主席であるということはIGDにおいてアレクに次ぐ権限を持っているということで、ましてや当のアレクがあらゆる事の決定にマーティアの意見を重視する、と言うよりも、殆ど言いなりという状態なのだから、その権力や如何ばかりだろう。もちろん本人はそんなものに驕るようなバカではないし、むしろ、そういう種類のバカを徹底的に嫌悪するからIGD独自の測定法というものが必要になったのであって、また、だからこそアレクが絶対の信頼を置いているとも言える。
"賢人会"に至っては更に問題が大ゴトだ。これはマーティアが提唱している"歴史の軌道修正プログラム"、そして"世界連邦構想"の基盤を構築するために設立されたもので、未来の歴史そのものを企画しようという集まりなのだからますますとんでもない。言うなればIGD自体がその"企画"の一部として機能しており、世界の流通を"正しく"コントロールするという目的を持っているのだ。International
Grand Distribution 〜国際総合流通〜
の名称がそれを端的に表しているが、"Distribution"には"流通"の他に"分配"の意味も含まれている。つまり、経済流通が齎す莫大な富を「集積し広く分配」するためのシステムとして機能することがIGDの理想的な在り方なのである。しかし、賢人会にとってはそれはあくまで目的に対するプランのひとつでしかない。
現代までの歴史においては様々な社会形態が現出して来ているが、その基盤を為すものは"論理体系"である。それが"思想"として哲学的に確立されたものであれ、もっとプリミティヴなものであれ、この基盤なくしては社会のあらゆる方面にわたる概念づけが不可能だからだ。善悪の概念でさえ、その基盤とされる論理体系によっては正反対なものとなりうる。そして今日まで、少なくとも過去の記録に残る限り"理想的な社会"などというものが存在していない以上、理想的な論理体系も存在していないことは明らかだろう。マーティアはこの論理体系そのものがこれまでのような個人の思想や歴史的な成り行きではなく、適切な集団による科学的手法によって合理的に構築されるべきであるとごくごく幼い頃から指摘してきたわけだが、なぜならば個人の能力や知識にはそれがマーティアほどの知性を有する者であっても限界があるからだ。ましてや解決しなければならない問題は従来の思想家の想像を絶するほど多岐に渡っており、その全てに対する専門知識を一個人が網羅することはそれこそ不可能である。そこで、これらの問題を総括して論じ、より客観的かつ正確な科学的分析を可能にするために賢人会の成立が必要だった。
主要なメンバーは現在マーティアも含めて9人で、この数は目的に対してあまりにも少ないように思われるかもしれないが、マーティアの下に円卓会や多方面に渡る研究、開発グループが存在しているように、各メンバーがそれに相当するとまでは言えないが多数の協力者を有しているから、携わる人間の数を総合すればかなりなものになるだろう。ただ、扱う問題が問題なのでこれに関わることだけでも様々な危険に晒される可能性は高い。従って、マーティア以外のメンバーが誰であるかは殆ど一般に公開されていない。
どちらを取っても今後の歴史が快方に向くかどうか、マーティアはその総合責任者という本人にとってはちっとも有難くない地位に、ある意味イヤイヤいるわけだが、彼なくしてはそれら全てが存在すらしえないことも事実だ。それなのに、今のようにTシャツとジーンズという軽装で小さな子供を膝に乗せている様子は、その二十代後半という年齢に相応しくまるっきり近所のおにーちゃん状態。プライヴェートな時のマーティアは大体においてこんな風である。ウィルを始め、客たちはそれにますます好意を感じているようだった。
そうこうするうち、皆が落ち着いたところへチャールズがワゴンを押して入って来た。ワゴンの上にはトロピカルなフルーツだの植物だので飾った飲み物のグラスや、様々な冷菓が満載だ。
「どれでも好きなものをどうぞ。きみたちのために用意しておいたんだから、ご遠慮なく。あ、夕食も海の幸をたっぶり味わわせてあげるからね」
それへ皆は口々に礼を言い、好みのものを取り分けてもらっている。
「あの、ルーク博士」
デュアンは大きなゴブレットに満たされたマンゴーのジュースを一口飲んで満足そうな顔をしていたが、ふいに何か思いついたらしくマーティアに声をかけた。
「何?」
「アシュバって、凄いんですね。ぼく、以前からコンピュータがもっと自由に話せたらいいのになって思ってたから感動しちゃって」
それへマーティアは、にっこりして答えた。
「子供の頃、おれもそうだったよ。だからアシュバを作ろうと思ったんだ」
デュアンはそれに納得顔で頷いている。
「あ、それでさ。みんなにひとつお願いがあるんだけど、おれのことはマーティアでいいからね。未だにルーク博士って呼ばれると"それ誰?"って感じがしちゃって馴染まないもんで」
「え〜っ」
声を上げたのはデュアンだが、客たちはみな同じ気持ちだったに違いない。
「なんで、え〜なの?」
「だって、ルーク博士はルーク博士ですよ、少なくともぼくたちにとっては。ってゆーか、それ以外ありえないじゃないですか」
「無理です。ぼくは、お名前でなんて呼べません」
デュアンに続いて言ったのはウィルである。彼が殆ど蒼白と言えるほど本マジな表情で言うものだからマーティアはついつい笑ってしまったほどだ。
「だからさあ、あんまりおれのこと過大評価しないでよねってことだよ。それは確かにいろんなことをやっちゃいるけど、それはどれも回りの協力があって成っていることでおれ一人の力じゃないしね。まあ、外では立場上、仕方ない。でも、おれだってまだこんなトシなんだしプライヴェートでまで"ルーク博士"を期待されちゃ、はっきり言ってしんどいわけ。きみたちがおれのこと、どう思ってくれてるかは大体分かるけど、実態はそんなにご立派なもんじゃないから、最初にそれは言っとかないと。たぶん、きみたちとはこれから長いつきあいになると思うし」
そう言われても畏れ多いというのが皆の本音だったかもしれないが、そこへ横からリデルが口を出した。
「マーティはマーティよね。つきあってれば、分かるわよ」
そのナマイキな言い分に思わず皆から笑いが湧いた。マーティアが彼女をずいぶん甘やかしているらしいのがそれでよく分かったからだ。マーティアも笑いながら言っている。
「まあ、そういうこと。よろしくね」
ウィルは初対面だったこともあってまだ固まっている様子で"努力してみます"と言ったが、ファーンとデュアンはアレクと初めて会った時のことを思い出してなにがなし納得した気分になっている。アレクも"ディんちにメシ食いに来てまでロウエル卿なんてやりたくない"と言っていたのだ。こういうところがディ曰く"苦労知らずの脳天気お坊ちゃまどうし"の似たところなのだろうし、彼らの肩書きに驕らないそういう性質がIGDという組織全体にも大きく反映されているように思われた。
マーティアだけなら皆の緊張感がほぐれるのに多少時間がかかったろうが、リデルがいるおかげでどうやら速やかに打ち解けた雰囲気になってゆきそうだ。
original
text : 2011.4.24.-4.29.


|
