|
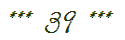
人通りの多いメイン・ストリートをデュアンとファーンが二人で歩いていると、美形兄弟のことで道行く人たちを振り返らせずにはいない。しかし、デュアン同様、ファーンもそういう反応には慣れっこらしく、あまり気に留めていないようだ。
「兄さんて、なんか意外性ありますよね」
「そう?」
「ええ。なんか、全然冗談なんて言いそうにないのに、けっこうヘンなこと言うし」
"ヘンなこと"と言われてファーンは笑っている。
「そういうところ、やっぱりお父さんによく似てる気がする」
「そうかな」
「ええ。お父さんも、会う前は冗談なんて絶対言わないと思ってたんですけど、あれでけっこうヘンなとこがあって」
「ああ、そうか。きみは、もうずいぶん前からお父さんと会う機会が何度もあったんだよね」
「はい」
「なるほど。うちの母もよく、ぼくは彼と似てるとか言ってたよ。会う前はどういうことか分からなかったけど、今ではなんとなく分かるような気がするね、それ」
「なんかやっぱり、当然なのかもしれないけど、ぼくたちそれぞれお父さんにどこか似てるとこがあるんですよね。ぼくは、まあ見た目がこうだし、メリル兄さんはお父さんから凄く才能もらってるみたいだし」
「きみだって、もらってるでしょう?」
「え〜、でも、ぼくはイラストですもん。油彩って遥かに遠い存在ですよ。ママからは才能もらってるかもしれないけど」
「イラストと油彩ってそんなに違うもの?
基本的には同じ絵なんだし、素材が違うだけで芸術的な本質からゆけばそれほど違うものだとは思えないけど。ま、ぼくのは素人考えにすぎないけどね」
「う〜ん、どうだろう。なんていうか、ぼくから見ると油彩って敷居が高いっていうのかな。そういう感じがすごくあって。特に、お父さんの絵は単に見たり飾ったりするためだけの絵じゃないでしょう?
キレイなだけじゃなくって...。ママにいろいろ教えてもらったんですけど、彼の作品ってどれもすっごく深い意味を持ってるじゃないですか。芸術的にっていうか、歴史的にっていうか」
「うん、それは分かるけど」
「イラストってそういうのあんまりないんですよね。どっちかっていうと見たり飾ったりするための絵っていうか、イラストにヘタに"芸術"持ち込むと重くなるってママが言ってたし」
「でもそれは、描く人がどういう目的で描くかによるんじゃない?
油彩でも、単に見たり飾ったりするためだけに描かれてた時代もあったし、現代でもお父さんのような画家は特殊と言えば特殊だと思うけどな。まあ、だからこそ彼は"デュアン・モルガーナ"なんだけれど」
そんな話をしている間に二人はメイン・ストリートから少しはずれて、レストランやバーが並ぶ一角にやって来ていた。夜は酔客でごった返す辺りだが、昼間はランチを出している店も多いとあって、大通りとそれほど大きく雰囲気は変わらない。
「あ、ここ、ここ」
角を曲がってしばらく行ったところでファーンが立ち止まって指差したのは、シャレたイタリアンのトラットリアだった。
「ここでいい?
昼はパスタとピッツァが凄く美味しいんだよ」
「シーフードのピッツァってあります?」
デュアンの問いにファーンはにっこりして、ありますと答えた。
「じゃ、ぼくそれがいいな」
ファーンは頷くと弟を伴って店に入って行った。ランチもピークを過ぎる時間だったので、店内はほどよくすいて来ている。
「おや、ファーンじゃないか。久しぶりだね」
「こんにちわ、親父さん」
でっぷりしたカンロクの体形に、きりっと前掛けをしめた店主らしい親父が満面笑みで出迎えてくれるのへ、ファーンも笑って挨拶している。
「友だちかい?」
「あ、いえ、弟です」
「へえ、弟がいたのか」
「ええ」
「お入り、お入り。奥の席が空いてるから」
「有難う」
二人が席に落ち着くと、ウエイトレスではなく店主自らがメニューを運んで来てくれた。ファーンに渡しながら言っている。
「こんな可愛い弟がいたんだな」
「ええ、デュアンというんですよ。デュアン、こちらはこのお店のオーナーでコノリーさん。でもみんな、アーノルドの親父さんって呼んでるよ」
「こんにちわ、はじめまして!」
さすがにデュアンはその場の空気を読むのが早い。すぐにここは単なるレストランではなく兄のテリトリーだと見て取って、元気よくそれ仕様の挨拶をした。そのはきはきした様子ににっこりしてアーノルドが言っている。
「おお、はじめまして。よく来てくれたな。腹いっぱい食ってってくれよ」
「はい」
「シーフードのピッツァが食べたいんですって」
「そうか。じゃ、たっぷりシーフードをサービスしとこう。それと、パスタにサラダでどうだ?」
「そうですね」
「ぼく、イカスミのパスタってまだ食べたことないんですけど、出来ます?」
「もちろんだとも」
「じゃ、ぼくもそれをお願いしようかな。サラダは海老と生ハムでどう?
ここのドレッシングが美味いんだよ」
「いいですね。どっちも好物です」
「よし、じゃ、ウデによりかけて作ってやるぞ。アーノルド・スペッシャルといこう。あ、それはそうとファーン、こないだはせっかく来てくれたのに、こき使って悪かったな」
「そんなことないですよ、ぼくも楽しかったですから」
「助かったよ。ランディにも宜しく言っといてくれ」
「ええ」
アーノルドが行ってしまうと、デュアンが尋ねた。
「こないだって?」
「ああ。この前、友だちとここに来た時に、ちょっとお手伝いしたんだよ。すごく忙しそうでさ。昼はふつう厨房、息子さんがやってるんだけど、身体の調子崩して急に来れなくなったらしくて、その上、ウエイトレスの人が一人お休みで」
「お手伝いって」
「だから、ウエイター」
「えーっ、兄さんが?」
「うん、面白かったよ。お役に立つんだったら、またやってみたい」
その答えに、やっぱり兄さんて意外性ある、とデュアンは改めて思っていた。なにしろ、大公爵家の令息である。それが気軽にウエイターとはちょっと驚かされる話だ。しかし、デュアンも最初から思っていたのだが、この兄は年のわりに貴族的で鷹揚なところがあるくせに、それでいてお高くとまっているような鼻持ちならないところが微塵もない。アーノルド親父の態度からして、彼もそういうファーンのことが気に入っているらしいのは一目瞭然だった。
「そういえばさっき、おじいさまとチェスしたって言ってたよね?」
「ええ」
「きみもチェスをやるんなら、ぜひ今度対戦しようよ。ぼくも好きなんだ」
「え〜、兄さんと?
なんかボロ負けして自信喪失させられそう」
「ってことは、けっこうきみは強いってことかな?」
「まあ、それなりには。...っていうか、ネット経由でよくいろんな人と対戦するんですけど、わりと勝率は高いんですよ。でも、兄さん相手じゃ、どうだか」
「ご謙遜だな。これは楽しみだ」
「お手柔らかに」
「そちらこそ」
二人は対戦前からもうお互いを好敵手と認めているようで、無言のうちに負けないぞ、という微笑を交わしている。
「あ、ね、兄さん」
「ん?」
「ロウエル卿とディナーって、もうすぐでしたよね?」
ファーンは言われて、今度はちょっと緊張した面持ちになった。そのディナーにデュアンも参加することは、父から話があった直後に弟から電話で聞いている。
「そうだね」
「ぼく、すっごく楽しみにしてるんです。ママなんかもう羨ましがっちゃって」
わくわくした様子で言うデュアンに、ファーンはいつもの彼らしくもなく戸惑った様子で答えた。
「度胸あるなぁ、きみは」
「え、なんで?」
「だってさ、ロウエル卿だよ?
ぼくなんか、お父さんから話聞いて以来、そのこと考えるたびに頭のヒューズ飛んじゃうっていうか、どうしたらいいんだってパニクっちゃうというか...」
兄の言うのに驚いたようで、デュアンが頓狂な声を上げた。
「兄さんがですかぁ?」
「ぼくだってパニクることくらいありますよ。そりゃ、いつかはって思ってたけど、そんなの何年、いや少なくとも十何年は先のことだと思ってたのに、いきなりだろ?
実際、きみが参加してくれるって聞いてほっとしたよ。ぼく一人で、お父さんとロウエル卿の相手だなんて、とてもじゃないけど荷が勝ちすぎるもの」
デュアンは相手が相手だけに、う〜ん、それは確かにあるかも、と考えている。
「考えてみるとなんだかね...。お父さんやおじいさまとのあの初の対面以来、まだたった4ヵ月しか経っていないのに、いろんなことが一気に動いちゃったなあっていうか、改めて考えると感慨すらあるよ。決定的にそれを感じたのは、お父さんからロウエル卿と会えるって話が舞い込んで来た時だったけど」
「ああ。ぼくも兄さんの気持ち、なんとなく分かります」
「メリル兄さんはあっさり逃げちゃったけど、きみとぼくは跡取りになったっていう点で同じ立場だものね」
「ええ」
「それは確かに、この先の進路が決まってすっきりしたって気はするし、すごく面白そうとも思うんだけど、同時になんか、重いよねえ」
「重いですね、確かに」
デュアンは兄の言い分に納得して、深く頷きながら言っている。母にも父の後を継ぐということは大変なことだと言われたことでもあり、本決まりになる前に比べてその責任を重く感じ始めているところだったからだ。
「いつかは会いたいなって憧れてるだけだった時はずっと遠い世界だったのに、なんか、ふと気がついたら知らない間に壁を越えちゃってその世界に入り込んでたっていうか。まあ、ロウエル卿に取ってはぼくたちって"親友の息子"ってことなんだろうけど、そうやってお会い出来ることそのものがもうぼくたちが彼と同じ世界にいるってことなんだしね」
「でも、兄さんは今までだってそうだったじゃないですか。ぼくなんて、正真正銘"異世界"ですよ?」
「それはそうかもしれないけど...」
「それともぼくの場合、あまりにも"異世界"すぎるからパニクるほどワケが分かってないのかもしれないですね。もし兄さんがホントにパニクっちゃうとしたら、ぼくなんかよりずっとロウエル卿のことをよく知ってるからじゃないかな。そうするとぼくのは恐いもの知らずってやつなんだろうし、だから、当たってくだけろっていうか」
弟の言うのにファーンが笑って言っている。
「今、思ったんだけどさ」
「はい?」
「やっぱりお父さんの跡取りはきみに決まって正解だと思うよ。おじいさまもおっしゃってたけど、きみのその度胸なら何があっても大丈夫、って気がする」
「え?
そうかなあ」
「うん。じゃ、ぼくもきみを見習って、当たってくだけろ精神でゆくかな」
可愛い顔してこのコはもしかしたらぼくより強いかも、と思いながらファーンは言った。何にしても、彼にとっては全く頼もしい弟である。
そんなこんな話している間に、アーノルド親父がウエイトレスに手伝わせて二人の食事を運んで来てくれた。言っていた通り、パスタもサラダもピッツァも、食べきれないくらい大盛りてんこもりの大スペシャルである。
「わあ、美味しそうっ!」
デュアンの屈託のない感嘆に、親父はすっかり御機嫌だ。
「ウマいぞぉ。デザートも用意してあるから、頑張って食ってくれよ」
「分かりました、気合い入れて食べます」
それを聞いてファーンと親父は顔を見合わせて笑っている。
さすがに育ちざかりの男の子二人のことで、一旦テーブルに料理が並べられるとたちまちのうちに平らげてゆく。特にデュアンは、背はそこそこあるがどちらかといえば華奢なくせに、その食いっぷりは天晴れなものだ。アーノルドはしばらくそれを楽しそうに眺めていたが、厨房から呼ばれて席を離れて行った。
「おいし〜い♪
これ、ディリバリーのやつとチーズが段違い!」
「だろ?
ここの親父さんはイタリア系でさ。若い頃は本場の味ってやつを研究しに向こうも随分歩いたらしいから。夜に出すもっと手の込んだイタリア料理もなかなかのものなんだよ」
「へえ、そうなんだ。今度は是非、そちらも食べてみたいな」
「さすがに夜はね、ぼくだけじゃ連れてきてあげられないから、じゃ、そのうち、叔父にでも頼んで一緒に来てもらおう。叔父もきみに会いたがってたから、喜んで来てくれると思うよ」
「そうなんですか?」
「うん。あ、それで思い出したけど、ひとつ相談があったんだ」
「はい?」
「実はうちの母もきみに会いたがってるんだよ」
「え?
兄さんの?」
「きみがお父さんの子供の頃そっくりらしいって言ったら、会ってみたいって」
「えーっ、なんか緊張しますね」
「もともと、ぼくの兄弟に興味は持ってたみたいで、メリル兄さんにも会いたいって言ってるけど、ぼくもまだちょっとそういう話を持っていけるほどには親しくなれていないし、なにしろ彼はああだろう?自分のお母さん以外で、お父さんが昔つきあってた女性ってことになるとどういう反応が来るかが」
「ああ...」
「それを考えるときみのお母さんも良い気はされないかもしれないんで、一度尋ねてみてくれてからでいいんだけど、どう?」
「そうですね...。ぼくは兄さんのお母さんなら会ってみたいけど、でも確かにママが...」
「ついでに言っておくとさ、ぼくの母はきみのママのファンなんだよ」
「え、本当?」
「うん。もう随分前からそうで、ショップもよく覗くみたい。油彩も何枚か持ってるよ」
「それはすごいかも。ママ、最近ではイラストとテキスタイルで手一杯で、殆ど油はやってないから」
「らしいね。うちの母も、それはもうかなり昔に買ったものだって言ってた。だからさ、そのへんもアピールしてみてよ」
「分かりました。大丈夫だと思いますけどね。自慢じゃないけどぼく、ママをまるめこむことについては自信あるので。それに、長年のファンでショップのお得意さまときちゃ、ママだって考えると思いますよ。お客さまは大事にしなきゃって、いつも言ってますから」
それからしばらく二人は食べるのに忙しかったが、皿の上のものが殆ど片付くと、デュアンが大満足でほっと一息ついてから言った。
「でも、兄さん、よくこんな店知ってますよね。穴場的じゃないですか?
こういうとこって」
「まあね。ぼくも知人に連れてきてもらったんだけど、そういうのよく知ってる人がいるんだよ」
「へえ。グルメですね」
「っていうのかなあ...。この界隈には確かに詳しいけど」
ファーンをここに初めて連れて来てくれたのは、従兄のウィルの友人であるランドルフ・シンプソンだった。なんでも、彼が一番グレていた頃にこの近所でタチの悪い酔っ払いと乱闘になってしまい、この店の裏手でノビていたことがあったのだそうだ。店の終いがけに裏に出てきたウエイトレスがそれを見つけてアーノルドを呼んだのだが、彼もたまにあるような酔客どうしのケンカ騒ぎなら警察と救急に連絡して終わりにする。しかし、ハデに怪我してのびているのは見ればまだほんの少年だ。それで警察だのなんだのと騒ぎになれば、この子が困ったことになるのじゃないかと心配して、閉店した店の片隅に運び込んで手当てしてくれたのである。
見かけはハデだが幸い深い傷はなく、呼ばれて来た近所の医者の見立てでは大事ないだろうということだったし、それにその医者が店の常連だったこともあって、親父の口利きでコトは内密に処理されたのだ。しかし、この時の経験はランドルフにとってけっこう考えさせられるものだったようで、親父には恩義を感じているようなことを言っていたのをファーンは覚えている。
ファーンがちょっとそんなことを思い出していると、二人がどうやら食べ終わったらしいのに気づいて、アーノルドがにこにこしながらテーブルに寄って来た。すっかり空になった皿を見て感心しながら言っている。
「おお、みごとなもんだ」
「ごちそうさまでした。すっごく美味しかったです!」
デュアンが言うと、アーノルドは嬉しそうな様子で答えた。
「これだけ見事に平らげてくれると料理人冥利につきるよ。しかし、どうだ?
デザートは入りそうにないだろう?」
ちょっと意地悪そうにからかう親父にデュアンは、とんでもない、まだまだいけます、と切り返した。
「よおし、それでこそ男の子だ。ジェラートは好きか?」
「大好物♪」
「ファーンも好きだったな」
「ええ」
「じゃ、シメは特大パフェといこうか。バッファローズのなんかメじゃないやつを作ってきてやるぞ」
「期待してます!」
親父はすっかりデュアンを気に入った様子だし、デュアンはデュアンでもう十年も前から知っているかのように振舞っていて何の違和感もない。ファーンはそれを見ながら、う〜ん、これはこのコの特技だなと改めて感心していた。彼との初対面の時も、こんなふうにデュアンはくったくなく飛び込んで来てくれたものだ。
それから調子に乗った親父が、手づからメニューにはない特大パフェを二つ作って運んでくると二人の前に置いた。デュアンは歓声を上げてパフェに取り掛かっている。その様子を見ていてファーンは連れて来て良かったなと思いながら、同時にこんな可愛い弟が出来たことの喜びを改めて実感していた。
original
text : 2009.8.7.+8.9.


|
