|
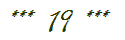
跡取りのことについて話合ったあと、万が一にも息子が気を変える可能性も考えてマイラはしばらくディに返事するのを遅らせていたのだが、二週間も経つとメリルの方はそんな話があったことすらすっかり忘れた様子でいつもの日常を機嫌よく送っている。それを見届けて、彼女は最終的な解答を伝えるためにディに電話した。彼はちょうど家にいて、執事が取り次いでくれると受話器から、やあ、マイラ、といういつもの魅力的な声が聞こえてきた。
「今ちょっといいかしら?」
「かまわないよ、何?」
「この前のお話ね。跡取りのこと」
「ああ、うん」
「メリルと話してみたんだけど、あの子の結論は"ぼくは、もうお父さんとは会わない方がいい"なんだそうよ」
― え?
「だから、メリルが言ったの。"ぼくは、もうお父さんとは会わない方がいいかも"って」
― ちょっ...。ちょっと待ってよ、マイラ。それってどういうこと?
「だから言ってる通りだと思うわよ?
メリルはあなたに何とも思われてないようだからって、あなたとは関係ない世界で生きてゆくことにしたみたい」
電話口の向こうで珍しく絶句状態のディを想像して、マイラは少し楽しそうだ。
― だから、ちょっと待って、マイラ。なんで跡継ぎになって下さいってお願いしているのに、そういう答えが返ってくるわけ?
「さあ?
だって、あの子がそう言うんだから」
― つまりそれは、お断りされているってこと?
「まあ、そういうことになるわね」
ディは内心、やっぱりかいと思ったが、口に出しては、酷いなあ、と言った。
― 第一、ぼくに何とも思われてないって、なんでそういう話になるの?
ぼく、あの子に何か誤解されるようなこと言ったのかな?
「誤解っていうか...。私もあの子に言われてなるほどと思ったんだけど、これまであなたは自分に子供がいるなんてこと、少しも気にしたことすらなかっでしょう?
あの子が言うには、お父さんにとっては負担になるとかならないとか以前に、そもそもが居ても居なくてもどうでもいい存在だったんじゃないかって」
― いくらなんでも、それこそ誤解だよ。そりゃ確かに、生まれてから十何年も放りっぱなしにしてたのは事実だから言い訳できる立場じゃないだろうけど、でも...。
反論しようとしてディはふと、メリルがどうしてそんな事を言い出したのか分からないでもない気がして来た。確かに自分は、メリルのみならず子供たちのことを"居るとも思っていなかった"かもしれない。実際、肯定的なものであれ、否定的なものであれ、子供に対する世の一般的な父親のような感情はこれまでまるっきり持ったことがなかったのは確かだ。だからこそ"会ってみたい"という気持ちもなかったし、逆に"疎ましい"という気にもならなかったのだろう。
「思い当たるフシがあるでしょう?」
マイラに意地悪く言われても、ディはしばらく言い返せなかった。彼自身が気づいていなかったことを敏感に感じ取って鋭く指摘するあたり、メリルという子はなかなか侮りがたい少年だと改めて感心していたからである。だからと言ってもちろん、ファーンやデュアンが鋭くないというわけではない。デュアンはそもそも、ディが何を考えてこれまで自分たちを母親任せにしていたのかなんてどうでもいいくらい彼に心酔しまくっているし、ファーンはファーンでそういうことに気づいていてもそれを苦にするタイプではない。事実はおそらく、これまでファーンの方でこそ"父"という存在にそれほど執着してはいなかったのだろう。しかし、メリルは元々十数年間も音沙汰ひとつなかった父親に対して反感を持っていたから、そのせいでディが自分をどう思っているのかについて深く考える必要があったのだ。
「あの子、言ってたわ。本当ならあんなふうに機嫌よく"おもてなし"してくれるような人だとは思えないし、本当に自分たちに関わってくれるつもりなら、もっとちゃんと接してくれるんじゃないかと思うって。それを聞いて私、思ったの。もちろん、あなたが薄情だったり冷たかったりして子供たちのことを気にしていなかったわけじゃなく、これまであなたには"子供"というものが意識の外にしか存在してなかったんじゃないかしら。だからこそ、あなたにとってメリルは"お客さま"だったのよ。違う?」
ディはすぐには答えなかったが、しばらくして降参したらしく、違わないかもしれない、と言った。マイラはそれに微笑している。
― でも、だから、ぼくは元から父親失格だって思ってるんじゃない。そういう、普通に親が持つ感覚ってぼくにはよく分からないから。
「はいはい」
― それにさ、これでも今はちょっと父親らしい気分にはなってきてるんだよ?
ぼくとしては"親"を始めたばっかりみたいなものなんだし、初心者なんだからそのへんはいくらか大目に見てくれなくちゃ。
「私は分かってるつもりよ、そうなんだろうなってことは。それに、それについては私にも責任はあると思ってるの。今まであの子を独り占めして、あなたに少しも"父親"をやらせてあげようとしなかったのは私なんだもの」
― だろ?
「ええ」
― だったら、ちょっとはきみも協力してメリルを説得するとかしてくれればいいのに。
「跡取りのこと?」
―
そう。
「ねえ、ディ。メリルはあなたの息子なのよ?」
― 分かってますよ?
「だったら分かるでしょ?
私が説得したくらいで考えが変わる子だと思う?」
―
それって、ぼくのせいなんですかぁ?
ディは心外という様子で素っ頓狂な声を上げたが、マイラにはそれが彼らしい冗談と分かっているので笑っている。
「そうとばかりも言えないでしょうけど、あなただって私のことよく知ってるじゃない。たぶん、あなたと私、両方のせいよ。それにね、私のちっぽけな会社ですらメリルに継がせるなんてこととっくに諦めているし、ましてやあの子はモルガーナ家の当主が務まるような器じゃないの。それは本人が一番よく知ってるわ」
― そんなことないよ。なかなか鋭そうだし、しっかりしてるし。あの子なら十分務まると思うけど?
なにしろ、ぼくでも出来るようなことなんだから。
「"ぼくでも"って、本気で言ってるの?
私やメリルにだってそれがどんなに大変なことかくらい分かるつもりよ?
でも、メリルはあなたのように画家としてあれだけの仕事をしながら、伯爵さまとしてもやってゆけるような器用な子じゃないのよ。これは半分だけあなたの血を引いたんだと思うけど、画家になれようがなれるまいが、あの子は一生絵を描いてるわ。それほど、絵を描くことに取り憑かれてるような子なの。だから、あの子にはかまわずに、このまま好きな絵だけ描かせておいてやって頂戴」
母の立場からこうまで言われては、さすがにディもそれ以上押せなくなった。これは本当に諦める以外にないかなと思いながら、彼は今度はさっきまでと違ってずいぶん真面目な声でマイラに言った。
― ね、マイラ
「何?」
― もう、いくつか小さな賞なら取ってるって言ってたけど、どうなのかな?
きみは、メリルが画家になれる素質があると思ってるの?
それへマイラはきっぱりと答えた。
「そうね、今はかなり思ってるわ」
― そう。
「あなたに見てもらえば一番確実なんでしょうけど、少なくともグレアム・マーフィーとコレット・アーヴィングが気に入ってくれてるの。これは、メリルにはまだ言っていないけど」
クランドルで最も信頼度が高いとされる画廊のオーナーと、著名な評論家の名前を聞いて、ディはなるほどと頷いている。二人とも彼自身親しくしていて、その鑑賞眼を認めている人物でもある。
― 分かったよ。じゃ、メリルのことは残念だけど諦めるしかないね。ただ、伝えておいて欲しいんだけど...
「メリルに?」
― うん。確かにぼくは優秀な父親じゃなかったし、これからもそうはなれそうにないけど、でも、ぼくはぼくなりにメリルのことを思ってるつもりだって。それだけでいいから。
「分かったわ。伝えておきます」
― じゃあ...。ああ、そうだ。きみもメリルも、ぼくで何か力になれることがあったらいつでも言っておいで。待ってるから。
「有難う」
― じゃあね。
言って、ディは複雑な表情で受話器を置いた。
出版社のオーナーとして、今のマイラが特に文化人に太い人脈を持っていることはよく知っている。それで彼女も息子の才能についていろいろ専門家の意見を聞いてみていたようだが、ディにも納得できる連中がメリルの才能を認めているとすると、確かにあの子には絵だけ描かせてやっておく方がいいかもしれないと思えた。しかし、それを言えばデュアンだって条件は同じだ。メリルから断られた今となってはどちらかの跡継ぎの役をどうしても引き受けてもらわなければならないが、油彩とイラストの違いこそあれ、こちらはこちらで既に雑誌の編集者が目をつけているとカトリーヌから聞いている。
どちらも才能があるらしいのは親として嬉しいし、それは確かに自分の血筋というものなのかもしれないが、今の場合はちょっと困ってしまうのだ。できればどちらにも好きな道を伸び伸びと歩ませてやりたいと思うのも親心というものなのかなあと思いつつ、しかし現実はシビアでどちらかに重荷を背負わせなければならない。全く貴族になんか生まれるものじゃないとディは深い溜め息をついてソファに沈み込み、煙草に火をつけて、さて、どうしたものかと考え込んでいた。
マイラにメリルのことを打診した時にアンナにも連絡をつけて事情を話し、ファーンにはシャンタン家を継いでもらいたいと思っているのだがとは言ってあった。それについてはしばらくしてアンナから返事が返って来ていて、ファーンに話してみたら彼には異存はないようだということだ。それはロベールにも既に伝えてあったし、今度、彼がクランドルに来たら正式な申し込みも兼ねてクロフォード家に挨拶にゆくということにもなっている。
しかし、長男のメリルがモルガーナ家を継ぐことをはっきり断って来た限り、デュアンに話を持ってゆく前にもう一度、ファーンにどちらの家を継ぎたいか改めて聞いてみておく必要があるかもしれないなとディは思っていた。なぜなら、シャンタン家を継ぐということになると将来的にクランドルから出ることになるからだ。海峡ひとつ隔てただけの隣国のようなものではあるし、行き来するのにそれほど時間はかからないとはいえ、そのあたりは後で問題が出ないように十分調整しておく必要はある。しかし、言葉の面でも既にファーンは不自由がなく、これまでも母や他の家族とヨーロッパに何度も出かけていて文化的にも馴染みがあるようだ。それにあちらの社交界にももう見知った顔が少なくないこともあって、そちらは難なく話がまとまりかけていたのである。ロベールの言っていたように家風という点でも、どちらかといえば事業の家という色彩が濃いシャンタン家の方が、クロフォード家で育ったファーンには切り回しやすいだろうということもあった。
ともかくその辺りをもう一度アンナやファーンと相談し、その意向を聞いてから今度はデュアンとカトリーヌに話すのが順序というものだろうなと結論して、ディは受話器に手を伸ばした。デュアンの方にも希望があれば、それはそれでまた双方と相談だ。電話をかけながら、跡取りがどうのこうのなんて全く面倒な話だよなと思って、また彼は溜め息をついていた。
original
text : 2008.9.17.+9.21.+9.22.+2009.1.23.
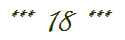

|
