|
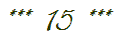
「え、本当?」
「うん。3日ほど前に、マーティアが来てそう言ってたんだ。きみにも迷惑かけたからって」
次に学校に行ってエヴァと顔を合わせた時、アレクからの伝言とアークで船旅という豪勢なご招待の話をすると、彼女は目を丸くして驚いていた。
「すごい!アーク号って私、雑誌やテレビのニュースで何回も見たことあるわ。とってもキレイな船だよね」
「そうだよ。大きなプールやシアターもあるし、船室やダイニングも凝ってて、船上パーティとかのためにボール・ルームまであるんだから。船とは思えないくらい大きくて広いから快適だしね。普通の客船とは違ってアレクさんの個人的な持ち船だから、こんなふうに招待される以外では中まではなかなか見れないんだ。それに、この前乗せてもらった時なんか、他に全然お客さんいなくてさ。貸切状態でリッチ〜って感じだったんだから」
「いいなあ」
「太平洋上にはいくつかIGDが所有している島があるらしいんだけど、この前連れてってもらったのはそのうちの一つだったんだって。元々は無人島だったのをアークが停泊できるように改良して、その広い島にマーティアたちの別邸があるだけなんだよ。別邸って言うよか、殆どホテルみたいな大邸宅だけど」
「すてき〜」
「で、行く?」
「もちろん!
あ、でも、先にパパやママに一応は聞かなくちゃ。でも、大丈夫だと思うわ」
「じゃあ、言っておくね。春休みが近づいたら打ち合わせするって」
「うん!
楽しみにしてる」
「それまでに、アレクさんに何をおねだりするかも考えておくといいよ」
言われてエヴァはちょっと複雑な顔をした。
「どうしたの?」
「え?
あのね、なんか世界が違うなあって。アレクさんって、アレク・ロウエル卿なんだよね。そんな人、今までは一生縁もゆかりもあるわけないって感じだったのに、この前はお話しちゃったし、一階まで降りるのに抱いてってもらったりまでしたのよね、私。なんか思い出すと夢みたいって感じで、帰って来てからも素敵な人だったなあとか思ってたの」
誘拐されたことについてはそれはそれなりに怖かっただろうし、ショックでもあったのだろうが、デュアンが一緒にいたこともあって、どうやらエヴァにはこれはトラウマティックというより、どちらかというとエキサイティングな経験であったらしい。それはデュアンも同じだったようで、そうすると二人が回りの心配をヨソに、素早く立ち直ったのも頷ける。連れ去られてからすぐに閉じ込められて、犯人たちとは殆ど直接接触していないことも幸いしたのだろう。しかし、テレビや映画で誘拐だの銃撃戦を見慣れている今どきのお子さまとはいえ、実際にそんな目に合ってなおこういう風に受け取れるということは、どちらもなかなかオオモノということの現れであるのかもしれない。
「それはぼくもずっと思ってるよ。やっばりお父さんの親友だけのことはあるなあって」
「それに、アレクさんだけじゃなくてデュアンのお父さまだって以前の私には別世界の人だよ?
だから、余計思うんだけど、デュアンも別世界の人になっちゃったのかなぁって」
「なんで?」
「だって、次のモルガーナ伯爵じゃない」
それを聞いてデュアンはちょっと困ったような顔をした。これまでは「友達であることに変わりはない」と確信を持って言っていれば良かったのだが、自分と友達であるということが、ああいう危険を呼び込んでしまうことでもあると思うと、もう手放しではそう言い放てないような気もしたのだ。しかし、デュアンの中では、どんなに立場が変わっても友達でいて欲しいという気持ちは変わらない。
「確かに立場は変わったかもしれないけど、ぼく自身は前と何にも変わってないよ。そりゃ、お父さんの後を継ぐってことについてはこれでけっこう重く受け止めてるつもりだけど、それで別世界の人になったとか、そんなのちっとも思ってないし、エヴァも他のみんなもぼくには大事な友達だってことは変わらないよ。前にも言っただろ?」
「うん...」
それでも、今回のこのスーパースペシャルなご招待や、どんなに大きなユメの扉でも開けてしまうことが出来そうなロウエル卿への「おねだり」のことを考えると、それがデュアンのその立場の変化が齎したものであることはエヴァにも明らかだった。今は偶然とはいえ自分が関わってしまったから、みんな気を使って大事に扱ってくれるけれど、根本的に既に住む世界が違う以上、いつまでデュアンとこんなふうに親しく友達でいられるのかなと思うと、彼に密かに恋する少女としては複雑な気分になるのは無理もなかった。彼女の両親も市内やその周辺にいくつも店を持っているから十分に裕福な暮らしではあったが、モルガーナ伯爵家ともなれば本質が違う。それでエヴァには「身分違い」などという言葉もチラつくし、しかも、デュアンとあの美しい「お父さま」は、どう考えたってタダならない関係としか思えない。そんなこんなで、彼女としては告白しようにも出来ない状態にあったのも事実だ。
しかし、エヴァがそんなふうに自分に友達以上の気持ちを持っているなどとは、ディに夢中で自分の恋しか眼中にないデュアンは迂闊にもまるっきり気づいてさえいなかった。それで、例の寄宿学校の件にしても、そんなことまでは考えず、ただ、これからもみんなに迷惑をかける可能性があるのなら、早いうちに転校した方がいいかもしれないという結論に傾きつつあったのだ。ディとも話合い、今までの友達に迷惑をかけずに済むことと、将来的に関わることになるだろう階層の子供たちとも親しくなっておくことはプラスになるだろうということから、しばらく考えてデュアンは春休みが済んだら寄宿学校に変わると決めた。ディと離れるのは何より辛かったが、幸い彼の行っていた学校は屋敷からそう遠くないので、週末ごとに帰って来ることが出来る。
そう決めた限りは、やはり何よりもエヴァに誘拐騒ぎに巻き込んでしまったことを改めて謝り、今後の対策として転校することに決めたことを伝えるべきだろうと思ったデュアンは、春休みの旅行日程の相談もあったので彼女に電話をかけてみた。最初ベンソン夫人が電話に出て、デュアンと分かるとエヴァの部屋に回線を回してくれた。
「エヴァ?」
―
あれ? デュアン?
「うん。今、いい?」
―
いいわよ。なに?
「あのね、春休みの話なんだけど、ご両親は許可してくれた?」
―
もちろんよ。でも、私、ダメと言われても行くつもりだったもの。
きっぱり言うエヴァのワガママ娘ぶりに微笑してデュアンは続けた。
「それなら、アークがこっちに回る都合があるから、だいたい3月15日くらいの出発でいいかな」
クランドルの現在の学校制度では、3月の中旬から4月いっぱいが春休みということになる。学ぶ時は学び、遊ぶ時は遊べという気風が強いこの国では、寒さから開放されて一年で一番良い季節になるこの時期は、勉強なんかしているより遊ぶべし、ということでそんな風に決まっているんだと、ウソか本当かは分からないが以前誰かが言っていたことがある。
―
私の方はいつだって準備OKよ。ママにねだって新しいドレスとクツも作ってもらうことにしてもうオーダーしたし、何を持っていくかも決めたんだから。あ、新しい旅行鞄も買ってくれるって。なにしろ、こんなこと一生に一回かもしれないんですからね。ママだって一緒に行きたいくらいって盛り上がってるわ。
エヴァのいれこみぶりがデュアンにはちょっと可笑しかったが、じゃ、そういうことでマーティアに連絡しておくよ、と言ってから、ちょっと改まった口調になった。
「それからね、エヴァ」
― なあに?
「この前は、怖い思いさせて本当にごめんね」
― なんだ、そんなことまだ気にしてるの?
私は全然気にしてないわよ?
ましてや、あんなことがなかったら、今度の旅行だってないんだもの。私としてはもう、おつりが来るって感じだわ。
ポジティヴ・シンキングだなあとデュアンは思ったが、美少女だし、見た目あまえたの一人っ子のくせに、エヴァは実際のところリーダー肌でしっかりしたお姉さんタイプだ。それもあってデュアンのような男の子の友達が多いし、仲間うちやら上級生やらで密かにエヴァっていいよねと言っている連中がいるのもデュアンはよく知っていた。
「それで、またあんなことがあって、きみや他のみんなを巻き込むようなことになっちゃいけないと思って、ぼく、転校することにしたんだ」
エヴァは言われたことの重大さに、一瞬アタマが理解を拒否したのだろう。一旦絶句した後で、次になんですってぇ?!と大声を上げた。
「うん、だから...」
― 転校?!
なに考えてるのよ、デュアン。冗談じゃないわ。
「だって」
― だってもさってもないわよ。バカなこと考えるのやめて!
「バカなことって、ぼくこそ冗談ごとじゃないんだよ。きみはそんなふうに言ってくれるけど、それは無事だったから言えることで、次もこうとは限らないんだから」
― 次があるとだって限らないじゃないの。
「あったら困るからそう決めたんじゃないか。ぼくだって、エヴァやみんなと離れたくなんかないよ。でも、ぼくのせいでまた誰かをあんなめに合わせるかもしれないなんて、ぼくには我慢できないんだ。だから、お父さんとも話し合って、寄宿学校に行くことにしたんだよ」
― でも...。
デュアンが「お父さんとも話し合って」と言ったために、エヴァはそれがお父さまの意向なのかなと一瞬考えて言い返しそこなった。以前も寄宿学校の話は出ていたのだが、結局デュアンが今のままと決めたらしいので、エヴァとしてはひと安心したのもそう遠い昔の話ではない。貴族の家柄ともなると普通は名門の寄宿学校に行くものというのが、クランドルでも一般的な感覚だったからだ。
「とにかく、あんなことにも巻き込んでしまったし、誰よりきみにだけはちゃんと謝って伝えておきたかったんだ。これまでみたいに毎日学校で顔を合わせるってことはなくなるけど、でも、寄宿学校に行くからと言って会えなくなるわけでもないし、もしきみがイヤじゃなければ、これからも友達でいてくれると嬉しいけど」
― それはもちろんよ。でも、デュアン...。
これからも友達でいて、と今は言っていても、学校が変わってしまい、環境もどんどんモルガーナ家の後継者に相応しいものになって行ってしまえば、デュアンだってそうそう前の学校の友達を気にかけることもなくなってゆくだろう。去るものが日々に疎いということを理解できないほど、エヴァももう子供ではなかった。だからデュアンのこの結論は、ただでさえ困難な彼女の恋の決定的な終わりを宣告されたも同じで、大が千個くらいつくほどのショックだったのだ。通話が終わってもエヴァは受話器を置くのも忘れて、しばらく呆然としていた。
original text : 2008.4.8.


|
![]()