|

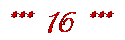
リムジン二台を連ねて四人はロングアイランドの屋敷を後にしてマンハッタンに向かっている。路面を重々しく巻きこんで進んでゆく車の中で綾は居心地の悪そうな顔をしてドレスのすそを気にしていた。ウォルターはそれを微笑して眺めていたが、彼女がふいに彼を見て言った。
「ねえ、ほんと、おかしくない?」
「きれいだよ」
「・・・まやさんの選んでくれたのだったら安心してられるんだけど」
「とってもよく似合ってる」
「ほんと?」
「うん」
「・・・よし、じゃあ信じよう。ドリーもセンスいいしな」
「ぼくの方こそ凄く心配してるんだ。こんなのめったに着ないから」
彼が不安そうに言ったので綾はにっこりした。ダンがめがねを取り上げているし、もともと長身に煌くブロンドときているから、ウォルターの方こそ王子さまと言っても通る。
「とってもよく似合ってるから心配しないで」
「ほんとに?」
「うん」
「きみが言うんだったら信じようかな」
「ダンも言ったろ、お姫さまと王子さま、って」
「言ってたね」
「この際信じてそれで行こうよ」
「・・・お姫さまはともかく」
「めがね取られたの忘れたの」
「あ、そうだっけ・・・・」
「もう逃げようがないんだからさ。なりきって行くしかないと思う」
「・・・不安だなあ。歌うたうだけじゃだめなんだものな、この世界って」
ウォルターがしかめっつらでマジに言うので、綾は笑って彼にもたれかかると、愛してるよ、と言った。
*****
リムジンがザ・プラザのエントランスに滑りこんで来た。ドア・マンがドアを開いてくれ、ショーファーも降りて来てその横で迎えてくれる。二人は車を降り、ウォルターのエスコートで綾はロビーに入って行った。総支配人以下、主だったマネージメントのメンバーが出迎えてくれるのへ、綾は微笑して美しいクイーンズで答えている。ウォルターはそれに驚きながらフロア中の視線が綾に集まっているのに気がついた。
彼女が誰か知らなくても思わず振り返って見入ってしまうほど綾は美しい。
けれどもボール・ルームに入って行って見回した時のウォルターの驚きはさっきの比ではなかった。綾たちが入って行くと出席者たちのお喋りの喧騒はふいに低くなったが、その人たちを眺め渡してウォルターはびっくりしたのである。内輪みたいなもんだしさあ、ダンちみたいにうるさがたの集まってるわけじゃなし、と綾は言っていた。
これを内輪と言う神経が信じられない。ウォルターにしてみれば錚々たると言ったって言い過ぎではない顔ぶれだ。どの顔もTVや新聞、雑誌や音楽関係の専門書で目にしたことのある人たちばかりなので、見渡す限り即座に名前が浮かんで来る。大体マイペースでものごとにあまり動じないウォルターも、それを見て今夜ばかりはどうしていいか分からなくなって来た。
「綾・・・」
「え」
「どうして言ってくれなかったの。来る人みんなこんな人たちだったなんて・・・」
「だって・・・。RMC(うち)の新人のおひろめやるから気に入ったら来てってテープ送ってさ。誰が来てくれるかぼくだって出席の返事確かめたわけじゃないし・・・」
「そんな無責任な・・・」
「どうして無責任なの」
「だって。・・・だって、もし誰も来てくれなかったらどうするつもりだったの」
「来てるじゃない」
ウォルターは、それはそうなんだけどと思いながら、言い返しそこなった。
「それにしても盛会だなあ。良かった」
綾があまりにもあっけらかんとしているので、かえってウォルターの方は足が地につかなくなって来た。もうだいぶ馴れたと思っていたのだが、要するにこれが綾の"内輪"なのだ。彼女が日常としている世界、おそらくその中でも綾は超一級のセレブリティだろう。この落ち着きはとても真似できない、どうしよう、と思っているところへ、あとから着いたダンとドリーが二人を見つけてやって来た。
「へえ、けっこうすごい顔ぶれだな、姫」
「うん、ぼくもびっくりしてる」
「ダン・・・」
「なんだ、ウォルター。どうした、顔色が悪いぞ」
「・・・帰り・・・たい」
それを聞いてダンは絶句したが、綾はウォルターを見て小声だけれども今度こそ鋭い調子で言った。
「もう逃げようがないってさっき言っただろ。聞こえてなかったのか」
「聞こえてたけど、・・・でも」
「ここに来てる連中がどうして来てるかわかってるの」
「・・・どうしてって」
「みんなウォルターの曲が気に入ったからに決まってんだろ。いくら連中がぼくの顔見知りだって、あいつら才能のない奴にかまけてるひまなんかないんだぞ。しっかりしろよ」
「そーそ、姫の言う通り」
「ダン」
「おまえな、一度だっておれのこと恐いと思ったことあるか」
「えー、でも、ダンは昔っから知ってるし」
「連中だって中身は似たよーなもんだって。心配するな」
ダンはウォルターにウィンクして見せた。その横で、ドリーは微笑を浮かべて頷いている。
家族みたいな二人と、それに綾がいてくれると思うとウォルターは少しずつ落ち着いて来た。そうこうしている所へ声をかけて来たのは一昨年ピューリツァー賞を受賞したばかりのピート・アーヴィングである。
「やっと主役のお出ましだな。しかし驚いたよ、きみがお父さん以外のエスコートで来るなんてね。あ、紹介しておこう、妻のエリザベスだ。リズ、彼女が加納綾、私のお気に入りのお姫さまだよ」
ジャーナリストとして、またノンフィクション・ライターとしても著名だが、大の音楽ファンでその方面の評論家としても知られている。人の好いおじさんといった感じの丸顔の彼は、昨年結婚したばかりの二十才も離れた二度目の妻を伴っていた。
「はじめまして。ピートからよくお話は伺っていますわ」
エリザベス夫人は優しそうな微笑を浮かべて綾を見た。ブルネットの巻毛に濃いブルーのドレスが瞳の色と引き立てあっていて、とても美しい女性だ。綾の記憶によると彼女は綾より十才近く上なはずである。
「はじめまして」
その声を聞いてウォルターは、え?、と綾の方をまじまじと見てしまった。ついさっき彼に喋っていた時と同一人物とはまるで思えない声だったのだ。そう思って見ていると、表情、仕草、声、なにもかも普段の綾と微妙にすりかわっていた。内輪の、と言っても立派に一流どころを集めたパーティーなのである。
― ちゃんとできるんだ、綾って。
そう言えばさっきフロアを歩いていた時だって、ずいぶん歩きづらいはずのドレスのすそを優雅に揺らしていた。言葉も流麗なクイーンズに終始して、いつもの達者なスラングなんかおくびにも出していない。けれどもだからと言って化けきっているというわざとらしさがあるわけでもなく、あくまで綾は綾なのだが、フォーマルなのである。言葉の調子もピートとは仲が良いのかいつもの綾らしく威勢がいいし、崩した英語も使ったりするのに、いつもみたいに崩しきっていない。ダンと初めて会った頃に較べればずいぶん修行が足りて来ていて、お嬢さまぶる必要もなくなっていたのだ。
「来期のルネッサンス会議ではきみが議長席に座ると聞いたよ。すごいじゃないか」
「単なる修三さんの代理だよ」
「それが大したものなのさ。それはそうと、じゃあ彼がダンの秘蔵っ子ってわけだね」
ピートが親しみやすい笑顔を浮かべてウォルターを見た。
「そう。ウォルターだよ。ウォルター、こちらピート・アーヴィング。知ってるだろ、名前ぐらい」
綾が紹介すると、彼は微笑み返してピートに言った。
「あ、ええ、もちろん。・・・はじめまして」
「はじめまして」
ウォルターと握手を交わしたあとでピートが意味のありそうな顔をして言った。
「ウォルター・ウルフ、変わった名前だが本名かい」
「ええ」
「そう。いい名前だ。インパクトがある」
言われてウォルターはどう答えたらいいのか分からず、微笑だけ返した。
「ダンが見こむだけのことはあるね。なかなか良かったよ。妻と聞き入ってしまった。今夜も聞かせてもらえると思ってね、楽しみにしていたんだよ」
「ありがとうございます」
「で、綾とはいったいどういう関係・・・」
「ピート」
綾が割って入った。
「フェイントかけて何か引き出そうとしたって無駄だよ」
「ほお、何かあるわけだ」
「何にもないよっ。ただ、うちの未来のドル箱にキズつけてもらいたくないからね」
ピートはどうしたものかという様子でエリザベスを見たが、彼女が微笑して首を小さく横に振って見せるので、頷いてウォルターに視線を戻した。その顔はさっきと同じように人好きのする笑顔だった。
「あまえたのお姫さまがやっとお父さん離れして、いや、めでたい、と思ったんだがねえ。はずれだったか。残念残念」
「怒るよ、ピート」
「まあまあ。せっかく今夜はそんなにエレガントなんだから、女の子らしくしていて欲しいね。それから・・・」
言って彼はウォルターに向き直り、改めて言った。
「ウォルターと呼んでも構わないだろうね」
「ええ、もちろん」
「妙なことを聞いてしまったが、ちょっと好奇心でね」
「いえ」
「それはそれとして、さっき言ったのはうそではないよ。きみはいい。とてもいい歌を歌う」
ピートのどこか説得力と深みのある声にウォルターはどう答えていいのかまた戸惑っている。
「これからをとても楽しみにしているよ」
綾は ― そしてダンも ― やった、と思った。
ピートはめったに人を褒めない。けなすことも決してしないが ― けなさなければならないようなものは、はなから相手にしないのだ ― 褒める限りはかなり評価している。
その彼が楽しみにしていると言ったのである。ウォルターの才能がダンや綾たち身内だけの買いかぶりではないことがこれではっきりしたと言っていい。ウォルター自身はそこまで考えていなかったのに違いないが、周りの三人にしてみればひとつ肩の荷が降りたという安堵感があった。そしてそれは他の出席者たちの彼への好意的な態度にも表れていた。
誰もがウォルターに期待している。
それが彼 ― ウォルター・ウルフが生来その才能に約束されていた成功の縁に立った夜だと言って良かったかも知れない。彼にはこれから登るべき際限のない階段が待っていたが、それは同時に運命の輪が綾を彼から引き離してゆく始めの夜でもあった。
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.10.22.
revise : 2010.11.29.
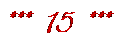

|
![]()