|


イエロー・キャブが彼の目の前を猛スピードで駆け抜けて行った。信号が赤に変わる寸前だったのだ。ウォルターは危ういところで歩道に長身を一歩引いてやり過ごしていた。雑然とした街の空気も人の流れも見なれたいつものニュー・ヨークである。
少し高級な住宅街やミッド・タウンに目を向けると、観光客が喜びそうな洒落た街並みや気の利いた店が連なっているが、奥へ踏みこめば決して安穏とした光景ばかりでもない。建物は古いし、地下を網の目のように走り回っている下水道のおかげで冬は道路が陥没してバスが溺れるなんてことまである。冬は厳寒、夏は酷暑、よく言われるようにあらゆる人種がひしめいていて、笑いごとでは済まない問題も山積しているのだが、しかし逆に言えばこの街の根底にあるクリエイティヴなパワーは、その中で生きようとする人間の生命力から来ているのかもしれない。
843エーカーというスケールのセントラル・パークを中心に東西で4キロ、南北で20キロそこそこのマンハッタンがウォルターのホーム・グラウンドだ。そしてその大して広くもないスペースには、天国から地獄まですべて本物がそろっている。彼はこの街で生まれて育った。しかもその最底辺でと言っていい。けれども、もしウォルターに特別なところがあるとすれば、それは何よりも彼の澄みきった淡いブルーの瞳に他ならない。決して楽に育ったわけではないのに、どんな毒にも染まらないペイル・ブルーの優しい瞳、それはウォルターの本質であり音楽の核でもあった。
彼は今、人の波に乗って歩道を渡り、自分のアパートがあるブロックへ歩いている。それはまだ彼がレコード・デヴューする半年ほど前、レコード会社との契約がうまくまとまらず、もうだめかも、と思い始めていた頃のことだ。その頃の彼はスタジオ・ミュージシャンとしては一部で知られていたものの、結局のところクオリティの高いアメリカの音楽業界の中にあって、まだまだレコード一枚作らせてもらえるようなチャンスには恵まれずにいたのである。
古いコートのポケットに手をつっこみ、冴えないめがねをかけている顔はどことなく浮かなそうで、足取りもとても軽いとは言えなかった。
― あーあ、またダンにしかられちゃったよ、ついてないなあ。
街の喧騒を逃れて彼はアパートの建物に入って行った。
古ぼけたビルの階段を登ると二階にある部屋の扉を開き、誰も迎えてくれる人がいるわけでもないのにI'm home.と呟いて、彼はコートを脱いでソファに放った。それほど広くはない部屋はベッドひとつでもう大したスペースは残っていない。他にあるのはソファとギターが何本か、それと楽譜に本の山だ。オーディオのセットだけがそぐわないくらい立派である。あとは小さなキチンとバスルームがついているだけの部屋だが、音楽にひたっていられれば住む所なんかウォルターにとってはどうでも良かった。
― そんなに面白くないのかなあ、ぼくの曲。
考えこみながらベッドに腰を降ろすと、側に積んであった楽譜をひと束手にとって眺めている。ついさっき仲のいいプロデューサーのダン・ロックウェルにどやしつけられたのもそのあたりが原因だ。決して曲の出来は悪くない。いや、彼の場合、良すぎるのが大きな問題なのだ。
ダンもウォルターのことは買っていて、いくつもレコード会社は紹介してくれたし、向こうも乗り気でいい所まで行くのだが、結局最後はウォルターの方で蹴ってしまう。それというのも彼のブロンドに蒼い瞳とすらりとした長身、という恵まれた養子がすべての元凶なのだ。確かにそれにはリリースする側も喜んで寄って来るのだが、ウォルターが彼側の条件、というか希望を述べると、たいていの場合ご破算になってしまうのである。
ウォルターは音楽的に面白くていいディスクが作りたい。それには時間もいるし金もかかる。しかも自分のイマジネーションを誰にも矯められずにそのまま表現したい。そこが折り合わない。売る側はせっかくいい商品になるんだから売れるようなディスクを作らせたいし、メディアにもそういう乗せ方がしたい。ウォルターはいやがる。どうどう巡りである。
もうこの際、英国へでも移住するしかないか、というところまで来ていて、今日という今日はダンがRMCレコードの企画部長を務めるつれあいのドリーに頼んで無理矢理上層部へねじこんでまで取ってくれた契約内容だったから、とうとう大目玉をくらってしまったのだ。
「何度同じことを言わせれば気がすむんだ、おれに」
「それは悪いと思ってるけど・・・」
「そんなものデヴューしちまえば、あとあとどうにでもすることは出来るって言ってるじゃないか。そこそこ売れりゃあ上の態度だって変わるし、どういう出かたをしたって実力さえしっかりしてりゃファンはついてくるんだよ。限られた範囲の中でも全力を尽くそうという謙虚さがおまえにはないのかっ。誰だってやってることだぞ。それをおまえときたら、曲が制約されるだの、好きなエンジニアを使えないだの、売り方が気にくわないの、今度で何回めだ、このばかやろうっ」
「だって・・・、ダン。ぼくだって出来ないことってあるよ。歌うたうのも曲作るのも絶対自信あるけど、役者でもないのにカメラににっこりなんて出来ないよ」
「それが仕事だと思ってやってみろ!」
「無理言わないでくれる?
とにかく要するに、みんなぼくにポップ・アイドルみたいなことやれって言うんだろ。曲の出来なんかどうだっていいから適当に歌ってTVなんかにも顔出して」
「それがどーしてっ、そんなにイヤなんだっ」
「歌を聴いてもらう余地がないじゃないか、それじゃ」
「おまえなあ...」
「ぼくは歌が歌いたいのっ、音楽がやりたいのっ、RMCにしてもどこにしても結局買ってくれるのはぼくのルックスで歌じゃない。それがどーしてもっ、いや、なんだっ」
このくそガキっ、とダンは今にも爆発しかねないようなものすごい顔でウォルターをにらみつけている。彼がウォルター・ウルフからこのセリフを聞くのはもう軽く十回を超えている。怒鳴りつけもしたし、すかしもおどしも泣きおとしもやれるだけはやった。ところが落ちないのだ、このガキは。
なんとか呼吸を整えてダンは二、三度頷くと言った。
「まあ、な、ドリーに頼んでもうしばらく保留にしといてもらってやるから、考え直してみろ」
「でも・・・」
「考え、直して、みるよ、な?」
彼の形相にウォルターは反射的に頷いていた。
― ぼくってわがままなのかなー。ダンが言うのがあたりまえなのかも。
ダン・ロックウェルと言えば一般には大プロデューサーとして知れ渡っている、とっても偉い先生である。今までロック・ミュージックという範疇において名作と評価されるディスクのミックス・ダウンに数多く関わって来た男だ。今年四十才、口髭が自慢のひょうきんなおじさんだが、音楽に関する限りその耳と目の確かさには定評があった。本来ならそのダンがこいつはものになる、と言えばレコード・デヴューも遠い話ではないはずなのだが、ウォルターの美貌が邪魔をしている。おかげで彼は目も悪くないのに冴えないめがねをかけっ放しにして、すねまくっている始末なのである。
ウォルターは反省しながらキチンでありあわせのオープンサンドとコーヒーという朝食みたいな夕食の支度をしていたが、もともと食べるものもわりと何だってかまわない。とにかく音楽、それがウォルター・ウルフという二十四才の青年だった。
一方、ダンはダンで全く不機嫌きわまりない顔をして家に帰り、ぶつぶつ文句を言っていた。彼にしたところでウォルターを買っていればこそ才能があるのにデヴューできないというのがいまいましくてたまらないのだ。夕食をすませ、ソファで考えごとをしていると、六つになる息子のベンがじゃれついて来て尋ねた。
「ね、パパ。今日土曜なのにウォルター来ないの?」
「めしのひとつも食いっぱぐれれば頭も冷えるだろ」
「ウォルター夕食ないの?」
「ぬきっ」
「かわいそーっ」
毎週末になるとウォルターはこのアッパーイーストにあるけっこう豪華なアパートに顔を見せる。ひとり暮らしをしているから、ろくにまともなものも食っていないだろうと思ってダンが呼ぶようになったのだ。ベンとは仲良しで、兄貴のように思われている。
「プラモ作ってもらおうと思ってたのに」
「パパじゃだめかい」
「こわすもん」
言われてダンは、ごもっとも、という顔をしている。そういうことは苦手なのだ。そこへ、ドリーが笑いながらリヴィングに入って来て、ソファにかけるとベンを抱き寄せて言った。
「ベンはウォルターのファンだもんねー」
「うんっ」
金髪長身のアメリカ美人、しかもやり手のキャリア・ウーマンだから、どちらかと言うとダンの方が家での立場は弱いのだ。
「困ったわねえ、それにしても」
「困った」
「うちとしても契約したいのはやまやまなんだけど・・・。とにかくディスクを作ろうという気になってくれないものかしらね」
「言ったよ、それも」
「何度となく」
「何万回も言ったような気がする」
「ああもったいない。あれだけルックスが良きゃ、それだけだって売れるのに」
「それだけは売りたくないってのが奴の言い分」
ダンは嘆息してつくづく言った。
「大きいホールで演(や)らしてやりたいよなあ・・・」
「そうね。私もウォルターの歌って好きよ」
「ライヴ・ハウスなんかにも出てるけど、どっちかってとああいう場所よかホールばえする曲が多くてさ。歌はうまいなんてもんじゃない」
「ね」
「なに」
「手がなくもないんじゃない」
「何を考えてるんだ」
「貴方と同じことよ」
「同じこと?」
「言ってあげましょうか?」
「うん」
「お姫さまに頼んでみようかな」
Book1 original text
: 1996.10.15〜1997.1.15.
revise : 2008.7.15.+6.15.
revise : 2010.11.28.

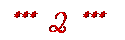
|
![]()