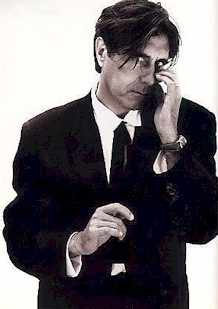|
the best of both worlds Is Bryan Ferry indecisive? Does the Pope wear a funny hat? But the man whose new LP has been in the works for seven years admits that it's been worth it Maybe... by Mark Edwards * photography Horst 1994 Arena 47 Translated by Ayako Tachibana
|
||
|
When you're in doubt Question what you see And when you find an answer Bring it home to me"
『疑惑を感じるならばそこに留まりたまえ そして君が抱いてきた疑問に答えが見出されたら ぼくの元に持ち帰ってくれないか』 Bryan Ferry "Manifesto"
★「そうするときみは、ぼくがグループを再編するべきだと思うってこと?」 慎重に、慎重に。たいていインタヴューされる側はジャーナリストに彼らがこれからどうすべきか尋ねるものだが、その理由は全く簡単だ。おだてられたジャーナリストは、好意的な記事を書くことが多いからである。つまり、彼らは我々がどう思っているか本当には興味などないわけだから、ありきたりな答えを返しておけばよい。しかし、ブライアン・フェリーから彼がロキシー・ミュージックを再編すべきかどうか尋ねられた場合は、答える前によく考えるべきである。なぜなら彼はおだてるつもりなど毛頭なくて、本当にどう思っているのか知りたがっているからだ。 「他の人の意見を聞きたいんだよ」と彼は言う。この「他の人」という言葉には、思っていたよりずっと彼の元々の北部なまりが強く感じられた。「物事を相関的に判断したいから、回りの考えに興味があるんだ。レコーディングをやってる時でも、"これはぼくのレコードだからぼくが一番正しい。誰も口を出すな"って具合にはやりたくない。全然そんなタイプじゃないよ。いつでも"で、どう思う?"って尋ねる方だから。たまにそれが優柔不断に見えて周りを怒らせちゃったりするんだけど、そういうのとも違うんだ。ぼくはただ、望みうる限りの情報を元にして結論を出したいだけ。」 それは7月の最初の土曜の遅い午後だった。我々はホテル・ランカスターに取られたフェリーのスイートで話している。シャンゼリゼ通りからいくぶん奥まった所にあるランカスターは、18世紀のアンティークで飾られていて、パリでフェリーお気に入りのホテルだ。 フェリーはやっと、1987年の"Béte Noire"以来初の全曲オリジナルアルバム"マムーナ"を完成させたところで(9月5日、ヴァージンよりリリース)、アルバム装丁に関していくつか細かな部分を決めるかたわら、プロモーション活動を開始したばかりである。フェリーの友人であり、初期ロキシーの頃から広報を取り仕切るサイモン・パクスレーが、アルバムのバックカバー用アートワークと2枚の装飾用上張りを持って現れた。ひとつは黒に黒のカバー、もう一つはピンク。フェリーはCDのジュエル・ボックスに1枚ごとに差込んでみて、「ぼくとしては黒がいいと思ってるんだけど、レコード会社がピンクの方がいいというのも頷けるんだ。」 そうするとスティル・メイトだろうか。 とんでもない。フェリーがピンクを差し戻し、その上に黒を重ねると、結果はブラックの周りにピンクの縁取りが現れることになった。「これでどうかな?」と彼はパクスレーに尋ねている。「とてもぼく好みなんだけど。」 「それがきみの困ったところなんだ」、とパクスレーは言う。「いつだって双方取りしなきゃ気がすまないんだから("You always want the best of both worlds.")」
だが、アリーナ誌は、なかなか素敵なヘマをやってくれた。我々はパリにいたというのに、服を調達できなかったのだ。ちょうどその週末、主なメゾンのファッションショーが開催されている最中で、普通なら撮影のために喜んで貸してくれるはずのサンプルはどれも会場で必要だったのである。その結果、服はモデルの自前で間に合わせることになってしまった。 フェリーはイヴニングを選び、カルティエ財団のパフォーマンス・スペース一面に置かれたロン・アラッドデザインによるテーブルのひとつに注意して上がったが、テーブルがその体重に耐えられることを確認するや、嬉しそうにフェリー・エフェクトを発揮し始めた。片方のひざを少し曲げ、肩をちょっとナナメにして、髪がよいバランスに来るように頭の角度を取り、ほんのちょっと微笑を浮かべる。家で真似ないでもらいたい。3歳の恥ずかしがりなコドモに見えるのがオチだからだ。しかしフェリーがやると、結局その効果は優雅でクールな印象をもたらす。 撮影の間、フェリーはリラックスして楽しそうだった ―事実そうだったのかもしれない―。"マムーナ"は12年前の"Avalon"以来、彼の最高の作品と言える。一聴してはアピールに欠けるかもしれないが、少しばかり我慢してみて欲しい。そうすれば、すぐにそれが素晴らしい作品であることが分かるだろう。フェリーの近作にもれず、洗練されていて細部まで作りこまれている。明らかに週末のやっつけ仕事ではないが、かと言って7年という苦闘の創作活動の末に生み出されたものというようにも聴こえない(事実はそうなのであるが)。 生では明らかにないが、調理されすぎてもいない。それにフェリーが"Avalon"以来の幽玄を踏襲する一方で、初期ロキシーからのファンは何曲もブライアン・イーノがフィーチャーされた曲があることに気づいて喜ぶことだろう。そのクレジットは"sonic ambience", "sonic emphasis", "sonic swoops", "sonic awareness" そして"sonic distress"といった具合に、様々に名付けられている。二人にとってこれは20年来で初めてのコラボレートでもある。
★"マムーナ"はリリースされるまでにずいぶん時間がかかったが、フェリーの作品においては「〜以来初の」という形容は珍しくない。9月の終わりには、フェリーは1988年以来初のツアーに取りかかることになっている。彼がいろいろな作品の側で撮影している間、パクスレーは、カルティエ財団の一人を脇に連れてゆき、財団はスポンサー・シップに興味がないかどうか尋ねている。 「ぼくは結婚していて子供もいるし、だからツアーに適したライフスタイルを送っているとはもう言えないな」と後にフェリーは言っていた。「でもほくにとっても、ぼくの作品にとっても、ツアーに出ないでいるのは物足りない感じがしてね。その方が山ほどインタヴューを受けるより、ずっといいプロモーションになるように思うし。」ちょっと黙ってから、彼は笑い出した。「ねえ、ぼくが正しいと言ってくれないか。もうそのつもりなんだから。」 「前にツアーをやった時には元気が出たんだよ。"すばらしい、ぼくにはオーディエンスがいる。この人たちはみんなぼくが好きなんだ。"って思って。インタヴューを沢山やるのは正反対で、ツアーの時のような達成感が得られないから物凄く疲れる。何かに騙されてそんな状況に追い込まれているような自己嫌悪に陥るし。ついこの前、新聞で、"インタヴューを受ける人は誰でも、虚栄心からそうするんだ"なんてバカげた記事を読んだんだけど、全くクソったれ! だったね。ぼくは誓って楽しんでなんかいないよ。フットボールの話題でもあるなら話をするのも楽しい。だけどぼく自身のことになると、いきなり悩み出すんだから。」 ニューヨークのCondé Nast編集長であるジェイムズ・トルーマンは、70年代の終わりからフェリーを知っている。彼はフェリーのインタヴュー嫌いの原因を、いくらかシャイだということもあるが、自己分析を恐れる性質のせいもあるだろうと言う。「彼の作品は、彼自身プラヴェートに置いておきたいような部分から出て来ているので、隅々まで自己探索しすぎるのもイヤなんだと思うよ。自分で見えなくなるのが恐いから、夢見がちでロマンティストな側面を細かく分析しようとしたことがないんだろうね。」 話し始めると、フェリーはテレビのリモコンに手を伸ばしてスイッチを入れた。音を絞り、半分眺めながらチャンネルを変えつづけている。見え透いた自己防衛ではあるが、そのままにさせておこう。なぜなら私はもう彼にサングラスを取るように頼んだし(そうすると防衛手段をふたつ一度に取り上げるのは、ずいぶん酷いような気もする)、それに彼はツール・ド・フランスを放映しているEurosportで画面を止めたからだ。 フェリーは14から15歳の頃、サイクリングに夢中だった。それほど長けていたわけではないが、工事現場や鉄工所、ニューキャッスルにあるノーザンバーランド通りのジャクソンズというテイラーなどで、週末や休みの日に働いていたから、必要なものは何でも手に入ったようだ。「ニューキャッスルというのは、着るものに関して進んだところでね」、と彼は回想する。「主にモッズだけど」。 大学に行く直前の夏休み、サイクリング・クラブの友人が彼に歌が歌えるのかと尋ねた。「ぼくが、歌えるよと答えたら、彼の父親があるバンドのマネージャーだと言うんだ。フィッシュ・アンド・チップスの店と美容院を経営してたんで、バンドは美容院でヘアドライアーに囲まれて練習してたんだよ。」 フェリーはこのグループ "ザ・バンシーズ"で一夏過ごした後、ファイン・アートを学ぶためニューキャッスル大学へ進む。そこでは"ザ・ガスボード"というアメリカのブルースやR&Bをカバーするバンドで活動していたが、他のメンバーがプロになるために大学を中退した時も、彼だけは学業を続けることを選んだ。「当時、ぼくには二つの面があったんだ」、と彼は説明する。「大学でやってたことと、夜は歌。で、グループにいるより美大にいる方がシャレてるって感じかな。ちょっとばかりスノッブなところがあったから、『学業の座』に座っている方が良かったんだろうね。」 「それから2年ほど経って、ぼくが本当にやりたいことは、ぼくの作品をかつて夜にクラブでやってたような、より動きのある活動と結びつけることだと思うようになったんだ。一旦、曲を書き始めると、それが可能なことが分かって来た。と言うのは、ぼくは音楽的にもクリエイティヴでありうると感じたし、それは黒人シンガーたちを真似て歌おうとするような、いくらか恥ずかしさを感じていたこととは違っていたからだよ。」 フェリーの作品と「より動きのある活動」との融合は、間もなくロキシー・ミュージックとして結実する。ロキシーはピアノやサックスの入った初期ロックンロールをリバイバルさせながら、同時にそれをシンセサイザーを通して変貌させたのだ。その結果は大変なものだった。パクスレーは彼らの演奏を100クラブに見に行った時のことを回想する。「全く驚かされたよ。それは在り得るかもしれないという気がしていたもの、ロックンロールとしてずっと聴きたかったようなもの、正にそれだった。新しい音であり、成立しなければならないものだったんだ。」 そう、もちろんそれは成立し得た。少なくとも、1976年までは。その年、"The Bride Stripped Bare"が酷評を受け、商業的にも不成功に終わったため、フェリーは彼のソロ・キャリアで初めての暗礁に乗り上げることになる。そして、その収拾がつくまでに、2年を費やしたのだ。「悪夢のような時期だったよ」、と、このアルバムで5人のブロデューサーの一人に名を連ねたパクスレーは言う。「録音のためにスイスに行っていたんだけれど、到着して間もなくジェリー・ホールがミック・ジャガーの元に去ったという知らせがあってね、ブライアンは、ひどく傷ついていたし、雰囲気が張り詰めている感じだったよ。騒ぎや争いが酷くて、それにみんなコカインをやりすぎていたんだ。そういうのが、いくらかアルバムから窺い知れるかもしれないね。神経質でとげとげしい印象がいくらかあると思うから。」 1978年、フェリーはロキシー・ミュージックを再編したが、しかし4年後に解散する運命の種は既に撒かれていた。「"The Bride Stripped Bare"ではLAのミュージシャンを多用したんだけど、彼らの演奏には落ち着きやゆとり、それに頑張りすぎないところがあってね。」、とフェリーは言う。「やりすぎないところに、深みがあるんだ。アンディやフィルは、そういうのに馴染まなかったんだよ。」 ロキシーは更に、1982年の最高傑作である"Avalon"を頂点とする3枚のアルバムを発表したが、義務的なツアーをこなした後、フェリーは再度グループを解散する。「グループの一員としてではなく、自分の曲を、独力で創り上げてゆきたいと思ったんだ。誰を使うかは自分で選び、ツアーにももう出ない。スタジオだけで仕事をし、そうすればその後はみんな幸せでいられる、そう思ってね。」 そう言いながら、フェリーは笑って見せる。「間違うことだってあるよね?」 それから彼は溜め息をついて、次の言葉をなかなか続けられなかった。「80年代というのはなんというか...、全く...、そうだな、良い時期とは言えなかった。...ぼくにとって...。キャリアの点でね。」
★かつて1975年に、フェリーはローリング・ストーン誌に語ったことがある。「ぼくはいつも"OK、それでいいよ"と言い切れなくて締め切りに間に合わず、リリース予定を台無しにしてまうんだけど、でも、そういう(音楽に対する)誠意は持ち続けられるようにと思っているんだ。」その点に関して彼は心配するに及ばない。"マムーナ"は"Avalon"以来の12年間で、フェリーにとって4枚目のアルバムであるにすぎないからだ(70年代の始めには、彼は18ヶ月で4枚ものアルバムをリリースしていた)。"Boys and Girls"には3年、"Béte Noire"には2年を費やし、座礁した"ホロスコープ"プロジェクトに至っては、カバー集である"Taxi"をレコーディングするために中断されるまでに3年過ごしている。それから"ホロスコープ"の曲に戻ったわけだが、"Taxi"の後でそれは比較的早く"マムーナ"に転じた。 "マムーナ"の歌詞には、時が過ぎ、時が尽きてゆくという表現がいくつも見受けられる。明らかにフェリーは ― 来年50歳になるのだが ― 80年代に完成させた作品が僅かなこと、特に"マムーナ"制作に膨大な時間を費やしたことに落胆している。「それについてはよく考える」、と彼は言う。「実際ぼくはあのアルバムに全財産を費やしたわけで、同じようなことは二度とやりたくないな。」 80年代を通してフェリーはより複雑なレコーディング・フォーマットに沿って、革新的な音作りをして来ていた。それは"Horoscope"/"Mamouna"を始める頃には、56トラックにまでなっていたのだ。 ― そしてそれは、彼のような仕事のやり方をする者には、泥沼にハマり込むことになりかない事態だった。「彼の選んだやり方は、ミュージシャンよりファイン・アートの背景を持っている者に適している。」、とフェリーのニューキャッスル大学時代の同期であり、長きに渡る友人、協力者でもあるニック・ド・ヴィルは言う。フェリーはド・ヴィルの"5つの同時発的可能性"と名付けられた一連のリトグラフを所有している。「ぼくは彼が音楽を作る過程をずっと見て来ている。同時にいくつもの可能性が生じるという概念が、それに適しているんじゃないかな。オーバーロードになるまで次々とトラックを作り上げて、それから細分化を始める。」 フェリーにはいつでも代案、つまり他の可能性が見えており、それゆえそれに通じる道を閉じるような決断を下すのをためらうのだろう。彼は全てにおいてベストを目指したがるのだ。そしてそれは際限ない可能性が同時に生じるということでもある。「デジタル・テクノロジーは彼にとって泥沼と言えるね。」とド・ヴィルは言う。「可能性があまりにも大きくなりすぎる。そのせいでこのアルバムを統制するまでに、あんなに時間がかかったんだろう。可能性が無限に増殖することは、ガンに陥りかねない危険性を内包してもいたんだよ。」 "Horoscope"/"Mamouna"のプロジェクトを開始した時、フェリーにとってひとつの問題は、マネージャーやプロデューサーがいないことだった。そして彼の近作がそうであるように、ロキシーの時のようなバンドという環境も失われていた。トルーマンは言う、「かつてブライアンは私にロキシーについてこんな風に言っていたことがある。"ぼくが回りにいる連中を好きなのは、彼らがスタジオに現れてとんでもないヘマをやらかすと、ぼくはそれに影響されて、より良くしようという気になるからなんだ。"思うに、バンドのメンバーが彼を困らせるもので、さっさとスタジオから逃れたかったんじゃないか。だからレコードも早く仕上がったんだろう。」 そうするとフェリーは作品を完成するのに触媒的なものを必要とするということだろうか? 自分で優柔不断だと感じているのだろうか? 「ん...、場合によるよ。」彼は答えた(まじめにだ)。「『優柔不断』というのは、あまりいいコトバじゃないね。時おりそうなることもあるんだろうけど、大抵は単に納得のいくレベルに達していないというだけなんだ。何か、しっくりこないというか。それが何なのかハッキリとはしないんだけど、良くないということだけは分かる。ぼくが優柔不断になる時というのは小さなことで、例えば今夜どこのレストランに行こうかというような問題の時だね。」 実は我々はパリで最も古いとされる(しかしパリではどこもそうなのだ)Bofingerに出かけたのだが、それもフェリーの選択ではなかった。彼は大して気にも止めていなかったのだ。これからのツアーについての構想も深く考えていない様子だったし、ロックスターらしくレストランまで行くのにメルセデスが来るのを待つようなこともなく、側にいるわれわれとヨレヨレの古いタクシーに飛び乗って行くことにも構わなかった。
フェリーを特集した過去10年の記事を読み通してみても、一行の歌詞も引用、若しくは言及されていないことに驚かされる。実際、意識されず、全く認識されずにいるものの、彼はロック史において最もすばらしい作詞者の一人であるというのにだ。 初期ロキシーの曲のようなNoel Coward風の言葉遊びと対照的に、現在の彼の歌詞は殆ど俳句のように圧縮されている。解説的な意図よりはむしろ、言葉そのものを楽しむかのようだ。このような方法は"Manifesto"のタイトル・トラックあたりから始まっている。 私がその話をするとフェリーは、「え、"マニフェスト"? うん、あれは好きだな。」と言う。「気に入りのひとつなんだ。誰もそれについて言ってくれないんだけど、...それって傷つくよね。」 彼の歌詞をちょっと見るだけでも、フェリーは傷つけられるのを待つかのように、その心をそこに晒しているのが分かる。彼の作品には、深く巣食っている悲しみに満ちた孤独が浸透しているのだ。「彼の中でも大変孤立した部分から出て来ているんだよ」、とトルーマンは言う。「必然的にね。そして人がそこに踏み込んでくるのを嫌がるんだ。新しいアルバムには『きみはぼくを落ち着かなくさせる、電話を掛けてくる、気が変になりそうだ、一人でいたい』、こんな一節があるけれど、これが彼の歌詞の真髄だと言えるだろうね。」 技術的なものが齎す危険性よりもなお、彼の制作を遅らせるのが歌詞である。書いては消し、書いては消す。草稿に継ぐ草稿。それがその優柔不断さの現れであると言うものもあるだろう。若しくは、ニューキャッスル時代の彼の師 ― ポップアートの開拓者、リチャード・ハミルトン ― の言を引き合いに出す者もあるかもしれない。「もし私の生徒が私から学んだものがあるとすれば、行動より思考に重きを置くということだろう。」、とハミルトンは言う。「大切なのは質であり、質というものは作品を吐き出すような行為からは生まれ得ない。憂うべきは下痢のような状態になることなのだ。」 ハミルトンが永続的な影響をフェリーに残したことは明らかだ。我々の多くがその作品を、ロックスターに期待されるものという観点から測る一方で、彼は一緒に勉強したアーティストたちと同じ観点から評価されることを望んでいる。「面白いことに」、とフェリーは言う。「画家が2年に一度くらい開いている個展を見ると、例えば20点の作品があるとしようか。そうすると、それらは実は全てが一つの絵なんだ。ピンクのがあるかと思うと、ブルーのもある。― ひとつのテーマに対して、カラーバリエーションがあるだけなんだね。だけと音楽ではそういうわけにはゆかない。毎回、10点の傑作を期待されるんだ。もしその挑戦を受けて、そうだな、けなし屋連中に目にもの見せてやるぞ、みたいなことになったらそれはもう大変で、ぼくはそういうのにまるで向いてない。ぼくに言えることがあるとすれば、それはとにかくやってみようということだけだろうね。」 フェリーはその『けなし屋』の一人を思い出して笑っている。「去年,"タクシー"のプロモーションをしていた時に、あるフランスのジャーナリストが"For Your Pleasure"のような作品をどうしてもう作らないのかって攻撃して来てね。言うんだよ、『"Avalon"が気に入りすぎて、以来同じことを繰り返してるだけじゃないですか』って。落ち込まされたな。そのインタヴューのあと、ひどい気分だったよ。」彼はまた溜め息をついた。「そんなにぼくってダメ? ヤツの方が正しいのかな。どうなんだろう。」 "マムーナ"の素晴らしい仕上がりを前にした今、フェリーは正しく、そのジャーナリストが間違っていることは明らかだ。"Avalon"後のサウンドから彫り出されてなお、すばらしい曲が多々あるのだから。 撮影とインタヴューの間にレコード会社やカルティエ財団の代表者たちと一緒に昼食に出かける必要があった。Raspail通りを歩いていると、フェリーは迷わず歩いてゆく。私は彼に追いついて、我々が向かっているレストランが実際にどこにあるのか知っているのかと尋ねた。「いや」、彼は答える。「誰かがぼくに止まれと言うまで、こっちの方向に歩いているだけだよ。」 2005.5.4.-5.7. revise / edit 2007.1.11.+ 1.16.
Copyright Information ★ 著作権に関するお願い The intention of this site is purely enjoyment and for providing information about the band ROXY MUSIC. Though credits are given as long as it is possible, if you are the owner of any of the artwork or articles reproduced within this site and its relating pages and would like to see them removed, please contact Ayako Tachibana via E-mail. Your request will be completed immediately. Or if there is no credit on your creation, please let me know. I'll put your name up ASAP. Anyway the site owner promise to respect the copyright holder's request seriously. I hope visitors also respect those copyright and please do not use the articles and artwork illegally,このページ及び関連ページにおける画像、記事は、あくまで個人のホームページにおいて、文化振興を目的に掲載しておりますが、著作権者のご要望があれば直ちに削除いたしますのでメールにてサイト・オーナーまでお知らせ下さいませ。著作権者様のご理解を賜れれば、これに勝る喜びはございません。また読者の皆さまにおかれましても、著作権に十分ご配慮頂き、商用利用等、不正な引用はご遠慮下さいますよう、宜しくお願いします。
|